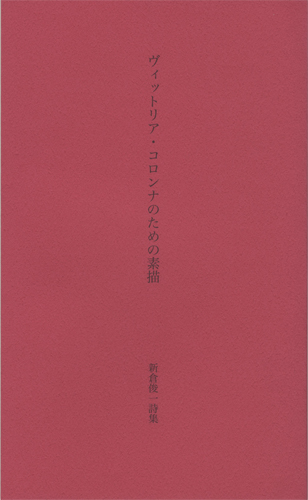
ここしばらく自由詩の仕事から離れている。二十代から三十代にかけては詩のことばかり考えていた。ほとんど詩に取り憑かれた詩狂いだった。自信過剰に聞こえるかもしれないが、今なら詩作品も詩論も書こうと思えばいくらでも書ける。正確に言えばようやく自在に書けるだけの力と思いきりがついた。しかし人が一年なら一年の時間にできる仕事の量は限られている。詩の仕事をする順番は少し後でも良いだろうという思いがある。
ほかの詩人たちがどのような考えで仕事をしているのかはわからない。ただ今のようにほぼ全ての既存の文学的価値規範が崩れ、文学の世界全体が新たなパラダイムを模索して苦悶している時期に、自由詩だけに専念することは僕にはできない。もし一九六〇年代に青春時代を送っていたら、なんの迷いもなく戦後詩人や現代詩人として詩と詩論を書いて暮らしただろうと思う。あるいは文学のパラダイムが安定している時期なら、詩の可能性だけをとことん追求しただろう。
しかし人は生まれてくる時代を選べない。今は新たなパラダイムを作り出す時期だ。そうしなければ、現代の作家たちは生きたまま死者と化すだろう。誰かがこの面倒な仕事を片づけてくれるだろうと期待する時期はとうに過ぎた。他者に一切期待せず、自力で困難を乗り越える者だけが次世代の文学の礎になる。また自由詩は他の文学ジャンルに先駆けて、新たな文学ヴィジョンを開拓することでその不安定な文学的アイデンティティを保ってきた。その仕事を成し遂げるのが僕でなくてもかまわない。ただそのような真摯な試みを続けた文学者の一人でありたいと思う。
たった一枚の紹介状を携えて
はるばるロンドンに訪ねて来た
アメリカの青年パウンドから
「ダンテの詩は明喩で
カヴァルカンティのそれは
暗喩だ」と聞かされて
イエイツは即座にこの赤毛の
青年詩人を信用した
それから二人の希有な共作が
始まるのだがその歴史は
今のわたしには関心外だ
詩の衰えた乏しい時代には
むしろ朝の海の鏡のように
冴えたダンテの明喩が
必要なのではないか
そんな不埒な発言を
今の流行の詩人たちは
一笑に付すだろうが
「萎んでうなだれていた花が
朝日を受けてまた開くように」
とダンテの詩にあるように
いつかは生気を取り戻すだろう
(詩篇『比喩』全篇 新倉俊一詩集『ヴィットリア・コロンナのための素描』より)
新倉先生はこれまでも二冊詩集を出しておられるが、いずれも私家版だった。今回の『ヴィットリア・コロンナのための素描』が誰でも入手できる形で刊行された処女詩集ということになる。以前『エズラ・パウンドを想いだす日』(私家版)について書いたが四部構成の長篇詩で、田村隆一さんと飯島耕一さんの追悼詩でもあった。『ヴィットリア・コロンナのための素描』は短詩集で、『ヘレニカ』、『ヴィットリア・コロンナのための素描』、『中世』、『水脈』、『アンフォラ』、『ホロスコープ』の六章に全五十四篇が収録されている。
多くの詩人が新倉先生を学匠詩人と呼ぶだろうが、そんな奥歯に物が挟まったような言い方はもう不要である。先生は学者かもしれないが、それとは別に詩人として歩み出された。また先生はもしかすると僕らよりも強く詩の力を信じておられる。田村さんや飯島さんと同様に先生の詩は断言である。僕もまた「詩の衰えた乏しい時代には/むしろ朝の海の鏡のように/冴えたダンテの明喩が/必要」だと思う。ダンテの明快さは単純さではない。世界認識の確かさと思想の強さが明確で力強い表現を生んでいる。それは豊富な詩の知識と的確な状況判断ができる詩人にはわかるはずだ。今は曖昧に問題から逃げ回るのではなく、勇気をもって断言すべき時代なのだ。
曖昧で多義的な暗喩は、あるパラダイムが確実に存在している時にのみ力を発揮する。たとえば〝現代詩の時代〟がそうだ。詩人たちは新たな表現領域を開拓することに熱中し、言葉の意味伝達機能を無化する純粋言語表現を目指した。それが象牙の塔にならなかったのは、安保闘争や戦前からの知の伝統、あるいは従軍作家たちの一種特権的な生死の境を見る戦後文学が仮想敵としてあったからである。しかし今の文学者たちは、白黒を鮮明にするのではなく、世界のストラクチャそのものを明らかにしなければならない。
ゴールウェイの
古い街を訪ねて静かな
流れの畔に奇跡のように
立っている塔をみた
ここはイエイツという詩人が
むかし住んでいた場所だ
古いプラトニストの棲家に
ふさわしい塔の象徴として
「塔」という詩集を出している
何もないがらんどうの
内部に足を踏み入れると
イエイツの朗々とした声が
どこからか響いてくる
いまやどの街に行っても
盲いた眼の空洞の建物ばかり
立っていて詩人の声は
どこからも聞こえない
中世の都市サン・ジミニヤーノ
では互いの権勢を競った
高い塔が今も残っている
煌々と満月に照らされて
プラトンの書を読む
この海辺のマンションが
せめてもの塔の名残だ
(詩篇『塔』全篇 同)
新倉先生は逗子のマンションの一室で今もプラトンを読み、イエイツの『塔』を読んでおられるようだ。僕は先生の仕事に導かれてきた。喩と観念にまみれたフランス詩に染まっていた僕に、アメリカ詩の明快さを教えてくださったのが新倉先生だった。明快さの極みが複雑な表現を生み、単純なはずなのに決して思想や観念に還元できない詩を生み出すことを教えてくださった。今はどこまでも詩の力を信じる先生の作品に導かれている。崖を見下ろす横浜の団地の五階で、僕は詩を疑いながら詩について考えている。先生とはもう十数年はお会いしていないが、文字だけで結ばれた僕の大切な詩友である。
低い門を潜り抜けると
傍らになにげなく
沙羅双樹の花が
ひっそりと咲いている
本堂の裏手に回って
濃い紫や白に美しく
彩られた杜若の群生に
しばらく言葉を失った
つかのまの人の世の
楽しみのためにだれが
こんな豊かな彩りを
添えてくれるのか
草木国土悉皆成仏
という経文がどこやら
聞こえてくる気がする
むかし祇園精舎に
あった無常堂では
僧が臨終を迎える度に
ひとりでに鐘が鳴った
われわれが帰りがけに
沙羅双樹の脇を通ると
先ほど咲いていた
白い花の一輪が
ほろりと散っていた
(詩篇『無常堂』全篇 同)
詩集『ヴィットリア・コロンナのための素描』の中で最も優れた作品は、『無常堂』のような詩だろう。詩は謎かけではない。すべてを理解できて、しばらくして「あれはなんだったのだろう」と思い返すのが良い。詩篇『無常堂』で花は咲いて散り、そのたびに鐘は鳴るのである。
鶴山裕司
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


