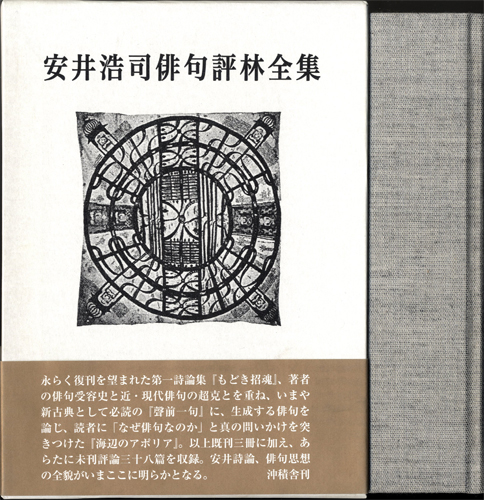
重信における多行形式とは何であったろう。それは、(中略)多行形式を行うことによって、俳句の新しみを求め、今の「詩」を獲得しているのではない。それは、もっと逆説的なもので、古来の俳句形式において、多行形式を実践することによって、そこに高柳重信即多行形式(あるいは高柳重信即俳句形式)というマイナス部分を生じさせることである。体系からマイナス方向へ引いたもの、つまり「世界」に対して〝虚〟なる陰型として、この形式をこそ捉えてゆくことである。俳句形式とはもっとも逆説的なものではないか、として、それが重信における真実の〝俳句〟行為ということなのであった。そういう認識以外に、多行形式が重信の方法論として立つことはありえないのである。
(「高柳重信の世界 その熾烈なる軌跡と業績」)
引用の重信論のポイントは〝虚〟にある。この思想を安井氏は、「有季定型の営為とは、(中略)遂に虚構として捉えるしか在りようがないのではないか」(「有季定型は化け物か」)、「俳句形式という言葉は、(中略)俳句それ自身の肉体的存在に対する虚構性を含みもった言い切り」(「俳句形式の彼方」)だとも表現している。季語や五七五の定型(形式)を絶対のものとする限り、俳句本体の姿は捉えられない。俳句定型を共同幻想としての虚構だと認識することで、初めて俳句本体の肉体性はちらりとその姿を現すのである。重信は俳句定型の〝虚〟を露わにする試みを最もラディカルに実践した俳人だった。重信文学は未踏の表現領域を切り拓くという意味での前衛ではない。俳句定型に多行形式を対峙させることで、俳句定型という虚構の共同幻想が浮かび上がるシステム――そのダイナミズムこそが俳句本体の肉体性である――を把握するのである。
俳句定型を不動かつ不可侵の形式だと認識した時点で俳句文学はその生命を終える。作家ではなく俳句定型が自動生成的に俳句を生み出し始めるのである。俳句を動的な文学として生かし続けるためには、俳句定型を虚構とみなし、それに揺さぶりをかけ続ける必要がある。重信の方法はセンセーショナルだったが、その多行作品は「来し方の俳句に対して反・俳句を掲げたわけではなく、自らの認識の中に俳句たらんとして書こうとした〈俳句〉作品以外の何物でもなかった」(「放物線の行方」)わけだ。安井氏は重信を、「高柳こそ「敗北の詩」、あるいは亜流性の決意において俳句のニヒリズムを信じた、いわゆる俳句史の一本道に繋がる本格的な俳人だったかもしれない」(同)と位置付けている。
加藤郁乎は、高柳の〈俳句〉という作品に対して、〈作品〉という俳句をこそ用意したように思える。そこでは〈反・俳句〉を俳句形式に作用化させたと言ってよいだろうか。いわゆる俳句従来の変容にあらず、〈俳句〉から、俳句形式の確定要素を捨てることで書かれる〈作品〉への問いがあった。まず自律としての〈作品〉が定立することで、受容される〈俳句〉化の、近来はじめて見られる真の前衛風景である。
(「放物線の行方 加藤郁乎以降の俳句」)
重信論での思想を援用して、安井氏は「放物線の行方」ではっきり前衛俳句運動の終焉を宣言している。晩年に山川蟬夫名義で一行の有季定型俳句に回帰したことからもわかるように、重信は、本質的に俳句は有季定型に収斂するだろうと予感する保守的作家だった。そのため重信に〈反・俳句〉という意識はなく、多行俳句は明確に「俳句」作品として認識されていた。
しかし加藤郁乎はその先へと進んだ。「落丁一騎対岸の草の葉」で始まり「このソノラマの死へいざ桂冠の金枝篇!」で終わる郁乎の第二句集『えくとぷらすま』収録作品は、もはや俳句ではない。ほぼ完全に「俳句形式の確定要素を捨てることで書かれ」ているからである。『えくとぷらすま』では従来の基準・思想では決して俳句とは呼べない作品が俳句として提示されているわけだが、多くの俳人たちがそれを諾うことで初めて俳句・句集として成立する。俳句として認知された上でその意義が議論されるのではなく、非・俳句〈作品〉が提示され、次いでその〈俳句〉作品化が起こるのだ。安井氏はこの変化を、
‘俳句→作品
作品→’’俳句
とまとめている。重信の多行俳句は俳句文学の動的ダイナミズムを試す作品だという意味で「‘俳句」と捉えられる。しかし郁乎は非・俳句「作品」まで進み、それを「俳句」化しようとした。一種の裏返しの伝統俳句である重信の「‘俳句」という審級を脱して、ほぼ完全な「(前衛俳句)念願の虚構完体」である「’’俳句」作品を作り出したのである。だがこの先はない。郁乎の試みは「真の前衛風景」かもしれないが、作品は俳句定型に揺り戻るほかないのだ。実際、『えくとぷらすま』以降の郁乎はそのような道筋を辿ることになった。
「放物線の行方」は平成二年(一九九〇年)に書かれたので、安井氏は時間をかけて前衛俳句の意義を考え、その可能性に終止符を打ったのだと言える。しかし基本的な考え方は既に初期批評で表現されている。『もどき招魂』収録の「道化の華 高柳重信論」(昭和四十七年[一九七二年]発表)で安井氏は、「私は、多行形式を、もっともらしい属性を振りかざしつつ、その効率のよさを説明する手合いは、何にもまして愚かさの極みである、と思っている。多行形式こそ、無効で、不毛で、不能で、重信一人で終熄して果てることにのみ、面目のすべてがあるのではないか。はっきり言い切ってしまえば、俳句の一行が滅ぶとき、多行も滅ぶはずである」と書いている。
重信や郁乎の試みは俳句文学にとって重要だが、一回限りのものだった。俳句は形式として現象するが、「俳句の肉体」は本質的に形式化を拒むのである。技巧であれ内容であれ、それがいったん形式(様式)として成立してしまうと俳句は文学としてのダイナミズムを失う。この意味で、逆説的だが俳句定型を仮想的として戦うのは無駄だ。どんなに斬新な技巧・内容でも俳句は易々とそれを飲みこみ、気がつけば何の驚きもない形式に変えてしまう。しかしこのような認識は安井氏に絶望をもたらしていない。ほとんど虚無的な諦念と紙一重のところで俳句と遊び、その可能性を更新してゆく共生の道が残されているからである。それを安井氏に伝授したのは、安井氏の師である永田耕衣である。
永田耕衣も、己が老年を新しくして、〈長生〉という思いを大切にする。(中略)これもまた一ツの〈生〉の方法論であったのである。生きて、永らえ、誰よりも何よりも多くのものを捨て去ることである。早逝の者には、捨てるべきものが少い。いや捨てるべき量の問題ではない。(中略)間髪を入れず、即座に捨ててゆく、そこに捨てられたぶんだけが、生の無意味性を強調してくれることになるのだ。これはもう、何と俳句自身の弁証法と酷似してくることであろうか。
(「歳月の方法 永田耕衣論」)
耕衣は現代俳句における真の巨人である。彼は重信よりもさらに「俳句史の一本道に繋がる本格的な俳人」だが、伝統俳句にも前衛俳句にも分類できない独自の作品に誰もが戸惑った。耕衣が「間髪を入れず、即座に捨ててゆく」作家だったからである。重信のように俳句に真正面から戦いを挑み、俳句定型の虚構性を焙り出すような方法は採らなかったが、耕衣の作風は刻々と変わっていった。安井氏は「耕衣俳句はおしなべて、永田耕衣という生の、きわめて生ぐさい生命の〈跡〉として書かれたものと言うほかはない」(「歳月の方法」)と書いているが、耕衣俳句は一所不住だった。しかしそれは「俳句自身の弁証法」に合致していたのである。
耕衣は「俳句の地金は、伝統的にいって、その卑俗性であると思う」(「田荷軒俗談」)と書いている。この思考を敷衍して安井氏は、「俳句が、どこか通俗と結びつき延命を強調する、こういう反文学の生理を果たしおおせた俳句だけが、残り続けていくのではないか。(中略)通俗という名の虚像に参加していなかった者にとっては、形式蘇生の快感や、そういう一句が放射した作品現場の同時性は、とても得られないのである」(「昭和俳句の虚実」)と論じている。
形式として現象しながら、本質的に形式化を拒む俳句文学の特質は、安井氏の「反文学の生理」という言葉で表現することができるだろう。それは「花にふけりて実をそこなふべからず」という芭蕉の虚実論にも通底している。花、すなわち虚は明透な観念とも、すっきりとした形式だとも解釈することができる。しかし俳句文学はそれでは成り立たない。通俗で力強い生の混沌を実に持つ必要がある。虚と実、つまり天上(観念)と地上(通俗)との激しい往還が俳句文学を支えている。
安井氏は芭蕉以前の俳句では「人生、死、歴史、動物、植物」が「ひたすら踏襲と反復」されていたが、芭蕉によって「それらはみな一回性の「造花」の位相に置かれることで、芭蕉の「生きる」思想は究極化した」(「イメージの根拠 「生きる」とは」)と論じている。芭蕉は本質的に同じ試みを二度繰り返していない。彼が未踏の地を求めて旅に出て、〝旅の途上〟で死を迎えたのは象徴的である。
重信や郁乎の前衛俳句ばかりではない、伝統俳句もまた本質的に「一回性」の芸術である。アプリオリに俳句定型(形式)が存在するわけではなく、一回ごとに俳句の肉体を垣間見せるような俳句定型への昇華が行われなければならない。悟るなど論外で、俗にまみれ、迷い、その都度俳句定型を発見する必要がある。そのようにして定型(必ずしも五七五に季語ではない)にまで昇華された作品だけが俳句文学として認知され、後の世代にまで受け継がれてゆく。俳句界にはそこそこ良い俳句を書いた作家がたくさんいる。たまさかであっても俳句の肉体と定型が結びついた作品は記憶されるのである。安井氏が言うように様々な意味で俳句文学は「イロニー」だが、絶望や諦念とは程遠い無限継続的な戦いの文学である。
世界終末予言日過ぎても夏の雲 安井浩司(句集『宇宙開』より)
理性的論理思考で俳句文学を探究するのは、『評林全集』の試みくらいが限界だと思う。俳句に憑かれた作家は、まず「なぜ俳句なのか」という問いを発して「俳句とはなにか」という難問に挑むようになり、また「なぜ俳句なのか」という自問に戻る。難問の本質を理解した者だけが二度目の自問を発することができるのだと言ってもよい。ただこの問いに対する散文的な答えはない。俳句作品がその解答なのであり、その成否は作家自身にもわからないだろう。
鶴山裕司
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■




