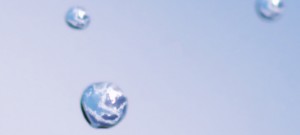 「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」
「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」
辻原登奨励小説賞受賞の若き新鋭作家による、鮮烈なショートショート小説連作!。
by 小松剛生
序文
詩人と呼ばれる人たちに憧れている。
こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。
なぜか。
そもそもの話だ、と僕は思った。
考えてみれば詩人とそうでない人との違いがいまいちよくわからない。
尾ビレを使って泳ぐのがサメ、胸ビレを使って泳ぐのがエイ。
そんなような決定的な見分け方を知らないからに他ならない。
困った。
これではいつまで経っても詩人と会うことができない。
僕は考えてみて、考えてばかりいても仕方がないので、自分の思う「詩人」とやらを書いてみることに決めた。
つまり、この後に出てくる彼、彼女たちは僕が勝手に「おそらくこういう人たちが詩人なのではないか」と推測したことをもとにして描かれた人物たちである。
もちろん、だからといって突如として彼ら(そして彼女たち)は胸ビレを使って泳ぐわけではない。
けれど僕と同じように、詩人とそうでない人との区別に困っている方々が仮にいたとして、少しでもそういった方々のご参考になりさえすれば、僕はそれで満足なのである。
いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする。
君は軍曹
やれやれ。
中野天平が仕事を終えて家に戻る頃、かつてあったドイツ軍のポーランド侵攻よりもよほど恐ろしい出来事が彼を待ち受けていた。
「一時間前からずっとあの状態なのよ」
愛すべき妻の恵美は心底疲れきったという表情で、たくしあげていたセーターを元に戻した。
出産を経てお腹に余分なものがいくらか加わったものの、まだまだ天平を夢中にさせてくれるほどの器量をもつ彼女ではあったが、さすがにこの様子だと迫りつつある老いを隠しきれないでいるようだった。
「なんて言われたってアタシはここを出ないわよ」
みんなウソっぱちなんだわ、と二人の愛しい(はず)の娘がトイレの中で叫んでいた。
「ウソ? ウソってどういうこと。ママはあなたにウソついた覚えはないけど」
「ウソ、それもウソ。知ってるんだから、アタシ」
「なにを知ってるの。言ってみてちょうだい。ママが悪いのなら謝るから」
沈黙が流れた。
天平と恵美はお互いを見つめあった。
しばらくしてからドアが「とにかくアタシはここを出ない」と言った。
「さっきからずっとこんな調子なのよ」
恵美はため息をついた。
若い小娘にはとても出すことのできない、ある種の感慨深さがそこにはあった。
「なにがあったんだい。お前、何かしたのか」
「何もしてないわよ」と、彼の妻が答える前にドアが言った。
「ママは別に何もしてないわ、これは本当よ。何もないし、何もなかった。だからパパはママを責めないでちょうだい」
「ふむ」
彼はまだ仕事着のままだった。
およそガラスと言われるガラスに、耐熱効果や飛散防止効果のあるフィルムを貼るのが彼の仕事だった。
フィルムを貼るためには、ガラスとフィルムの間にゴミが入るのを防ぐため丹念に洗わなければならない。
彼は今日、八十七枚のガラスを洗い、そのうち三十四枚にシルバー加工のフィルムを貼ってきた。
「籠城作戦、というやつだな」
親バカかもしれないがこれはなかなかに有効な作戦だな、と彼は思った。
下手に家出されるよりもなかなかに親を困らせることができる戦法だ。
「感心してる場合じゃないわよ」と、恵美。
やれやれ。
「でもそんなところに閉じこもってどうするつもりだい。お腹も減ってくるだろう、パパとママはトイレぐらいお隣さん宅に借りれば事は済むけど君はどうだ。ご飯はトイレには存在しない。どうにも未来使のない作戦のように思えてならないね」
「未来なんかどこにもないわ」
存在しない未来ならトイレのほうがいくらかマシよ。
その声はいくらか強い調子で廊下に響いた。
「なかなか気の利いたこと言うね」
「だから感心してる場合じゃないでしょ」
すでに日は暮れようとしていた。
窓から射し込む西日の眩しさに、天平は目を細めた。
「ほんとに気にしないで。別にこれはパパとママのせいじゃないわ。いずれこうなる運命だったのよ。二人はご飯食べていいんだからね。アタシはずっとここにいるから」
まったく。
どこでそんな言葉を覚えてきたことやら。
「そんなわけにいかないでしょう」と恵美が応戦する。
おそらくこれも本日何度となく繰り返されてきたのだろう、妻の表情がそれを伝えてきた。
「なんで。食べればいいじゃない」
お手上げ、とばかりに妻は両手を上げてみせた。
ドアの向こうの敵軍に気付かれないよう、こっそりと。
「あー、恵美」
「なに」
「ちょっと彼女と二人きりにさせてもらえないかな。君は夕飯の支度がまだだろう」
「そうだけど、でも」
だいじょうぶ? と妻の唇が動いた。
彼はうなずいた。
「わかったわ」
キッチンのほうへ消えていく妻の背中を、彼は静かに見送った。
西日はもはやかなり低くなり、それにつれて気温も下がっていくのを天平は肌で感じとっていた。
「さて」
「ママは行ったの?」
「ああ、もういない」
彼は腕時計を確かめた。
18時45分。
20時までには決着をつけたい。
それでダメなら今日の勝ちは彼女にゆずろう、学校を一日休むくらいなら構わない。
今すぐにでもシャワーを浴びたい気持ちをグッとこらえて、彼はドアの前に座った。
なにしろガラスフィルム屋は汚れるのが仕事みたいなもんだ。
「ところでパパはすごく疲れてるんだ。お仕事から戻ったばかりでね、何か言うことはないかな」
ドアからはまたしばらく沈黙が続いた。
――これは根比べだな。
根比べでたかだか10歳そこそこの女の子に負けるわけにはいかないな、と決意を固めたものの、敵もなかなかにしぶとかった。
何か声をかけたほうがいいかな、と迷い始めた頃になってようやく。
「ないわ」
「そうか」
小さくすすり泣く声がした。
かすかに嗚咽を漏らしながらもそれを我慢しようとしゃくりあげる音が廊下に響いた。
彼はひどく後悔した。
あの子が父親に抵抗するための返事をするという決断をくだすのに、いったいどれほどの勇気と覚悟が必要だったのかなんて彼には想像できなかったのだ。
今の今まで。
「とても残念だ」
「ええ、残念ね」
それでも気丈に振る舞わんとするドアを前に、彼は「これはもはや少女のそれじゃないな」と思った。
立派な女性である。
「どうしてこんなことになったのかできればパパに教えてくれないか。君が僕とママに責任はないと言ったが、こっちは素直に敵軍の言うことを信用するわけにもいかないんだ。もしかしたら僕とママでなんとかできるかもしれないじゃないか」
「できないわ、絶対に」
「絶対に?」
「ええ、絶対に」
力強い答えだった。
よし、ならばこちらも作戦を変えよう。
「いったいどうしてだい。今朝までのいい子だった君はどこに行ってしまったんだ。今朝、僕が家を出るとき君は僕に「行ってらっしゃい」をしてくれた。帰ってきたらこのあり様だ」
「別にずっと前からいい子なんかじゃなかった。そうすればパパとママが喜ぶのを知っていたからいい子の振りをしてただけ」
そうか。
「そいつは知らなかった」
「知らなかったでしょう」
「まんまと僕は騙されてたってわけだね」
「ひどい娘でしょう?」
今度は彼のほうが黙った。
彼女は果たしてひどかったのだろうか、いや、ひどいのだろうか。
そんなことはない。
仕事から帰った彼に「お疲れ様」と言ってくれなかったのは今日が初めてだ。
そのくらい許せなくてどうするんだ、俺。
やがて時間がきて、彼は答えた。

「ああ、ひどい娘だ」
なるほど、娘の言うとおりだ。
大人というものは、いや大人に限らずみんなウソっぱちだ。
なんてことだ、こんな小娘にモノを教えられるなんて。
「君はひどい娘だ」
「でしょう」
「なら泣く必要がどこにある。君は見事に僕を騙すことに成功していて、今だって僕に一杯喰わせたんだ。悦んでいいのにどうして泣くんだい」
「別に泣いてなんかいないわ」
ウソだね、と彼は思った。
ドアの向こうでは嗚咽としゃくり声の入り混じった音が続いていた。
あのくらいの年頃からすれば、他人に泣き声を聞かれるのなんて恥ずかしいことだろうに。
「そうか、僕の勘違いか」
「そうよ」
「それはすまなかった」
すまなかった、もう一度彼は言った。
「さっきの答えをまだもらってないね。どうか教えてはくれないかな。いったい何があって、いや何もないとさっきの君は言った。言い方を変えよう。何が君をトイレに閉じ込めたままにさせるんだい。それが以前からあったにせよ、君をそこに縛り付けているなにかを僕は知りたい。このままじゃ僕はシャワーも浴びれないし、トイレにも行けない。君もご飯を食べることができない。ちなみに今晩の献立をこっそり教えよう、海老フライだそうだ。我が軍特製の手作りタルタルソースが絶品なことは君も知っているだろう。我が軍の料理長はたいへん優秀な人物なのだ」
そうね、異存はないわとドアが言った。
「ではその正体を教えてはくれないか」
そうね。
「とても建設的な意見だと思うわ」
「お褒めに預かれて光栄だ」
まったく。
どこでそんな言葉を覚えてきたことやら。
「じゃもう一度訊こう。君を閉じ込めているものの正体はなんだ」
「絶望よ」
絶望。
およそ10代の女の子には似つかわしくない言葉だった。
これには天平も意表を突かれた。
――なんてこった。
ポーランドはもはやドイツ軍の手に落ちる寸前である。
「ぜつぼう?」
「そう、まったく何の前触れもなくアタシは気づいたの。世界は絶望に満ちているっていう事実に」
「詳しく話してくれないか」
僕はどうも絶望に関しては君よりも無知らしい。
「これはとても恥ずかしいことだ」
「仕方ないわね、教えてあげる」
「ありがとう、おっとその前に」
「なに」
「灰皿を取りに行っていいかな。じっくりと君の話を聞きたい」
「いいでしょう、許します」
敵軍の許可をとりつけた彼はキッチンのほうへと、わざと足音を立てて歩いた。
鍵をかけた向こう側までちゃんと聞こえることを意識した。
「やぁ料理長、首尾はどうだい」
「その様子だとそっちはあまりうまくいってないみたいね」
埃にまみれた仕事着のままでいる天平を見て、妻が呆れたように苦笑していた。備え付けのテレビでは巨人対ヤクルトの野球中継が流されていた。今日もヤクルトは負けていた。別にヤクルトファンというわけではないが、天平はヤクルトの本拠地である神宮球場の改修工事も過去に経験があり、そういう意味ではなんとなく思い入れがあるチームだった。
「苦戦している。小娘だと思っていたがなかなか手強い」
「ついこの間までこんなだったのよ」と、彼女はまん丸のキャベツを掌に乗せてみせた。
まったくだ、と彼も答える。
「あの子がまだオムツしていた頃、僕の仕事用メモ帳に落書きしたことあったろう」
「懐かしいわね」
「あのせいで発注元の連絡先をもう一度訊き直さなくちゃならなくなった。そんな幼稚なイタズラしてたガキんちょが、今じゃもう僕らを手玉にとってる」
絶望、だってさ。
絶望、ねぇ。
妻はキャベツをミジン切りしながら呟いた。
包丁がまな板を叩く、小気味良い音が続く。
「援軍は?」
「いらない」
彼は戸棚にしまってある灰皿を取りだすと、ゆっくり廊下を歩いてトイレの前に座った。
辺りはすっかり暗くなっていた。
「ふむ」
かすかに寝息が聞こえてきた。
無理もない。
僕とやり合う前に妻と数時間の交戦を経て、の今である。
床の冷たさが彼に現実を突きつけていた。
天平は待つことにした。
彼女が目覚めたら二人で絶望について語り合うのだ。
そして人生の儚さについて愚痴をこぼし合うのだ。
いつの間にか、彼はシャワーを浴びることをすっかり忘れていた。
自分が深い喜びに包まれている事実に彼自身はまだ気づいていなかった。
彼は待った。
寝息が。
止んだ。
おわり
そのサメはビートルズのファンだった
そのサメが横断歩道を渡っているのを見たのは、ある年の夏も近い時期のことだった。
サメは、とても丁寧にそこを渡っていた。
新聞を小脇にはさんだスーツ姿の男やらスマートフォンをいじっている高校生のそれらとは全く違い、サメは他に何をするでもなく横断歩道を渡るという行為に勤しんでいるように見えた。
――いまだかつてこんなにも真剣に横断歩道を渡るものがいただろうか。
僕は少し、いやかなり驚いてその様子を二度見、三度見と繰り返した。
相手がサメだからか。
それともその真剣さに気をとられたが故か。
もしくはその両方かはわからないが、目を奪われずにはいられない何かが彼にはあったということだ。
サメ。
昔、図鑑か何かで読んだことがある。
サメが人を捕食する確率は自動車での死亡事故よりよほど低いらしい。
では。
サメが横断歩道を渡る姿を目撃する確率はいったいどのくらいなのだろうか。
周りの人たちは誰ひとりとしてサメに注視するでもなく、各々が普段通りらしき行動をとっている。
さっきのサラリーマン風の男はネクタイピンの位置が気になるらしく、何度かそこに手を添えて微妙に直している。
どうやら世界は僕の知らないところで日々、変化しているらしい。
と、するとさきほどの確率論も当てにはならない。
なにしろ僕が図鑑を見たのはひどく昔の話なのだ。
横断歩道を渡り終えたサメはひと仕事終えたとばかりに少し立ち止まると、ちいさなため息を吐いてみせた。
音のしない、吐息だけが漏れるやつだ。
美しかった。
これは僕の持論だが。
音のでるため息はどうも、なんだかあからさますぎて厭らしい。
そばにいる連中に「さあ心配しなさい」とでも号令をかけているような気にさえなる。
はぁ(さあ心配しなさい)。
はぁ(さぁさぁ心配したらどうかね)。
それをするくらいなら最初から「頼む。今から僕のことを心配してくれないか」と願い出てくれたほうがまだ幾分かマシだった。
それならばこちらも「おう、そうか。では心配しよう」と大いに心配を重ねてみせるものを、いじらしい振りなのか「はぁ」などとは。
それでは心配なんぞしてやるものか、と妙な啖呵を切るはめになる。
サメは違った。
美しいため息だった。
ヘミングウェイの長編を読み終えた後の決定的な何か、そんなものが彼のため息からは垣間見えるのだ。
サメもずいぶんと文学的な生き物なようだ。
「あの」
初対面の人間、ましてや初対面のサメに話しかけるのはなかなかに勇気のいる行動だが、不思議とそのときの僕にためらいはなかった。
「はい」
サメは男とも女ともつかない、中性的な声色をしていた(さきほど僕が「彼」と書いたのはサメという生き物から僕が勝手にイメージした結果の産物であり、多分に偏見が含まれていることは否定しない)。
「なんでしょうか」
「その、なんていうか」
――あなたの横断歩道を歩く姿が美しかったので、思わず声をかけてしまいました。
なんて言えるはずもなかった。
つくづく人間とは厭な生き物だと思う。
己の何処に出すともわからない見栄のために小さな嘘を平気でついてしまう。
「あの、サメが横断歩道を渡るなんて珍しいなって思って。どうして渡っていたのかなって」
サメは首をかしげながら言った。
「それはもちろんその方向に私の行きたい場所があったからですが」
「あ、そうじゃないんです。サメのあなたからしてみれば、横断歩道を歩くという人間の規則に従うなんてナンセンスに思えるんじゃないのかなって気になったんです」
最後に「ごめんなさい、なんだか失礼なこと言ってしまっているかもしれません」と付け足した僕に、彼は何かを納得したのか「ああ」と笑顔でうなずいてくれた。
紳士だ、と僕は思った。
「つまり君はこう言いたいんですね。「サメが人の敷いた道を歩く必要はないのでは」と」
「失礼をするつもりはないんです。ただ本当に気になって」

「かまいません。むしろ私たちサメ界に興味をもっていただいて光栄です。いくら生物学的な歴史があろうとも、人の中に混じってしまえばどうしても少数派になってしまいますからね」
彼(そう呼び続けることをどうか許してほしい)は無礼千万な僕にもごく自然に接してくれた。
――やはり。
紳士だった。
僕はサメに対する自身の評価を改めなければ、と心の奥底で反省した。
「横断歩道を渡る理由も、あえていえばそれに尽きます。私たちは少数派、つまりは部外者といっていい。別に私自身、大したサメではございませんが、良くも悪くも私の行動ひとつで一般的なサメのイメージが決定し兼ねないことは十二分に理解しているつもりです。サメとして、私は常に自覚ある行動を心がけています」
――現にあなただって、私を見てサメという生き物の生業を決めてしまうでしょう。
彼は冗談交じりに笑った。
「確かに」
僕は彼の頭の良さに舌を巻いた。
「それにしても暑いですね」
6月だった。
先週訪れた台風の湿り気が、街路樹のクヌギの幹から漂う独特の臭みを強めていた。
駅前の広場では子供連れの家族らしき人影が目立って多かった。
その日は日曜日だった。
「もしよければ」と、サメは言った。
「近くで一杯飲みませんか」
「日曜の昼間にやっている店があるんですか」
「いい店を一軒だけ知っているんです」
――私の用事も急ぐ種類のものでもないですし。
促されるまま、僕はサメと一緒に大通りを歩き、10分後にはとある小さな路地から地下へと続く階段を下りていた。
案内されたドアを開けるとなるほど、そこは静かな、余計な音楽など一切かかっていないバーであった。
室内の隅には小さなテレビが置かれていて、野球中継を映していた。音声は無かった。横浜球場でのヤクルト対DeNA戦だった。打者の畠山が豪快なスィングで三宅の速球を打ち、ショートゴロのダブルプレイを取られていた。
客は誰もおらず、バーテンダーがカウンターの内側でひとり、氷を砕いていた。
「ダイキリを」
「じゃあ僕はビールで」
「かしこまりました」
ダイキリを飲むなんて、ますますヘミングウェイ気取りじゃないか。
出されたビールはとても冷たかった。
現実じゃないんじゃないかと思わせられるくらいの冷たさだった。
「サメもカクテルを飲むんですね」
「もちろん」
暗い空間で、サメの小さな目が妖しく光っていた。
「横断歩道も渡るし、カクテルだって飲みます。ビートルズも聴きますよ。好きな曲はイン・マイ・ライフです」
僕はカクテルなんて普段ほとんど飲まないし、ビートルズのアルバムなんて一枚も持っていない。
彼のほうがよほど人間界に馴染んでいるようだった。
「なぜその曲を」
「タイトルが洒落てるじゃないですか」
なにしろ実際に曲を聴く前から好きでしたから。
「聴く前から?」
ええ、と当然のことのようにサメはうなずいた。
「言葉とはこねくり回しすぎるとろくなことになりません。かといって大げさに書き過ぎると抽象的すぎて、私のような平凡なサメには理解できません。それでイン・マイ・ライフです。どうです? 最高じゃないですか。私はいっぺんに気に入ってしまいましたよ」
ビートルズに思い入れがあるのだろう。
酒のせいもあるかもしれない、彼の口はよく回った。
僕はサメの話を訊きながら、さっきから氷を砕き続けているバーテンダーの手元を眺めていた。
バーテンダ―は氷の塊をひととおり砕き切ってしまうと、冷凍庫から新たな塊を取り出してまた砕き始めるのだった。
「あなたはどうして」
サメは訊いてきた。
「私に声をかけることに思い至ったんですか」
「さぁ」
自分でもよくわからなかった。
「こんなこと言うと、なんていうか、キチガイだなんて思われるかもしれないですけど」
なんだか、僕と似ている気がしたんです。
「サメである私と?」
「はい」
サメはカウンター脇にある灰皿に胸ビレを伸ばし、ゆっくりとタバコに火をつけた。
手慣れた動作だった。
「これは私の勝手な推測なんですけどね。もしかしたら」
「もしかしたら?」
あなたの中にも何かサメ的な要素があるのかもしれませんね。
「サメ的な要素」
「そうです。それが私とあなたを引き合わせた。少し安っぽい結論かもしれませんが、日曜日の昼間にしてはちょっとばかし刺激的な展開じゃありませんか」
僕の中のサメ的な。
それはとても魅力的なものに思えた。
「サメであることは、幸せですか」と、僕は訊いてみた。
「ではあなたは自分が人であることを幸せだと思いますか」
「考えたこともありません」
それと同じです。
サメは幾分柔らかい笑顔を向けてきた。
彼なりの気遣いなのかもしれない。
サメはタバコの灰を灰皿に落とした。
バーテンダーは僕が見る限り計4個目となる氷を砕きにかかっていた。
僕とサメは出会った交差点にて別れた。
あたりはすっかり夕方になっていた。
「ではまた、いつか」
そう言って、サメは自身が向かう予定だった方向へと再び歩き出した。
「はい」
結論から言う。
二度と彼と会うことはなかった。
だいぶ後になってその日曜日のことを思い出した僕が案内されたバーにひとりで行ってみると。以前氷を砕き続けていたバーテンダーはおらず、初老近くの女性がカウンターの内側に立っていた。
「ビール」
「かしこまりました」
出てきたビールは生ぬるかったが、ほどよい温度ではあった。
テレビは相変わらず野球中継を映していたけれど、ヤクルトの畠山は怪我のせいでレギュラーから外されていた。
何もかもが少しずつ違っていた。
僕の中のサメ的な何か。
それが僕とサメとを引き合わせたのだとすれば、どうやら僕はそれをすっかり失くしてしまったらしい。
「もう一杯」
僕は空になったグラスを自慢のヒレでつかんで、彼女に差し出した。
おわり
小さじ一杯の答え
その疑問は小さじの形をしていた。
銀色で一本調のそれはスプーンというよりも、やはりさじだろう。
口に含むには角の丸みが少なすぎるし蔓のような装飾もなく、言ってしまえば味気ないものだった。
近ごろ複雑な疑問が増えていくなかで珍しい、とニワさんは思った。
――世の中が複雑になれば、疑問もまたそれなり。
親方の言葉である。
「なるほど」
ニワさんは小さじの疑問を手にとって眺めてみた。
なにかほんとうにささやかなものをすくうことぐらいにしか使えなさそうな、その程度の小さな疑問であった。
ニワさんの仕事は疑問を拾うことにある。
疑問、といっても非観想的現象学に乗っ取った思想的な話ではない。
文字通り、疑問を「拾う」のである。
一口に疑問といっても内容如何によって姿形は全くといっていいほど違ってしまうので一般人(親方曰く「素人」)たちの目には単なるガラクタにしか見えない。
――いや、むしろ疑問なんかガラクタそのものなのかもしれない。
ときどきそんな思いに頭を巡らされながらも、ニワさんは疑問を拾い続けている。
それはビー玉であったり、食卓用布巾であったり、中には書店名ロゴの入った紙袋であったりする。
それらは一見するとビー玉や布巾や紙袋でしかないのだが。
いいか。よーく目を凝らして、目線の角度を変えたりして見分けるんだ。そうすりゃほら」
親方はよくそう言うと地面に這いつくばって疑問をことごとく見つけてみせてくれた。
見習いだった当時のニワさんが実際に手にとってみると、果たしてそれは疑問となってようやく本来の姿を現すのだった。
「ふむ」
そしてこの小さじである。
正確にいうと小さじの形をした疑問であるが、今までに触れたどの疑問よりも「そのもの」との見分けがつきにくい代物だった。
よく見つけたものだと自分でも感心するほどに、それは小さじに近かった。
――いったいどれだけささやかな疑問だったのだろう。
塩ひとつぶほど。
それとも胡椒ひとつぶくらい?
残念ながら疑問が結晶化してしまった今となっては、それの内容を知る術をニワさんはもたない。
ニワさんの仕事は疑問を拾うことであって、結晶化したそれらから疑問を取り出したり吟味したりすることではないのだから。
「こりゃまた見事な」
拾い集めた疑問は研磨工場にて削られ、また新たな形を伴って一般の人々に売られてゆく。
その工場を取り仕切る守谷所長は小さじ型の疑問を見て顔色ひとつ変えずに、言葉でだけ驚いてみせた。
「じゃぁこれが今日の分だね」
時に人造人間と呼ばれるほどの無表情さは所長の特徴であり、ニワさんにとって話しやすい相手ではあった。
不景気とされるこのご時世にあって、仕事の絶えないニワさんのことを影でいろいろと言う輩もいた。
それが世のせいなのかニワさん自身に問題があるのかはわからないが、同じようにどこか噂の矢面に立たされる守谷所長にはどこかしら似た境遇を感じ取っていたのかもしれない。
とにもかくにも。
ニワさんは日々、疑問を拾うだけだ。
「これは削るのやめとこう」
帰り際、所長から小さじのそれを「倉庫に持っていってもらっていいかな」と渡された。
うなずいたニワさんが表に出ると、辺りはすっかり暗くなっていた。
工場にぶら下がる蛍光灯の明かりが、蒸し暑い空気の中でやけに目立っていた。
「これが疑問、ですか」
僕にはさっぱり分からないな、と文学君は手のひらで小さじを転がした。
彼はニワさんの住むアパートの数軒ほど離れた大きな家屋で暮らしていて何を隠そう、隠しようもないほどの資産家であった。
普段は本ばかり読んでいるのでニワさんは文学君、と呼んでいる。
――世界中の疑問を並べてみたら、どんな景色になるんでしょうね。
初めてニワさんから仕事の話を訊いた文学君がそんな恐ろしいことを言った。
「世界」だとか「運命」だとか、形にはならない言葉を彼は好んで用いた。
「やめて」
ニワさんは苦笑した。
「そんなのひとつひとつ拾う手間を想像したらうんざりするだけだから」
「大変なんですねぇ」
文学君は目を輝かせながら何度もうなずくのだ。
「でもどうして持ち帰っちゃったんですか」
「親方に知れたらひどく怒られるだろうねぇ」
普段は下着の裏表さえ気にしないほどのテキトーな人ではあったが、こと仕事に関してはびっくりするくらい几帳面だった。
仕事に関してだけいえば、所長と親方はよく似ているといってもいいほどだった。
仕事だけ、ではあるけれど。
ニワさんは文学君の家の夕食に招かれている。
汚れた作業着を洗濯機につっこんでいるところ、脱衣所の窓を開けた顔だけの文学君に声をかけられたのである。
――無頓着というか節操無し、というか。
お金持ちという事実に関係しているのかいないのか、とかく文学君は時間も場所も気にしない様子で用件を告げてくるタイプの青年で、それもどこか浮世離れした文学君らしいといえば、らしい態度だった。
がらり、と音がした方向に振り向けば文学君が窓から顔を出している。
「下着はちゃんと自分のサイズに合ったやつ着けたほうがいいですよ。それ、自分のバストサイズより大きいやつでしょ。ちょっと余ってるじゃないですか」
「うるさいな」
――無頓着というか節操無し、というか。
「自分でもびっくりしてるの、それを拾えたことに」
守谷所長だってやっと見極められたほどの難しい疑問なんだからとニワさんは口に出してから、それが本当の理由としてもっともらしいことに驚いた。
たった今、考えたにしては上出来だ。

二人は小さな食卓を囲みながら、プロ野球中継を観ていた。すでに交流戦が開幕していて、今季の快進撃を起こしていた広島はオリックスに七点差をつけられていた。「今日負けてしまうと泥沼の五連敗です」と実況アナウンサーが熱を帯びた口調で話しているのを二人でぼんやり眺めていた。
なんだか家族みたいだ、と勝手に思ったニワさんは勝手に顔が赤くなるのを自覚した。
「ってことは疑問なんですね、やっぱり」
「まぁね」
いつだって文学君は疑問であるという事実に感心しているようだった。
それがニワさんには少しさみしい。
少しだけだから特に文句があるわけでもないが。
「こんな小さなさじで何をすくおうとしたんでしょうね」
「そりゃぁ」
ニワさんは目の前の皿にある蓮根炒めをつまんだ。
「疑問の答えとか何かじゃないかな」
「なるほど」
小さじ一杯の答えってわけですね。
文学君は頬を緩ませ嬉しそうに笑ってみせる。
やっぱり、とニワさんは思った。
少しさみしい。
八月も終わりに近づくと、拾うべき疑問も売れる疑問も一気に増える。
残暑が人を感傷的にさせるんだよ、とは親方の弁であるが忙しくなるのは確かである。
多くの疑問拾い職人の例にもれず、ニワさんも深夜まで働いて次の日にはまた朝から拾いはじめるといった日々が続いた。
「お疲れさん」
所長も珍しく顔を汗で真っ赤にしながら、職人らが持ち寄ってくる大小さまざまな疑問の対応に追われているらしかった。
お疲れ様です。
はいお疲れ。
お疲れ。
お疲れ。
人の流れが一段落着いた頃、所長がビニール袋片手に近づいてきた。
「ひとつどうぞ」
「どうもです」
袋の中身は大量のアイスキャンディーだった。
皆にも配ってあげて、と工場で働く若い連中に袋を任せると、所長自身もアイスの封を開けにとりかかった。
コーヒーの色をしたそのアイスはバニラ味で、バニラアイスは白いものだとばかり思っていたニワさんはちょっと面食らいながらもそれをかじった。
所長もどうやら同じものを口にしていた。
「この前の小さじのやつね、覚えてる?」
「ええ」
「あれ、削ってみたらほんと小さい疑問でね。ここ数年じゃ一番かもなぁ」
「へぇ」
世間話程度に守谷所長は告げる。
疲れきったニワさんにその真意はわからない。
アイスが冷たい。
「あ、これバニラなんだ」
ふと漏れた所長の一人言にうなずく。
「コーヒーみたいな色してるのにね」
「そうですよねぇ」
「なんでだろうね」
「なんでですかね」
すくう必要もないくらい小さな疑問は、やがて民家のほうから流れてくるテレビの音に紛れてしまった。
夜、電話のベルで起こされた。
ディスプレイの番号表示蘭に母の名前を見つけたニワさんはそのまま布団にくるまった。
留守録に吹きこまれた母の声が聴こえてきた。
「無理にとは言わないけど、お盆は帰ってこれなかったんだから合間を見つけ帰って来んしゃいよ。お父さんにお線香の一本でもあげてやってちょうだい。それと」
録音時間が20秒しかないため、声はそこで途切れた。
無視して正解だった、とニワさんは思った。
もし出ていたらまた口論になりそうな気がした。
父が死んで以来、それまであまり自分の意見を表に出さなかった母は急に娘に連絡するようになった。
寂しさからか、それとも何らかの使命感(もしくは義務感?)からか、それまでそんなおしゃべりだとは思わなかったニワさんは母の変化に少なからず驚いた。
――母も「うるさい人」になってしまった。
父の隣に黙って立っている母の背中が、ニワさんは嫌いではなかったのだ。
――でもなぜ。
その疑問は結晶化されませんように。
祈ることしかニワさんにはできなかった。
その年の繁忙期が静まったのは、肌寒さを感じ始めた十月も末のことだった。
工場を後にする途中、またいつものように倉庫に寄ってからニワさんは帰途についた。
日が暮れるまでまだ少し間があった。
「ニワさん」
路角から急に文学君が顔を出した。
「そこはウチの窓じゃないんだよ」
「おもしろいものが手に入ったんですよ」
相変わらずの文学君はニワさんの手に何かを握らせた。
――あれ。
それは小さなさじだった。
「ずいぶん前に見せてくれた疑問にそっくりなやつが、今日行った雑貨屋で売ってたんですよ」
「まったく」
おそらく使い道など考えもしなかったのだろう。
――お金持ちはこれだから。
いや、と考えなおす。
文学君ならお金がなくともその場で買ってしまいそうな気がした。
「どうです」
似てるでしょう、と嬉しそうに訊いてくる文学君に、ニワさんは仕方なく「そうだね」と頬を緩ませてみせた。
ああ、そうか。
母の静かな背中が頭を過ぎった。
銀色の光沢に反射した自分の文学君を見る眼は、あの人の父を眺めるそれに似ていた。
小さじ一杯程度の疑問がニワさんのどこかからこぼれた。
道端に落ちて、音もなく消えていった。
おわり
(第01回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『僕が詩人になれない108の理由あるいは僕が東京ヤクルトスワローズファンになったわけ』は毎月24日に更新されます。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
