ザ・詩画集である。成立がなかなか難しいと言われている、あの詩画集だ。なぜ難しいかと言えば、詩と絵の創作者同士のエゴのぶつかり合いがいかんともし難いからだろう。ただ自分の方が目立ちたいという、いわゆるエゴでなくても、こうあるべきだという美意識が一致する方がまれだと思わなくてはなるまい。
そんな幸福が訪れるには、きっとそれなりの理由がある。『水の領分』の場合はわりと単純で、二人が父娘だということだ。それは羨ましい、幸福な光景である。父・憲二の出自と来し方を記した後書きのタイトルは「至福」であって、それにふさわしい。


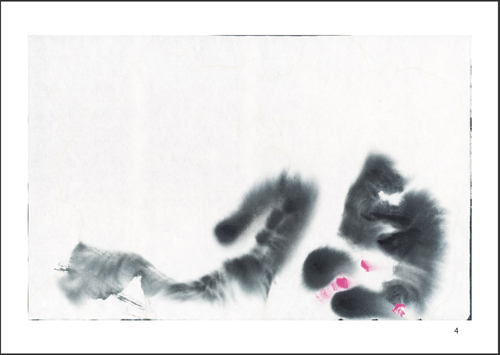
父娘という関係性、成立の状況ということでは、以上に尽きる。しかしそれが幸福な光景であっても、一冊の書物として幸福なものになるかどうかは、手に取る者に幸福感が伝わるか、という一点にかかる。小原眞紀子が孝行娘であることは、他人を感心させ、羨ましがらせることはあっても、書物としてはその感情や感慨のうちに消費されるに過ぎない。当然のことながら、小原眞紀子はそれを警戒する。そのとき彼女は娘ではなく、一人の創作者である。
創作者として、父親の画業を評価し、詩行とともに編集する作業は彼女にかかっている。そこがぶつかり合わない統一感の理由ではある。しかしそれは支配関係ではない。詩行の書き手として、詩人は憲二の絵の持つ言語以前の力を大前提とし、それをこの書物の根拠、正統性として完全に依拠している。つまりこの書物は間違いなく憲二の絵のためにあるのだが、一方でその成立は詩人の絵に対する評価に依っている。ここでの詩行は絵を評価するためのものであると同時に、これらの絵の持つ無意識に近い力によってのみ生み出されたものだ。
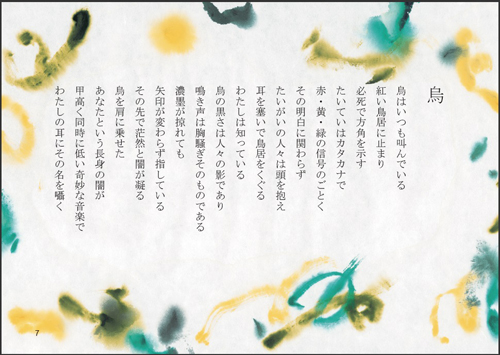

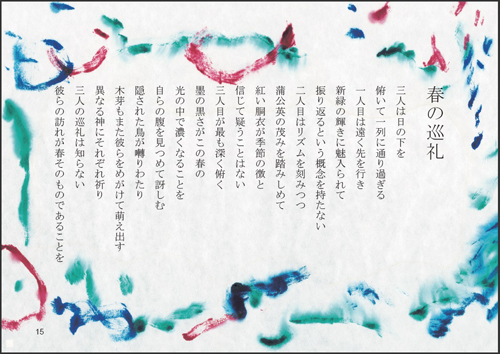
父・憲二が脳梗塞を患い、そのリハビリを兼ねてというのは、いかにも凡庸な物語に過ぎないし、それに安心できるのは芸術一般に無縁の者だけだ。「アウトサイダー・アート」といったラベリングも同じことで、自分はインサイドの隅っこにでもいるという幻想でもなければ、とうてい使える言葉ではあるまい。そのセンスのない訳語の源となったアール・ブリュット、すなわち「生(き)の芸術」という語はしかし、偶然かもしれないが、その絵の呼び名として相応しいように思える。
当たり前のことだが、子供や老人、障害者であれば誰の絵であってもアール・ブリュットと呼べるわけではない。社会的な力やそれを行使する健康を欠落させ、すなわち死に近づくことで逆説的に生の輝きを得る、それには生まれながらの感受性、才能を要する。つまりはそのような恩寵のインサイドにいるわけである。凡庸な社会のインサイダーこそがそこではアウトサイダーだ。

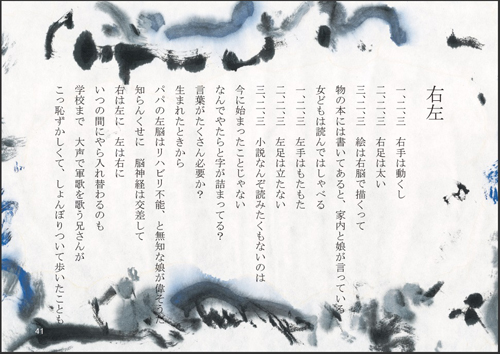

恩寵に恵まれた者に対し、ならばその才能の評価には容赦する必要はあるまい。憲二の絵についての小原眞紀子の選択眼は、純粋に言語的な判断である。新たな言語を生み出す無意識が醸造されているかどうか、その一点にかかる。娘ではなく、詩作品を創り出さなくてはならない者として追い詰められるからである。
その手になるあとがき「至福」が冷徹な言葉で描写されているのも、しかしそれが「至福」と題されているのも、死が近づいた憲二の生から、永遠なる何ものかを抽出しようとする手つきに他ならない。それはもとより絵が上手かったという憲二の才能から病いと年齢の力、偶然と直観の導きによって、多くのものを捨て去る作業であったに相違ない。
金井純
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■






