 偏った態度なのか、はたまた単なる変態か(笑)。男と女の性別も、恋愛も、セックスも、人間が排出するアノ匂いと音と光景で語られ、ひしめき合い、混じり合うアレに人間の存在は分解され、混沌の中からパズルのように何かが生み出されるまったく新しいタイプの物語。
偏った態度なのか、はたまた単なる変態か(笑)。男と女の性別も、恋愛も、セックスも、人間が排出するアノ匂いと音と光景で語られ、ひしめき合い、混じり合うアレに人間の存在は分解され、混沌の中からパズルのように何かが生み出されるまったく新しいタイプの物語。
論理学者にして気鋭の小説家、三浦俊彦による待望の新連載小説!。
by 三浦俊彦
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 終電がなくなってしばらくたった時刻、乗り遅れた会社員たちがタクシー乗り場にのろのろと並びつつあるバスターミナル角の飲み屋の裏道、ふと自販機コーナーの陰、いかにも死角といった物陰の境のあちら側を何気なく覗くと、なにやら人間が縦横に一塊になっているような不思議な光景が。どうもこっそり近寄ってみると、横の部分は酔いつぶれた男の体、ネクタイを半分ほどいた乱れ背広腹であり、縦の部分はセーラー服の重なり合いであり、薄暗がりに目を細めて察するに、泥酔男の顔面のあたりにJKたちが輪になって外向き背中合わせにしゃがみこんでいるようなのだった。六人ほどか。集団で壁を作り、囲った中にもまだ誰かうずくまっているらしい。沈黙する女の集団というのが稀であり不気味であることをはじめて思い知った瞬間である(男の沈黙集団とは何度か心地よくすれ違ったことがあったが)。むろん袖村もこれまでの経験が経験なので、そう、この沈黙女子集団がやっている不可解な行為は「あの種のこと」だな、ということがもちろんすぐ察せられた【袖村のノートより】。おのがビジュアル体質というか目撃体質というか、とにかく遭遇体質を鬱陶しく感じていた頃で、もうこれ以上目撃談が積み重なるとろくなことがない予感がしていたので、なるべく見ないように、集団の中央部を視界に入れないようにそそくさと立ち去る袖村であった。冬の寒空だったので、その視覚像の鮮烈さがなおさら想像されたのである。

ともあれ袖村は、同じような女子高生スクラムを、場末の自販機コーナーとガードレール陰にてその後たてつづけに四回目撃した。いつも、少し離れて見張りらしき少女が二、三人、街路の方を伺っていた。
袖村の体質的運命に鑑みて、街中で誰も気づいていなかった「これ」を目撃するのは当然というかむしろ遅すぎたとも言うべきなのだが、それにしてもいつものビジュアル体験とは異質っぽい連続ビジュアル導入に戸惑い、なにやら己れの因縁の特異体質に由来しつつ拮抗する何者かの、あるいは何者のでもない「場」のパワーが作用する磁界に自ら迷い込みつつあることを感じ取って、袖村は微妙に戦慄した。五回目の目撃時、そのときも自販機コーナーの一番奥で、袖村はむ、森永製菓の自販機は珍しい、今どき缶烏龍茶も珍しい、と仙人五人の図描かれた「芳麗香烏龍茶」深紅缶を購入し腰に手を当ててごくごく飲み始めたとき(茶葉原産地中国福建省。富士山系のおいしい水使用。袖村の趣味の一つは340ml烏龍茶缶収集なのである。ビジュアル体質と烏龍茶色との因果関係の向き如何は別として相関関係自体は明らかだろう。百六十種に及ぶ340mlの色、味、香りを克明に整列分類した習作小説もものしていたが、アサヒ飲料株式会社「優(ゆう)」白薄青緑缶(茶葉原産地台湾。包種茶使用。コールド専用)に時間の経過によりお茶の成分が沈殿したり、液色が濃くなる場合がありますが、品質には問題ありませんと記されてあるのを見てから色スペクトル表作成は中止していた。そのぶんビジュアル体験における色彩への注目度が増しており、このときは真っ先にまず)渋め鮮やかの黄土金(ちょうどサッポロビール株式会社「鉄観音茶」(香気清冽、滋味芳醇・鉄観音100%)スチール缶の色を思い浮かべればぴったりであろう)がどろどろと、そして人参風赤粒鏤った正統黄土色(ちょうど三国フーズ株式会社「アクアマリン烏龍茶」(赤チャイナ服の人物・茶もてなしの図・芳香馥郁、請君品賞)アルミ缶を思い浮かべればぴったりであろう)がにゅるにゅるにゅると、その二体の粘流がDNA二重らせん状に絡まりあいながら迸ってくるのに視界の焦点が合ってしまったのである。その物質の本体はこってり濃い焦茶色で、物陰から人喰いアメーバのように袖村の足もとに輪郭を押し寄せてきていた。

「ああ、やっぱりこの系統だよな……」
目にしてしまったものは仕方ない。袖村は諦めて、いつもながらの目撃に身を委ねることにした。視野に入ってきた本体ももちろん「その種」の光景だったのである。
路上仰向けに足裏蟹股に合わせた細身長身背広男の顔面が、見事な円盤というか円錐というか、埋めつくされていた。山吹色と焦茶色の二色折半されたピザというかホットケーキというか、予想どおりの冬季気温効果、モワモワモウモウと鮮やかな湯気がこれでもかと立ちのぼっている。街灯も店頭看板の光も届かぬ闇の底で、水蒸気は自らの光を放って黄褐二色盤面色組織をくっきり照らし出している。半端でない濃度の蒸気的輝きが、ふたりの体内健康を余さず指し示していた。そう、ピザ顔男の傍らに、ふたりの制服JKがたった今まで背中合わせにしゃがんでいた的深い溜息をつきながら、屈み姿勢でスカート腰回りをそそくさと調えていたのだ。二人とも極平凡無個性ながらどちらが山吹色の産み手でどちらが焦茶色の産み手かが一目瞭然の対照性を示すという、不思議な第一印象だった。自販機陰でまさか見つかると思っていなかったのか少女二人は「あ……」闖入者袖村とお互いとを交互に見やるばかりの呆然顔。今まで袖村が出会い続けていた六~八人スクラムはなにやら恐怖だったのに比べ、ここは素朴顔の少女がただ二人。がっちり多人数スクラムのように見張りを立てることもせぬ無防備体勢がこの道初心者という風情でほんのり安全感親近感、フム黙って立ち去るよりいっそこのさいと袖村は決意して、
「……一体、何、やってるの……?」
ぎこちなく好奇心を解放する羽目になったのである。袖村にとっても少女たちにとっても幸いだったのは袖村の烏龍茶色の視線が、酔いつぶれ背広男の顔面をズッシリ覆う黄褐二色上未消化人参粒散る大黄金芸術の輝きに再び吸引され、「うーん……、きれいだなあ……」本心からの感嘆声を吸い出すことができたこと。少女二人はたちまちホッと打ち解けて、二十分後には駅前のビル四階の深夜喫茶窓際隅の席に人の耳憚ることなく会話できる状況に三者身を置いていたのだった。

二人はこの道は浅いわけではなく、以前からたびたび見よう見まねで携わってはいたが、二人でチームを組むようになったのはひと月ほど前だという。
あまり要領を得ない話を総合して袖村が察したところでは、「この道」を最初に始めたのは某他校のギャルたちで、援交の相手がたまたま「この趣味」だったことからこの「自主バイト」を思いついたのではないかということだった。嬉しい盲点だったというか、「妊娠や病気の心配がないこんな楽なプレイ」で稼げるならいくらでもやったろうじゃないのと、路上で酔いつぶれているオジサンの顔面に、一日分の体内発酵物質をたんまり盛ってあげて、その報酬として財布からいくらかを戴いてゆくのである。むろんいかに統計的常識に欠ける今どきのJKといえども、路上に横たわっている見ず知らずのオジサンがたまたま「その趣味」の人である確率がそう高くはないだろうことはわかっていた。だから普通ならばそんな非理論的な「自主バイト」が普及したはずはない。ところがブレーンがいたのだった。切っ掛けとなった援交相手による冗談交じりの入れ知恵だったともいうが、とにかく道徳的にこの消化器系アルバイトが成り立つべき理論的根拠があるというのだった。その鍵は「期待値」である。
なるほど行きずりのオヤジが「この趣味」を持つ確率などそう高かろうはずがない。すなわち酔いつぶれから目覚めたとき、「そんなもの」を顔面にてんこ盛りされていることを知って喜ぶ確率はむしろ低い。ところが期待値の理論によれば、確率の低さは、効用の高さによって補うことができる。当たる確率が1万分の1のクジでも、賞金が1億円であれば、1万円払っても買う価値があるというわけだ。酔いつぶれているオジサンが「その趣味」である確率の低さを補うには、万一「その趣味」であった場合に喜ばせる度合いを高めればいい。「その趣味」の歓喜度を決める最大要因は、なんといっても「物質の量」であることは彼女らもなんとなく知っていた。そこで、ブツ量を増やせばよいという理屈になる。ブツ量大なれば、賞金の高いクジさながら、当たる確率は低くても万一当たった時の、つまりターゲットが「その趣味」だったときの喜んでもらえる度合いが高まり、この「自主バイト」は期待値的にフェアな仕事として成立。幾万円を戴くに値する仕事となるわけである。
期待値押し上げのためのブツ量増大には、もちろん、人数を増やせばいい。というわけで、集団でお腹の調子を整えて、ターゲットの顔面に物質をシンクロ盛り上げというワザが開発されたのだった。通常の援交と違って面倒な会話などせずにすむ一方的コミュニケーションなので、人見知り激しいオタクギャルたちにも好評なバイトとして広まっていったのである。吸収不全のノンシュガー系甘味料を含んだ『テイカロキャンディ』などヘルシーなアイテム摂取でお腹具合を常に臨戦体勢に調え、おかげで皆体調もよくなり、新奇なチームワークによって友だちづきあいも楽しくなり、古典的援交女子に比べH系の体の張り方をしなくていいぶん堕落感の囚われもなく、産み落としたブツの品質を自主評定しつつ財布から抜き取るべき報酬額を良心的にそのつど算出する期待値計算の納得努力を重ねるうちに数学の成績も上がり、いいことづくめだったという。
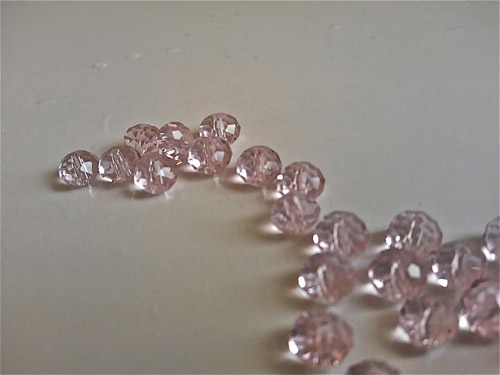
ターゲットが「その趣味」だったときに感じてもらう喜びを増加させるため、現金を抜き取った財布にはプリクラを入れておくのが暗黙のルールとなった。もちろん足がつかぬよう顔は切り取ったり塗りつぶしたりしておいたものの、こんなプリクラを携行している人種は写真に写っているとおりの現役JKに他ならないと確信させて、年齢性別定かならぬ通り魔的狼藉という可能性を排除してやる思いやりだった。
「しかし君ら二人だけにしてはさっきの、とんでもなく量が多かったようだけど?」
それは「先客」の残したブツ量の上に追加したからであるという。以前は、先客のブツをどかしてから、新たに自前のブツ量を盛り上げるという、いわばJKどうしの縄張り争いというかマーキングというか手柄の上書きというか、そんな慣例だったというが、そうした野生の排他的風習は「ブツ量で期待値を確保」というこのバイトの核心的倫理を破壊することが気づかれ、今は科学的な多層追加方式へとみな移行してきたのだという(科学的どころか袖村にしてみれば他人のブツをどかす手間の要らぬぶんむしろナチュラルな方式だと思われたのだが、夜行性JKの本能的嗅覚論理はわからんものである)。ともあれ、先客ブツを除去せずにおけばそれだけ顔周りの土台も保持されて新追加ブツ量が安定的に顔面を覆うことができるので、確かに今やJKらにとっても合理的な方式に違いないのだった。
この手のチームワークが「自主バイト」として流布するためには、一定数以上の「酔いつぶれオヤジ」が路上にたえず供給されていなければならないのはもちろんである。そんなことが可能だろうか。いくら大都会といっても、そんなに大の社会人がごろごろ酔いつぶれていてくれるものだろうか。ここから、匿名のブレーンによる示唆が後押ししたことは確からしいにせよ、異説の余地がある。彼女らの自主バイト開始の動機というか切っ掛けというかは、期待値理論家ブレーンとは別方面に本筋を置いていたのではとの推測が当然視されてくるのである。それは、「酔いつぶれオヤジども量産の経緯」そのものであり――、ということはすなわち「ネオおろち」は、「怪尻ゾロ」の模倣犯として始まったのではないか、という仮説も有力となってくるのだ。

話が先走りすぎたが。
「ネオおろち?」
少女二人がそう名乗ったのに対して袖村が怪訝に聞き返すと、少女らは「進化したおろち系……」と名乗り直した(なお先述のとおり二人の少女は容貌、体型、語気、性格とも極平凡無個性と袖村には見えたので、本稿でもあえて名前を記録する必要を認めない)。改めてストレートに記述し直そう。進化したおろち系すなわちネオおろち系は、街の泥酔中年に顔面脱糞してやる代わりに、財布から現金を抜き取るという夜間活動に邁進していた(便種によって金額を自己設定していたチームもあるという。ちなみに先ほどのような生下痢の場合は自然極太おろちに比べて半額、便秘便の場合は四分の一に自粛するが、先ほどは生下痢なるも二人完全シンクロが出来て温度差ゼロという稀に見る快挙だったので逆に極太単独おろちの三倍、十五万はいけるのが相場だと)。「だけどそんなにゲンナマ持ってるおじさんっていないでしょ、その場合は名刺抜いといて写真とか撮っといてあとで連絡したりとかね」「そういうことしてる子もいるけど、足がつくと大変だからあたしたちはやらない。シンクロのときは有金全部戴くだけで恨みっこなし」
「うーん……、まだいまいちわからないんだが……」袖村がさらに(そっち系文化への体質的深入りを厭うことをつい忘れて)問いつめたところ、この女子高生ネオおろち軍団の中核に、問題のブレーンすなわち「おろちの達人」の存在が明らかになったのである。彼女らはその達人をまっしぐらに〈教祖〉と呼んでいた。驚いたのはこの〈教祖〉という語を少女らは「カリスマ」「ディレクター」「バイト」のように尻上がり的平坦アクセントで発声していることだった。袖村ははじめ「競争」かと思って意味が取れず二度訊き返したのだった(ちなみに「おろち」という語は「お」にアクセントが置かれていたのを聞いて袖村がふと安堵したのはなぜだったろうか)。
二人の少女によれば〈教祖〉(〈キョーソ〉と表記すべきかもしれない)の「イケテるところ」はなんといっても――
(第9回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『偏態パズル』は毎月16日と29日に更新されます。
■ 三浦俊彦さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


