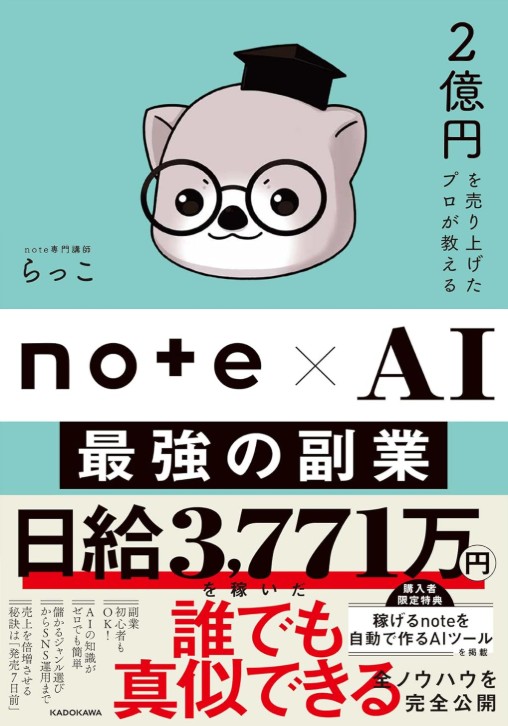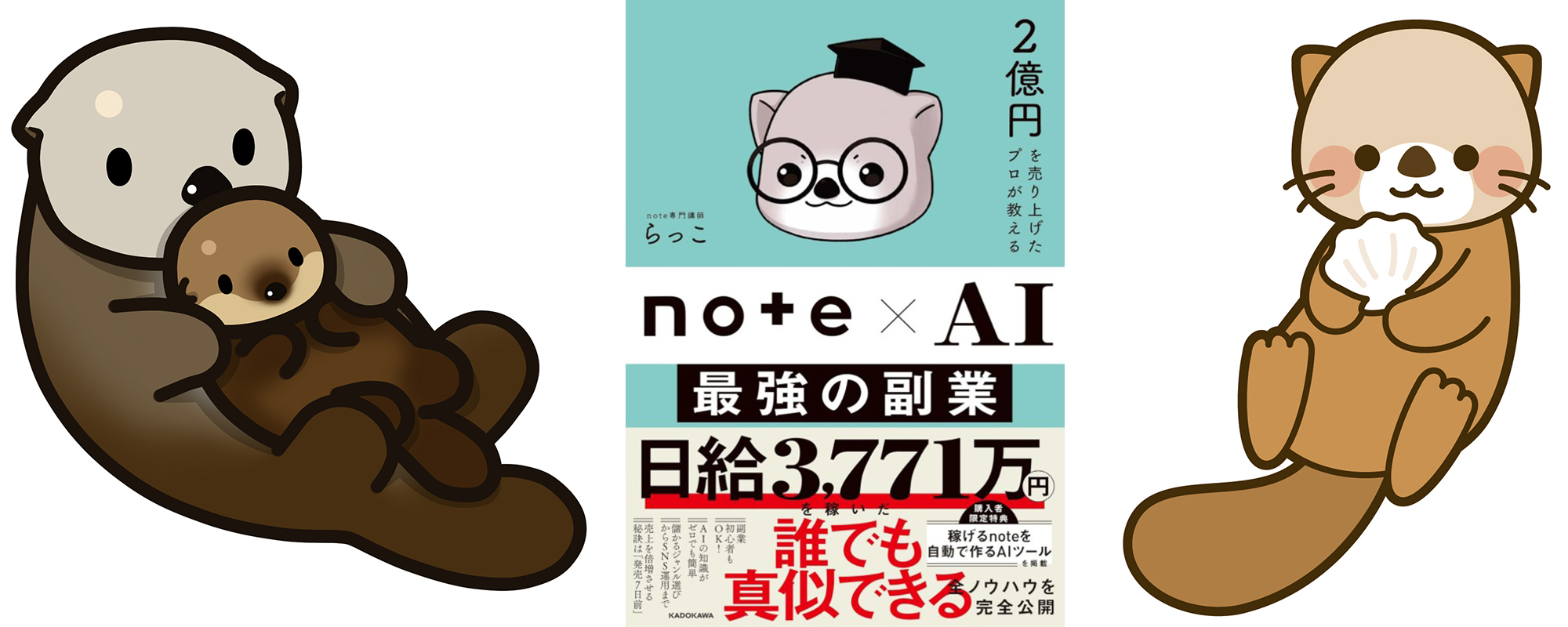文学金魚の書評で、まさかビジネス実用書を取り上げる日が来ようとは。編集部内でも「これ、うちで扱うの?」という声が上がったのは事実。だが、待て。クリエイティブ・ライティングとテクニカル・ライティング、この二つを峻別することに、どれほどの意味があるのだろう。
考えてみれば、エンタメ小説の構成術には意外なほどテクニカルな側面がある。登場人物の配置、伏線の張り方、クライマックスへの盛り上げ――これらをマトリックス化して整理する作家はいる。必要な要素をピックアップし、組み合わせ、最適化していく。そのプロセスは、本書が説くnote記事の設計法と驚くほど似通っている。創作とは実のところ、感性と技術の絶妙なバランスの上に成り立つものだ。
とはいえ正直に言おう。この本を開いた瞬間、ちょっと引いた。「いかに売るか」「いかにバズるか」という言葉が踊る紙面。クリエイティブ・ライティングの書き手たちは、何より自分自身のために書く。読者を想定するにしても、それは「内なる読者」であり、市場調査の対象ではない。売上至上主義への違和感――それは文学に携わる者として、当然の反応だ。
しかし、だ。作家が「内なる読者」を楽しませようとする行為そのものが、すでに客観視の始まりだ。自分の書いたものを一歩引いて眺める。これは面白いだろうか、退屈ではないか、伝わるだろうか。そう自問する瞬間、作家は既に読者の視点を内面化している。本書が提示する「客観的な分析手法」は、この内的対話をより精緻にするためのツールに過ぎない。テクニカル・ライティングの思考法は、クリエイティブ・ライティングの質を高める補助線になり得る。
「売れるものを書く」という言葉には、確かに抵抗があるだろう。自分の書きたいことを曲げてまで、という想いは誰にでもあるだろう。だが、再びちょっと待ってほしい。「書きたい」とは何か。それは本当に自分の内側から湧き出たものなのか、それとも狭い意味での思い込み、エゴの産物ではないのか。この問いを深く掘り下げるきっかけとして、本書の視点は有効だ。
著者のらっこ氏は一方で、自分の得意分野、自分ができること、他者より優位に立てることを冷静に分析し、そこから発信のジャンルを定めるという方法論を説く。これは一見、打算的に映るかもしれない。しかし自分の強みを客観的に把握することで、逆説的に「自分が本当に書きたいこと」の輪郭が鮮明になる。自分のためと他者のため、その境界線は思うほど明確ではない。むしろ両者は、螺旋階段のように絡み合いながら上昇していくものではないか。
らっこ氏自身の来歴も興味深い。ビジネス書のお約束として、親しみやすく、やや面白おかしく語られる自己開示。様々なビジネスを転々とし、自分の居場所を探し続けた日々。多くの読者が共感するであろうその遍歴の先に、noteというツールとの出会いがあった。彼はそこで広義の「書くこと」に自分自身を見出したとも言える。それはつまり我々同様に彼自身のためであり、同時にビジネス的価値を介して他者のためでもあった。俯瞰的に見れば、これは一種の「私小説的」営みでもある。彼が提示する数々のノウハウも、この理解を前提にすれば、また違った味わいを帯びてくる。
noteというプラットフォーム(最近ではXの記事機能も)が、テクニカル(およびある種のクリエイティブ)・ライティングの新しい場になっているという事実は、注目に値する。そしてまたペンを走らせることだけが「書くこと」ではないかもしれない。であれば、私たち文学金魚がそこでの「作品」を支援することに、何の躊躇があろうか。価値観は異なる。しかし人はそれぞれ違うからこそ、互いに吸収できるものがある。その可能性に賭けてみる価値は、十分にあるのではないか。
石川良策
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■