 妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。
妻が妊娠した。夫の方には、男の方にはさしたる驚きも感慨もない。ただ人生の重大事であり岐路にさしかかっているのも確か。さて、男はどうすればいいのか? どう振る舞えばいいのか、自分は変化のない日常をどう続ければいいのか? ・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第5弾!。
by 金魚屋編集部
テレビを点けて、どうでもいい番組を小さい音量で流す。座布団と畳の感触を楽しみながら、ビールを注いでもらう。ホテルではなく旅館で正解だった。追加オプションの豪華な刺身に喜ぶサクラちゃん。さっきからスマホで何度も写真を撮っている。四千円プラスして正解だった。向かい合わせに座りながら、今日一日をお互いに思い返しながら喋った。たくさんの言葉を使って話してはいるが、煎じ詰めれば「楽しかったね」と言い合っているだけ。決してそれは嘘ではない。正解だ。本当に楽しかった。そして、まだやりたいこと、話したいことはある。
たとえばデュークのこと。彼の店で美味しいジン・トニックを飲んでほしい。あのカウンターでテンションが高くなったサクラちゃんに、デュークがどう接するかは予想がつく。ジャズを楽しみながら、俺も彼女と一緒になって背伸びをしてみたい。
また「夜想」で会う連中の話も聞いてほしい。トミタさんの娘の件は重すぎるかもしれないが、面白い話はたくさんある。マスターの話だけでも一晩では足りないくらいだ。
あとは大学の同級生、「余り者」のヤジマーやイノウエ、トダの話。この間、リッちゃんとトダの店に行った話はどうだろう。学生時代の話は写真を見ながらの方が面白いかな……。
あれもこれもと頭の中を幾つもの話が廻っている。でも俺は楽しそうなサクラちゃんを見ながら現実を受け入れなければいけなかった。話したいと思っている話は、どれも話せないことばかりじゃないか――。
サクラちゃんとはこの旅行で終わりだ。きっと会わなくなる。「次」や「先」はないし、そういう人に聞かせる話なんかない。それが現実だった。俺たちが喋れることは、今日というたった一日の話だけなんだ。
「下のお土産売り場にマッサージの椅子あったの見ましたかあ?」
「え? 知らない」
「あったんですよお、お金入れて動かす昭和な感じのがあ」
まだビールしか飲んでいないのに、サクラちゃんの顔はいつもより赤い。
「へえ、ちょっと試しにマッサージしてきたら?」
「え? いいですいいですう、だってえ、時間もったいないじゃないですかあ」
可愛いことを言ってくれる。いい子だ。でも、俺はこの子に何も話せないんだ。
「あのお……」
「ん?」
「一本貰ってもいいですかあ?」普段は吸わないが、たまにこうして欲しがる。
「もちろんどうぞ」
「すいません」
煙を吐き出して、満足そうにグラスのビールを飲んでいるサクラちゃん。テレビの天気予報が明日も晴れだと言い、彼女は「やったあ」とガッツポーズを作った。
もしかしたら、お互いに寝る時間が来るのを怖れていたのかもしれない。気付けばいつも以上に酔っ払ってしまい、二人とも布団の上に倒れこんでいた。仲居さんが片づけをしてくれたのは何となく記憶にあるが、それ以降は思い出せない。

とにかく目が覚めたら、午前三時で電気は点けっぱなしだった。眩しさにはどうにか慣れたけど、喉が渇いて仕方がない。起き上がってテーブルの上にあるペットボトルの水を飲み干した。窓ガラスには、はだけきった浴衣をボロ布のように巻きつけている俺の姿が映っている。ひっでえな、と呟きながら帯を締め直す。煙草を吸おうかと思ったが、喉が痛かったのでやめた。今日は喋りすぎたのかもしれない。
サクラちゃんは胎児の姿勢で眠っている。灯りは点けたままだ。その丸っこい背中を見ながらやはり煙草を吸うことにした。テレビは消されていて、聞こえるのは彼女の寝息だけ。俺は灰皿を片手に広縁へ出て、窓の外の闇を眺めた。窓ガラスには部屋の全景が二重に映っている。そこに額をくっつけると、冷たくて気持ちがいい。きょろきょろと視線を動かしてみたが、闇は深くて何も見えない。視界の下の方のガラスは俺の息で曇っている。
額に感じる程よい冷気は、周囲の状況をぼやかしてくれた。ここが箱根だということを一瞬忘れる。そして初めて俺は、自分が父親になるという未来を、気負いなく素直に受け止められた。変なタイミングだが仕方ない。真実は曲げられない。
今までずっと父親になるという事実から逃げ回ってきた。以前、コケモモに中絶をさせたことも理由のひとつだ。なのにそれさえも認めたくないから、なぜ人を殺してはいけないかと周りの人に尋ね続けた。きっかけは愚かで醜かったが、結果的には良かったと思う。ただそのおかげで未来を受け止められた、というのは違う。俺はそんなに理論的ではない。なんだか慣れちゃっただけだ。
この数ヶ月、みっともなく、そしてだらしなく足掻き続けた結果、ようやく「自分の子が産まれる」という事実が頭や身体の内側に溶け込んできた。このまま溶け込み続ければ、いつか俺もマキに追いつけるような気さえする。とにかく慣れるのが一番だ。
うーん、というサクラちゃんの寝言に振り返る。微かに肌寒い。煙草を消して明るい寝床に戻った。彼女を起こさないよう静かに横たわる。ふと、枕にこぼれる髪の毛に触りたくなった。でも、もしそれを自分に許してしまったら、望んでいる結果にはならないだろう。だから必死に堪えていた。
「寝れないですか?」
ふいに訊かれて驚いた。ずっと起きていたのだろうか。
「いや、すぐまた寝るよ」そう答えてからが長くなった。「……電気、消そうか」
彼女が寝ていないのは分かる。返事を待たずに立ち上がって電気を消した。出来立ての闇の中、身を屈めてまた布団に横たわる。
「奥さんのこと、愛してるんですね」
たしかにそう聞こえた。愛してる、という言葉とサクラちゃんの声は釣り合いが悪い。ん? と訊きかえす。大人はずるい。
「でもお、大丈夫です」俺には差し出す言葉がない。「よく分かんないけどお、何か大事にされてる気がして嬉しいですう」
君は勘違いをしている。俺がこれ以上の関係を求めないのは、妻を愛しているからでも、君を尊重しているからでもない。今ここでむしゃぶりつき、朝まで激しく腰を振り続けたら、せっかくの決心が鈍るからだ。そうなったら、きっと俺は東京に戻っても会おうとしてしまう――。
そう言えば、真実を伝えたことにはなるだろう。真実は曲げられない。でも俺は真実を伝えるために生きているわけではない。闇の中、サクラちゃんがこっちに顔を向けるのが分かった。呼吸と体温が想像できる。もう一度だけキスをしたかったがこれも堪えた。
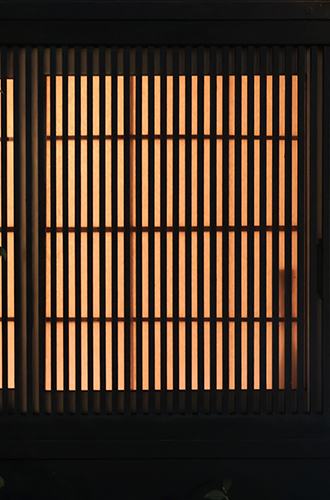
「ありがとう、おやすみ」
努めて冷静に声をかけた。数秒の沈黙の後、彼女は「はあい、おやすみなさあい」と囁き、再び元の位置に向き直る。その声の奥にある低い震えを聞き、愚かな俺はようやく気付いた。この子は勘違いなんてしていない。ずるい大人に傷つけられないよう、鈍い振りをしているだけだ。
箱根から帰ってきて数日、飲みに行く気になれなかった。外でだけではなく家でも飲まない。そしてサクラちゃんからはメールも電話も一切来なかった。やっぱり鈍い振りをしていたんだなと思う。
禁酒状態のまま週末を迎えた。特に体調に変化はない。実家の喫茶店で父親の「新人研修」を受けた帰り道、ちょっと迷いはしたが「夜想」には寄らず真っ直ぐ帰った。家ならまだしも、まだ外で酒を飲む気分ではない。ポストから郵便物を取り出すと、ピザや引っ越しのチラシに混ざって茶封筒が一通入っていた。差出人はマキ。なんだか嫌な予感がして、焦るようにして封を開ける。中には便箋が一枚。見慣れたマキの字で、短い手紙が綴られていた。
一人暮らし、どうですか。
迷惑をかけちゃってすいません。
でも、私はあのまま一緒に暮らしながら、この子を産む自信が持てなかったんです。
わがままを許してくれて、どうもありがとう。
この手紙のことはすぐに忘れてね。
俺は何度も読み返した。その度にどんどん分からなくなる。そんな内容だ。今すぐにでもマキに電話をしたい。愛おしさからではない。この手紙の真意と、俺がどうするべきなのかを教えてほしい。
マキの真意はよく分からないが、今、何かがこじれていることは分かる。ヌメヌメとした後味の悪さを流してしまおうと、久しぶりに冷蔵庫からハイネケンを取り出す。味がよく分からないまま、すぐに飲み干してしまった。
もう一缶飲もうか、それとも一度シャワーを浴びようか。冷蔵庫の前で考えていると電話がかかってきた。テーブルの上のスマホを手に取る。もしかしたらコケモモ、という俺の読みは正解だったが、画面の表示は公衆電話を意味する「不明」ではなく「コケモモ」。つまり、あいつ自身の電話からだった。躊躇うことなく通話ボタンを押すと「もしもし」と懐かしい声がする。自分から電話をつないだくせに鳥肌が立った。二十六日でもないのにどうして――?
「コケモモ?」
「お、私はまだコケモモのままなんだね」
その一言で、あれから六年経ったんだと思い知る。声の響きは懐かしいが、やはり顔が思い浮かばない。似ている女優の顔になってしまう。あとでビデオ通話にしてもらおうか。
「電話番号だってそのままじゃないか」
「……うん、そういやそうだね」
「元気か? 今どこにいる? 東京か?」
「その前にさ、教えてほしいことがある」
「ん?」
「もう結婚はした? で、子どもはいる?」
「結婚はした。子どもはまだ」
そろそろ産まれることを告げなかったのは、あいつが電話をしてきた理由も、そんなことを訊く理由も分からないからだ。

「電話してて大丈夫?」
「ああ、大丈夫」
そうかあ、と呟いて数秒、あいつは「じゃあ、話そうかなあ」と言った。俺はその口調に懐かしさを感じつつも身構える。たいした要件もなく、連絡をしてくるわけがないんだ。
ごめんね、と静かにコケモモは謝った。二十六日でもないのに連絡をしたことと、少し前の無言電話を謝った。別に気にしてないよ、と答えた気持ちに嘘はない。謝らなければいけないのは俺の方だ。六年前のあの日、妊娠を告げられコケモモの部屋から逃げ出したこと。そして中絶という決断をさせてしまったこと。いや、それ以外にも俺が知らないところで、たくさん辛い思いをさせてしまったはずだ。謝っても謝り足りない。
「いや、俺の方も……」
そう言いかけると、コケモモは「やめて」と少し大きな声を出した。そして沈黙した俺に「ごめんね」とまた謝る。
「今謝ったから言い訳はしない。でもね、私にも理由はあったんだ」
「……」
「電話をした時は本当に話がしたかったの。でも私の番号からじゃ出てくれないと思って、公衆電話からにした」
「お前からのなら出るよ」
「うん、それはごめん。自信がなかった」
違う、と言いたかった。コケモモの自信の問題ではない。俺が信頼されていないだけだ。
「で、公衆電話からかけたけど、声が聞こえた瞬間に何も言葉が出なくなった、っていうか、何から話せばいいのか分からなくなっちゃった」
コケモモは話す順番に悩むほど大きな何かを抱えている。そんな事実に改めて身構える。今日連絡をしてきたのは、話す順番が分かったからだろう。テーブルの上のマキの手紙からそっと目を逸らした。今はまずこっちに集中しなければ。俺は黙っているコケモモに恐る恐る声をかけた。
「今はもう、話す順番、分かってるんだろ?」
沈黙が鼻をすする音に変わった。受話器の向こうであいつは泣いている。俺の緊張もピークに近い。肩が痛いのは身構えすぎたせいだ。ごめん、と謝りながらコケモモは泣き止もうと頑張っている。簡単に三、四分が過ぎた。
「……ごめん、もう大丈夫」
「謝らなくていいから。な?」
「うん。あのね、七月の十四日に、ツヨシがね……、ツヨシがなくなったの……」
再び泣き出したコケモモの声を聞きながら、俺は言葉の意味を考えていた。確かに無言電話があったのは七月だ。ただ「ツヨシ」が分からない。誰なんだろう? 俺とあいつの共通の知り合いなんて、「余り者」の連中くらいじゃないか。しかも、その「ツヨシ」とやらが「なくなった」?
「だから、それを伝えなくちゃって……。ごめん、本当にごめんね……」
俺に出来ることはひとつしかない。コケモモが落ち着いて話せるようになるまで待つだけ。だから目を閉じ、落ち着くようにと祈りながら、耳を澄ましていた。
「……あのね、ツヨシはね……、私たちの子どもなの」
言葉の意味が伝わるまで、少し時間がかかった。生まれて初めて頭の中が真っ白になる。息は苦しいし、声は出ないし、胃の辺りが強烈に痛い。そしてコケモモの声がやけに近い。
「私、堕ろさなかったんだ」
(第19回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『オトコは遅々として』は毎月07日にアップされます。
■ 金魚屋の小説―――金魚屋の小説だから面白い! ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


