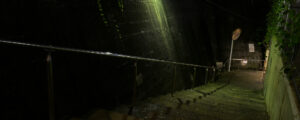 世の中には男と女がいて、愛のあるセックスと愛のないセックスを繰り返していて、セックスは秘め事で、でも俺とあんたはそんな日常に飽き飽きしながら毎日をやり過ごしているんだから、本当にあばかれるべきなのは恥ずかしいセックスではなくて俺、それともあんたの秘密、それとも俺とあんたの何も隠すことのない関係の残酷なのか・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第四弾!。
世の中には男と女がいて、愛のあるセックスと愛のないセックスを繰り返していて、セックスは秘め事で、でも俺とあんたはそんな日常に飽き飽きしながら毎日をやり過ごしているんだから、本当にあばかれるべきなのは恥ずかしいセックスではなくて俺、それともあんたの秘密、それとも俺とあんたの何も隠すことのない関係の残酷なのか・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第四弾!。
by 寅間心閑
四十七、うなぎ
「もしも身長がぐーんと伸びたら、今着てる服って来年には着れなくなるかもしれないでしょう? その着れなくなった服を、捨てちゃうんじゃなくて売ってくれれば、また誰かに着てもらえるし、その人も普通より安く買えるの」
安藤さんが行う古着の解説を、真剣な表情で聞きながらメモを取っているのは、計六人・男女半々の小学四年生たち。時間は午前十時過ぎ。こんな早い時間に店を開けるのは初めてだ。五十嵐先生は恐縮していたが、通常営業中に相手をする方が難しい。
「じゃあ、お店の中の物、みんな色々と見てみて。うちは大人用の服しかないけど、バッグやアクセサリーならそっちのコーナーにあるから」
わーっ、と女の子たちは歓声をあげて駆け寄っていく。男の子たちは照れ臭そうに店内を見回している。それにしてもみんな足が長い。俺たちの頃と背丈は変わらないが、バランスは全然違う。
「
えっと、この後何するんでしたっけ?」
「おお、安藤先生。結構サマになってたよ」
やめて下さいよ、と顔をしかめた後、「このくらいの女子は案外オトナだから」と声を潜める。五、六年じゃなくて? と訊いたが「これだから男子は」と相手にされなかった。
「私、四年の時は色々と自覚してましたよ」
それは可愛かったからだよ、とは言わなかった。ちょっと違う響きになるし、それは六人のゲストとそぐわない。まぜるな危険、だ。習字の先生の中一の息子にときめいていたという、小四の安藤さんの甘酸っぱい話を聞きながら、俺の頭には冴子のことが浮かんでいた。思い出した、とは違う浮かび方。もしかしたらあいつも、小さい頃から色々と自覚していたのだろうか。
プレゼントのバンダナを渡した後、店の前で記念写真を撮った。これでお願いします、と差し出されたのは懐かしい使い捨てカメラ。最近また流行っている、という先日読んだネットの記事は本当らしい。スマホと違ってタイマーがないから撮影役を買って出ると、一番背の高い女の子が「ええ、みんなで一緒に撮りましょうよお」と身をよじらせる。だったら、と歩いてきた若い男の子に頼んで撮ってもらった。

五十嵐先生の話では、来週お礼の手紙やイラストを持ってきてくれるらしい。ありがとうございました、と声を合わせて頭を下げる六人に別れを告げ、店に戻ると「一緒に撮りましょうよお」と安藤さんがさっきの子の真似をした。自覚してるかな、と尋ねると「間違いないですよ」と頷く。
「でも無邪気で可愛いですよね。まだ自覚が浅いっていうか」
「浅い、か」
「私も無邪気にお願いしときますね。三つだけだからいいでしょう?」
そう言って身をよじらせる安藤さんが、どこまで自覚しているかは考えない。
「まずは中華街。これ、すぐ、叶いますよね。次は旅行。一泊でいいです。箱根とかならすぐでしょう? で、最後は……んーと、3P」
え、と反応した俺を見ながら彼女はピンクの舌を出す。あれは仲の良い男とするもので、好きな女とはあまりしたくない。
次の日はオフだったので、昼過ぎにナオと待ち合わせた。父親が退院して家に戻っただけではなく、母親が「卒婚」の延期を提案したという。中止じゃなくて延期っていうのがねえ、と電話では言っていたが、その声はどこか明るかった。めでたい。だからうなぎだ。だから人形町だ。だからちょっと遠いけど嫌じゃなかった。
「別にミシュランのビブグルマンとか、食べログ高評価って店じゃないんだけど、うちは小さい頃からお祝いの時はよく行ってたんだよね」
完璧じゃん、と笑ったのは嬉しかったからだ。うなぎでも穴子でも、何ならアナギでもウナゴでも俺の舌は喜ぶに決まっている。ここよ、と馴染みのない街で案内されたのは、怪しげなブティックとコインパーキングに挟まれた頼りない店で、人形町と呼ぶには少し駅から離れすぎていた。でも外見なんてどうでもいい。中は狭くても綺麗で、おかみさんは感じが良く、他の客はみんか和やかに御馳走を食べている。お新香と肝焼きで、瓶ビールをちびちび呑みながら聞くナオの話は、親戚の家の話くらい距離感が近い。やっぱりこいつはちゃんとしてるな、と思いながら大瓶を追加した。
「まあ家族だから腹も立つし、家族だから色々面倒見てるんだよねえ。マジでくだらないと思ってんのよ。くだらないし、つまんないって」
だよなあ、と乗った。そして「本当古いタイプの人間なんだよなあ」とありきたりなことを言った。だからバチが当たったんだと思う。数分後、うな重が運ばれてくるタイミングで電話をかけてきたのは俺の家族、冴子だった。もしもし、という俺の声を待ちきれずに「ねえ」と前のめりに喋る。
「ねえ、お兄ちゃん、今誰かといる?」
やけに声がでかい。「どうした?」という俺の問いかけも潰されてしまう。
「ねえ、一人なの? ねえ」
何が知りたいかは分かった。こいつは少し前から余裕がない。だからわざわざ俺に連絡してくる。そしてそれは安太のせい。そう睨んでいる。
ごめん、と店の外に出た。さすがに泣きはしないので、俺も安太の名前は出さないが、だからこそ話は終わらない。「本当に一人なの?」「カノジョと飯食ってんだよ」を繰り返し、「私のこと怒ってんでしょ」「心当たりがあるのか?」を繰り返し、「ちょっと会わないか」「失踪中なんだから放っといてよ」を繰り返し、最後はあいつから切った。何だよ、と怒るつもりはない。大丈夫かな、と心配なだけだ。安太を恨むつもりもない。今でも一緒に3Pしたいと思っている。
店に戻るとナオはうな重に手をつけてなかった。食べてればいいのに、という資格は俺にない。ごめん、と小さく謝って蓋を開ける。もちろん旨そうだ。でも冷えてしまっている。さっき運ばれてきた時に食べた方が百倍旨かったはずだ。
同様に冷えきったお吸い物を飲みながら「おいしいでしょう?」とナオは寂しそうに笑った。うん、と言ったが温かい方がもっと良かった。ナオの両親の卒婚延期の祝いの席、せっかくの御馳走を台無しにしたのは俺だ。冴子でも安太でもない。

店を出るともう日は暮れかかっていた。馴染みのない街を勘に任せて歩いてみる。ナオもこの辺りはあまり詳しくないらしい。うなぎ屋から引きずる会話の少なさを何とかする為、もう少し酒が欲しかった。
ふと通り掛かった古い造りの酒屋の前で立ち止まる。引き戸の向こう側では背広姿のオジサンたちで賑わっていた。忘れていたが今日は平日だ。どうやら店の中で呑ませるらしい。面白そうだと迷わず入る。瓶ビールの位置や、お金の払い方や、栓抜きの場所をオジサンたちに教えてもらいながら、何とか隅っこのスペースを確保できた。テーブル代わりの台はあるが椅子はない。ナオも楽しんでいるのは顔を見れば分かる。柿の種を分け合いながら、大瓶二本を空けて店を出た。気付けばいつものように話せている。
「ちょっともう一軒、覗いてみようか」
馴染みのない夜の街をあてもなく歩いていると、まるで旅行に来たみたいだ。多分、この辺りはもう人形町ではない。ナオが興味を示したいくつかの店の中から、オイスターバーを選んでワインを一本頼んだ。重めの赤。トイレで冴子からのメールに気付いたけれど気にしない。さっきはごめんなさい、だけのメール。気にならない。大きな牡蠣にレモンを絞り、濃い色のワインで流し込む。気にするもんか。
ナオと話していたのは、例の寛十郎の予言に基づく悪だくみ、ではなく儲け話。鶏蜥蜴は製薬会社とドラッグストアに狙いを定めているらしい。威勢のいい予想を繰り広げながらワインを飲み干し、さあ次の店へ。まだ九時過ぎかと浮かれながら、次は焼肉屋で軽く食べようと提案してみる。てっきりOKだと思っていたが、馴染みのない街で信号待ちをしながらナオは首を横に振った。慌てて他に食べたいものがあるのか尋ねると、安太の家の近くまで行くべきだと言う。
「それは、どういうこと?」
「……」思案顔のナオ。
「これからあいつの家に行くっていうのか?」
我ながら情けない声を出している。別に覚悟がなかった訳ではない。ただ、まさか今日だと思っていなかっただけだ。
「……さっきの電話、妹さんからでしょう? 結局いつかは確かめなきゃいけないわけじゃない? もしかしたら今だってホンマさんの家にいるのかもしれないし」
信号が青に変わり、人々が一斉に歩き始める。安太の家に行くことをいつから考えていたのだろう。やっぱりさっきのうなぎ屋からだろうか。また情けない声を出しそうな俺の手を、ナオは力強く握ってくれた。
「こうやって先延ばしにしても、嫌な思いをする時間が増えるだけだよ」
正論だな、と納得したから「うん」と返事をした訳ではない。さっきうなぎを台無しにしたことへのお詫びだ。
「もし二人に会えたとして、何をしたいかは分かってる?」
「……」
「前に言ってたよね。覚えてる?」
もちろんだ。忘れるわけがない。場所だって覚えている。新宿の中央公園だった。あそこで俺は、安太と冴子からノケモノにされたくないという自分の気持ちと向き合ったんだ。
「うん。ノケモノにするなって頼むんだ」
「……ごめんね」
お前が謝ることはない、と言おうとしたけど涙腺が緩みそうだったから、口には出さずにナオの頬を軽くつねった。仕方ない、覚悟を決めるか。寛十郎も出来るだけ早いうちに会った方がいいって言ってたしな。
つねられて微笑んでいるナオの顔を見ながら、俺は背筋を伸ばした。大丈夫、俺にはユリシーズとイグアナがついている。

時間のせいか、下高井戸の駅前商店街は人通りが少なかった。ばったり安太に会いそうな気がして実は落ち着かないが、平気な顔でぶらぶらと歩き、陸橋で甲州街道を渡った。頭のすぐ上を走る首都高を、ナオが物珍しそうに見上げている。陸橋を降りたら、あとは川を目指して直進。見慣れた安太の家が近付いてくる。久しぶりの風景に罪はないが、懐かしさが恨めしい。
途中、このままでは俺の体力が持たないと思ったのか、「やっぱり焼肉食べてからにしようよ」とナオが言い出した。素直にありがたい。少し回り道をして焼肉屋に入った。マジックで書きなぐった短冊が画鋲で貼ってある、昔ながらの汚い焼肉屋。昭和だね、とナオが微笑む。今日何度目かの乾杯をして、網の上に肉を並べた。派手な音をたてて煙がゆっくりと昇っていく。
肉をひっくり返しながら、店を出たら直接安太の家に行こうとナオは提案したが、俺は反対した。電話を一本入れてから行く方がいい。
「えー、だってさ、逃げたりするかもしれないじゃん」
そう言ってから、ナオは小声で謝った。状況はどうあれ、友達のことを悪く言って申し訳ないという意味だろう。いいんだ、と俺は首を横に振る。でも譲れなかった。
「やっぱり電話を一本入れてからにしようぜ」
そうね、とナオは頷いてくれた。不意打ちみたいなことはしたくない。まだ俺には余計な見栄がある。安太に対しても、もちろん冴子に対しても、だ。
大一番を控えての焼肉は少し胃にきつく、あまり食えなかったが、冷えたビールは文句なしに旨かった。二杯目のビールを片付けた俺に、「あまり呑みすぎないでね」とナオが釘をさす。
店を出たのは午後十一時前。深呼吸をしてから電話をかけた。呼び出し音が八回鳴った後、留守電に切り替わる。もちろん何も入れずに切った。何だ、いないのか。そんな風に内心ほっとした自分が恨めしい。
「いないみたいだな、留守電になった」
「じゃ、家の前まで行ってみようよ」力強いナオの声。
反論したかったが、冴子のスマホにかけてみようと言われたくないから従った。安太って居留守を使うような奴だっけな、と思いながら歩く。二人で何度も歩いた川沿い。住宅街独特の静けさを持て余し、俺もナオも無口になる。
安太や女たちと乱交をやるだけの、幾度となく過ごしただらしない夜。その記憶の断片が頭をよぎり、少し気持ち悪くなった。しかめっ面の俺を見て「大丈夫?」とナオが首を傾げる。大丈夫、と嘘をついた。多分、ばれてるだろうな。やがてアパートが見えてきた。思わず凝視してしまう。角を曲がると二階の一番奥、安太の部屋の窓が見える。電話には出なかったけど、灯りは――点いていた。つまり、そういうことだ。
「灯り、点けっぱなしなのかな」
とぼけてそう呟くと、「今度は私が電話してみるから、ちょっと貸して」とナオは右手を差し出す。逆らわずにスマホを渡すと、今来た道を戻りながら、電話をかけ始めた。生ぬるい空気に乗ってナオの声が聞こえてくる。「マスカレード」で働いている時の声。高くて少し軽薄なトーン。
「もしもし誰かいますかあ、もしもしい、ホンマさんが具合悪くなっちゃってえ、近くまできたんですけどお、もしもしい、ホンマさんがあ……」

声が途切れた。なるほど、トラップか。声が途切れたということは――。
「……あ、すいません、ホンマさんをお家まで運びたいんですけどお、家の場所がよく分からなくてえ」
冴子がまんまとトラップにかかったのだろうか。立ち尽くす俺に電話を切ったナオが近付く。いつものちょっと低めの声。
「誰だか分からないけど、女の子が出たよ。ちゃんと家の場所、教えてくれた」
「でも、妹じゃなかったらマズいだろ」
ナオはしっかりと俺の目を見て「そしたら酔っ払いの真似でもしてごまかそうよ」と言った。そして、何か言いかけた俺を手で制して続ける。
「本当はさ、妹さんだった方がマズいんでしょ」
ああやっぱり止めときゃよかった。今日は絶対に行きたくないと言い張れば、何とかなったはずなのに。
今怖いのは、冴子がいるかもという可能性より、強い視線のまま立っているナオの方だ。昔の感覚が蘇る。こういう強さが苦手で、付き合うのは無理だと思っていた。でも今、ここで全部投げ出したら楽にはなれるけど、一生軽蔑されるだろう。もちろんユリシーズからもだ。それは避けたい。ごめん、と謝って煙草を一本ねだった。ナオの視線が咎めている。
「これ吸ったら行くよ」
そんな情けない声を聞き、険しかったナオの表情が一瞬で和らぐ。同情されてんだな、俺。これ以上厳しくしたら可哀相だと思われてるんだろう。いつまでもオスワリすら出来ないバカ犬だ。優しい飼い主は優しい表情のまま「私も一本吸おうかな」と言ってくれた。
街灯の発する光は弱く、煙草の吸い口の方が眩しい。深く煙を吸い込んで気持ちを落ち着ける。タクシーが俺たちの横を通り過ぎていった。その姿とエンジン音が消える前に話しかける。
「あんな手段、考えつかなかったよ」
ナオの怪訝そうな顔。電話をかけるジェスチャーをすると、ああ、と微笑んだ。
「昔ね、よくあの手をつかったのよ」
自分の恋人の行状をああやって調べた経験があるんだろうか。しかも複数回。どんな男で、何年付き合って、どこに遊びに行って、どんなプレイをしたんだろう。こんな状況でバカ犬は昔話に嫉妬している。
絶対怒ったり怒鳴ったりしちゃダメだよ、というナオの声に「大丈夫だよ」と頷く。言われなくても、俺は怒らないし声を荒げたりはしないだろう。
俺はあの二人にとってノケモノかもしれなくて、もしそうならば二人に「ノケモノにしないでくれ」と頼むんだ。それだけだ、バカ犬。お前にだって出来るだろ。簡単だ。出来るだろ。出来るんだ――。
煙草終了。さあ、行かなければ。
携帯用灰皿に吸殻を捨てて歩き出す。何度も昇ったアパートの階段を昇りきると、ナオが頬にキスをしてくれた。大丈夫だからね、のメッセージ付き。危なく吠えるところだった。
(第47回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『助平ども』は毎月07日に更新されます。
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■






