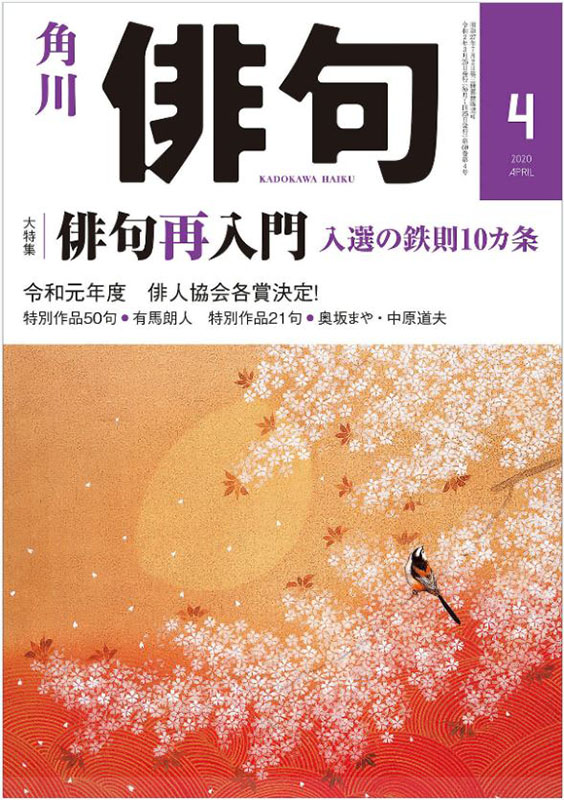
今回もまた白濱一羊さんの「現代俳句時評」を取り上げるというか、ネタにします。まーはっきり言って角川俳句は退屈なんだな。特集は初心者に手っ取り早くノウハウを教えて俳句が書けるようになるためのTipsの羅列ですね。作品が掲載されれば嬉しいだろうけど、みんな自分の作品が載ったページをじーっと見ている気配だ。いわゆる状況論も載っているわけだが、これは状況があるように見せかけるためのメディア御用達状況論で、俳句文学の共通パラダイムになっていない。少しでも刺激のある原稿を見つけるのが難しい。なべてコトナシ終日のたりのたりかなでいっこうに構わない、というのが俳壇の総意のようだ。しかしそれではやはりあまりにも退屈なので、俳壇の総意に少しでも抗う原稿にどうしても目が行く。
平成の三十年間、俳壇ではたいした事件も論争もなく無風状態だった。それを「平成無風」というそうだ。昭和には、新興俳句運動や太平洋戦争を挟んだ戦火想望俳句の流行と俳句弾圧事件、戦後の第二芸術論の衝撃、現代俳句協会の設立と分裂等々、俳壇全体に関わるようなダイナミックな出来事があった。
それに対して、平成には東日本大震災があったが、それが俳句に大きな変化をもたらすことはなかった(個人としては句風に影響を受けた俳人もいたが)。
平成初期には俳句ブームが起こり、俳句人口の増大とともに俳句結社や俳句商業誌が次々と生まれた。カルチャースクールでも俳句は人気コンテンとなり、中堅俳人はレッスンプロ化した。俳句の大衆化は大いに進んだが、俳句の本質を捉えようとする議論の場は多くなかった。
白濱一羊「令和時代の俳句理論を――芭蕉でも子規でもなく」(現代俳句時評④)
高柳重信に『戦後の西東三鬼』という比較的長いエッセイがある。読んだのはだいぶ前だが、最初は重信にしては歯切れの悪い退屈なエッセイだなぁと思った。しかしさすが重信である。なぜ歯切れが悪いのかという理由がちゃんとあった。重信は基本的に俳句〝文学〟について書く作家だったが、『戦後の西東三鬼』では文学ではなく〝俳壇〟について書いている。三鬼は「天狼」を同人誌として刊行するつもりだったが、山口誓子の元に参加を打診しに行って気圧され、実質的に誓子主宰誌にしてしまった云々といった書きにくい話を暴露していた。また重信自身の誓子面会記も書いていたと記憶している。重信ばかり話し、高そうな和服を着てキチンと白髭を整えた誓子はほぼ言葉を発せず、話が一段落すると「今日はこれで失礼」というような意味のことを言って重信の話を打ち切ったのだという。この若造が、といった感じであしらわれたという意味のことを書いていた。誓子の方が二十歳ほど年上で、押しも押されぬ俳壇の重鎮だったのは言うまでもない。
誤解のないように言っておくと、誓子批判をするつもりはまったくない。こういう大家がいなければ世の中面白くない。むしろ生意気な重信を面白がっているのである。俳壇政治はくっだらないと思っているし、誓子は大先輩で尊敬はしているが、やっぱりどこかで乗り越えなければならないと虎視眈々とうかがっている。そういったちょっとガキっぽい意気軒昂な若手がいなければ、俳壇に限らずどの文学ジャンルでも新しい動きなど出てこない。
ただ一方で、俳句史上、最高に生意気だった重信の前衛俳句運動は、その極端さゆえにその後の俳壇で非常に大きな負の遺産となったと思う。重信が亡くなったのは一九八三年だが、その後二十年近くは重信的な前衛の遺風は継続した。ざっくり言って二〇〇〇年ちょい前くらいまで、前衛俳句はかろうじて生きた運動だったわけだ。ただ二〇〇〇年を超えたあたりで完全に霧散したと言っていい。
もちろん金子兜太の社会性俳句も戦後の前衛運動だったわけだが、こちらは定型を守って俳句の表現内容を重視したムーブメントであり、最初から前衛と伝統俳句に二股かけられる仕組みを持っていた。総帥兜太のその後の巧みな俳壇遊泳術がそれをハッキリ示している。それゆえ兜太的前衛は、結果として見るとスタンドアロンで終わったかのような重信前衛運動とは別の、まあはっきり言えば半端な前衛運動としてここでは排除しておく。
で、本題に戻ると、重信系前衛俳句が俳壇で完全に消滅、ということは、その弟子たちが俳壇ではもうどうにもなりませんね、決して日の目は見ませんねという形の冷や飯食いになるのが二〇〇〇年以降である。意気軒昂で生意気な若手俳人の多くは一度は重信系前衛に共感するだろうが、この状況が若手の足をすくませたところが確実にあると思う。
要するに前衛指向を持っていて、作風も明らかに重信系前衛に影響を受けている若手俳人であっても、決して自分は前衛だと言わないのである。あるいは俳壇の圧倒的マジョリティである伝統俳句派に対して、自分は対立する俳句思想を持っているとはおくびにも出さない。むしろ俳壇では偉い、ということは、俳人たちの生殺与奪の現実権力をもっている伝統系俳人たちにおもねる。結社未所属、前衛的作風といった個性はあくまで個性の内に留まるのであり、それ以上の反抗心は持っていませんよーという従順なテイで、穏当な俳壇出世を願っているわけだ。これでは「平成の三十年間、俳壇ではたいした事件も論争もなく無風状態」になるのは致し方ない。
ただこれも誤解のないように言っておくと、中途半端な前衛としか言いようのない若手俳人を批判するつもりはぜんぜんない。むしろそりゃそーだよなーと共感する。誰だって最初からそうなるとわかりきっている冷や飯食いは真っ平だ。また彼らだけが悪いわけではない。状況をより悪くした原因は重信系の弟子たちにもある。俳人はとにかく型が好きで重信前衛俳句を型にしてしまった。多行俳句継承とかわけのわからないことを言う。五七五に季語の伝統俳句に対立する型として、よーく考えれば意味不明の無季無韻俳句派(立派な集団になっている)などもあるが、それと同じになってしまっているわけだ。型と型の争いで、無季無韻や多行俳句に勝ち目があるわけがない。
重信は「伝統俳句という俳句はないし、前衛俳句という俳句はない。俳句は俳句である」と書いたが、弟子たちは前衛俳句の型につながる重信の言葉以外はほぼ無視してかかる。それでは前衛にならない。前衛とは本質的に、未踏の認識や表現領域を明らかにすることである。伝統俳句と前衛俳句の対立は関係ない。しかし型になった途端、当たり前だが動的な思考は停止してしまう。ほんじゃあどうしたらよかんべ、ということになりますね。
俳壇が無風状態になっている要因の一つとして、議論の前提となる俳句用語が整備されていないということがあるように思う。議論が起きかけても、使っている用語の解釈がまちまちで噛み合わず、結局は両論併記といったところに落着して、議論の広がりや深まりがないように感じている。
同
白濱さんの提案は表面的にはそのとーりなのだが、いざ「俳句用語」の「整備」に取りかかると「両論併記」どころか三論、四論、十論併記になり、しかもそれが、ささいな季語とか切れ字とかのトリビアルな解釈や用法の違いになるのは目に見えている。すんごい時間をかけて喧々諤々やってみても、気がつくと「議論の前提となる俳句用語が整備されていないということがあるように思う」という最初の地点に戻っているだろう。まあ今までも散々繰り返されてきたことですな。
この時間と労力のムダを回避するには俳句を外から相対化するのが一番効果的だろうと思う。正岡子規のように短歌も散文(小説)も書いてみて、しかもそれなりの完成度と評価を得るんですな。俳句の世界に精神がとらわれているということは、今のところ俳壇に精神が雁字搦めだということと同義である。新興俳句であれ俳句第二芸術論であれ、それがパラダイム、つまり俳句界全体の共通認識として議論の土台になり得たのは、俳句を外から捉えて相対化する視線があったからである。もちろん重信前衛俳句にもそんな要素があった。俳壇内で常識となっている議論の方法では新たなパラダイムを作るのは難しいでしょうな。永田町と同じで、俳壇の常識は世間の非常識であることが多い。
降り注ぐ光さくらの吸ふ光
花にとけ込みて宴にとけ込めぬ
木洩れ日のなか人の影花の影
夜の闇と花の闇とは揺れ合ひぬ
夜桜やふと大人めく子どもの手
花吹雪空にこころの中にかな
もう誰も気にしてをらぬ桜散る
抜井諒一「花宴」より(角川俳句賞作家の四季・春)
「角川俳句賞作家の四季・春」として、第65回受賞者の抜井諒一さんが「花宴」を掲載しておられる。花見に行っても「花にとけ込みて宴にとけ込めぬ」とある。また「夜の闇と花の闇とは揺れ合ひぬ」と闇の句が多い。人のいない空間で、「桜散る」と「闇」がテーマになっている連作だと言っていい。つまり孤独の影が濃い。連帯はない、戦線が見えないということだろう。この状況はしばらく続くでしょうね。
岡野隆
■ 白濱一羊さんの本 ■
■ 抜井諒一さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■






