 女優、そして劇団主宰でもある大畑ゆかり。劇団四季の研究生からスタートした彼女の青春は、とても濃密で尚且つスピーディー。浅利慶太、越路吹雪、夏目雅子らとの交流が人生に輪郭と彩りを与えていく。
女優、そして劇団主宰でもある大畑ゆかり。劇団四季の研究生からスタートした彼女の青春は、とても濃密で尚且つスピーディー。浅利慶太、越路吹雪、夏目雅子らとの交流が人生に輪郭と彩りを与えていく。
やがて舞台からテレビへと活躍の場を移す彼女の七転び、否、八起きを辻原登奨励小説賞受賞作家・寅間心閑が Write Up。今を喘ぐ若者は勿論、昭和→ 平成→ 令和 を生き抜く「元」若者にも捧げる青春譚。
by 文学金魚編集部
歌手・越路吹雪の人生において昭和二十八年は重要な一年だった。この年の春、彼女は初めてフランスのパリへと渡り三ヶ月滞在したのち、帰国してから第一回目のリサイタルを開催する。宝塚を退団してから二年後のことだ。開場は銀座のヤマハホール。当初は二、三日の公演だった。
リサイタルが日比谷の日生劇場で開催されるようになるのは、それから更に十二年が過ぎた昭和四十年の十月。その四年後には公演日数を約一ヶ月に伸ばし、その名のとおり「ロング」なリサイタルとなる。
ちなみに戦後初の本格的な劇場である「日生劇場」が、日本生命日比谷ビルの中に完成したのは昭和三十八年。浅利先生は石原慎太郎さんと共に、その構想の発案者だった。
今回おチビちゃんが携わることとなった『ロングリサイタル』は、越路さんにとって三十二回目のリサイタル。そして彼女の生涯におけるリサイタルの公演数は三十五回。そう、ここから三年も経たないうちに、日本が誇る「シャンソンの女王」は胃ガンによりこの世を去ってしまう。
無論そんなことは誰ひとり知る由もない。今日も大町の山荘では、本番に向けての稽古が越路さんと浅利先生、そしておチビちゃんの三人で行われている。
「でも……、そんな時ってどうするのかしら?」
「どうするも何も、かかってきたものは仕方ないから……」
「出ちゃうの? え? だってすぐそこに奥さんいるんでしょう?」
「だけど出なければリンリン鳴りっぱなしになっちゃう。それもおかしいよね」
「え、じゃあ出るの? 出て何を話すのかしら……」
さっきから浅利先生と越路さんの話は続いている。傍で聞いているおチビちゃんからすると、堂々巡りの感じがしないでもない。論点ははっきりしている。奥さんが家にいる時、愛人の女性から電話がかかってきたら男性としてはどうするべきか――。

ただ、この議論が今回のリサイタルにどう活きてくるかは少々はっきりしない。今まで経験してきたダメ取りとはずいぶん勝手が違っていて、稽古と雑談、そして休憩の境目がとても曖昧だ。ダメ取り係兼嫁入り前のおチビちゃんは、二人の声に耳を傾けながら密かに恋人・ダビデさんのことを考えている。
数日前、互いに忙しい合間を縫って久しぶりにデートができた。時間は少し短かったけれど、本当に会えてよかった。電話はたしかに便利だと思う。でも実際に会って、話して、触れることはとても大切だ。思い出しただけでも、うっとりしてしまいそう。おチビちゃんは「集中集中」と短い咳払いをしてから背筋を伸ばした。
ただひとつ、気にかかっていることがある。別れ際、彼はいつもみたくぶっきらぼうに、海外へ行くかもしれないと言った。
「え、またなの? だって、ちょっと前にインドへ行ってたでしょう?」
「ああ、あれは何ていうか、遊びに行っただけだから」
「じゃあ今回は遊びじゃないの?」
「うん、遊びではないかな」
「……ということは留学とか?」
そう尋ねたおチビちゃんに彼は「いや、分かんない分かんない」と首を振り、なんとなく話は終わってしまった。その慌てた感じが珍しく、胸の内側にぺたりと貼り付いている。
「じゃあ、もし浅利さんだったら何も言わないということ?」
「いや、言わなくはないんだけど、僕にもほら、女房としての意地があるから……」
「そうよねえ」
「この電話あやしいわね、と思ってもあれやこれや言いたくはないかなあ」
気付けば浅利先生は奥さんの立場で考えていた。越路さんは何度か頷き、「なるほどねえ」とゆっくり天を仰ぐ。こんな風に二人はよく話し込んでいて、その度におチビちゃんは普段の稽古との違いを実感する。
浅利先生が投げかける提案やアドバイスを、越路さんはしっかりと受け止めてから深く考える。その中心にあるのは言葉、歌詞だ。脚本には歌詞がちゃんと記されていて、二人はその世界に入り込もうと、あらゆる角度から言葉を見つめ直す。だから大抵は一曲ごとに突き詰め、全体の流れを確認するのはその後になる。ということは、今のこのやり取りも必ず本番に活きてくるはず――。
おチビちゃんはそう考え、手元の脚本を再び読み始めた。
もちろん張り詰めた時間ばかりではない。その場所が大町の山荘ならば尚更だ。ある日、こんな出来事があった。
立ち位置が稽古の時とは違ったので、あれは雑談していた時だったと思う。三人一列に横並びで、左隣には越路さん、そして右隣には浅利先生が座っていた。つまりおチビちゃんは二人に挟まれていたのだ。いざそうなってみると案外緊張してしまう。すると越路さんが、「ねえねえ、ここなんだけど」と、目の前で開いた楽譜を指差した。
「見えるかしら? この三連符のとこね、どうやって音出せばいいのかしら?」
え、と思わず声が出てしまった。天下の越路さんが私に何を質問してるんだろう? 一瞬頭の中が真っ白になるが、それは本当に一瞬だった。すぐに我に返りタジタジになる。もしかしたら冷や汗が出ていたかもしれない。えっと、と言いながらちらりと越路さんの方を見る。ああ見なければよかった、とすぐに後悔したのは瞳のせいだ。越路さんの瞳は期待感に満ち溢れていた。
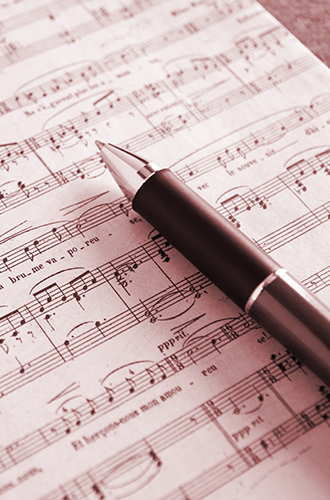
――きっと的確に答えてくれるはずよね。
グッとプレッシャーがかかる。もちろん三連符なら知っている。研究生時代にもレッスンで習ったし……、と何気なく右隣に視線を投げると、浅利先生が楽譜を覗き込んでいた。うんうん、と頷いている。
――うちの子はきっとやってくれるはず。
更にググッとプレッシャーだ。いや、大丈夫。先生に恥をかかせる訳にはいかない。今回のダメ取りを任せてくれた気持ちに応えなければ!
「ね、ちょっとやってみてくれる?」
はい、と答えた声は自分でも驚くほど大きくしっかりとしていた。きっと御二方の目には自信満々に映っただろう。これ、おチビちゃんの長所でもあり、まあその、アレでもある。本当はしどろもどろな時に、「はい、その件に関してでございますね」と落ち着き払ってしまうのだ。
この時もそうだった。本当に「三連符」は知っている。嘘じゃない。音符を三等分すること、タタタ、タタタだ。でも迷う。越路さんともあろう御方が、こんな簡単なことを質問するかしら?
きっとこれって、ああいうことよね。そう自分なりに考えて一所懸命に説明している途中、おチビちゃんは薄っすら気付いてしまった。今話してるのって「三連符」じゃなくて「シンコペーション」のことかも……。でも、自信満々の声は引っ込められない。話し終わると越路さんも先生も「……ふーん」「……ほうほう」という感じで席を立った。あ、と慌てても後の祭り。当然優しい御二方が、その件を蒸し返すことはなかった。
都内に場所を移してからは、段々と本番に近い形で稽古が行なわれるようになる。歌の世界に入り込む苦難を見てきたおチビちゃんは、その成果のひとつひとつに納得したり驚いたりを繰り返した。
越路さんと先生と自分、三人だけの小さい輪っかだったのに、こんなに大きくて立派な輪になるなんて……! そんな想いを噛み締めながら迎えた昭和五十三年九月一日・金曜日、遂にリサイタルの初日が来た。
後年語り継がれるように、歌手・越路吹雪は観客に最高の舞台を観てもらう為の努力を厭わなかった。その結果、同じことの繰り返し――ルーティンをとても好んだという。
朝起きる時間や劇場へ入る時間に始まり、紀州産の梅干しを口に入れたまま日本茶を飲むことや、屈伸運動や逆立ち、入浴など、慣れ親しんだ所作をいくつも積み重ねて開幕の時間を待つ。そして彼女は毎回、極度の緊張に襲われていた。だから本番直前、マネージャー役の岩谷時子さんが指で背中に「虎」の文字を書く必要があった。
――あなたは虎だから、こわいものは何もない
そんな暗示で緊張を解し、岩谷さんに背中をポンポンと叩かれながら舞台へと向かっていく。この日もそうしたかった、と思う。ただ一点違ったことは、その岩谷さんが不在だったことだ。
開演前、おチビちゃんはスタッフの方と共に越路さんの楽屋で過ごしていた。中には御主人であり音楽監督、ピアノも担当する内藤法美さんや、「ジャズドラムスの神様」と呼ばれたドラマーのジョージ川口さんを擁するバックバンドのメンバーもいた。
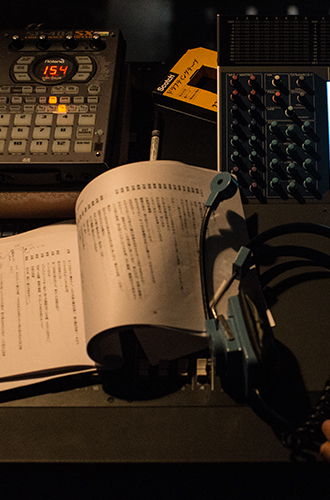
もちろん時間が経つにつれ人の数は少なくなっていく。バンドのメンバーが準備を始める為に部屋を出たので、そろそろ客席に戻ろうと立ち上がった瞬間、越路さんから「ちょっとちょっと」と呼び止められた。
「はい」
「あの、そこにいてくれる?」
「え? でも……いいんですか?」
どうしていいか分からず、楽屋を出ようとしていた浅利先生の方を見る。視線が合った瞬間、ゆっくりと頷いてくれた。これは「そうしてあげなさい」という意味だろう。
「うん。いてちょうだい、そこに」
「はい、分かりました」
「ありがとう。じゃあ、そこに座ってて」
浅利先生も退室して二人きりになった。越路さんはドレッサーの前にいる。おチビちゃんはその後ろの椅子に座った。本番まであと十五分ほど。しんと静かな楽屋の中、越路さんの背中を見ながら鏡越しに話をした。
「越路さんでも緊張することあるんですか?」
「もうね……、もう怖くてしょうがないのよ」
「……」
その悲痛な声色に胸がぎゅっと締め付けられる。
「いつも思うのよ。今日こそ幕が開いたら、お客様がひとりもいないんだわって」
稽古をしている時や、他愛もない会話を楽しんでいる時の越路さんが頭の中で混ざり合う。今、目の前に見える背中はとても寂しそうだ。孤独なんだな、と思った。なぜか「この人の子どもになりたい」と浮かんだ。
「あの……」気付けば口が動いていた。
「ん?」
「見てきます」
「……何を?」
「お客様が入ってるかどうか、私、見てきます」
少し間があった。変なこと言っちゃったかな、と俯いていると「ありがとう」と優しい声が聞こえた。
「じゃあお願いできる?」
はい、と答えておチビちゃんは楽屋を飛び出した。どう考えたってお客様は入っている。だから早く確かめて知らせてあげたかった。カーテンの陰からそっと客席を覗く。まだ客電が点いているからよく見えた。予想どおりの大入り満員だ。よし、と呟いて楽屋へと舞い戻る。

「越路さん、満席です!」
「あら、そう。ありがとう」
そう言ってもまだ安心していないのは分かった。見て分かるほどに震えていたからだ。だからおチビちゃんはそのまま楽屋に残り、越路さんの背中を言われるがままに優しく撫で、本番直前の舞台へと一緒に向かうことにした。
絶対に大丈夫と分かっていても、心臓の鼓動が伝わるほどの距離にいると、本当に歌えるのかしらと心配になってしまう。この幕の向こうには千三百人超のお客様。客電が落ちた直後の生々しい静けさがある。望んでいた最高の状況だけれど、このままではもしかしたら、と不安で仕方がない。
「大丈夫ですから」
そんな囁きが届いたかどうかは分からないが、越路さんを舞台に残しておチビちゃんは袖に戻った。いよいよ始まる。気付けば拳を握りしめていた。幕が上がり、音楽が流れ、歓声が湧き起こる。その瞬間の越路さんは凄かった。頭のてっぺんから何かが入った感じ。嘘ではなく、本当に膨らんで大きくなったのだ。もうそこに十数秒前までの震えていた孤独な越路さんはいなかった。
長ければ五時間以上、短くても三時間は続く日々の稽古を近くで見ていたからこそ分かる、本番ならではの力強さ、美しさに圧倒されてしまった。表現することの素晴らしさだけではなく、恐ろしさにも触れたような気がして、おチビちゃんはしばらくその場を動けなかった。
公演が終わった瞬間の姿もまた印象深い。客席に向かって深々とお辞儀をして、歓声と拍手に包まれながら幕が下りた瞬間、フラフラと今にも倒れんばかりの頼りなさで越路さんは袖へと戻ってきて、おチビちゃんに抱きついた。
「ねえ、どうだった?」
「……凄かったです。すごく良かったです」
少し間が開いたのは、越路さんの身体の熱に驚いてしまったから。燃え尽きる、とはこういうことなんだ。あんなに大きかった越路さんは、もうそこにはいなかった。
(第12回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『もうすぐ幕が開く』は毎月20日に更新されます。
■ 金魚屋の本 ■



