 ごく普通の女たちが再会したとき、何かが起きる。同窓会のノスタルジーが浮彫りにするあやふやな過去の記憶、すり替えられたイメージ。そして今、この信じがたい現実に女たちは毅然と向き合う…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ちょっぴりハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第4弾!
ごく普通の女たちが再会したとき、何かが起きる。同窓会のノスタルジーが浮彫りにするあやふやな過去の記憶、すり替えられたイメージ。そして今、この信じがたい現実に女たちは毅然と向き合う…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ちょっぴりハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第4弾!
by 小原眞紀子
8(前編)
「これはどう?」
「色はいいっすけど、生地が夏っぽいなあ」
青葉台のマンションで、川村仁は瑠璃の着物を品定めしていた。
「だって五月だもの」
「そうっすけど。写真に気温は写らないでしょ。写るのは季節感だけだからぁ」
その日、月曜の昼過ぎに来てほしい、と瑠璃は仁に頼んだ。前日の急な頼みだったが、その理由は彼も承知している。
二時頃、瓜崎の妻が訪ねてくる。
日曜日に、柿浦から瑠璃にメールが入った。もし差し支えなければ、早急にお訪ねしたいとのことです。
比較的丁寧な文面だったが、あの四人が教室にやってきてから丸一日も経っておらず、有無を言わさぬ恫喝とも読めた。
そうこうするうちに瓜崎は家に戻っていた、というのが一番ありそうなことだ。瑠璃はそう高をくくっていた。が、こちらも一応、誠意は見せなくてはなるまい。さもなければ瓜崎が出てきたとき、あの四人と本人を、どやしつけてやることもできない。
それでも独り住まいのマンションで、瓜崎の妻を一人で迎えるのは気が進まなかった。まるで妻と愛人の対峙の図ではないか。
「撮影のときだけ、羽織を着るってのはどう?」
「帯が見えなくなっちゃうなあ。この帯、すごくいいっすよ」
先日、姑に頼んで借りておいた帯だ。昔、古美術倶楽部の「おみ帯を誉めあう会」で評判を博した、と自慢していた。
「じゃ、カンペキに冬の装いでいきましょうよ」
仁は膝を叩いたが、最初からそう言い出すつもりだったに違いないなかった。このところ彼は、腹芸に近いものを見せる。
「えーっ。五月にこんなの、みっともない」
「いいじゃないすか。受講生には前もって、ことわっておけば。正月の回だし、カメラは入ってるし、当然っすよ」
「電車の中は?」
「誰も気にしませんって」
「車で送り迎えします、とか言えるようになってよ」
インターホンが鳴った。瑠璃と仁は一瞬、顔を見合わせた。
その玄関で、瓜崎香奈恵の姿を初めて見たとき、瑠璃の胸の奥に亀裂のようなものが走った。香奈恵が振りかざす、感情的なナイフで切られたのかもしれなかった。
「今、ちょうど打ち合わせ中で」と、瑠璃は言った。「取り散らかししていて、すみません」
帯や小物の取り散らかし。これ見よがしなひけらかしとも取られかねなかったが、香奈恵はそんなことにかかわずらう様子はなかった。リビングのソファにかけ、正面から瑠璃の顔を見ると、緊張し切った彼女の表情はいっそう固くなった。

「主人がお世話になっております」
「とんでもありません。昔、お世話になったのはこちらで」と、瑠璃は言った。「それ以来、ずっと疎遠にいたしまして、ろくにお礼も申さず」
ずっと疎遠だったと強調しても、瓜崎の妻の耳には入ってないも同然らしかった。
瓜崎香奈恵は、場違いなほど装っていた。裾が花型にカットされたサーモンピンクの華のあるスーツに、真珠のイヤリングまでつけている。居所のわからない亭主を心配して来たという格好ではない。指には結婚指輪のほか、ダイヤの婚約指輪もしていた。二カラットほどもある。ただしブランドはわからなかった。
「今、お茶を」
と、立とうとしたが、ダイニング・テーブルに用意したティーセットには、仁がすでに湯を注いでいた。見よう見真似でできるのだろうが、瑠璃にすれば逃げ道を塞がれたことになった。
気が利いているようで、やっぱり利いてない。
瑠璃は内心、舌打ちしたかったが、仁は盆を運んでくると、さり気なく近くのスツールに掛けた。そばで見守るつもりのようだ。
「あの晩のことですが」
瑠璃は自分から口を切った。認めたくはなかったが、仁の存在に励まされたかたちだ。
「十一時頃、品川でタクシーに乗せてもらって、それきりです。わたし、実はその晩から体調を崩しまして、ご馳走になったお礼のメールも差し上げないでいて」

「瑠璃さん、とおっしゃいましたね」
瓜崎の妻は一言ずつ、ゆっくりとしゃべった。押し込められていたものが漏れるようなしゃがれ声で、歳取った老婆にたしめられている気がした。その一方で、せいいっぱいの虚勢を保ち、準備した台詞を間違えないようにしている様子でもあった。
「その頃、皆さんにメールを送られてますよね。どなたか男の方とご一緒されていて、二人でどこかへ行く、といった内容の」
それが自分の亭主とはかぎらない。香奈恵はあの四人と違い、そこまで厳密に考え詰めているのだった。
「わたしがご一緒していたのは、間違いなく瓜崎さんで、そのときに他の方はいません。ただ十一時頃、四人にメールを送ったのは、わたしではありません」
「つまり、あなたの携帯からではない、と? アドレスを書き換えられたとか? 基地局に調べてもらいましょうか」
どうぞ、と瑠璃は頷いた。
「こちらからもお願いしたいくらいです。でも、仮にわたしの携帯からだったとしても、打ったのはわたしではありません」
「皆さんにも、そのようにおっしゃっているようですね」
瓜崎の妻は早口で呟いた。「では誰が? うちの主人? あなたが携帯から目を離した隙に?」
「送られた時刻からすれば、他にはいないと思いますが」
「あのメールには、彼、としか書かれてませんでしたけど。お店にいた、別の客の悪戯とか」
あらゆる可能性を考え尽くしたのだろう。香奈恵の言葉は、メールの送り主は自分ではない、という瑠璃の弁明を頭ごなしに否定してはいなかった。が、それは単に、目の前にいる女と亭主との関係を信じたくない、という裏返しに過ぎないかもしれない。
「他人の悪戯というのは残念ながら、あり得ません。高梨さんのアドレスはもともと、わたしの携帯になかったものだし」
寺内のもない、と思っていた。が、あのホールで名刺をもらい、登録しておいたのを忘れていたのだった。いずれにせよ、アドレス帳の画面から同級生だけを選び出せるのは、見知らぬ他人にできる技ではない。
「それに瓜崎さんが姿を消している以上、そのことと無関係に、偶然、悪戯メールが送られるなんて」
「でも、あなたはここにいる。あなたと一緒にいると、思わせたかったということ? どうして?」
それはわたしには、と瑠璃は口ごもった。
香奈恵は激してくると、口元に力が入って横へ伸びた。
カエル。湧き上がる不快さとともに、瑠璃はふと思った。昔、駅のホームで瓜崎に抱きつかれたとき、メスに飛びついて生殖を果たすオスのカエルだ、と憤った。以来、最近まで瓜崎を思い出すことなど、ほとんどなかったが、あるとすればカエルのイメージがまとわりついていた。あの日の再会が最初、存外に楽しく思えたのは、歳月とともに彼からそんな印象が消えていたからだった。
ここでそれを瓜崎の妻に見出すとは。
二十数年前、瑠璃に飛びつきそこねたカエルが、間髪を入れずに別のメスに飛びついて、自らに相応しい生殖を果たした。メスガエルはゼリー状の長い卵をいくつか孕み、衰えた肌と皺の寄った目尻でゲコゲコ鳴いている。卵を産ませたオスは今どこ?
「それは誰か、別の女性と一緒だからじゃないですか。瑠璃さんより、もっと知られたくない誰かと」
突然、仁が口を挟んだ。まぐれなのか、紅茶は瑠璃に劣らず美味く淹れられていて、仁もそれを啜っている。
水分のない丸い瞳で、香奈恵は仁を見た。感情を抑え、続く説明を求める様子だったが、仁はそれきり押し黙った。
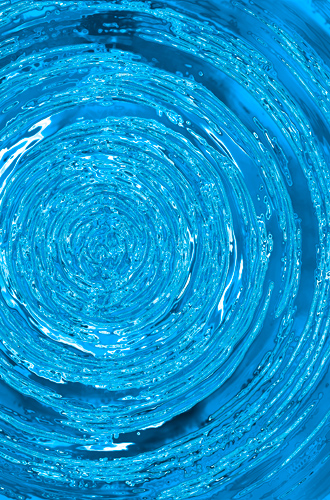
香奈恵は目線を落とし、しばらく無言でいた。
姫子の息子が瓜崎の種だという噂は、この妻の耳にも届いているのだろうか。少なくとも、そんな噂の立つ亭主に、何かしら思い当たる節がないはずもない。
しかし自分はこの女に対し、不必要に意地悪な見方をしている、と瑠璃は感じた。それはなぜだろう。姫子の息子は人間の子で、この女が果たしたのはぬたっとしたカエルの生殖だ、と思えてしまうのは。ただ姫子の葬式で、あの少年の顔を見たせいなのか。
「香奈恵さんも、南園大学のご卒業ですか?」
そうではないのを承知の上で、瑠璃は訊いた。案の定、南園の近くにある女子大卒だった。そこの女の子たちにすれば、南園の男を捕まえるのは「上がり」の部類に違いなかった。オスカエルなぞには見えないだろう。
ようやく瑠璃は、自分が腹を立てている理由に思い当たった。
桂華女子大にも、もうちょっと上玉がいたはずではないか。こんな横に潰れたみたいな女じゃなくて。サーモンピンクが似合わない、くすんだ肌色をどうにもできない女じゃなくて。もっとすらりとして、たとえ化粧や服にしか働かない知性であっても、センスというものを持ち合わせた女の子がいたはずだ。隣りの女子大にも女がいる、とやっと気づいたオスカエルであったとしても、何も最初に目に入ったメスに飛びつくことはあるまい。
まただ。瑠璃は自身の視線を嫌悪した。
もし瓜崎の妻がすらりとした美しい女だったら、別の意味で不快だったかもしれない。自分は最も軽蔑していたはずの、狭量でくだらない見栄に捕らわれている。それも瓜崎という、瑠璃にとっては何者でもない男のために。
香奈恵はおそらく、瓜崎の宣ういちいちに感心し、尊敬の眼差しを向けたのだろう。若い男がそれに安堵し、愛情を寄せるのは当然のことだ。しかし、男と女はそれだけでは済まない。従順だった妻は家の中で肥大化し、亭主の裏を知悉するようになる。亭主は歳月を経て、社会的に重みを増した自分の価値を評価し、裏の顔は知らない女に安らぎを感じるようになる。
姫子の息子が瓜崎の種だということ、少なくともその噂の根拠は、香奈恵を見れば十分納得がいった。
「柿浦さんがおっしゃるには、あなたの携帯には、メールを送った四人に対して着信拒否の設定がされていたとか」
そのようでした、と瑠璃は応えた。「わたしはその設定自体、知りませんでしたけど」
「あなたが目を離した隙に、というのは洗面所か何かに立ったときでしょう? 普通、携帯はハンドバックに入れて持っていきませんか?」
普段なら、と瑠璃は曖昧に応える。
「いつあなたが戻ってくるかもわからない短い間に、未登録のアドレスを書き込んだり、メールを打ったり、着信拒否の設定までしたと? それまで触ったこともない、あなたの携帯で?」
そうですね、と瑠璃は頷いた。
「その点は不思議に思います。だけど瓜崎さんは機械に、コンピュータには抜群に強いですから」
あり得る。少なくとも、あの瑠璃が記憶を失っていた二、三十分ほどの間なら、どんな設定だって。
「しかも店の中で? あのビアホールのウェイターだって、そんな様子を見た覚えはないそうですし」
「え。あの品川の店に、行かれたんですか?」
もちろん、行ったに違いなかった。瑠璃にとって、瓜崎の行方不明はつい先日、聞いた話だが、いなくなって一週間以上にもなる。
「客が携帯をいじってる姿なんか、記憶にないのは当然かもしれませんが。でも普段と変わらず、研究所に来たお客様を接待していると思ったと」
「普段と変わらず? 店を出るところまで?」
そうです、と瓜崎の妻はきっぱり答えた。特別な関係らしく見えたわけではない、と言いたいらしいが、そんな関係などないことは、瑠璃が一番よくわかっている。
ただ、瑠璃には店を出た記憶がないのだ。
店で意識を失い、瓜崎が誰かの手を借り、瑠璃を連れ出したものと思っていた。その様子を聞きに明日にでも店へ、ただし一人では口実が見つからず、それも仁に同行を頼もうか、と考えていた。
なぜ。なぜ覚えていないのだろう。
「とにかくメールのことは、わかりません」
瑠璃の動揺を見て取ったかのように、香奈恵は低く、だが確信を持って言う。「あなた以外、考えられないわ」
「覚えがないんです」
覚えがない。文字通り、そうだった。

だが、香奈恵に対しても、あの四人に対しても、記憶が途切れているのだ、と打ち明けることはできなかった。そんなことを真に受けるだろうか。あまりにも下手な言い訳で、もし本当だとしても、ますます信用おけない人物ということになる。実際、その記憶の失い方は、瑠璃自身にすら辻褄が合わない。
「そのメールとやらを瑠璃さんが打ったんだとしたら、どうなるんです?」
仁がまた、ふいに割り込んできた。瑠璃の加勢をしてというより、本当に疑問を抱いた口調だった。
(第15回 第08章 前編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『本格的な女たち』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■





