 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(十一)象の腰
目を開くと、まだ眩しい。いえ、違うわ、まっ白け。頭の中がじゃなくって、天井が。それから壁が、シーツが、そしてお布団が。いわゆるひとつの病室だったのでありました。
「あれっ」
ここはどこ、わたしは誰って感じだった。あれ、ちょっと右手が不自由。そんな違和感を感じて手を挙げてみたら、包帯でぐるぐる巻きになっていた。

「おや、目覚めたみたいだね」
覗き込んできたのは、姉ではなく〝もじゃ〟種山だった。
「よかった。気がついたんだね」
と太く低い声。あっちゃー、おじさんまで来てるわ。なぜに、種山およびおじさんが来てて、姉が来ていないのか。またいつもの逃げ口上の仕事ってやつか。
いずれにせよ、手首包帯でぐるぐる巻きになってるってことは、なんかやっちゃったのかね、わたし。
「これは、あやかくんですかね」
種山がわたしの顔をじっと見ながら問いかける。
「いい加減にしてくださいよ、先生」
むっとしてわたしは答える。
「見ればわかるでしょ。わたしはわたし、さやかですよ」
「ああ、そうでしたか。これはすみませんでした」
ちょっと気まずそうに眼を背ける種山。そうだ、恥ずべきだ。いったいいつまでこんな間違いを繰り返すつもりなのか。世界を股にかける(とかいわれてる)頭脳のくせに、まさに灯台もと暗しってやつだ。
といいつつ、ふと思い出すわたし。なにかがブツ切れになっていたような。そんな記憶の糸をたぐりよせたぐりよせするうちに、ああ、思い出した。
「そうだ。あの人あれからどうなったんです、ほら和也さん」
ついでに、「なぜにわたしがあの社長室からこの病室へとどこでもドア的な感じで移動しているのか」という問いの答えも知りたいところであった。
「覚えてないんですか?」
「って何のことですか?」
もちろん、覚えてないから聞いているのではないだろうか。
「君が活躍したんじゃないですか。ほんとあの時の身のこなしにはさすがのぼくも驚きましたよ。バンカラとは聞いてたけど、あれはすごかったですね。なにしろ、あなたはいきなり叫びながら宙に舞い上がったんですから」
「宙に?」
「そう、飛び蹴りってやつですよ。びっくりしましたよ。死のうとした和也氏の手からバタフライナイフをふっ飛ばしたんですから。そのまま勢い余ったのか、着地と同時に、和也氏の脳天に回し蹴りのおまけつきでした。おかげで和也氏は卒倒して、ソファの上に倒れたんですよ」
「まあ、飛び蹴りに関しては、わたしに責任がある」
おじさんが、種山に説明し始めた。
「ほら、わたしはご存じの通り武道の鬼だからね。この子を引き取ったときから、毎日道場に連れて行っていっしょに修業させたんだ。だから、合気道、空手、柔道、柔術、そして剣道の心得がこの子には一通りあるんだよ」
そうなのだ。おじさんは、父の弟であり、もう長らくわたしと姉の保護者でもある。さらには、いまや警視庁の警視である。若かりしころは剣道や空手で全日本選手権にも出場したことのある猛者である。名前は一条玄奘。経歴が示す通り、かつては泣く子も黙る暴れ者だったと聞いたことがある。けれど、わたしと姉にとってはいつも優しいおじさんだった。

「あれ、でもそれじゃ説明つかないじゃないですか。これ」
と包帯ぐるぐるの手を差し出すわたし。
「いまの説明じゃ、わたしが怪我をするいわれはない」
「うん、そうですね」
うなずく種山、困り顔になる玄奘おじさん。
「なんなのよ。どういうこと。勢い余ってすっ転んで手をねん挫したとかそういうことなわけ」
「そうですね、あやか、いやさやか君でしたね」
種山が確認するように聞いてくる。
「ですよ。さやかです」
よくできました。頭なでなでってところだ。
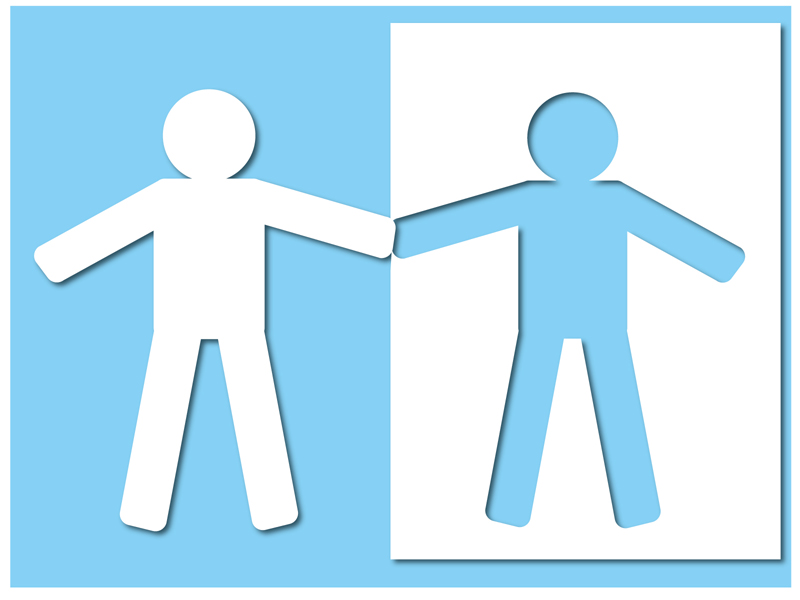
「あなたは覚えていますか。記憶が飛ぶ直前に何を見たのかを?」
「ええと、なんでしたっけ」
記憶を反芻するわたし。社長室。春山の顔をもった和也。それまで自信満々だった彼が、種山の言葉で次第においつめられて、ふいに席を立った。そして、
「あっ」
思い出した。
「バタフライナイフ!」
映像のバタフライナイフが、ふいにギラリと輝く。悲鳴がこみ上げる。
きえええええええっ。
ぎえええええええっ。
自分が叫んでいるのが遠くで聞こえる。ばたばたと暴れるわたしを、種山とおじさんが抑えつけているのがわかる。種山の力はほとんど感じられない。わたしを羽交い絞めにしていたのは、ほぼおじさんの腕力だった。割合としては、種山二%、おじさん九八%といったところだろうか。
でも、そこにわたしはいないような。遠くでそれを見ているような感じ。
「しっかりするんだ、あやか君」
種山が声をかける。だからあ、と訂正しようとしたときだった。
「もういないんですよ、さやかさんは」
わけのわからないことを言い出した。そのせいで、あっけにとられたわたしの体から力が抜けた。
「なにを、なにを」
わたしは、あきれて何か言おうとするのだけれど、さっき叫んだせいなのか、声がかすれてしまうのだった。
「いいですか、あやかさん。よく聞いてください。あなたの妹のさやかさんは、あの日に死んだんです。ご両親といっしょにね。たまたま友達の家に泊まりに行っていたあなただけが生き残った。そして、そのことであなたは罪悪感を感じたんでしょう。自分だけが生き残ってしまったこと、その直前にさやかと喧嘩して、お前なんかいなくなってしまえと叫んだこと。そのすべてがあなたを苦しめた。だから、あなたは呼び戻したんです。いや、作り出したんですよ。自分のなかにさやかというもう一人の人格を」
なによなによ、やんなっちゃう、種山ときたら。なにわたしを妄想化しようとしてんのよ。そりゃ、わたしの得意技は妄想だけど、わたしはここにこうしてちゃんと実在してるってのに。
それにしても、わたしまた今日も大学さぼっちゃったってことね。もうフラ語なんて、名簿から名前抹消されてるかもしんないな。ダブるのか? わたし、ダブっちゃうのかな。うわあ、かっこ悪う。
そんなわたしの内面の焦りとは(いつものように)無関係に、
「実はね、もうずいぶん以前から君のおじさんに相談を受けてはいたんです」
と種山は言った。
「でも、ぼくもそれなりに忙しかったから、今回ようやくあなたの問題に取り組むことができたんですよ」
「どういうことです。いったい何を言っているんですか先生は」
わたしはここにちゃんといるじゃない。はーい先生、わたしはここにいまーす。これがわたしこと、一条さやかでーす。
「あなたの妹のさやかさんは、バタフライナイフをもった犯人が君の父親や母親を殺す現場を見ていた。そして、最後に自分もまたそのバタフライナイフでめった刺しにされて命を落とした。現場検証の結果、殺された順番が明らかになり、そういう経緯が浮かび上がったわけです」
事件発生時、その場にいなかったあなたは凶器のバタフライナイフを見ていない。だけど、それゆえに逆にあなたの中にバタフライナイフの映像が強烈に焼き付いてしまった。蛍光灯の光を反射してギラリと光るそのイメージが。だから、あなたは刃物が光るのを見ると自分を制御できなくなる。ここの心理的な機構はとても複雑だから説明するのが難しいんですけどね。あなたはとにかく光る刃物が誰かの命を奪おうとするのを見ていられない。だから、全力でこれを阻止しようとする。けれども同時に、自分の内奥にある罪悪感が、今度は自分も死ぬべきだという信号を送るんでしょうね。だから、あなたは奪い取ったバタフライナイフを握りしめた。

「握りしめた?」
「そうなんですよ、それも柄ではなく、刃の部分をね。ぼくが止めなかったら、指が切れて落ちるまで力を込めていたかもしれません」
「そんな馬鹿な。それに、先生は、どうしてわたしが存在しないなんておっしゃるのですか」
「いや、存在はするんです。でも、あやかさんと別人ではない。まるでジキルとハイドみたいに、同じ体のなかにいて、なんらかの瞬間に入れ替わるんですよ」
「つまり、二重人格?」
「まあ、そんなものです。本来なら五歳で命を落としていたはずのあなたは、あやかさんのなかで、あるいはあやかさんといっしょに、小学校、中学校、高校と卒業した記憶を作り上げたんです。ちょっとグレた、喧嘩上等的な青春時代と、あるすてきな男性との出会いによる自我への覚醒、そしてついには大学生にまでなってしまった自分という、歴史を作り上げたというわけなんです」
「以前はお前も、ときどきわたしさやかよと名乗るくらいだったからわたしも大して気には止めていなかったんだ」
おじさんが言った。
「でも、近頃はあれだ。服装も、髪型も、顔つきも、そして人格のみならず体形すらもがあやかの時とさやかの時で異なり始めた。特に殺人絡みの事件になると、さやかが出てくる頻度が増えて、捜査に一貫性を欠くようになってきたんだ。だから、今回はさやかに任務を与えることにした。種山君と組んで事件を解決してもらうという任務をね」
「そんな」
あまりにもあまりにもだ。こんな事件を解決したと思ったら、最後に実は探偵の助手役だった娘自身が、実は存在してませんでしただなんて。
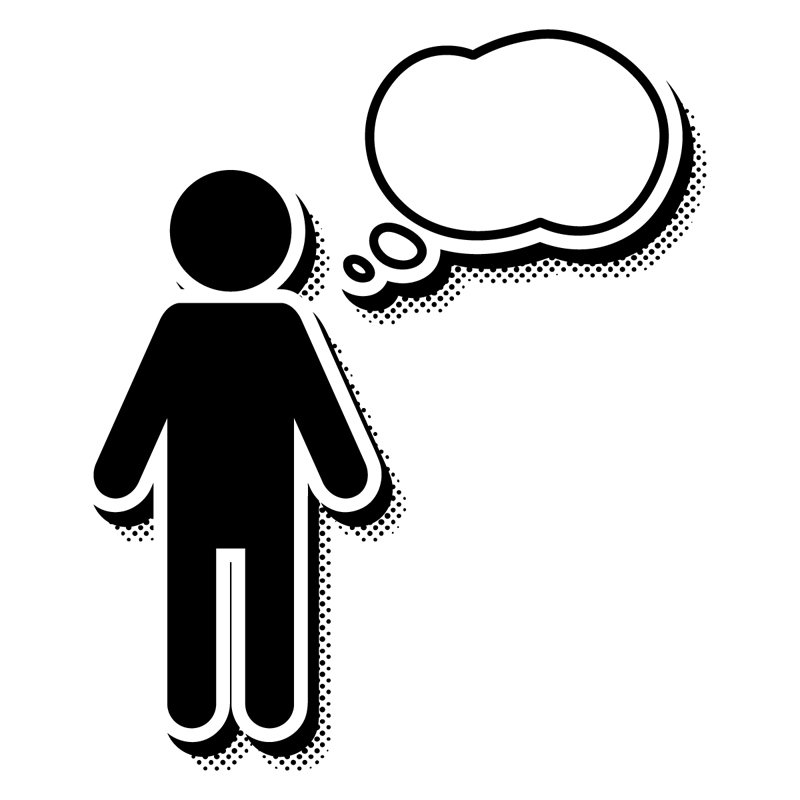
「もういいでしょう」
種山が口を挟む。
「今回はこれくらいにしておきましょう。さっきはぼくも言いすぎたかもしれません。いずれにせよ、ある意味であなたは確かに存在するんですから、頭ごなしに否定するような言い方は悪かったですね。なんにせよ、解決には時間がかかる問題だから、じっくりと取り組んでいかなくちゃあね」
「どういうことです?」
「つまり、あなたはあなただってことですよ。ぼくも考えを改めるとしましょう。あなたがやって来た時には、ちゃんとさやか君と呼ぶことにしましょう。そして、いっしょに解決の糸口を探ろうじゃないですか。あの迷宮入り事件のね」
「よろしくお願いしますよ、種山先生」
おじさんが深々と頭を下げた。
(第26回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







