 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(十二)象のお尻
そんなわけであっさり仮承認されました。わたしは、さやかです。
わたしがわたしじゃなくって、姉の一部だなんていわれてもピンとこない。だって、わたしはリアルに実在するし、リアルに悩み、リアルに感じてるんだから。姉の存在だって、リアルだし、おじさんだって、種山だって、今回の事件だってリアルだった。だから、わたしなんか実はいないのだァなんて話は、素直には呑みこめない。種山とおじさんが、二人してわたしをからかってるような気がする。まあ、よく考えれば、そんなブラックユーモアのセンスがありそうな人たちじゃないんだけどね。

まあ、いいわ。とりあえず気を取り直すことにする。そして、事後報告ね。
なんのって、そりゃ今度の事件のに決まってるじゃない。
結局和也さんは、和也さんとして生きることを決心したそうです。つまり、自首してすべてを告白し、人を殺したという事実を認めました。そう、種山のあの操作がなかったら、彼には自分が人を殺したのだという実感すらなかったのだというから驚きです。死んだのはあくまで和也で、自分はやっぱりハルなのだと、いまでもふとした瞬間にそう思っている自分がいたりするのだそうです。
どうして人間はそこまで自分を偽れるのか、ってこのわたしがいうと説得力ないか? だって、私自身が実は存在するはずのないキャラだっていうんだからね。うわっほお、こりゃまいった。
あらあら、ちょっと余計なおしゃべりが過ぎたかしらね。じゃあ、退院して、種山のところを訪ねて行った時のことを最後に話しておくわね。
「ひとつ残念だったのは」
コーヒーを飲みながら、種山が言った。
「ほんとうの黒幕に手が出せなかったことですね」
「えっ」
驚くわたし。久しぶりに訪れた先生の博物館でわたしは、コピをいただいていた。そうあのコピ。でももういいの。おいしいから許すの。ええ、もうなんだかいろんなことに驚かなくなったわたしなのですわ。
「どういうことです」
「ほら」
と指を一本立てて、
「もう一人いたでしょ、重要人物が?」
「えっ、誰でしたっけ?」
和也、ハル、ウライ、・・・ああそうか。
「滋郎氏ですか?」
「そうですよ」
「どうして滋郎さんが、黒幕なんです?」
「おそらく、彼は知ってたんですよすべてを。兄の弱さ、そして兄が憧れている人物がいるということ。そしてその人物が起業したということを」
「そんな」
「兄を焚きつけて二年間経営をやらせたのは、実は弟のほうだったってことです。最初から、失敗するのを見込んでのことだったわけですよ。その先のプランまですでに堅実な滋郎氏の頭にはあったんだと思いますよ」
「つまり、あれですか。自我の弱い和也氏を操って春山の起こした会社を乗っ取ろうと考えたということですか?」
「証拠はないんです。でも、いくつかの絵を突き合わせると、そういう答えが導きだされてくるんです。彼のことだから兄からの手紙とか、自分が彼に与えた暗示を立証できるような物証は何も残していないでしょう。だけど、純朴な和也氏に、あそこまで手の込んだ演出ができるとはぼくには思えないんですよ」
「で、どうするんです。このままほっとくんですか」
種山は首を縦に振った。
「現状では、こればかりはどうにもなりません。滋郎氏はなかなかの役者ですからね。和也氏の告白を聞くまではぼくにもそこまでの絵は見えなかったくらいですよ」
うーん、悔しい。そこのところは今回は泣き寝入りというわけか。
忸怩たる思いとはこういうのを言うのだろう。
悪人の高枕ってやつだ。真のアメリカ的経営者は実は滋郎氏だったってことだ。しかも、彼にはなんのお咎めも及ばないというわけだ。
わたしたちはしばし言葉を失った。ただ黙ってコーヒーをすすった。
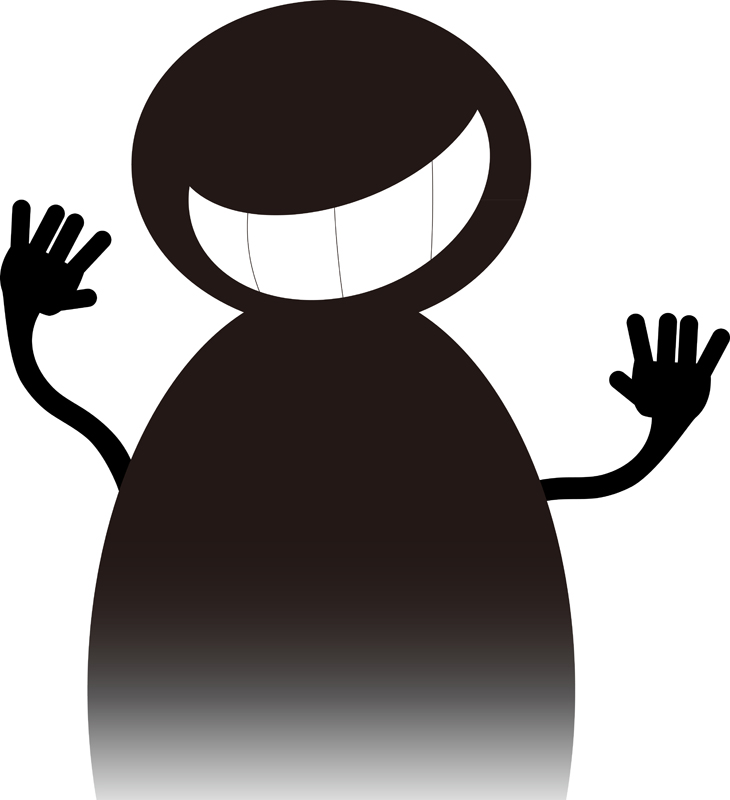
「そういえば」
ふとわたしは思い出して顔を上げた。
「先生、まだ最後の謎が残ってますよね。ほらお定まりの」
「そうでしたっけ」
「そうですよ」
「なんです?」
「あれですよ、密室」
「密室?」
「忘れたんですか。あの山荘の殺害現場は小さな書斎で、内側からは閂錠、外側からはカードキーできっちり施錠されていたんですよ」

「なんだそんなことですか」
くすりと笑う種山。おいおい、そこ笑うとこかよ?
「そんなことかってなんですか。ここを解決しなきゃ、探偵物とはいえないでしょうに」
「わかりましたよ、さやか君」
おお、なんかちょっと感動。ほんとはあやかなわたしなのかもしれないけど、いまはさやかなわけだから、やっぱりさやかって呼ばれると満足感あるわ。
「じゃあ、閂錠から行きましょうか」
「ええ、お願いします」
「あれは、実に簡単なんですよ」
「と言いますと」
「覚えていますか。タイの村の村長さんが言ってたこと?」
「どれのことですか」
「ほら、あれですよ、和也が釣りの名人だったって下りですよ」
「ああ、そういえば」
「そして、ドアの上のガラスに開いていた小さな穴です」
「ってまさか」
「そのまさかですよ」
と微笑む種山。
「小さな穴から釣り糸を下ろして閂に引っかけ、それをぐいっと引いてかけたっていうんですか?」
種山はうなずく。
「あの閂は、少し錆びてたし、閂自体が少しずれてたからなかなか横に引いてもしまらなかった。でも、少し上に持ち上げてやればスムーズに閂鎹に入るものだったんです。だから、和也氏はまず閂に釣り糸をかけ、それを上に持ち上げながらずらしたんでしょう。少しずつ少しずつずらしてきちんとはまったところで力を抜いた。すると釣針が閂から外れて落ちる。そこを巻きあげて回収したっていう感じだと思いますね。実に他愛もない方法ですよ。まあ、釣りの名人でなきゃ思いつかない方法だろうし、閂の特徴だって、当の住人だからこそ知ってたわけですしね」
「なんか拍子抜けですね。そんなチープなトリックだったなんて」
ほんと、あっさりしすぎた味のラーメンみたいだ。食べた気がしないってやつ。
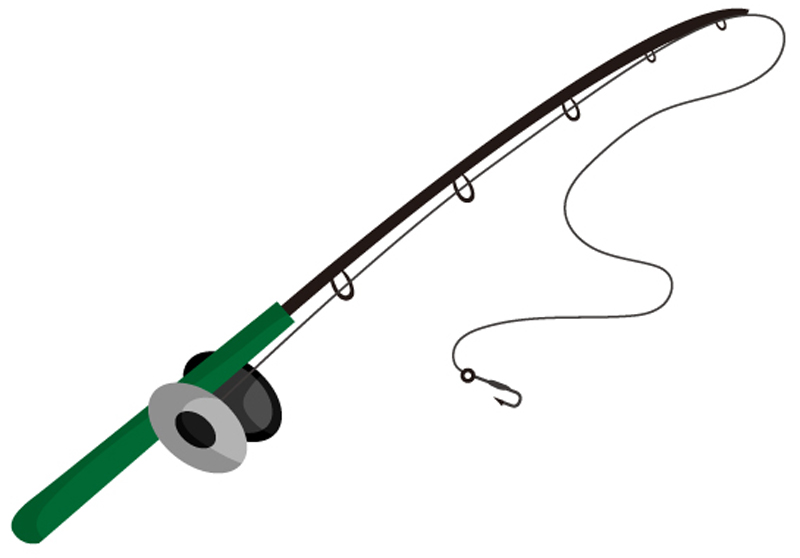
「でも、もうひとつはもっと拍子抜けじゃないですか」
「カードキーの件ですね? どうしてです」
わたしにはまだわかっていなかった。いまでも思い出すだけで、恥ずかしさに顔が赤くなる。
「だって、そうでしょ。あの部屋は滋郎氏の部屋だったんですよ。そして、事件当時は、代わりに社長をやってた和也氏自身の部屋だったんだから」
「あれ、そうか」
うわあ、まじやばい。これ問うべき問いじゃなかったわ、ほんと。ああ、やめてぇ。でも、秘技快刀乱麻!を発動する暇も与えず、種山は容赦なく、答えを口にしていた。
「そう、和也氏は自分の部屋を自分の鍵でロックした。いつものように。それだけのことですよ」
(十三)象の尻尾
赤面したわたしの目の前には植木鉢。
そこには、一輪の花が咲いていた。いいのよ、そんなこと恥ずかしがらなくってもとわたしを慰めてくれているようだった。菊のような細くて黄色い花びらが、何本も放射されている。
でも、奇妙なのは、その花が石を割って伸びていること。
そしてわたしは思い出したのだ。いまは玄関ホールのコーヒーテーブルに置かれているそれが、以前一○二号室で見たあの青磁玉だったことを。
微笑みながら種山が教えてくれた。
「そうなんです。これは、実は石ではなく植物なんですよ。リトープスという多肉植物の一種なんです。一見石にしか見えませんけど、秋になるとこうして分厚い葉が割れる。そして、中から伸びた蕾がきれいな花を咲かせてみせるのです」
生きていないはずのものが、花を咲かせる。そのイメージは、なんだか奇妙な安堵感をわたしに与えてくれた。どうしてだろうと、戸惑っているわたしに種山が微笑みかけてきた。とはいえ、相変わらずこの人は〝もじゃ〟なので、何かがそれで芽生えたりはしない。まかり間違ってもしないのではある。でも、そうではない何かがわたしを優しく包んでくれたのは確かだった。それは逆説めくけれど、もしかしたらこの人が〝もじゃ〟だからこそ、可能なことであるのかもしれなかった。そんなことを思う自分に自分で驚いていたところ、
「こういう驚きこそ、いまのぼくたちには必要なんじゃありませんかね」
なんて台詞が種山の口から出たので、「えっ、おいおいっ」てな感じにちと焦った。

でも、それは読唇術なんかではもちろんなく、青磁玉についてのコメントだとすぐに気付いてわたしは体制を立て直すことができた。
コーヒーカップをおろすと、種山はその一見石にしか見えない緑の塊を指先で押した。ぷにっ、と薄くへこむさまからは、傍目にもどこか肉球的な感触が伝わって来た。
「すてきじゃないですか? 石にだって花を咲かせることができるっていうんですから」
(了)
(第27回 最終回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







