 私は「ニラスミレ」のハンドルネームで、文学愛好者が集うXのスペース「文学の叢」で小説を公開している。小説家になるのが夢で小説新人賞にも応募しているが、「文学の叢」の仲間だけがわたしの小説を話題にして批評してくれる。金魚屋新人賞受賞作家によるサイバー空間で紡がれてゆく小説内小説の意欲作!
私は「ニラスミレ」のハンドルネームで、文学愛好者が集うXのスペース「文学の叢」で小説を公開している。小説家になるのが夢で小説新人賞にも応募しているが、「文学の叢」の仲間だけがわたしの小説を話題にして批評してくれる。金魚屋新人賞受賞作家によるサイバー空間で紡がれてゆく小説内小説の意欲作!
by 金魚屋編集部
小説の続きが書けそうになかったので、仕事のフォルダから「朝比奈興業」と書かれたものを開いた。朝比奈興業は名前は結構ゴツいが、私の地元のスポーツジムを始め手広くビジネス展開している、結構名が知れた会社だ。長くお世話になっている企業さんで、今回の依頼は女性専用に営業されているジムの二十周年記念グッズのデザインを任されていた。提案に上がった主なグッズはTシャツ、ハンドタオル、マグカップ、タンブラー、ボールペン、エコバッグなど。女性会員専用ジムなので、女性に喜んでもらえるデザインにしたいとのこと。また、二十周年独自のデザインやロゴを新たに考えたいとのことで、部下と毎日打ち合わせをしていた。今の会社では役職がついているのだけれど、そんなのは名ばかりで、平のデザイナーと一緒に毎日お絵描きしている。私としてはそんな日々の方が充実していた。なにせ、絵を描くのが好きだった。
「今どき記念アイテムにボールペンってどうなんでしょう?」
後輩と呼ぶには若すぎる部下の岡林さんが、iPadのペンシルを鼻と唇の間に挟んで私に訊く。あんたこそ若いのにその昭和のおっさんのような態度はやめろ、と思ったが、彼女には案外新しい動作なのかもしれない。
「だって、今どき紙にもの書く人いないと思いません?」
「思いません」
「韮山さんだってデザインするのにiPad使ってるじゃないですか」
「まー、そうだけど、でも私は未だにメモなんかは紙とペンよ」
「マジですか?」
「マジですよ」
「でも、ジム通いする女性なんて最先端行く人が多い印象ありますけど」
「そうでもないんじゃない? 私みたいなおばさんだっていいスタイルが保てるなら、ジムに行ってみようかなぁ、って思うもん」
「顧客の年齢層、先に確認した方がいいやつですか?」
「いいやつですねぇ」
岡林さんはりょ、と言って、Zoomの画面から消えた。消える直前に口だけが「失礼します」と言ったように思えたのは、私の贔屓目か。
コロナが始まってすぐにうちの会社はZoomによるリモート会議を始めた。出社して来なくていいからその代わりにZoomの使い方をすぐに覚えるように、とのことだった。Skypeと何が違うんだろう? と思った。そのうちに「チーム」だとか「スラック」だとか、何かそんなものをインストールしているかというのが、メールで回ってきたが、役職が付いていることを利用して無視させてもらった(その後社内は「韮山さんがスラックに入ってないですから」みたいな理由で、業務連絡に関してなぜか混乱をきたしていた)。この年齢になると新しいことを覚えるのが億劫で、パソコンで書類を書いたりデザインしたりするのを覚えた頃に比べると、断然記憶力と応用力が乏しくなっている。デザイナーという立場上、辛うじて創造力は残っていたけれど、人と会話をするのに、やれミュート解除だ、背景がどうだ、あれ? これって自分の顔なの? と相手との会話内容より自分の顔にシワやシミが案外多いことの方に気が散って、最初のうちはなかなかミーティングに集中できないでいた。でもそのうち、大したもので、自分の手持ちのデザインや書類のシェアの仕方を覚えたり、周知していて欲しいことをチャットにリンクをはっつけたり、画面の設定を変えると少々薄化粧でも誤魔化せることが分かってきた。その頃ちょうど新しいパソコンを買おうと思っていたところだったので(あくまでも仕事用に)、上質のカメラが内蔵されているものを購入した。おかげでリモート会議の時はお世辞と分かっていても、上司や部下から、いつもおきれいで、と言われると嬉しいものだった。しかし、上半身しか映らないことをいいことに、いつも下半身はパジャマで、カメラの修正度数をぎりぎり一杯まで上げて、いかにもよそ行きの私を演じた。
リモート会議は多い時で週に四回くらいあり、そのうち顧客との打ち合わせもリモートになった。企業によってはセキュリティの高いWebexを使いたいと言うところが出て来て、新たに使い方を覚えなくてはいけなくて、アラフィフの私のシナプスは爆発寸前だったに違いない。出かけなくなったので、シナプスの爆発に反して、皮下脂肪の燃焼はなくなってしまった。自宅勤務が始まって半年ほど経った時だった。それまでは欲しい物や食材を配達で賄っていた私だったが、どうしても外に出なければいけない用事ができた。今となってはそれが何だったのか全く覚えていないのだけれど、外に出たらウィルス怖いなぁ、と思ってたことだけは覚えている。ところが、それより恐ろしいことが家を出る前に起こった。久しぶりにジーンズを履こうとした。よそ行き用のなるべく新しめのジーンズを手に取り、脚を突っ込み、ジッパーを閉める。それだけの作業。ところが、最後の作業がなかなか完了しなかった。朝起きて寝るまでパジャマのズボンを履いている生活を続けていた私は、ジーンズが入らない体型になっていた。この日より前に少し感じていた、しかし認めたくないことが実は起こっていて、自覚はしていた。お風呂で椅子に腰掛け身体を洗う時、少し前屈みになっただけなのにずいぶんお腹の周りがきついのだ。なんというか、お腹の肉が太腿を圧迫しているのがはっきりと分かる。その日もなんとかジーンズの中に肉を押し込め、車に乗り込んだ。車に乗るのも久しぶりだった。シートに身体を埋め、いざシートベルトを閉めようとすると、すでにシートベルトを閉めたように太腿の付け根が窮屈なのだ。さっきジーンズに押し込んだ肉が、居心地悪そうにジーンズの布を内側から押し戻そうとしていることは明らかだった。我慢して運転していると、脚が付け根から鬱血しているのがはっきりと分かり、それからというもの、私は外出が色々な意味で恐怖になった。
しかし家に篭るようになってからのメリットも見逃してはならい。今までに増して小説を書く時間が増えたのだ。
小説というか、物語というか、そういう創作を始めたのはかなり幼い頃だった。小学校の二年か、三年、確か担任の先生が杉山先生ではなかったから、きっと四年生の時ではない、もっと若い時だった。自分で話を書いて、絵も描いて、ホッチキスで留めて装丁して、でも学校の図書室に置いてもらうのはさすがにためらったので、自分の教室の本棚に置いてもらった。といっても誰の許可も得ず、勝手に貸出しカードも作ってみんなに読んでもらおうと考えた。喜んでもらえると思った。人生初の自費出版だ。貸出状況がどうだったのかの記憶はないんだけれど、その後も空想や妄想を文字にすることは得意だった。宿題の作文や絵日記はほとんどが作り事だった。書くことがなければ自分で作ればいいと思ったから。それに読んだ先生は皆褒めてくれたし、罪の意識なんて少しもなかった。そんな創作活動は高校生になっても続き、この頃初めてちゃんとした小説を書くようになった。友達が読んでくれるからますます書くようになり、私が書くから友達がまた読んでくれた。そのうち友達の一人が、何かの賞に送ってみてはどうかと言い出した。

「よくは知らないんだけど、私のお兄ちゃんがなんか時々やってるみたい。訊いておこうか?」
私は何だか曖昧な返事をしたような気がする。その頃の私は小説家になろうとは思っていなかった。絵を描くのも好きだったから、デザインの専門学校か美大に行こうと思っていたから。それに小説家って、何だか大変そうな仕事だと思っていた。連載が大変だとか、家から一歩も出られないで煙草ばかり吹かしているとか、ホテルで缶詰にされるとか、そんな印象の職業で、絶対にやっていけない仕事だと思っていた。実際に小説家をやっている人に会った訳ではなかったけれど、世間で言われているそういう噂のようなものに、当時の私は絶大な信頼を持っていた。結局美大を受けることにしたのだけれど、そこの大学の入試に小論文があって、体験に基づくことを何か書かなければならならなくって、でもそんな体験したことがなく(外国人に出会ったらどうたらこうたらという内容だったような気がする)、だからあっさり嘘をでっち上げた。聞こえは悪いが、れっきとした創作品だ。
美大に入ってからは絵ばかり描いていて、自分がかつて文章を書いていたことさえ忘れてしまっていた。たまにアルバイトをして、人並みに恋をして、授業に熱中したりサボったりして、一般的な失恋の仕方をして、デザインに没頭するようになって、やがて卒業して普通に就職した。職場で出会った男性と結婚してしばらく仕事も疎かになるぐらい幸せな時もあったけれど、世間的には受け入れられないような理由で離婚して、その後は仕事に身を捧げた。
でもある日突然、私、小説家になっていないな、って気づいた。今晩カレーを作るのに、あ、じゃがいも買うの忘れたな、そんな感じだった。だから、本当にその日から書き始めた。小学生の時の初の自費出版と高校の時に友達を楽しませるためだけに書いていた小説とそれ以外の創作作文で埋められた私の人生の、ちゃんと小説家じゃなかった部分を黒い墨で埋めていくように、今まで私がずっと小説家だったと自分が錯覚できるように、時間があったらずっと何か書くようになった。高校の時の友達が言っていたように、新人賞に応募するようになった。書いては送り、送っては書き。でもただ時間が経過するだけで賞をもらうことはなかった。しかも歳を取るとだんだん体力が追いつかなくなり、鶴の恩返しの鶴か! という惨めさに身体が沈んでいった。過去の空白を埋めて目標に向かっているのではなく、まるで今と未来を無駄にしているように感じ始めた。未だに私はジムで配られるグッズのデザインをしている、五十才のおばさんデザイナーだ。
コロナでおうち時間ができて小説に打ち込める時間は増えたけれど、それは今まで以上に駄作を生み出す時間にもなりつつあることに、自分自身が気づかない訳はなかった。そんな時に出会ったのが音声アプリで、その中でも私の作品について唯一話題にしてもらえる文学の叢というスペースだった。世間の人は誰でも知っている。アイドルになれるのが一握りの人間だとすれば、小説の賞を獲ってプロの小説家になれるのも、また一人握りの存在だけなのだということを。だから、私がいい大人になってから「小説家になろうと思っている」と言っても誰も真に受けないし、そのことは誰よりも自分が一番知っているので、小学生が将来の夢を語るようには、もちろん私は喋らない。でも、本を読むことが好きで、文学が何たるものであるかを理解し、創作に厳しい意見を持つ文学の叢のメンバーには、私が小説家を目指していることを打ち明けた。それはまるで出生の秘密を暴露するような、ずっと隠していた痣を公開するような、そんな覚悟だった。
「うわー、それ、一度読んでみたいなぁ。読ませてもらえますか?」
今となっては誰の言葉だったか覚えていないのだけれど、「読ませてもらえますか?」の響きを聞いて私は余計に萎縮した。プロではない自分の小説を無料で読んでいただくことがどれだけ図々しく、また読者にとっては素人の作品を読まされることほど鬱陶しいことはないからだ。
「面白くなかったら、途中で止めていいですからね。知り合いが書いたものだから読まなきゃ、じゃなくて、嫌いだと思ったらそこで読むの止めてください。それも評価の一つですから」
メンバーは当時もう一人いた。歌舞伎山さんという、日舞、能、狂言、和楽器などをこなすという、得体の知れない、でもよく独り語りをする人だった。
「僕もねぇ、ニラスミレさんの作品、読んでみたいですよ。何かを表現するということでは、僕がやってることも小説を書くことに通じると思うし、ニラスミレさんが人の生き方や哲学のようなものをどうやって文字で表現するのか、読んでみたいですねぇ。ただ一つ質問なんですが、ニラスミレさんはどうして賞をとって小説家になりたいんですか? 小説書くなら、ネットに投稿したり、noteに有料で執筆したり、文学フリマもあるし、自費出版もあるし、なんで新人賞にこだわるんですか? 承認欲求あるけど不特定多数の人に不本意な評価されるのはいやなんですか? プロの小説家になって、結局本を買ってくれるのは不特定多数の人なのに?」
私は歌舞伎山さんの発言の後何も言えずに、歌舞伎山さんの般若のアイコンがピコピコ光るのを、焦点の合わない視野の中で感じていた。
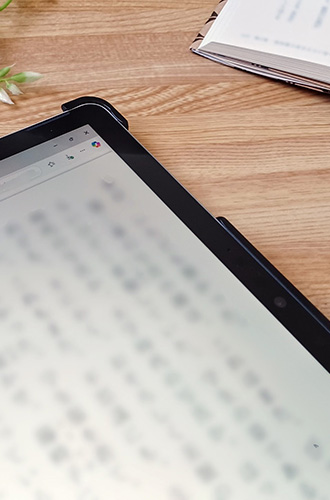
この後すぐだったと思う。文学の叢が今の音声アプリの方に移って来たのを境に、歌舞伎山さんとは話さなくなった。単に歌舞伎山さんがこっちのアプリのアカウントを持っていなかっただけなのか、グループ自体に興味がなくなったのか、私という存在に嫌気がさしたのか、この音声アプリという空間での人間関係というのは、リアル社会のそれとは大きく違って、親密にはなれない分、面倒臭さや後腐れのない関係も築ける。次の週から現れなければ、それだけのこと。その人が病気になっていようが、極端な話死んでいようが、自分の人生には直接関係ないのだから。
そう思う割には、このスペースのメンバーに対する自分の心の持っていきようが、そんなにドライじゃないことに気づいていた。コネクションというのかエンパシーというのか、読書好きの仲間だから持てる、遠く離れていても感じ合える何かそんなものを感じ始めていた。だから、私はここのメンバーのために小説を書き続けようと思った。
「うわー、ニラスミレさんが本当に小説家になっちゃうなんて、すごいなー。『あの小説の最初の原稿読んだの、僕たちなんだ』って自慢してるんですよ」
などと話すのを想像する。メンバーの他に十数人の、いや数十人のリスナーが集まっていて、質問や反響がメッセージに送り続けられる。この頃には実年齢がバレていて、「なーんだ、そうだったんだ。でも別に隠さなくてもよかったのにー」と笑い合うところも想像している。
全ては想像の中にある。私は、今晩朗読した小説の続きを書くことにした。理由はなんであれ、とりあえず父親の遺言書によって嫌いな男と結婚することにして、父親の意図なのか家訓なのか、その辺りは書いているうちに思いつくだろう。結婚式で派手なバトルなんかも書きたい。本人同士だけでなく、親や親戚一同が巻き込まれる壮絶なやつ。結末は決めてはいなかったけれど、嫌いな人と結婚した主人公の心情を表現するには一人称のままでいいだろう。書くことは孤独だけれど、意見を言ってくれる仲間がいるというのは宝だと思っている。しかも、隣にいて触れることができる人じゃなくて、見たことも触ったことも匂いを嗅いだこともない人たちの声だけで、励まされたりアドバイスされたり褒められたりしている。そんなおばさん、世界広しといえども私ぐらいだと思う。
沙良とドレスショップを出ると、わたしはすぐ隣の不動産管理をする事務所に入った。沙良にしてみればわたしのウェディングドレスの試着に興味があり、わたしは逆に彼女について行った形になった。結婚式を挙げること自体馬鹿げている。ウェディングドレスにも興味がない。偶然にもウェディングドレスの試着の店と不動産会社の事務所が隣同士だった。結婚後に住むマンションも父の遺言書に書かれていたもので、新しく住む場所がどんな間取りなのかだけ見に行こうと思ったからだ。わたしにはこちらの方が重要だった。
こんな業種には珍しく、カウンターには人間が座っていた。わたしたちの姿を認めると、ぎこちなく立ち上がり、ロボットのような動きでお辞儀した。
「ご予約の方でしょうか」
「いえ、入居が決まっているマンションの間取りを、見せていただけないかと思いまして」
「少々お待ちください」
事務員はわたしの名前を確認し、その物件なら新築でまだ内装は出来上がっていないが、案内は可能だ、と不器用な笑いをした。
「本日はAI事務員がメンテナンスのために休んでおりまして、よければ私がご案内いたしますが」
彼女は履いていた赤い健康サンダルを脱いで、気だるそうに黒のパンプスに履き替え始めた。メンテナンスが必要なのはこっちの人じゃないかと思いつつ、間取り図だけ見せてもらえれば、と彼女の貴重な履き替えを制した。
「見ておかれた方が引越しのお見積もりもしやすくなりますので、ぜひ」
と、笑いもせず勧める。おそらく「せっかく履き替えたんだから見ておけよ」とでも言いたいんだろう。そこで、実際に見た方が自分の物や家具を運び込むのに都合がいいだろうと気が変わり、お言葉に甘えることにした。車で十五分ぐらいの場所らしい。
閑静な住宅街だった。並木道の樹木が緩やかな春の陽射しを楽しんでいるかのように、太陽の光を葉の一枚一枚に受けて輝いていた。木によっては葉がすでに生い茂っているものもあり、そんな木は上部だけに光を受け、下の方には一切光などやるものかというようにざわめき揺れて、陽の世界を遮っているように見えた。
好きな人と一緒に暮らすのはどんな気分なんだろう、とわたしは並木道沿いを走る車の中から木漏れ日を目で追い、ぼんやり考えていた。しかし、わたしにはその気分を味わう機会はない。未だに父の遺言書の内容が理解できないでいた。生まれ故郷に伝わる風習でもなさそうだし、父が死んでしまってからの政略結婚など、父親に何のメリットもないはずだ。しかも住むところまで決められていて、何かの実験だろうかとも思った。
しかし会社の重役だったとはいえ、ただのサラリーマンだった人がマッドサイエンティストのようなことを、なぜ実の娘に強いるのだろう? 実はわたしの知らない父の本当の姿があったのだろうか?
事務員の「着きました」の声で、わたしの妄想は中断された。うわー、素敵じゃない? と沙良はすでに車外に出てマンションのエントランスから中を覗き込んでいた。エントランスを含め建物は薄いグレーのタイル張りで、落ち着いた感じのものだった。植え込みも丁寧に手入れされており、蕾をつけ始めたアジサイと満開に近いツツジが目を引いた。植えられたばかりに見えるあざやかな色の一年草もエントランスに色を添えていた。外見は申し分ない。

建物の中に入ると、新築というだけあって新しいペンキと知らない匂いが混じり合った空間になっていた。部屋は十階建ての七階らしく、わたしは事務員が押すエレベーターのボタンをじっと見ていた。勝手に決められた新居だが、十階建ならせめて最上階にして欲しかった。エレベーターを降りると、ペンキの匂いが鼻の中をさらに貫いた。
「ドアの開閉は虹彩認証と4桁の暗証番号で安全になっております。暗証番号は2種類まで登録することができ、ご夫婦で同じ番号を共有する必要はございません」
事務員はマスターキーでドアを開けながらそう説明した。玄関から続く廊下をまっすぐ抜けるとリビングになっており、その手前にキッチンと、廊下を挟んで同じ広さのダイニングルームがあった。壁や天井はすでに出来上がっていたが、クローゼットやキッチンなどの建具は剥き出しになっていた。
事務員によると、このマンションは特別な関係や訳ありの家族または夫婦が住む専用のものらしく、そのために特別な設計がなされている、ということだった。
「ご契約の際に、憎み合った夫婦でお暮らしになる、と承っております」
と、まるで日常のように言う、今は持って来たスリッパに履き替えた黒パンプス事務員が、先頭に立ってわたしたちを案内した。キッチンは広めで使いやすそうだった。夫婦揃ってキッチンに立つこともなく、食事は基本的にバラバラに摂るので、鍋や炊飯器といったものがどれも二セットずつ必要なために場所を広く取ってある、ということだった。リビングも広々としており、そのほぼ中央の天井に大型のスクリーンが備え付けてある。これを下ろすことで部屋を二分できるらしい。初めから二分されていないのは、同居人がいない間に自分の都合で広く使ったり、友達を呼んでホームパーティなどをしたりするためだと、事務員がてきぱきと説明した。もう何十回と繰り返した言葉なのだろう。ダイニングルームは廊下を挟んでキッチンと対照の場所にあり、キッチンと同じ面積のスペースを作るために申し訳程度の殺風景な設計だった。キッチンとダイニングルームを二つに分けてしまうと、夫婦同士が同じ空間に同時に居る確率が高くなるらしい。最初からこの部分は共同スペースだと分かっていたら、相手がいない時を見計って使おうと考え、かえって相手の顔を見なくて済むらしい。ベッドルームはリビングを挟んで部屋全体の端と端に位置しており、各自のバスルームとトイレがついていた。引越したらすぐに、どちらの部屋を使うか決めておくことを勧められた。洗濯乾燥機は一台しかなかった。わたしたちのような夫婦や同居人の場合、それぞれの衣服をそれぞれで洗濯するのが当たり前だけれど、それでも相手が自分の前に洗濯機を使ったかと思うと、その服を二度と着られないという話を聞いたことがあるし、わたしも同意見だ。わたしの結婚はかなり特殊だと思うけど、そんな夫婦や家族がいるのも確かだ。そこで、十年ほど前に、一回洗うと臭いもDNAも全て洗い流し、同時に洗濯機自体の洗浄を行う画期的な洗剤が開発された。あとは、同居人が自分の前に洗濯したという記憶を努力して消せばいいだけで、洗剤はたちまち人気商品となった。ただ、この洗剤に使われている香料か何かが、同居人と同じ洗濯機で洗っているという記憶を消す効果があるのではないかという、都市伝説のようなものが広まった。事務員にこの洗剤の使用を勧められ、わたしは洗剤の存在に感謝した。あんな奴の汚れ物と一緒に自分の服を洗うなんて考えられないし、別々に洗ったとしても、洗濯槽を覗くと、目には見えないあいつの身体から溢れ出た臭いや体液やDNAがみるみる現れてくるようだった。そんな毎日を送れるわけがない。都市伝説であろうとなかろうと、記憶を消してくれることはすごく助かる。
この間取りなら一人で住んでいるのと同じで気が楽かもしれない。わたしは大学を卒業してしばらく一人暮らししていた頃のことを思い出し、悪くはないな、と思い始めた。さっきまでは人生の墓場をうろつく幽霊のように過ごす自分を想像していたけど、あいつの存在を消して暮らせるのなら、案外墓場は静かで快適なのかもしれない。
黒パンプスがなぜか沙良に熱心に部屋の間取りを説明している間、わたしは窓の外の景色を眺めた。この地域から海が見えるとは知らなかった。海と言ってもビルとビルとの間にコンクリートの岸壁がほんの少し見えて、その向こうにキラキラ揺らめく物が見えているだけだった。光の反射で海がどんな色をしているのか判断できなかったけれど、最初から海はその長方形に見える部分だけしか存在していなかったかのように、水面の穏やかさは海の一部分を一つの物質のように見せていた。最上階だったら、もう少しはっきりと見えるのだろうか。しばらく海に行っていないことを思い出した。墓場から見る海は自分だけの秘密のようにも思え、悪くはない、と再確認した。
沙良が自分の新居に友達を初めて呼んだ時のような顔をして、わたしに近寄ってきた。どう、気に入ったでしょ? と、多数決で最後の一人の同意を得るためのような口調だった。同意も何も、父親がすでに決めてしまった物件なのだから意義もないし、結婚相手と意見を出し合って話そうとも思わない。わたしは沙良に同意して玄関に向かった。もう十分だった。黒パンプスは、入居予定の六月までには内装も出来上がっているのでご心配なく、と言い、最後に暗証番号の設定の仕方を説明して、「小村瀬様のお嬢様でしたら、仕方のないことでございますね。どうぞお幸せに」と深々と頭を下げた。わたしは振り返って、「わたしの結婚のことを何かご存知なんですか?」と尋ねた。彼女はただただ無言で、顔はAIのものよりずっと無表情に見えた。

「こんばんはー、お疲れさですぅ」
「こんばんはー。ふぇるまーさん、今日のホストありがとうございます」
「いえいえ。間に合ってよかったです。研究室寄ってて、しゃべってたら結構時間経ってて。来週の方が遅くなる可能性あるから、今日でよかったです。来週はニラスミレさんがホスト番ですよね?」
「確かそのはず」
「こんばんはぁ」
「あ、拓郎さん、こんばんはー」
「ニラスミレさん、読みましたよ」
「あ、どうでした?」
「面白かったですよ」
「僕も楽しく読ませてもらいました」
「ありがとうございます」
「特別なマンションがあるんですねー」
「父親が決めたマンションが、訳あり夫婦や家族が住むタイプのものってしておけば、不自然じゃないかなって思ったんで」
「うん、確かに」
「こんばんはー、今日は僕が最後かぁ。ホストじゃないと、時間忘れちゃいますよねぇ?」
「え? 忘れてたんですか?」
「そういう訳じゃないんですけど、気づいたら八時ぴったりでした」
「あるある、そういうこと」
「ニラスミレさんの小説、読みました?」
「読みましたよ。面白いなー。続きどうなるんだろう」
「どうしたらいいと思います?」
「まだ決まってないんですか?」
「んー、なんとなく決まってるんですが」
先週朗読した続きをGoogleドライブでシェアして、みんなに読んでもらった。いえ、読んでいただいた。それほど長くはなかったし、というよりあれからアイデアが定まらず、長いものにはならなかったのだ。しかも朝比奈興業さんからさらなるグッズのアイデアがあり、小説どころではなかった。三月末に締め切りのある賞に出そうと思っていたのに、少し不安になってきた。
私が書いた小説を周りの友達に見せるとみんな面白いと言ってくれる。面白いとは言ってくれるが、それだけだ。どこが面白いのか、逆に面白くないところはどこなのか、すらすら読めたのかそれともその逆なのか、本屋に売ってたらお金を出して買うか、そういうことを私は聞きたいのに、友達は皆気を遣っているのか、決して私を傷つけようとはしない。その点文学の叢の人たちは、私が聞きたくないことまで言ってのける。
「感情移入がしにくいです」
これをよく言うのはふぇるまーさん。彼は小説も数学的に読むと言う。
「A=BでB=Cだとすると、A=Cじゃないですか?」
「まー、そうなるんですかねぇ」
「僕はこのA=Cを小説の中に見つけると、うれしくなるんです」
ちょっと何を言っているのかよく解らない。
「物語の主人公はあくまでも物語上の背景なり設定なりに生きている人間ですが、それを自分に置き換えるという作業は、物語の空間と自分の思考の空間を行き来するということであって、難しい作業です。だから、双方のトンネルを抜けていくような工程中に矛盾や否定が見えると、感情移入がしにくいんです」
要するに私の小説にはA=Cと言うためのBが見つからないとか何とか、何かそんなようなことを言われたことがある。私が書く小説に限らず、他の課題図書の時にも同じようなことを言っていた。
「ふぇるまーさんって、あの『フェルマーの最終定理』のフェルマーから取った名前なんですよね?」数学に疎い私でもこのぐらいの知識はある。「やっぱりフェルマーを尊敬とかして?」
「いえ、別に。僕が本当に尊敬しているのはゴールドバッハなんですが、音声アプリ始めた時ゴールドをひらがな、バッハをカタカナにしたアカウントにしてたんですよ。ところが皆さん『音楽される方なんですか?』って訊いてきはって、説明するのが面倒になってきて、それで誰でも知ってるやろうフェルマーに途中から変更したんです。フェルマーだったら誰でも知ってるみたいやし」
という話を一度してくれたことがあった。「誰でも知ってる」ではなくて、自分たち凡人が知らない部分を抉られたような気がした。
拓郎さんはいつも文体のリズムについて語ってくれる。文章は歌と同じで、リズミカルに流れなくてはいけない、と。大いに同意できるのだけれど、百枚を越える原稿がいつもリズミカルに進むのは不可能だ。
「分かりますよ、うん、すごく分かる。オレもねぇ、曲書いて詩を書いて、曲にしていくうちに、なんか違うなーって思って、でも、絶対曲げたくないところとかあって、その極限まで行った時、芸術って美しくなれるんじゃないかなー」
どうぞご勝手におやりください。私は私のやり方でやっていきますから。多分、曲を作るのって小説を書くのとオーバーラップするところは多少あるでしょうけど、根本的に違うと思います。
国語教諭のF・牛森さんはもしかすると一番口調が柔らかく(柔らかいけれど甲高い)、そして一番厳しいことを言う人かもしれない。
「いいと思います」
感想を尋ねると、F・牛森さんはいつもこの言葉で始める。
「でも」
これが接続詞。
「すごく読みやすいです」
小説を書く人の九割が、この言葉を褒め言葉だと勘違いする。
「すらすら読めます」
これは、次々読みたくなる、というのとは違っている。
「意味が分からなくて立ち止まるというのではなく、これってどういうことを指しているんだろう? あれ? 今まで自分がこうだと思っていたことと違ってきている? みたいな、そういう疑問みたいなものが生まれた時って、読書してて楽しいじゃないですか?」
確かにそうだ。淀みなく読める話は、苦痛はないが印象も薄くなりがちだ。読んだ直後に話の内容を忘れてしまうこともあるかもしれない。でも途中で語り手が変わったり、媒体が変わったり、文体が変わったり、思っていた設定にどんでん返しなんかがあったりすると、あれ? と立ち止まると同時に何か新しい刺激がある。
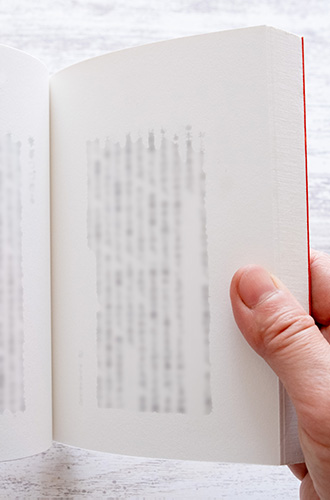
「そういうのって、なかなか難しくって……。やってみようとは思うんですけどねぇ」
とごまかすことにしている。
「えっと、ちょっと気になったことがあるんですけど」
ふぇるまーさんだった。
「はい、何でしょう」と私は身構えた。また訳の解らない数式を持ち出してくるのだろうか。
「ウェディングドレスってありますが、主人公は結婚式を挙げるんですか」
「はい、そのつもりですけど。文章中にも結婚式をあげないといけないって書いたはずです」
「それって、なんかきついなー」
「え、どうして?」
ここでまた年上風が吹いてしまった。
「結局は親に決められた、自分が嫌っている男性と結婚するんですよね? いくら親に決められたからと言って、結婚式まで挙げるのって、どうなんでしょう? 人権無視じゃないです? 僕やったら婚姻届だけで勘弁してもらいたいわ」
「はあ、なるほど」
私は結婚式の場面で、新郎新婦、つまり主人公と彼女が大嫌いな夫となる男性とが大喧嘩する場面を書くつもりだった。ここまではなぜ父親が主人公を嫌いな男と結婚させたいのか明かされておらず、それが分からないうちに結婚式での大喧嘩を描写するには、かなり心理描写などが難しいだろうなぁと思っていたところだった。
「そうですね。結婚するから必ず結婚式って考え方、古いですよね?」
「古くはないですけど、どんな結婚式になるのかな、と、ま、僕もそう言いながら興味あるんですけど」
と、このようにここの人たちはちゃんと私の小説に意見してくれる。結婚式はせずに、単に婚姻届を出そう。
ふぇるまーさんの意見に何か強い反論が出たわけではなかったが、小説の流れを再び修正した。あとは父親の遺言書の理由。でもこれは最後まで謎でもいいだろうか? で、三人とも続きが読みたいと言う。しかも、今回誰も課題図書の
アイデアを持って来ていない。
「しばらく課題図書はお休みにして、ニラスミレさんにどんどん書いてもらって、その感想をしばらく毎週話し合うのってどうでしょう?」
F・牛森さんの提案だったが、それって私は休みなく書き続けていなけりゃいけないってこと? 紫式部の苦悩が降りて来た。朝比奈興業の件でなかなか小説に集中できない時期なんだけどなぁ、でもこうやって強制的に書くことで、完成に繋がっていくものなのかもしれない。
「じゃ、やってみます」
承諾していた。
楽しみです、という内容のことをそれぞれの言葉で言った後、今晩もお開きとなった。
「あ、今気づきました」
浜ちゃんのキンキン声が聞こえた。
「来週で今年最後ですよね?」
みんなで同意。来週の土曜日が今年最後の文学の叢の集まりだ。
「じゃ、ニラスミレさんの物語も、いい感じで終わっていただきましょう」
「え? 完結しろってことですか?」
「そういう意味ではないです。なんかそのー、佳境に入っていれば、盛り上がるかと」
「やってみます」
何だか今晩はこればかりだ。
じゃ、また来週ぅーと言い合って、スペースは閉じられた。スマホの黒くなった画面を見てもやっぱりすぐには小説を書く気にはなれず、朝比奈興業のフォルダに目が行った。月曜の朝九時に、朝比奈興業の担当の人とリモート会議がある。朝比奈興業はZoomを使わない企業の一つだ。カレンダーにWebexのリンクが貼ってあることを確認した。先日私たちが出した案以外にスマホグリップの案が出たところだった。
「ほら若い子らがスマホの裏に付けてる、指をチョキにして持てるやつ。あれ、どうでしょうねぇ?」
社に持ち帰って検討します、と言った後、岡林さんに訊いてみた。
「まぁ、人気はありますよね、私は使ってないですけど。でも、リングとどっちがいいって訊かれたら、やっぱ今はグリップかなぁ。結構かわいいデザインのとか出てますからねぇ。朝比奈さんところのフィットWのキャラクターをデザインしたら、かわいいんじゃないですかねぇ」
フィットWというのが今回記念グッズを作る女性専用ジムなのだけれど、先日スマホグリップについて聞いた時は、とりあえず知ったかぶりをして帰って来た。フィットWのロゴにもなっているマスコットはラマ。そう、あのもふもふした馬なのか牛なのか羊なのか分からない、あの癒し系の動物ラマなのだ。しかし聞くところによるとラマは走ると非常に速く、時速六十キロほどになるらしい。見た目はおっとりでも動くと凄い、そんな女性を目指すためのジムとして始まったフィットWのロゴがラマ。
「私個人的には、このラマちゃんの形そのもののグリップがいいと思うんです、単に丸の中にプリントするんじゃなくて。予算は高めになりますけど」
岡林さんが自分のiPadにちゃちゃっ、と描いて見せてくれた。いいねぇ、じゃ、今度のリモート会議、入ってね、と言いながら、私は要らんなーと脳みそでため息をついた。私はスマホを手帳型のケースに入れている。ケースのポケットにクレジットカードやポイントカードや免許証などを入れて持ち運ぶ。以前はあの本を開くみたいにパカっと開けて、もしもし、って言うのがおっさんくさいなー、と思っていたのだけれど、使ってみると案外便利なのだ。
私たちの会話を横で聞いていた隣の課の課長の高橋さんが、自分は車内でワイヤレス充電するから、後ろにそんな出っ張りあったら使えんわー、と笑って離れて行った。高級車に乗っていらっしゃるようだ。結局岡林さんがちゃちゃっと描いたデザインも提案することになり、それも含めて月曜のミーティングの資料まとめをしてから寝た。
(第02回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『四角い海』は5日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


