 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(十)象の後足
「うーん」
わたしはうなった。
「なんか、やっぱり切なすぎるんじゃない。これって?」
「いや」
そうでもないのではないかと、種山の声音が語っていた。
「あなたは、きっとそれなりに幸せだった。そうでしょう?」
和也は素直にうなずいた。
「ええ、奇妙なことですけどね。わたしは春山になりきることで、救われていたのです。久しぶりに訪れた兄の会社の社長室で、経営雑誌を目にするまではね」
つまり、と種山が問うた。
「あなたは見つけたのですね、ハルさんを」
「そうです」
新世代のベンチャー経営者たち、という特集だったという。「ギターを手放さないユニーク経営者」という見開きに、彼が取り上げられていたのだそうだ。
「しかも、変わっていなかった。恐ろしいことに、まったくあのころのままだったんです。村にいた頃と同じようなジーンズにTシャツ姿で彼は微笑んでいました。まったく変わらない笑顔で。けれども、ニューエイジやヒッピーの生き残りとしてではなく、新しい経営哲学をもった企業家としてでした。なんと、ロングインタビューまで掲載されていたんですよ」
それは、と種山が確認した。
「アメリカ流の経営哲学だったのではないですか」
「そうです。社員への束縛は最小限、完全成果主義というやつです。自分も、必要もないのに毎日出社することはしない。むしろ、その日その日にやりたいことをやって、自分を育てる。結果的にそれが経営的な成功につながる、という独自の考え方でした」
否定されたと感じた、と和也は続けた。自分の存在を、こうして偽の春山として生きようとしている自分を否定されたのだと。和也には、写真の笑顔が、自分を、そしてウライを嘲笑しているように感じられた。
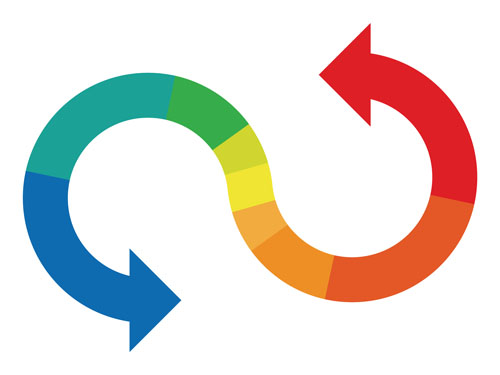
「だから、わたしはすぐにもそんな春山を乗り越えなくてはならないと感じたのです。あんなことをやっておいて、平気で変わらずにいられる春山を打ち負かさなくてはならないと」
かくして、今度は弟のペルソナにすがることになったわけだ。エイズだという嘘までついて、弟に懇願した。そして、社長の椅子を三年間の約束で借り受け、事業の拡大に乗り出した。
「春山が好きだったもので、春山を超えてやるつもりでした。つまり、映画とナチュラルフードで。そうした事業で名をあげれば、春山も自分に気づくのではないか、自分を認めてくれるのではないかと思ったのです」
「でも、うまくいかなかった」
「ええ、そうです」
「つまり、お兄さんのペルソナもうまく機能しないと感じたのですね。なんとかしないと、自分を取り戻せなくなると」
「弟に相談するか、それともハルか? その選択肢の答えは明白でした。なぜなら、弟はやはりわたしを根底から否定する存在でしかなかったからです」
「つまり、あれですね」
種山が解説した。弟さんは生まれつきあなたにそっくりだった。あなたの意志とは関係なく。そして、ドッペルゲンガーが本来の自分を殺すように、そっくりなあなたを否定する存在だった、そういうことなのでしょう。

「そうかもしれません」
うなずく和也。
「それに対して、春山にとっては、むしろあなたがドッペルゲンガーだった。自らの選択でそっくりな姿になったのだから。存在のありようとして、あなたは春山に勝っているはずだと無意識では感じていたのではないですか」
この後、元の存在を脅かすものは、最初からそっくりであるとわかっているものよりも、新たに、あるいは不意打ちのように現れたそっくりなものの方である。そんな風なことを種山が解説したわけだけど、わたしにはそういうテツガクっぽい話はてんで呑みこめないので秘技、快刀乱麻!以下略、ってことで、よろしく。
「そこまではわかりません。でも、兄に相談することが無理な以上、頼るべき存在は彼しかいなかったのです」
そんなわけで、店員の格好をして、追加注文を届けるために社長室に入ったのだということだった。春山の会社の動向は常にチェックしていたから、あの日曜日、マクロビキッチンへの注文が入ったとき、これは最後のチャンスだと思ったのだという。
「で?」
何があったのです、と種山が問うた。
「彼は歌っていました。あのころのように。ほんとうにまったく変わることなく、当時のままの雰囲気で。そして、パスタを届けにきたわたしを見て、あの人懐っこい笑顔を浮かべたのです。思わずわたしは、ハル、久しぶりだね、と呼びかけていました。仮面の顔、つまり和也の顔でです。全然変わってないじゃないかって。」
でも、ハルはきょとんとしていたというのだ。
「カズだよ。ほら、タイの村でいっしょにすごしたじゃないか」
そう言っても、ああ君はあのときの日本人なのか、と遠い記憶を探るようなそぶりを見せただけだったのだという。
「忘れたのかい、ぼくのこと」
と問うと、
「ぼくは、昆虫的記憶で生きているからね」
と、あっさり答えられてしまった。つまり、刹那刹那の記憶しか維持しないようにしているというのだった。
「自由っていうのは、囚われからの解放ってことなんだよ。そして過去ってのもまた囚われの一つだ。そういう不自由を産む因子を、ぼくは極力なくすように努力しているんだよ」
そんな風に、説明された。
「じゃあ、ウライは? ウライのことは覚えていないのか?」
そう問うと、
「ああ」
とうなずいた。
「それなら、多少は覚えているよ」
「そうだろ、彼女は君のことを」
言いかけた和也を手を差し出して制した。
「やめてくれよ、愚かなセンチメンタリズムは。あれだろ、象に踏まれて死んだ哀れな村娘だろ? 分不相応にも余計なことに首を突っ込んだ愚か者だ」
ハルはそう答えたのだという。
「そして、その瞬間でした。わたしが、自分でも予期しなかった行動を取ったのは」
うわあ、何をしたんだお前、と聞くまでも無く和也は語り続けた。
「とっさに手元にあったもので、春山を殴りつけていたのです。気が付けばそれは、バンケットルームで回収してきていた大皿でした。オードブルの追加注文があったので、新しい皿を届けて古い皿は回収したところだったのです」
無鉛健康陶器だわ、とわたしは思い出した。健康に気を使いまくった自らの生き方を凝縮したようなお皿で、春山は殴られたってわけね。スタンガンとかじゃなかったわけだ。
「バンケットルームの笑い声で我に返ったわたしは、即座に春山のオフィスの正面にあった巨大な音響システムに手を伸ばしました」
正確には、音響システムの脇に積んであったCDの山にだった。
「思いだしたんですね。タイの村でのことを」
「むろんです。忘れることはありません。何一つとして。だから、すぐにそのディスクを探り出しました。そして、懐かしい歌声を再生したのです」
あの村での、終わりのない歌声をもう一度復活させたわけです。後はもう説明する必要はないでしょう? 和也はそういった。
「あなたが推測した通りです。オーガニックキッチンのワゴンに気を失った彼を詰め込んで会社を後にしました。車に彼を乗せ、一路三頭山の別荘を目指しました」
「その時点であなたに殺害の意志はあったのですか?」
和也はうなずいた。
「こうなったら、やることはひとつしかないと思っていました。車の後部座席に積んであったウライの象の足と頭が、わたしが何をすべきかを告げていたのです」
「ウライの象?」
驚いたのはわたしだった。
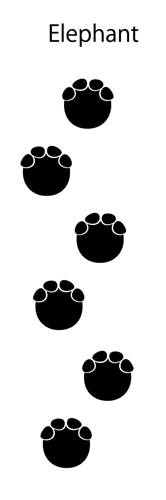
「そうです。ウライを殺した象のモーヒッカは、あの後長老の命によって払い下げられました。何をしているのかが明確な業者にです。象の保護センターがある一方で、動物を単なる金儲けの道具としてしか考えていない人たちもいるのです。殺されたモーヒッカは解体され、象牙と足と頭だけが残されました。土産物として加工されたのです。せめてあなたが買ってやってくれないかと、象使いの師匠だったバコディに頼まれ、わたしは即座にオーケーしました。だから、あれはわたしの手元にあったのです。先程お話ししたウライの仏壇の中に収納されていたのが、そのモーヒッカの足と頭だったわけです」
「ほんとうは」
和也は続けた。
「わたしが、モーヒッカの部品を持ってきていたのは、ハルに見せるためでした。象のばらばらにされた体は、わたしの心の隠喩でもあり、ハルとウライの関係性の隠喩でもあるとわたしには思われたからです。これを見せることで、ハルの心が動くのではないかとわたしは期待していたのです」
でも、結局象の足は、木にもたせかけられた春山の腹部に、めり込むことになった。和也は、車のフロントに象の足を取り付けた。そして、その車で思いっきりハルに突進したのであった。この時点で春山にまだ意識があったのかどうかすら自分には定かではなかったと和也は告白した。
「自分のなかでやることはひとつでした。だから、どの時点でハルが命を落とすかなんてことは考慮の外だったのです」
淡々と、作業をこなすようにその後のことは経過した。ピクリとも反応しない春山の頭部を和也は感情もなく、まるで丸太を切るような感じで切断したのだそうだ。
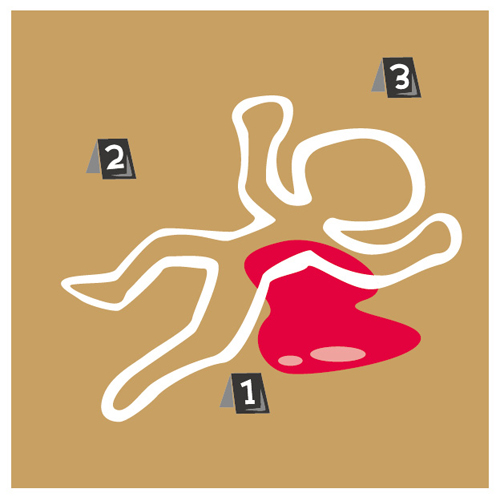
「確かにあらためてお話してみると恐ろしい行為です。でも、あの瞬間、わたしは恍惚を体験したのです」
「恍惚ですか」
ええ、あなたがいうところの、ドッペルゲンガーの恍惚でした、と和也は言った。
「つまり、もう仮面をかぶる必要がなくなったということですか」
「そうですね。これで、この世界にこの顔を持つ人間は自分しかいなくなったんだって思いました。今日からは自分がほんとうのハルなんだと」
東京に戻ると、オーガニックキッチンの社員を呼んで、自らワゴンの中に入り込んだ。親しいお客様から、商品の説明を求められている。だから、予想外のところから出て行って驚かせるつもりなのだと説明した。さらに、このことは口外無用だと言い含めておいた。社長の酔狂だと思った社員は、ハルのオフィスまでワゴンを運び、和也が出ると、皿を下げて一礼して帰っていった。
「わたしはオーディオ装置の再生を停止し、和也のマスクを外しました。そして、ふにゃふにゃの自分自身を机の引き出しに放り込むと、何食わぬ顔でバンケットルームに入って行ったのです。もう何も迷いはありませんでした。自分はハルだったからです。ハルになりたかった人間が、ついにハルそのものになった瞬間でした。社員たちも、何の疑いもなくわたしを受け入れてくれました。なぜなら、わたしはハルとしてのふるまい方を十分に知悉していたからです」

「うーん」
種山がうなった。
「それはどうかな」
と疑義をはさんだ。
「確かにあなたはずいぶんと春山氏らしくなった。ふるまい方にも表情にも、本来のあなたのものではない明るさが溢れている。でも、どうでしょう。たとえば、あなたの遺伝子工学に関する知識は? 話をするうちにわたしはすぐに気付きました。あなたの知識がうわべだけのものだとね。だから、すでに予測していた結論を、わたしは確信することができたんですよ。あなたが春山氏ではなく、和也さんなのだとね」
「それは問題になりません。実際には、細かい仕事は優秀な部下たちがやってくれますからね。わたしはすべてを理解しているふりをしていれば、それで十分なんです。それに、経営の仕事だってもうじき、わたしの手から離れることになるわけですし」
これは意外なセリフだった。せっかくハルになれたのに、その仕事を手放そうというのだから。
「どういうことです?」
朗らかに和也は答えた。
「実は、この会社ごと、弟の滋郎に買い上げてもらうことにしたんですよ。わたしの新規事業のせいで、会社にはずいぶん損失を出させてしまいましたしね。遺伝子工学を応用した製薬の分野は、これからどんどん伸びるといわれているんです。話をもちかけたら、弟は即座に了解してくれました」
「ほんとうですか」
「ええ」
「いつのことです。いったいいつそんな約束をしたんです」
「つい昨日ですよ。わたしの方から電話してもちかけたんです」
「どういう契約ですか」
「わたしは一生遊んで暮らせるお金をもらい、弟にこの会社を売ることになりました。だから、もう遺伝子工学なんかどうだっていいんです。わたしは、真にハルとなれる。ハルとして、世界を放浪することができるですよ。自由を手に入れることができるんです」
「いや、それは変でしょう、和也さん」
これはわたし。いうべきことはいっとかないとね。
「どうしてですか」
と和也氏。
「だって、あなた人を殺してるんですよ」
「おやおや、これは奇妙なことをおっしゃる」
とぼけてみせる和也。
「誰をです。わたしがいったい誰を殺したというのですか? 死んだのはわたしじゃないですか。弟が名乗り出たから、今や警察だって、死んだのは和也だって知ってるんでしょ? 春山であるぼくはこの事件とは何の関係もないんです。そうじゃないですか。あなたたちが、なにを言ったって証拠なんてどこにもないんですから」
「あなたをワゴンに乗せて運んだ従業員がいるじゃないですか」
「ああ」
和也氏は微笑んだ。
「だいじょうぶです。彼はもう日本にはいませんから。バングラデシュに戻って、消息不明ですよ。向こうで一生暮らしていける金を与えましたからね。もともと不法入国者で姓も名も偽りのものだったから、追跡することは難しいでしょうね」
なるほど、なかなか完璧だ。わたしは感心した。
「それでは、最後にひとつお聞きしてよろしいですか」
種山がぐっと身を乗り出した。
「なんでしょう」
「あなたは、タイのあの村を最近また訪れたそうですね。ハルとして。とはいえ、素朴な感覚の持ち主である村人たちには、あなたがもうハルであってハルではないことが十分感じ取れていたようですけど」

「ああ、そうでしょうね」
「で、あれはどういう目的だったのですか」
「墓参りですよ」
「墓参り?」
「ええ、ウライのです」
「それだけですか?」
「ええ」
「違うでしょう、和也さん。あなたは、あなたのなかの神話を完成しにいったのではないですか。土産として、ハルさんの頭を持って行ったのではないですか」
「そんな」
わたしは絶句した。なんという悪趣味な旅行者であろうか。生首との旅なんてそれに不可能ではないのか?
「例の密輸入業者を通して、あなたはハルさんの生首を冷凍保存状態でタイに送った。それを保冷バックに入れてあの村へ行った」
うわあ、あの山道登ったんだ。生首入れたバッグ提げて。

「さすがです」
心底参ったという顔で、和也は種山を見た。
「どうしてわかるのです」
「タブローですよ」
うわっ、出た例のやつだ。結合術とかいう、絵の組み合わせですべての答えが出るってやつ。なんせ、写真的記憶の人だからな。あらゆる場面が、言葉で聞いた話でも全部絵になってるってわけなんだろうな。
「タブロー?」
怪訝そうに尋ねる和也氏。そりゃそうだ。
「ええ、わたしの記憶の中の情報をすべて絵に変えて、それを無作為に並べ替えて行くんです。すると、その繰り返しの中で、答えが見えてくる。すべてが必然的にどこに収まるべきかがわかってくるんです。
あなたはウライさんを裏切り、その命を奪ったハルさんを罰した。ウライさんを心底愛した人間として、ウライさんになり替わってです。けれども同時に、あなたのなかの理想のハルさんを守ろうともした。つまり、ウライさんと愛し合う、愛の人としてのハルさんがあなたにとってはどうしても必要だった」
「ええ」
「だから、あなたは夜中にウライさんの墓を暴いたのではありませんか?」
「ええ」
って、認めやがった和也のやつ。なによ。そのあっさりとした肯定は。ここはむしろ、ええっ!、って驚く場面でしょうが。
「そして、そこにハルさんの頭を一緒に埋めた。二人があなたの願う理想のカップルとなるようにと」
「確かにその通りです。あの瞬間、わたしはすべてがつながったと感じました。ハルはウライと結ばれて成就し、わたしはすべてを理想通りに運ぶことで成就した。すべてが終わったのです。後には何が残ったと思いますか?」
「何です?」
「自由です。何の制約もない自由。それだけが残ったのですよ」
「とすれば、和也さん」
「はい」
「あなたは、確かに存在する。和也さんはやはり存在するのです。あなたは、周りの人から、いつも自分がないとか、自分を認められないとか、自分から逃げているとかいわれつづけてきた。そのせいなのか、自分に自信が持てず、常に他の誰かに自分を仮託していないと生きていられなかった」
同情いたします、和也さん。そりゃつらいわ。
「でも、そんなあなたが、真に和也として行動したのが今回の一連の事件だったのではないですか。あなたは心の底からウライさんを愛した。ハルさんに憧れた。それゆえに、ウライさんを弔い、ハルさんを罰するということを同時に行った。さらには、その二人を和解せしめるというシナリオまで完成した。それはまったくあなたのオリジナルの動機であり筋書きだったのではないでしょうか? 和也さんは確かに存在し、自分のやるべきことをやったのです。そうではないでしょうか」
「それは」
しばし、言葉を失う和也。
「いないはずだった和也さんは確かにいたのです。和也さんは、あなたがいま手にしているそのシリコン製のペラペラの仮面なんかじゃない。むしろ、そうやってハルさんになりきろうとしている今のあなたこそが薄っぺらいぺらぺらの仮面にすぎないのですよ」
「そんな、そんな馬鹿な」
狼狽する和也。平板な種山の口調が、いまはどこか催眠的な力を帯びて響く。
「馬鹿なことはありません。いずれ、和也が出てくるでしょう。ハルとして生きようとすればするほど、消そうとされた、忘れようとされた和也が回帰してくることになる。そしてあなたは二重化し、自分が自分ではないと感じ始める。自分は人を殺した罪人だという罪の意識にさいなまれ始めるはずです」
種山は容赦なく淡々と言葉をついでいった。
「ほんもののハルさんなら、人を殺しても痛痒を感じなかったかも知れません。でも、和也さん、あなたは、ハルさんではない。和也は確かに存在するのです。断固とした行動力で、弔いと罰を同時に行うために人を殺し、そののちに自分の愛と憧れを完成するために、タイの村まで死者の首を埋めにいけるほどの強固な意志をもったあなたが。だから、あなたは逃れられはしないでしょう、そうです、あなた自身から」
いいですか、和也さん、と種山はさらに詰め寄った。
「いまは逆転しているのです。あなたは、いまこそ仮面の人だ。春山氏の仮面をかぶった和也氏なのです。仮面の下には、隠しようもなくほんとうの和也氏がいる。顔をどういじくろうが消すことができない和也氏そのものがね。重ね書きとはそういうものなのです。消そうとしても消そうとしても、下に隠されていた文字が浮き出てくるのです」
鬼気迫る勢いだった。明らかに、心理的な効果を狙って種山は言葉を撃ちこんでいる。わたしはそう思った。
「いいですか和也さん。人間の肉体は象に踏まれたらひとたまりもありません。でも、心は違います。それは記憶の画像でできているのです。ウライさんの記憶。ハルさんの記憶。そしてあなた自身の思い出。どれひとつとして失われることはない。そう、記憶の映像は、象が踏んでもこわれたりはしないのですよ」
「うわわわわわわああっ」
突如、和也が恐慌に駆られた叫び声をあげた。立ち上がって背後にあった机の引き出しをあけ、銀色のバタフライナイフを取り出した。
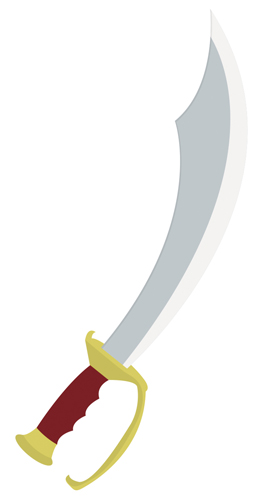
「どうしたんです。いったい何を」
驚いた種山が制しようとした。
「来るな、来るな、来るなああっ」
バタフライナイフを振り回しながら、和也が吼えた。
「俺は俺は俺は俺は」
そのバタフライナイフが天井の照明を受けてギラリと輝いた瞬間、眩しさでわたしは眼がくらんでしまった。
(第25回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







