 世の中には男と女がいて、愛のあるセックスと愛のないセックスを繰り返していて、セックスは秘め事で、でも俺とあんたはそんな日常に飽き飽きしながら毎日をやり過ごしているんだから、本当にあばかれるべきなのは恥ずかしいセックスではなくて俺、それともあんたの秘密、それとも俺とあんたの何も隠すことのない関係の残酷なのか・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第四弾!。
世の中には男と女がいて、愛のあるセックスと愛のないセックスを繰り返していて、セックスは秘め事で、でも俺とあんたはそんな日常に飽き飽きしながら毎日をやり過ごしているんだから、本当にあばかれるべきなのは恥ずかしいセックスではなくて俺、それともあんたの秘密、それとも俺とあんたの何も隠すことのない関係の残酷なのか・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第四弾!。
by 寅間心閑
十一、執着
ナオの家に入ったのは初めてだ。とりあえずソファーの上で横になり、シャワーの音を聞きながら目を閉じる。閉じたのに映像が浮かぶのは疲れているからだろう。一人、二人、三人……。見覚えのあるガキの顔が並んだと思ったら、なんだ、全員小さい頃の俺じゃないか。たまに混じっている女の子は冴子だ。昔から俺とあいつはちっとも似ていなかった。こうして並ぶとよく分かる。
子どもの頃は俺も冴子もお稽古ごとをしていた。あいつはピアノに習字に絵、俺は水泳に剣道にそろばん。
親から教わったこともある。あいつは母親から手芸を習っていて、俺はよくそれを見ていた。リビングだった。だらしなくうつ伏せに寝そべり、カーペットに頬っぺたを付けながら毛糸の玉を見ているのは気分がいい。あまり色を知らないから面白かった。今でも名前が分からない綺麗な色は好きだ。

俺は父親から将棋を教わった。昔から団体競技は苦手。全然向いてない。自分の力が正確に測れないし、俺のミスで他人に迷惑がかかるのも気にくわない。何ていうか不健全だ。それに較べて将棋みたいな個人競技は健康的でいい。俺の失敗が俺の首を絞め、俺の成功が俺を潤す。途中で作戦を変更してもスムーズに実行に移せる。
「ノーマルなセックスって個人競技っぽくない?」
いつか安太にそう言うと、「いや、敵のいないチームプレイかな」と返された。実はあれ、珍しく気に入っていた。いつの話だっけ? 多分安太の家に女を連れ込んでぐちょぐちょやった翌朝だ。どんな女? どんなきっかけ? どんなプレイ? 似たような夜が多すぎてなかなか探せない。頭が頑張って思い出そうとする度、身体の力が抜けていくみたいだ。気付けば俺の顔も毛糸の玉も将棋の駒も安太の部屋も全部消えていた。あとは闇。真っ暗。その闇の中にポンと放り出された。
どういうタイミングで起きたかは思い出せない。でも目が覚めた時にはもう裸のナオと繋がっていた。場所はソファーではなくベッド。ちゃんと移動している。新種の夢遊病でなければ、昨日久々に吸ったせいだろう。時間は分からない。でもテレビが流しているのはワイドショー。朝だ。
ナオと目が合う。至近距離。別に笑うでもなく目を逸らすから舌を入れた。感情が分からないのは不安だ。置いていかれそうで怖い。もう一度目が合う。舌を受け入れてくれたから大丈夫、なんて思わない。置いていくな、と腰にしがみついた。ナオも腰を浮かせてくれた。でもうまくいかない。あんなに奥まで届いていたのに、一気に距離が開いていく。こうなったらもうダメだ。バイアグラのジェネリック、飲んでおくんだった。ナオも察したらしく優しく抱き寄せてくれる。
「大丈夫? もう若くないんだから」
「え?」
「お互いにね」
理由は何となく分かっている。置いていくな、としがみついたからだ。快楽以外のものを欲しがってしまった。あの瞬間を終わらせたくなかった。そう、執着してしまった。
すぐそこに青い蝶がいる。じっと見つめている俺をナオも見つめている。刺青をこんなに近くで眺め続けたのは初めてかもしれない。
「どうしたの?」
どういうつもりなんだろう、と考えていた。ナオはどういうつもりで俺とクラブの便所でして、俺を家に連れてきて、俺とこうして一緒にいるんだろう。右田氏との関係も気になるが、それはひとつの可能性にすぎない。いったいナオはどうしたいのか――。
でも今はまだ知りたくない。こうしてだらしなく横になっていたい。だから「別に」とだけ答えた。いつかは、というか多分近いうち、色々知る羽目になるはずだ。人差し指で青い蝶をなぞる。犬にするような感じで、ナオが俺の頭をクシャクシャと撫でた。
「どうする? そろそろ起きる?」
「もう少しで強烈に腹が減りそうなんだけどさ、ちょっと眠いような気もする」
「ていうか、その前に職場に電話しなくていいの?」
すっかり忘れていた。起き上がってソファーの上にあったスマホを取る。店の留守電に「すいません、熱が下がらないので休みます」と吹き込んだ後、乾いたナオのぬめりをシャワーで流した。嗅ぎ慣れないボディーソープの香りが新鮮だ。洗面所で冷たい水を飲んでベッドに戻ると、ナオはTシャツ一枚で眠っていた。俺も隣で目を閉じる。今はまだ何も知らなくていい。
ピザの匂いで目が覚めた。着替え終わったナオが冷蔵庫から何かを取り出している。三、二、一、〇、と勢いをつけて上体を起こすと午後二時。さっき店に電話をしておいてよかった。
「おはよう」
「うん、ピザ?」
「ごめん。さっき味訊こうかと思ったんだけど、寝てたから好きなのにしちゃった」
テーブルの上に置かれていたのはハーフ&ハーフ。辛そうなヤツとチーズまみれのヤツ。立ちながら一切れずつ口に入れる。ナオは鮮やかな青のワンピース。蝶の色と同じ青。あの青にもきっと正式な名前がある。

「さあ、どこ行こうか?」
「え、私、これから『マスカレード』」
「あれ、昨日オフって言ってなかった?」
「ああ、あれは嘘。怒る?」
もちろん怒らない。文句もない。そのおかげでいい時間を過ごせた。いや、今も過ごしている。じゃあ留守番しとくわ、とナオの背中に投げると、振り返ることなく礼を言われた。どうやらいてもいいらしい。そしてあの感覚が再び頭をもたげる。この瞬間を終わらせたくない、という気持ち。執着だ。
ピザをもう一切れ食べ、ソファーに身体を埋め、ぼんやりテレビを見ているだけですぐに三十分が過ぎた。強めに冷房が入っているのでピンとこないが、今日の最高温度は三十一度と天気予報が告げている。驚くことはない。九月は真夏だ。毎年暑い。
「じゃあ行ってくるね。今日泊まっていくんでしょ? 出来るだけ早く帰るから」
「あのさ」
「何?」
「ここって何階?」
「七階よ。ごめん、もう行かないと電車に遅れちゃう」
ドアを数秒開けただけで外の熱気が伝わる。もう三十一度に達したのかもしれない。いってらっしゃい、という俺の声は不自然に柔らかかった。ナオの慌てた足音が遠ざかり、後ろ姿が消える。微かに青の残像を感じながら、しばらく玄関に佇んでいた。
本当、どういうつもりなんだろう。考えたけど何も出てこない。渡された鍵を靴箱の上に置き、またソファーで横になる。とりあえず寝て、起きたらまた考えればいいや。そんな風に油断していた。本当は気を抜いちゃいけなかったんだ。だからひどい夢を見た。目下失踪中の妹、冴子の夢だ。
ゲーム機がテーブル代わりの古くさい喫茶店、あいつは一番奥の席で煙草を吸っていた。見慣れない、というか似合わない。ドアが開く度にカランカランと音がして、ここが小さい頃によく母親と一緒に来た喫茶店だと気付く。名前は「ピエロ」。当時、このカランカランは、「ピエロ」でしか聞けない特別な音色だった。
まだ吸える長い煙草を乱暴に消し、ナポリタンスパゲッティーを食べ始めた冴子の前に移動する。「よお」と明るい声を出したが、こっちを向こうともしない。でもそんなに露骨に無視されても俺は腹を立てていない。不思議だ。
はいどうぞ、とメニューを持ってきたのは、鳥みたいな顔のおばさん。やっぱりそうだ。ここは「ピエロ」だ。どうやら俺のことも冴子のことも分からないらしい。昔、結構話しかけられたんだけどな。
とりあえずクリームソーダを注文する。味も好きだけど色が最高に綺麗だ。ソーダの緑もサクランボの赤も眩しい。いつもチョコレートパフェにしようかクリームソーダにしようかで迷っていた。今だって、ちょっと迷った。

「なんだか懐かしいな」
意を決して喋りかけたのに、あいつは無言でナポリタンスパゲッティーを口に運ぶだけ。俺、気に障るようなことでもしたっけな。なあ、と遠慮がちに呼びかけたが、返事どころか視線もくれやしない。気持ち悪いのは、食べても食べても一向にナポリタンスパゲッティーが減らないこと。もう一度喋りかけようかと思ったが、また無視されたら寂しいのでやめた。
クリームソーダが来たけれど、緑があまり綺麗じゃない。ストローを挿して一口飲んでみたが、味が無いうえに生ぬるい。これじゃまるで葛湯だ。鳥顔のおばさんに文句を言おうとしたが、まったく声が出なかった。喉に汚い緑が引っ付いてる。本当は聞こえているのかもしれないが、おばさんは振り向かない。反応がなければ声は声じゃなくなる。
助けを求めようと冴子の方に向き直ると――いない。代わりにナポリタンスパゲッティーを口に運ぶ人形が一体。俺、ずっとこいつを冴子と勘違いしてたのかよ。電気仕掛けなのか、ギーギーと一定のリズムでナポリタンスパゲッティーを口に運ぶ、目も鼻もない真っ白の人形。人を不快にさせる形をしている。よく見れば食っているのは赤い毛糸だ。ますます気持ちが悪い。
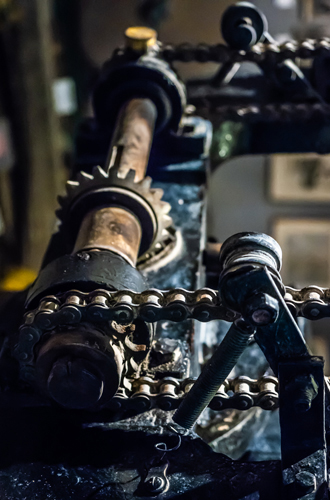
じゃあ、あいつはどこ行ったんだ?
店の中を見回したいけど首が動かない。いや、首の動きに合わせて店内が動いているみたいだ。ぐらんぐらんする。段々と視線も定まらない。畜生、どうなってんだ。
視界がぼやけるのは不安だから、気持ち悪い人形に頑張って焦点を合わせる。口から溢れ出る赤い毛糸。本当は見たくないものを見なければいけないのは辛い。
――そうか、本当は見たくないものを見なければいけないのは辛いのか。
そのうちギーギーと一定のリズムで聞こえていた機械音が狂い始めた。蝋燭が溶けるようにゆっくりと遅くなり、きついエコーがかかる。もうやめてくれ、吐きそうだ。人形の首が不自然にガクンと左に折れる。驚いて叫ぼうとしたが葛湯みたいなクリームソーダが邪魔をして声にならない。ボゴッと変な音が一回しただけだ。
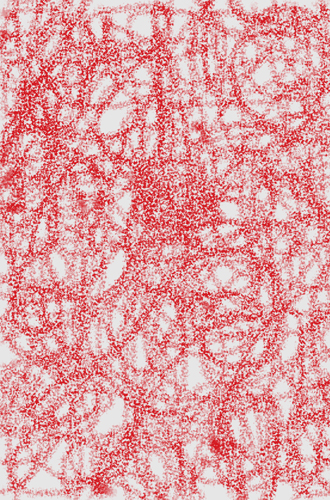
まず反響しまくっている機械音を止めないと、近所迷惑だしうるさくて仕方ない。どうやって止めるんだろうと、俺の視線はただただでたらめに動き回っている。何度か機械音の隙間からカランカランと音がした。店に誰か入ってきたんだ。身体ごと反転させてそっちを見たけど、逆光になっていて誰だか分からない。
気付けば機械音とカランカランが混じって、まったく違う音になっている。なんだ、この音。聞いたことがあるような気もするが、もうダメだ。何も考えられない――。
うつ伏せの姿勢で目が覚めた。全身汗まみれだ。目が覚めた、というよりは意識が戻った感じ。
――本当は見たくないものを見なければいけないのは辛い。
夢の中の言葉を繰り返してみる。時計を見ると午後八時前。五時間近く眠っていたらしい。今日は寝てばかりだ。
ナオの煙草とライターを手に取ってベランダに出る。風が生ぬるい。煙草を吸うなんて何年振りだろう。別に禁煙中という感覚もない。昨日もっと厄介なものを吸い込んでいたくせに、と可笑しくなる。深く吸い込んだ後、地上七階から見える景色に煙を吐きかけた。こういう地味な風景はやっぱり怖い。不安になる。冴子も今、この夜のどこかに潜伏しているはずだ。
少し先に広がる鬱蒼とした公園。街灯にぼんやりと照らされた校舎と空っぽのプール。のろのろと虫みたいに走っていく乗用車が二台。昨日タクシーの中から見た死にぞこないの商店街はどこだ。この時間なら、まだ死んでないんだろう?

うわごとめいた悪口を呟く度、つられて身体の内側が熱くなる。眼下の街並みに火が放たれてから燃え尽きるまでを想像しようとしたが、頭の悪そうなバイクの音が邪魔しやがった。苛立ちの隙間から湿度の高い性欲も押し寄せてくる。こんな時にそうなるなんて、俺、頭おかしくなっちゃったのかな。しかもここ、ベランダだぞ。
部屋に戻って冷蔵庫から缶ビールを取り出して流し込む。他人の家の冷蔵庫を開けるのは変な感じだ。家主の穴という穴に舌を突っ込んだくせに妙な遠慮がある。知るもんか、と一気に呑み干してみたが冷たいだけ。味はよく分からない。苛立ちと性欲が収まる気配もない。アルコールの力じゃどうにもならない。焼け石に水だ。いやな汗も額に滲んでいる。もうこうなったら、ひとつずつ片付けていくか。
風呂場のカゴを漁り、ナオがさっき脱いだ下着を手に取ってみる。顔や仕草や声を思い出しているうち、痛いくらいになっていた。その場に膝を突いてすぐに試したけど、さすがに薄く滲んだだけ。昨日から使い過ぎているんだ。立ち上がった瞬間、鏡に映る自分と目が合った。
やっぱり俺、頭おかしくなっちゃったのかな。
しっかりしようと冷たい水で顔を洗う。微かに目の奥が痛い。これ、風邪かもしれないな。そう気付いたが最後。病は気から。身体を動かすのが億劫になり、ベッドに身体を横たえるだけなのに時間がかかった。蛍光灯が目に痛かったが、灯りを消すのは嫌だ。もう眠りたくはない。でも駄目だった。
玄関の方からバタバタと音がする。目を開けるとナオが帰ってきていた。俺の顔を見るなり「どうしたの?」と驚いている。
「どうしたの? 大丈夫? 顔、真っ赤じゃないの」
体温計で測ってみると三十八度七分。慌てたナオがアイスノンと男物のTシャツを持ってきてくれた。着替えるだけで鈍い痛みが波紋のように広がる。
「救急車、呼ぶ?」
大丈夫、と言いたかったが喉が痛い。代わりに首を横に振る。だったらこれで様子見て、と市販薬を三錠飲ませてくれた。ナオの手は冷たくて心地いい。その手で布団をかけ直した後、「とりあえずシャワー入ってくるね」と灯りを消そうとしたので思わず声が出る。
「消さないで」
やはり暗闇は嫌だった。その言葉をどう勘違いしたのかキスをしてくるナオ。昨晩を思い出させる舌がゆっくりと歯茎をつたい、香水と汗と外の匂いでいっぱいになる。腰に手を回そうとすると「もう今日はダメよ」とたしなめられた。違う違う、と首を振る。
「何が違うの?」
いいから寝て、と身振り手振りで示す。怪訝な表情のナオは鮮やかな青いワンピースのまま、隣に横たわってくれた。外の匂いがする。
「苦しいんでしょう? 可哀想に」
俺は今、可哀想なのか。意外だったが悪い気はしない。少し落ち着いたぐらいだ。
「どうしたの? 何が違うの?」
さっき下着を漁ってしたばかりだから、したくても出来ないんだ、でも少しだけ隣にいてほしい――、とは喉が痛くなくても言いづらい。だから無言のまま横向きになってしがみついた。昨日もこんな感じだったな、と気付いたが仕方ない。これが一番落ち着く。
「ちょっと汗かいてるから待ってて」
「じゃあ十秒」一言だけでも喋ると喉が痛い。「十秒だけ」
「うん、十秒だけね。そしたらすぐにシャワー浴びてくるから」
ありがとう、と声を出そうとした瞬間に咳が出る。喉が潰れたような濁った咳。ナオは「ああ可哀想に」と軽く背中を叩いてくれた。やっぱり可哀想なんだな、俺。ふと全身の力が抜ける。青い蝶が飛び立つ気配がした。
「じゃ、灯りこのままにしとくね」
その声に頷いたつもりだが、首はまったく動いていなかった。しばらくしたら、きっとまた全身の力が抜ける。そうなったら再び眠ってしまうだろう。
眠りに落ちる寸前、忘れずに祈らなくちゃ。今度は余裕のないヤツをお願いします。夢を見る余裕なんかない、強めの睡眠を俺に下さい。
(第11回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『助平ども』は毎月07日に更新されます。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
