たね 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(三)象の目(上編)
「連想ということでいうならば、今回の事件現場の状況からは、まず二つのイメージが引き出されてくるわけです」
ひとつは、と人差し指を立ててみせる種山は、さあ、ずんずん行くぞという気配を滲み出させ始めていた。
「部屋にたくさん残されていたという象が暴れた形跡、そして被害者の腹部に残された足型から連想されるものは、刑罰です」
「刑罰?」
「ええ、象による踏みつけの刑です」
「そんな処刑方法があるのですか」
「いえ、あるというよりはあったというべきでしょう。主として東南アジア、特にインドで盛んに行われた処刑方法で、植民地化にともなって西欧諸国によって禁止されるにいたるのですが、十八から十九世紀まで続いていたとされています」
「つまり、伝統があったと」
「いえ、伝統などという生易しいものではありません。それはまさに、王の権威の象徴でもあったわけですから」
うっはー、なんかすごい感じ。象が死刑執行を取り行うなんて、動物園でおとなしくワラを食んでいるあのイメージとはかけ離れ過ぎている。
「そんなにすごいことだったんですか?」
「そりゃあそうですよ。だって、象といえば動物界で最大の生き物じゃないですか」
「ええ」
「それが処刑人になる、つまり王の命を実行する力となるのですよ。しかも象はそのためにしっかりと訓練されていた。一気に踏み殺させるという処刑方法にも、あるいは手足を徐々にちぎる形でゆっくりと拷問しながら処刑するというやり方にも命令次第で従うことができたのです。巨大なる獣を意のままに操る王が、自らに背く者らの命を奪うのです。これほどの見世物が、あるいは王の権威を示す場がほかにありえたでしょうか」
「なるほど」

そりゃあまあ、見世物としてはすごいものだっただろうなとは思う。象が踏んでも壊れないなんてコマーシャルが昔あったらしいけど、人間はちゃんと壊れるのだ。象が踏んだらそれでおしまいなのだ。
「つまり、犯人はある種の刑罰を意図していたということですか?」
「そうだとは思うんですが」
「ですが、なんですか」
どうも歯切れの悪い男である。
「ですが、そう一概には言い切れない感じも残るのです」
「どうしてです?」
「それはもう一つの連想とつながるのですが、罰することが目的だったとしたら、なぜ犯人はわざわざ首を切り取って象の頭とすげ替えたりしたのでしょう?」
「捜査を混乱させるため? かな」
「うーん、それもあったかもしれませんけど、むしろそこには犯人のもっと深い無意識の動きが現れているような気がするんですよ。欲動というか、象徴界的な願望というかそういうたぐいの」
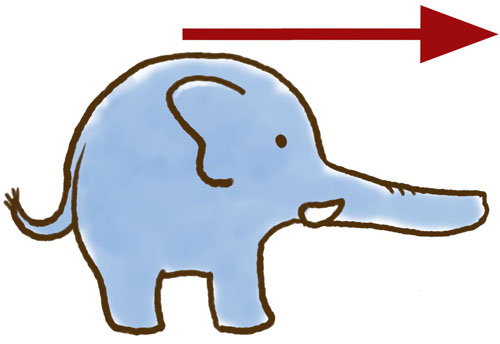
象頭の人間。そりゃ、確かに尋常じゃないっていうか、異様よね。
「ガネーシャって、先生がおっしゃったあれですか」
「ええそうです。ガネーシャはご存じで?」
「もちろんわたしのことだからよくは知りませんけど、つまりは象の頭をもった神様なんでしょ?」
「ええ、そうなんです。ガネーシャはシヴァ神とパールヴァーティー神の子供なんですよ」
シヴァ神ってのはこのわたしですら聞いたことがある。とすれば、かなり有名な神様なのに違いない。
「由緒正しい血筋なんですね」
「とはいっても、ガネーシャはパールヴァーティーの体の垢から作られたそうですけど」
「象の頭の粘土細工、っていうか垢細工ってわけですね」
ちょっとイメージとしては汚いよね、垢から作った生き物なんて。でも、種山は首を横に振った。
「いえ、違います。最初はちゃんと人間の姿でつくられたんですよ」
「そうなんですか」
へえ、最初は人並みだったんだ。素材は垢だけど。
うなずく種山。
「でまあ、垢から作った息子にパールヴァーティーは言ったわけです。『いいかい、ガネーシャや。ママはこれから湯あみをするから、変質者とか覗き魔みたいな変なやつが入ってこないようにちゃんと見張りをしておくんだよ』。すると素直なガネーシャは、『うん、わかったよママ』ってわけで見張りにたった」
「ずいぶん現代風の会話ですね」
「いまどきの大学の講義なんてこんな感じですよ。コンセプトはできるだけ身近な感じに、です」
まあ、確かにその方がわかりやすいけどね。いまどきの大学生であるわたしにも。
「ところがそこに、パパのシヴァが帰ってきたというわけだ」
「シヴァはまだガネーシャの誕生を知らないわけですね」
「そう、携帯電話とかなかったからね」
「で、どうなったんです」
「まあそのなんだ。帰ってきて浴室から音がするのを聴いたシヴァは、さっそく奥さんの湯あみに合流しようとした。ところが浴室の前には見知らぬガキがいて、『だめだ、ここは通さない』とか言い張るわけです」
「怒るわけね、短気なシヴァとしてはここで」
「そうです。『なんだこのクソガキぃ』みたいな感じで、ガネーシャの首をチョンっとはねて遠くへ放り投げてしまったわけです。その騒ぎで気づいたパールヴァーティーが顔を出して大騒ぎ。
『あんた、なんてことしてくれんのよ。うちらの子供なのよ、ガネーシャは』」
「っていったて、パールヴァーティーの垢なんでしょ」
「ではあるけれど、夫婦の子供ではあるわけだ。それで、『なんだってえ!』と大慌てでシヴァは飛び出すと、息子の首を探しに行った」

うわあ、なんかイメージ浮かぶう。シヴァってなんと破壊をつかさどる神様なんだって。だからって息子まで破壊しなくってもとは思うけど。でもそんなシヴァでも、奥さんの怒りにはかなわないってわけよね。わたしは、三つ目のシヴァが、必死になって息子の首を探す姿を思い浮かべた。
「でも、見つからない?」
焦るシヴァの顔をイメージ。ちょっと笑えた。
「そう、見つからないわけだよ。で、しかたなく出会った象の首をチョンパして持って帰ってガネーシャの首にくっつけたっていうわけ」
「ふーん、なんか変な話」
「まあ神話だからね。でもわかることはある」
「なんです?」
「シヴァが象の首を付けたのは再生を願ってのことだったということだよ」
「そりゃそうですけど」
といってから、「あっ」と気づく鈍いわたし。
「ってことは」
「そうなんです。犯人もまた、そうやってわざわざ象の首をつけたってことは、なんらかの意味での再生を願っていたとも考えられるわけです」
「うーん」
ますますわからなくなっただけだった。
「つまり、犯人は被害者のことを一方では、ひどく恨み、あるいは憎んでいた。というより死にいたる処罰を受けるにふさわしいと考えていた」
「で、他方では」
「死した後に、ガネーシャのように、あるいはガネーシャとなって甦ってくれることを願ってもいた」
「と、そうなるわけですね」
「そうです。なかなか複雑です。それでなくては人間的とは言えないのかもしれないですけど」
「先生、解決をお願いします」
「いや、まだ無理ですよ」
「じゃあ、次はどうします。殺害現場を見に行きますか?」
「それもいいけど」
種山は少し興味を示した。あるいは、三頭山の日本一高い所にある露天風呂に入りたくなっただけかもしれなかったが。けれども、さすがに考え直したようだった。
「でもまずは、残された肉親に会っておくことにしましょうか。和也さんでしたっけ、被害者のお兄さんの名前は」
まあ確かに第一容疑者ではあるからね、和也氏は。とはいっても、さすがにあのアリバイは崩せそうにないけど。わりとオーソドックスな捜査手順だなとわたしは納得した。
「わかりました」
じゃあ、姉にその旨伝えておきます、そう告げてわたしは早々にお暇をした。任務完了って、わけだ。もうこれでわたしは引っ込むつもりだった。なにせわたしは学生。勉学に励まねばならないからねえ。あとは、お姉ちゃん、あなたの仕事よ! と胸の中で連呼しながら夕暮れの円山町を急いで離れた。
さよなら〝もじゃ〟。これだけは間違いないと思ってた。
と思ってたのに、
・・・・・・・。
なぜだろう、なぜかしら、
またわたしは種山といっしょにいるのであった。
「ごめんっ、さやかっ」
今朝もふたたび語尾の「っ」が際立つ烈しい口調でわたしを拝み倒しながら再び姉が迫って来たのだった。
「今日どうしてもだめだわっ! すんごい事件起きちゃってさっ。もう全然手ぇ離せないって感じっ」
だから、頼むっ。って強引に押し出されて、
「いやっ」
と烈しく語尾の「っ」を効かせて拒んだのに、結局わたしがいまいる場所は高円寺なのであった。
高円寺のいかにもサイケデリックゥな感じの喫茶店で、人を待っているのである。誰あろう、あのもじゃもじゃ頭といっしょに。

もじゃ公は、壁といわず天井といわず、サイケデリックゥな模様がペンキで塗りたくられた店内を興味深げに見渡している。じっと見ていると目がちかちかしてくるような、蛍光色のカラーで、うねるような渦巻くようなのたうつような模様が、店全体を包み込んでいる。
「なるほど、マンデルブロー集合的な模様が多いですね。フラクタルな曼陀羅という感じです。ビジュアル・ドラッグとしての効果はかなり高いですね」
興味深げに、種山が呟く。
「だいじょうぶですか、先生。被害者のお兄さんに会う前に、一人でトリップとかやめてくださいよ」
店内には、世界中から集まったヒッピーの残党とでも呼べそうな人たちがたむろしている。メニューだって、一筋縄じゃいかない。わたしが頼んだのは「〝気〟珈琲」と書かれたやつで、名前の下に「インドの高名な霊能者サーストリが幸福実現身体安全病気平癒受験合格恋愛成就の願いを、気とともに送り込んだものであります」と解説がなされていた。待つこと数分、運ばれてきた珈琲はごく普通のというか、やや薄めのアメリカンという感じだった。気はどこにこもっているのか、と舌の上で転がしてみたが、むしろ気がぬけた感じの味わいであった。
種山は店員がうんざりするほどメニューをじっくり読みこんだ後で、イルーミネイテッド・アセンション・パフェを注文した。解説は、「甘味の桃源郷へようこそ! より輝かしい霊的向上が約束されたパフェです。パフェとはフランス語のパルフェ、すなわち完璧という言葉に由来したもの。祝福された甘みのコラボレーションが、あなたを七色の光の彼方へと押し出してくれることでしょう」。「ミカエルの息吹」というトッピングまで頼む念の入れようであった。ただ、運ばれてきたものは、どうみてもありふれたチョコパフェでしかなかった。わたしがその点を指摘すると、
「いやいや、あやかくん。そう決めつけるのは早計だよ。このミカエルの息吹なんて」
「でもそれ、ただのウェハースですよね。どう見ても。それから、さやかですからね、わたしは」
と二重の指摘を行ったのだが、
「いやいや、きっとこれには目には見えない力がこもっていて、いろんなものを見通す神通力みたいなのが宿ったりするに違いないんだよ」
などといいながら、ばりばりとそれを噛みくだいたものの、
「まあ、確かに、味はよくあるウェハースのそれではあるが」
と少し残念そうな顔つきになった。
(第08回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



