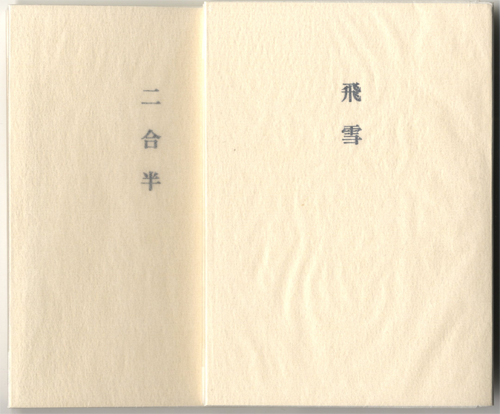
もうだいぶ前から俳人の高橋龍氏から本や雑誌を贈っていただいている。高橋龍氏は高柳重信の弟子で、重信主宰の俳句同人誌「俳句評論」の同人だった。昭和四年(一九二九年)生まれだから今年で八十五歳である。平成二十四年(二〇一二年)に金魚屋が主宰した「安井浩司「俳句と書」展」のオープニングパーティでは、安井氏のご指名で祝辞と乾杯の音頭をとっていただいた。このとき僕はパーティの司会をしたのだが、高橋氏には「お願いします」くらいの挨拶をしただけで、お話する機会はなかった。というか慣れない司会に大わらわで、どなたとも親しくお話できなかったのである。残念なことをしたと思う。
今年になって高橋氏から二冊の句集が届いた。『句集 飛雪』(平成二十六年[二〇一四年]二月二十八日刊)と『句控 二合半』(四月三十日刊)である。高橋氏の個人叢書シリーズ「不及齋叢書」の伍(五)、陸(六)冊目の本である。不及齋が高橋氏の庵号なのだろう。不及齋叢書はA六判の文庫本サイズで、並製本をトレーシング・ペーパーでくるんだだけの簡素な本である。表紙にはタイトルのみが印刷されおり著者名や発行所の記載はない。誤解を与えるような言い方になってしまうかもしれないが、現世の毀誉褒貶などは超脱した洗いざらしの清潔さがある。収録されている句にも気負いがない。
一本の木が枯れてより路地の冬
地の雪の白さを踏みに出でにけり
徒渉る秋水の輪を重ねつゝ
冬土みな動く老農野に出でて
岩山を越す冬蝶の翅痛む
かゝる間も雪積るらし黙のひま 『句集 飛雪』より
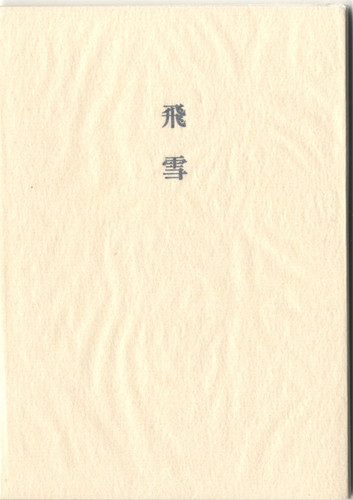
『句集 飛雪』 不及齋叢書・伍 再刊 二〇一四年二月二十八日
『句集 飛雪』は「飛雪」、「罪ゆえに」の二部構成で、巻末に「その頃」と題されたあとがきがある。「その頃」によると、「飛雪」は昭和二十四年(一九四九年)二月に刊行された句集の再録である。千葉県野田市にあったアド印刷工房から、孔版印刷(謄写版)で五十部刊行したのだという。高橋氏十七歳から十九歳(二十一年[四六年]十二月~二十四年[四九年]二月)にかけて制作された作品である。
「罪ゆえに」は昭和二十一年(一九四六年)八月から二十五年(五〇年)二月までに全三十二号が刊行された、「日本俳句新聞」からの再録である。今年の春に古書店の販売目録に「日本俳句新聞」が出ているのを高橋氏が見つけ購入したところ、ご自身でも忘れてしまっていた作品十句が掲載されていた。「これぞまさに十代最後の句ということになる。「飛雪」再刊作業をしている最中であったので併載した次第である」と「その頃」にある。
アド印刷工房は、小谷津順郎という野田町(現・野田市)の野田醤油(キッコーマン)が資金援助する興風会図書館の館員で詩人の副業にしていた印刷所であったが、ここはまた「前衛詩人連盟」の本部で「旧式機関車」という詩誌を刊行していた。この「旧式機関車」は、昭和四年に創刊された「リアン」の後継誌であった。「リアン」は、竹中久七らがマルキシズム・アナキズムを理念とした雑誌で、ここに野田町の岡田直哉、岡田重正(宗叡)の双子の兄弟が参加していた。(中略)
竹中久七(「リアン」)は当時盛行していた「詩と詩論」には批判的で、「詩と詩論」の第八册(昭5)に「超現実主義とプロレタリア文学の関係」を寄稿している。昭和三年の日本共産党弾圧に始った赤色思想の取締は治安維持法の強化によって昭和七・八年以降ますます強まったため、「リアン」は地下に潜って秘密出版となり昭和十二年六月まで続けられた。
わたしも小谷津にすすめられて「旧式機関車」に詩を発表したが、「新定型詩」を理解しないとさんざんに酷評された。
(「その頃」より)
高橋氏は散文の名手でもある。もちろん資料を参照されているのだろうが、その正確な記憶力には驚かされる。「旧式機関車」、「リアン」、「詩と詩論」などは今や文学史上の雑誌だが、高橋氏の文章は当時の雰囲気を生き生きと伝えている。面白いのでもう少し引用してみよう。
その頃、わたしにもっとも影響を与えたのは石井國雄であった。(中略)石井の父は当時千葉県視学をしており、満蒙開拓青少年義勇軍募集の担当者でもあった。(中略)息子の國雄が中学を卒業すると、無理矢理茨城県内原の義勇軍訓練所に入れた。國雄はそこで所長の加藤完治から満州における五族協和の精神を吹き込まれて渡満した。だが開拓団では日本人が現地の農民を支配し、五族協和などどこにもなかった。失望した國雄は開拓団を無断脱走して内地へ帰ってきた。(中略)石井は敗戦約一ヶ月前に応召し、復員した戦後しばらく、二人の関係は途絶えていた。
昭和二十二年の六月、わたしたちの「芦の花俳句会」の吟行会に石井が突如現れた。(中略)それから二人は文学の友になったのである。(中略)石井の家は豪農で、長屋門があり旧幕時代には名主もつとめたらしく、式台のある玄関をそなえていた。その玄関を上ったところの部屋が彼の居室であった。その部屋で(中略)読書会が月に一回か二回開かれた。(中略)主に石井が「近代文学」に連載中の埴谷雄高の「死霊」を大声で読み、あとで回覧した。「死霊」の首猛夫の口癖「ぷぷい」を石井が読むとまるで石井が首猛夫そのものになったようであった。
(同)
加藤完治は旧平戸藩士の教育家で農本主義者。ストレートに言えば、戦前から戦後にかけての右翼のビッグネームの一人である。加藤に感化された石井國雄氏は高橋氏の文学上の友人だが、特に有名な文学者ではない。しかし高橋氏の回想から、当時の青年たちがいかに残酷に時代の波に弄ばれ、その中で生の、文学の指針となるような作品を追い求めていたのかがよくわかる。ただ高橋氏の筆遣いは静かである。そこにはなにごとかを断罪するような批判意識がない。
昭和二十五年二月、石井國雄は山中湖の山林の中で、凍死という方法で自殺した。最後にわたしにきた葉書には失語症に悩み、文学を志す者にとって失語症は致命的だと書かれていた。遺体のそばにはウイスキーの空瓶とリルケの『マルテの手記』があったという。『マルテの手記』は彼がわたしに読めといっていた本で、石井國雄の自殺の知らせをわたしが受けたのは、その『マルテの手記』を買って帰った日であった。
その頃、わたしはどんな本を読んでいたのか。まず買った本。神田神保町の古書店街は焼け残ったのでよく出掛けた。
(同)
石井氏の自殺の経緯はごくあっさりと語られる。それに対する感情的なコメントは一切なく、高橋氏の文章は当時読んでいた本へとさらりと移っていく。しかし石井氏が『マルテの手記』を愛読していたという記述だけで十分である。詩人の吉岡実も出征の際に『マルテの手記』の岩波文庫本、それに北原白秋の歌集『花樫』を携帯した。ある時代に、ある年代の若者にのみ切実に訴えかける本があったのである。高橋氏の上善如水のような文章は、俳人にしか書けない優れた俳文だと思う。
新年 年末に腹部大動脈瘤手術のために入院無事退院
残りなき命まだある大旦
蔀戸(しとみど)を鵺(ぬえ)覗き見よ姫始
初島田凱旋門をくぐり行く
十七の次は十八初鏡
無意識を意識している落椿
亡き夫亡き妻ありて桃の花
かぎろへる大岡頌司地名学
壺を出て沖の畠に種を播く
真実はつくられるもの朧月
本物は偽物に似て春深し
夏みかん長い名前の人が買ふ
巫女さんも稚児さんもいて塚本忌
縦縞を横縞よりも涼し気に
咽ぶ耕衣無我の擦り切れパイプに詰め
鬼蓮に白髪の水子浮寢して
夕顔は言語密度を濃く淡く
たましひを鴨居にかけて濁り酒
白桃の汁気に母を抱く怖れ
桃の実は姉の下着にくるまれて
枕絵の手足からまるやぶからし
生前は死後に語られ秋深む 『句控 二合半』より
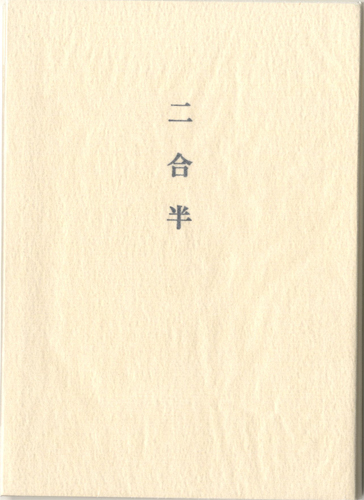
『句控 二合半』 不及齋叢書・陸 二〇一四年四月三十日
最新句集『句控 二合半』から二十一句を抜粋した。「二合半」は地名である。「〝にがふはん〟と読むが、わたしたちは〝にごはん〟と言っていた。ただし公称ではない。正しくは二郷半領であった。(中略)二郷半を二合半と俗称するのは、一説によると、伊奈半十郎忠次治水の功により、此辺を一生支配すべしとの命あり、よって一生を(一升)支配を(四分の一)として二合半と称した」と「あとがき」にある。
鶴山裕司
* 高橋龍氏の句集については以下までお問い合わせください。
高橋人形舎
〒132-0024 東京都江戸川区一之江2丁目9-15
Tel 03-3655-9235
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■




