
ではなかった/ない/という冬の日のふしぎな響きがことばから離れるのでもなくかといってついたままむなしい意味にこごえるのでもなくふるえ冬の日の午後(中略)/ない/ということばからすこしずつはじまるものがある/なにがとは聞けない人の声にはならない人ではない祝ものが透明な冬の鼓膜にかかってつよくうんとつよく大文字ではじまる(中略)/そもそもここで語られているのは/ない/ではない/肉体のない愛する人という/ない/ではなかった/冬の日はつややかな紙をめくることからはじまりやがてなつかしくやさしい音楽につつまれることはなくてもその頁を閉じべつのごわごわした厚紙に書きうつすゆれる輪郭ふるえる輪郭ではないなにを/なにをととわれるものではないものを/なにをとだけやがてうちかえされる冬の日
(詩集『密室論』冒頭 平成元年[一九八九年])
第四詩集『密室論』も「ではなかった/ない」という否定形から始まる。しかしそれは「ひとの名」や「物語の名」の否定ではない。「なにをととわれるものではないもの」、「なにをとだけやがてうちかえされる冬の日」とあるように、「ない」もの(こと)そのものを表現するのが『密室論』の主題である。
日常言語では決して表現できない新たな言語を希求する朝吹の試みは、必然的に矛盾、混乱した苦しいものとなる。ただ朝吹は苦痛にさいなまれながら『密室論』を書いたわけではない。朝吹は「密室論 序説」というエセーで、マルキ・ド・サドの『ソドムの百二十日』が『密室論』のヒントになったと明かしている。『ソドムの百二十日』はサドの処女作で、バスティーユ牢獄で書かれた未完の小説である。哲学書とも風俗壊乱的ポルノ小説としても読める。オリジナル原稿は幅十二センチ、長さ十二・一センチの巻紙で、両面に小さな字でびっしりと文字が書かれている。
朝吹は「この巻紙原稿に『密室論』の扉があるという予感はする」と述べている。またサドは「完全な自由は密室のなかにしか存在しないと主張しているかのようだ。閉ざされているものを無理にも開くこと。牢獄を、肉体を、エクリテュールを。だからサドの全作品は、扉を閉ざすことによって別の扉をあけるものであり、ありとあらゆる禁忌を解き放つための、解放のための密室/論なのだ」と書いている。
朝吹にとっては(不在の)新たな言語こそが実体である。だからそれを追い求めることは愉楽でもあるのだ。苦痛と同時にほとんどセックスと同質の快楽に包まれながら朝吹は『密室論』を書いている。比喩的に言えば、朝吹は未知の異性の身体の襞を一つ一つまさぐるような詩の書き方をする。またその行為が寿がれた「祝もの」であるという確信を抱いている。

『密室論』装幀
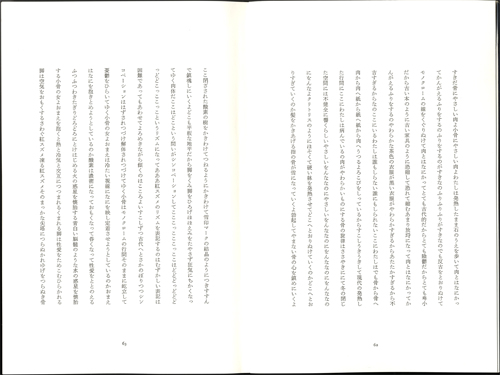
『密室論』本文
『密室論』は一九八〇年代はもちろん、日本の自由詩にとっても重要な詩集になるだろう。それは朝吹が隅々にまで神経を行き渡らせて制作した本だ。ビニールの外箱の中にボール紙の箱があり、その中に紙の束のような詩集が納められている。詩集には一行四十五文字、一ページ十一行の詩行がぎっしりと印刷されている。書き始め書き終えることの逡巡を表すように、詩集の最初と終わりには句読点があるべき場所に「/」が挿入されている。しかしやがてそれも消える。句読点もなく一度も改行されることのない文字列が九十四ページにわたって続くのだ。読ませるために印刷されたが、読まれることを拒否するような本である。
自費出版を基本とする詩の世界では、稀にこのような奇跡的な造本が生まれる。『密室論』は物理的な形状としても、活字の組み方においても〝密室〟を表現している。この詩集を読み通すのは容易ではない。しかしここには新しい試みがある。極論を言えば日本の自由詩は『密室論』のような投機によってその存在意義を確立してきた。物語でもなく短歌・俳句のような形式も持たず、多くの人が共感できる抒情すら排して、日本語の表現可能性を限界まで押し広げる前衛的試みが、日本文学における自由詩の本質的な存在理由(レーゾンデートル)である。
イカのふくらんだ胎のなかには無数のイカ子がうごめいているぎらぎら青黒い目をひらいているイカ子たちよ闇を吸収し憤怒をためるだけためてふくらんでゆくイカ子たちよ斑点をちかちか信号のようにしかしいったいなんの信号だろうか点滅させているイカ子たちよ私も空の青みのような無数のイカ子たちのいっぴきであるだろう死んだように覚醒している無数のイカ子たちのいっぴきであるだろう
(詩集『密室論』)
『密室』には不定形の欲動が蠢き続けている。それは海生軟体動物の「イカ」の喩で描写される。「イカ子たち」と呼ばれるそれらは巨大な塊となって蠕動しながら、その胎内にも無数のイカ子たちを抱えている。朝吹はそれを「密室である透明な箱のなかに透明な箱がありそのなかにまた透明な箱があり(中略)どんどんちいさくなりどんどんどんどん大きくなって光りの粒子となってうわわわっってちりぢりになる」とも記述している。朝吹の欲動は無限小であり無限大でもあるということだ。「私も空の青みのような無数のイカ子たちのいっぴきであるだろう」とあるように、朝吹の自我意識は密室に封じ込められたイカ子たちの一つとなって相対化される。では朝吹の新しい言語とは具体的にはどのようなものなのか。
棒っ切れに読み解くような物語はない恋愛の物語もない夢の物語も死の物語もないただ性愛の睦言の断片が読めない文字で書かれているのかもしれないしかしばらばらの破片をもっとばらばらな順列で組み換え不可解な建築物に組み立ててゆくだけの私は玩具の迷宮にまよっているだけだろうか私は玩具の迷宮に閉ざされているだけだろうか
(詩集『密室論』)
私は私であることを放擲せず私は私の仕事である玩具の建築を放擲せず黒い家具の製造を放擲せず空白であることを放擲せず私であるイカ子となって宇宙のへりの不可視の青のなかにもどる無数のイカ子たちのかたまりにもどるふたたび見えない目をあけふたたび斑点を明滅させふたたびぴかぴか光る透明体となってここやそこあちこちに見えない交叉路をひらいてゆく
(詩集『密室論』)
『密室』には「恋愛」であれ「夢」であれ、どんな「物語」も存在しない。論理はもちろん物語としても説明できない言葉以前、あるいは以後の「睦言」だけがひしめいているのである。朝吹はこの言語化できない「破片をもっとばらばらな順列で組み換え不可解な建築物に組み立ててゆく」。それは児戯に近い作業であり、自分は「玩具の迷宮に閉ざされているだけ」なのではなかろうかと疑っている。しかし朝吹はこの組み換え作業を止めない。「無数のイカ子たち」の一つになって「ここやそこあちこちに見えない交叉路をひらいてゆく」のである。
『密室』は言うまでもなく朝吹の自我意識が創り出したものである。しかし閉ざされた箱いっぱいに自我意識が膨張・肥大化するとき、自我意識は相対化される。限定されたものであれ世界が自我意識そのものとなれば、世界内存在の一つとして自我意識が相対化されるのである。「私は私であることを放擲せず」とあるように、朝吹の自我意識はその輪郭を保持したまま、世界内で相対化され他者存在と交流する。それは日本の私小説の構造とほぼ相似である。
ただ朝吹の言う「見えない交叉路」は詩人のものである。それは宮沢賢治の言う「有機交流電燈」、「すべてわたくしと明滅し/みんなが同時に感ずるもの」(『心象スケッチ 春と修羅』)に近いだろう。「見えない交叉路」はわたしたちの日常言語を生み出す源基に通じており、まだ未知の新たな言語の母胎でもあるはずなのである。
この紙片には意味を形成することのない文字の素粒子しか記されないぶわぶわ水分を吸収した紙それはかつて意味だったものを判読しがたいものに溶解させ(中略)いったいここにはなにが記されていたのか紙片がかさねられる紙片に記されるかさねられる記されるられるれるられるれるれれれれっしかししられるしれるれるられる主体はいったいどこにも/ない/(中略)/ではなかった/ない/という秋の日のふしぎな響きがことばから離れるのでもなくかといって意味にふちゃくしてひからびひびわれるのでもなくふるふるふるえひりひりひびき秋の日の午後にもう鍛えぬかれ磨きぬかれた肉体をまとった快楽の女もい/ない/ということばからすこしずつはじまるものがある/いない/ということからすこしずつはじまるものもある語られるわいせつでわいざつなものがある削除されふたたび挿入されるわいせつでわいざつなものがある
(詩集『密室論』)
『密室論』の末尾だが、日常言語を使って未知(不可知)に通じる言葉を描写しようと試みれば、それは「文字の素粒子」になってしまうだろう。その反映として言葉は「記されるられるれるられるれるれれれれっしかししられるしれるれるられる」、「ふるふるふるえひりひりひびき」と解体し始めている。この甘美とも痴呆的とも言えるエクリチュールが、日常言葉では表現可能な密室の実体だと言うことができる。それは無限増殖的に「削除されふたたび挿入されるわいせつでわいざつなもの」であり、密閉し封じ込めてしまうほかないのである。
朝吹がなぜこのような未知(不可知)の言語を表現することに憑かれたのか、わたしたちにはわからない。朝吹自身も正確には把握できていないのではないかと思う。しかしそれが肉体に根ざした欲動である以上、探究に終わりはない。朝吹は今度は自らが作り上げた『密室』を相対化し始めるのである。
[書翰は小]
書翰は小鳥たちのさえずりを模写する小鳥たちの光と翳
の消尽を模写する農園の午後を模写する農園の鶏と鶏の
穀物とこっここっことその空隙を模写する書翰は恋する
女のいつまでも終わらない性愛を模写する恋する女の尖
塔の勃起と液体の湧出と甘い吐息を模写する書翰は衰退
してゆくこの断片を模写する
[こうした]
こうしたすべての不運な出来事のために私は美しい
(詩集『明るい箱』より 平成六年[一九九四年])
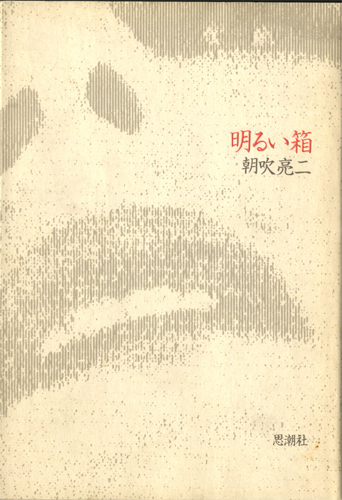
第五詩集『明るい箱』の表題は、言うまでもなく〝明るみに出た箱〟の意味である。引用は詩集末尾のフラグメンツだが、朝吹は自らの欲動を「恋する女のいつまでも終わらない性愛」になぞらえている。しかし朝吹のエクリチュールは衰弱し始めている。詩篇は現実世界の「小鳥」や「農園」、「鶏」を「模写」し、さらに自らが書き付けた書翰体のエクリチュールをも模写するようになる。それにより再び撞着的エクリチュールを紡いでゆく。このエクリチュールは「美しい」だろう。あらゆる存在可能性を秘めたまま、だが形あるものとしては絶対に顕現しない原(ウル)存在を巡っているからである。
さんの箱ひらいた手のままの空隙それは手わたされたのだったか置き忘れたままであったか私はその手の形のままの箱をうけとったのだったかそうだったのだろうか少しずつ世界は褪色しはじめ冬の光は氾濫しつづけ耳には海鳴りににたミミナリばかりが反響する足音もたたずに密室に踏み迷ったままだったかそうだったのだろうか(中略)ささやかな囁きだろうか姿をもたないあやかしい人語にかこまれて空隙を埋めようとして埋め尽くせないままやがて半身は痺れだけのやがて半身は透明な輪郭だけの失われるままの日日の空隙、さんがいないように
わたしもまた
いない
(詩集『まばゆいばかりの』「日録(終わらない世界の終わりのための)」部分)
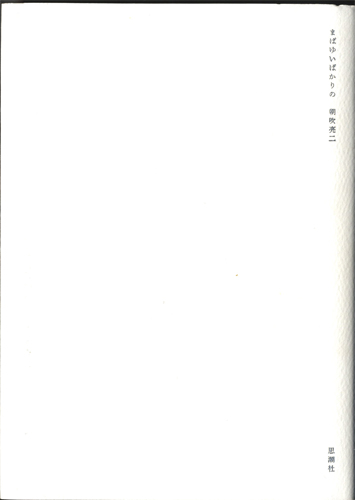
最新詩集(第六詩集)『まばゆいばかりの』には、敬称のみの「さん」という存在が現れる。「さんの箱ひらいた手のままの空隙(中略)私はその手の形のままの箱(=密室)をうけとったのだった」とあるように、「さん」は朝吹の自我意識のことである。だから「さん」がいなくなれば「わたしもまた/いない」。「さん」は『明るい箱』(=明るみに出た箱)を経て、『まばゆいばかりの』外界に一歩足を踏み出した朝吹が、今も密室に囚われている自我意識をさらに客観・相対化した呼称である。
確かに自我意識=世界である朝吹の密室では、世界内に存在する存在の一つとして自我意識が相対化される。しかし朝吹の自我意識世界での存在は、存在以前あるいは以後の、命名も定義もできない不定形をしている。だからこそ密室は、そこからすべてが生まれそこにすべてが収斂する新たな言語生成装置として捉えることができるのである。だがそれはあくまで朝吹詩のパブリックな側面だ。
たとえば、さん、あなたの
少年のような身体と書いて私は筆記が危険な行き先に進もうとしているのを感じるさんの身体についての言説はいつも堂堂巡りの統辞と論理に迷い込む(中略)さんと呼びかけられる肉体はあなたのものでもなく私のものでもなくいかつあるいはまたあなたの肉であり私の肉であり交換可能なしかし本当にそうだろうかむしろ交換不可能な重み不可逆的な重みのはずなのだがさきいかのように裂きたいのとさきいかのように裂かれたいのとでは交換不能な行為だろうか(中略)しかしこれは無限反復でもなく苛立たしい自同律でもなくさんの肉についての言説の話だいやいやちがう肉の交換の話だいやいやしかし肉の交換それは略奪し略奪されるべきものではないのか充実したしなやかさなんの譬喩も成立しない身体の来らるべき未来に私が惑溺するであろう肉体の話だったのではないか私の話はいつも尻切れトンボで終わる終わりの終わりが始まりだとしたらいったいなにが始まるというのだろう
(詩集『まばゆいばかりの』「終わり(終わらない世界の終わりのための)」部分)
閉ざされた密室の王である「さん」は決して老いることなく、「少年のような身体」をしている。「さん」と「私」の「肉」が「交換可能」であり「交換不可能」であることは、「さん」が朝吹の分身であり、かつ到達不可能な至高観念であることを意味している。
このような至高観念を抱えた前衛詩人は、たいていの場合老いることができない。いつまでも少年のような至高観念(夢)を抱えたまま、現実世界で起こる様々な事象から取り残されてゆく。近親者が亡くなろうと自己に大きな試練が襲いかかろうと、観念に取り憑かれた詩人はそれを作品化できないのである。しかし朝吹はそのような陥穽とは無縁である。
朝吹は「終わりの終わりが始まりだとしたらいったいなにが始まるというのだろう」と自問している。端的に言えば奇妙な老いが始まるのだ。朝吹は相変わらず密室に魅了されたままそれを相対化することで、じょじょに現実世界を回復し始めている。
朝吹的な密室、すなわち自我意識=世界は作家の想像界であると捉えることもできる。私小説作家は家や家族という狭い空間(関係性)いっぱいに自我意識を肥大化させる。それにより強引に他者の内面に食い込み、他者によって浸食され相対化される自己の心理を冷徹に描き出す。しかしそこに思想はない。私小説が日本文学独自の表現だと言われるのは、ほぼ完全に思想を欠如させたまま、普段は隠されている自他の関係性(の真理)を、結果論として抉り出してしまう芸術形式だからである。
これに対し詩人は自我意識=世界(想像界)内で、現実界に存在として析出する以前の不定形の原(ウル)存在にまで自己存在と他者存在を遡らせる。原(ウル)存在は、その輪郭を保持したまま他の存在と相互浸食を繰り返すのである。朝吹も宮沢賢治も自我意識=世界(想像界)でそのような形で自他存在を捉えている。
賢治の場合、この原(ウル)存在を現実界で存在として顕現させるのは、世界思想とでも言うべき高次観念である。法華経を中核とした世界思想が原(ウル)存在を現実界で明瞭な輪郭を持った存在として顕現させる。人間か動植物かを問わず、全存在が世界思想の秩序に沿って一つの作品世界を形作るのである。賢治はそれを童話の形で行ったが、現実界での原(ウル)存在の顕現を人間存在に限定すれば、夏目漱石の『明暗』のように、お互いに不可知の部分を抱えた絶対他者たちが高次思想によって統御される、現代小説の形で一つの秩序世界を描くことも可能である。
しかし朝吹の作品世界に世界思想は存在しない。彼を惹き付けてやまないのは羊水のような原(ウル)存在世界である。世界思想が存在しない以上、それは無秩序で混乱した世界のはずである。だがそれは不定形に蠕動しながら一つの秩序を保持している。
私は昇っているのだろうか
私は永遠にくだっているのだろうか
くちいっぱいに
墨の味があふれて
(詩集『まばゆいばかりの』「贈りもの(そっとさしだされるための)」最終部)
密室は朝吹作品の中で、蠕動し続ける不定形のエネルギー総体として息づき続ける。従って朝吹作品は「昇って」いくことも「くだって」いくこともない。彼にできるのは逃れようのない密室自体を相対化することで、様々な試練が襲いかかる現実世界でそれを保持していくことだけである。ただ高次観念不在のまま一つの調和世界を形作る朝吹作品が、極めて現代的な試みであるのは確かである。
朝吹の試みは人間が自我意識の深層まで意識を下降させれば、自己存在と他者存在の輪郭が曖昧になって不定形の存在源基になることを示している。この世界には中心も周縁も存在しない。しかし箱に閉ざされたような外形的輪郭は保持している。そしてこの世界は中心となる核(思想)を持たないままそれ自体で調和している。それは思想(共通パラダイム)を失った二十一世紀的ポスト・モダニズム詩の基層的な表現を示唆しているだろう。
一九八〇年代以降、朝吹と同様に極私的な執着(オブセッション)を表現の中核に据える詩人が詩の世界の大勢を占めるようになった。伊藤比呂美はもちろん、高貝弘也や千慶烏子、川端隆之らがその代表だろう。ただ詩人が年を取るにつれ、当初は純粋だった私的執着の中に、彼らとは本質的に無縁の社会的コードが夾雑物のように紛れ込んでゆく。それは私詩の詩人たちの作品世界を衰弱させ堕落させる。だが少なくとも朝吹は例外である。朝吹の密室への執着は個人的なものだがそこに隠された理由はない。すべてが明るみ出された純観念的執着にまで昇華されている。
また私詩の時代の到来は、平出隆、稲川方人、松浦寿輝らが着手して放棄した戦後詩や現代詩の総括の仕事を、それ以降の世代もまた成し遂げられなかったことの帰結でもある。このまま私詩の時代(吉本隆明的に「修辞的な現在」と言ってもいい)が続くのか、それとも二十世紀文学を総括し、二十一世紀文学を規定し得るような新たなパラダイムが現れるのかは誰にもわからない。ただ世界は変わり続けている。私詩の詩人が示唆する世界認識は普遍的なものであり、相対的に新鮮に見えているだけだとも言える。
鶴山裕司
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■




