
もう十二年前になるが朝吹亮二論を書いたことがある*1。当時朝吹は『終焉と王国』、『封印せよ その額に』、『opus』、『密室論』、『明るい箱』の五冊の詩集を刊行していた。現在はそれに詩集『まばゆいばかりの』が追加されている。ただ新詩集一冊で詩人の作風が大きく変わってしまうことはほとんどない。特に朝吹という詩人の場合はそうである。
私は十二年前の朝吹論の冒頭に、「戦後詩とポスト戦後詩の過渡期に現れた優れた詩人。それが詩史的な朝吹亮二の位置付けとなるだろう」と書いた。この考えは今も変わらない。しかしこの十二年ほどで、詩を巡る状況が緩やかに、だが決定的に変わってしまったと思う。
朝吹が詩の世界で大きな注目を浴びたのは、同人詩誌「麒麟」(昭和五十七年[一九八二年]~六十一年[八六年])が刊行されてからだろう。「麒麟」は朝吹、松浦寿輝、吉田文憲、松本邦吉、林浩平を同人とする雑誌だった。一九八〇年代はもちろん、私が朝吹論を書いた二〇〇〇年代初頭までは、詩の世界には詩人たちが気にかけざるを得ない共通基盤があった。「戦後詩」と「現代詩」のパラダイムである。

単純化して言えば戦後詩は直截な思想表現を中核とした詩であり、現代詩は言葉の意味伝達機能を無化して、建築物のような言語総体によって作家の思想を表現する詩だった。八〇年代当時、「麒麟」同人たちは現代詩派を代表する詩人たちだと認識されていた。中でも朝吹と松浦が「麒麟」の中核詩人であることは、誰の目にも明らかだった。
一九七〇年代から八〇年代は、戦後の詩の大きな変わり目の時期だった。戦後詩については平出隆、稲川方人、河野道代を同人とする詩誌「書紀」(版元の書紀書林は昭和四十九年[一九七四年]設立)の詩人たちが、それを継承しながらポスト戦後詩の姿を探る試みを行った。
稲川は「わたしは〈六〇年代の詩〉の気風の持続を、負うだろう。それはわたしひとりの場所に関わることだし、先行詩へのとるべき誠実な批判の態度だと思える」(「気風の持続を負う」)と書いた。また平出は評論集『破船のゆくえ』(五十七年[八二年])を刊行した。平出が『破船のゆくえ』というタイトルで示唆したのは、戦後詩の行方、狭義には堀川正美以降の戦後詩の姿だったと言ってよい。
吉本隆明が『戦後詩史論』(昭和五十三年[一九七八年])で分析したように、戦後詩は労働者や、大卒といっても学究にはならなかったインテリ層が創出したプロレタリア詩を基盤としていた。これに対してプロレタリア詩と並ぶ戦前の大きな詩の潮流(エコール)だったモダニズムを支えたのは、大学で教鞭をとる学匠詩人たちだった。
この構造は戦後にそのまま持ち越された。戦後詩の中核になったのは労働者階層に属する詩人たちと社会批判的な視線を持つ在野のインテリ詩人たちだった。現代詩はモダニズムと同様、外国文学に精通した学匠詩人たちが担った。文字どおり欧米詩の翻訳・模倣から始まった日本の自由詩は、その言語表現の幅を拡げるために、戦後のある時期まで欧米の最新文学や思想を積極的に取り込む必要があったのである。
この戦前から続く自由詩の実態的区分けから言っても、朝吹と松浦が現代詩派に区分されたのは当然だった。彼らはフランス文学者であり、ともにシュルレアリスムの研究者だった。ただ朝吹はまったくと言っていいほど批評活動に興味を示さなかった。「麒麟」の特徴ある論調を担ったのは、松浦一人だったと言っていい。
松浦の先行世代への批判は徹底していた。彼は「こうしたふるい人たちの(「ふるい人たちの」に傍点)持続ぶりに六〇年代的風土の復興を言うのなら、われわれはあの退嬰的な再現のイメージと狎れあうことしかできないだろう」(「独身者の言葉のために」)と書いた。松浦の言う「ふるい人たち」には戦後詩も現代詩の詩人たちも含まれる。松浦は戦後詩や現代詩といった、戦後の詩の試みすべてを激しく否定してみせたのである。
ただポスト戦後詩・現代詩のイデオローグとして登場した平出、稲川、松浦らの試みは、現在では一定の結果が出ていると言っていいだろう。彼らは理論的にも作品的にもポスト戦後詩・現代詩の姿を明らかにすることができなかった。もう少し穏便な言い方をすれば、平出は戦後詩の行方に興味を持っただけであり、その行き着く先を明示しようとしたわけではない。稲川は戦後詩の遺風を継ぐと言ったが、それはあくまで個人的問題だと補足している。松浦の場合はもっとはっきりしている。
松浦は、「彼(「独身者」のこと)はいささか記憶喪失の傾向があるので、過ぎ去った体験の厚みを既得の財として蓄積し、現在と未来のために活用するといった才覚をまるで欠いている。だから結局は同じことを反復することになるとしても、彼は、そのたびまったく新しい体験に向かいあうかのように、いちいちたじろぎうろたえながら現在を切り抜けてゆかなければならない」(「独身者の言葉のために」)と書いた。
松浦は、自己をすべての状況から切り離された孤独な「独身者」だと規定した。松浦が先行世代を批判したのは、その遺産を含め、すべてを白紙還元し忘却するためだった。彼は本質的に新しい詩や新たな詩のパラダイムを生み出すことに関心がなかった。反復であっても〝自分が書く〟際の新鮮さを維持するために、先行世代の仕事を全否定したのである。ただこの松浦の姿勢は現在の詩の状況を先取りしていた。
ポスト戦後詩・現代詩の模索が始まった一九八〇年代には、もう一つ大きな詩の潮流(エコール)が生まれた。「女性詩」である。女性が書いた詩はすべて女性詩と呼べるが、八〇年代の女性詩はそれとは区別されるべきである。戦後には富岡多恵子、茨木のり子、白石かず子、多田智満子、金井美恵子、吉原幸子、新川和江らの優れた女性詩人たちが登場した。しかし彼女らは同時代の戦後詩や現代詩の影響を大きく受けていた。詩法の上でも意味内容面でも、女性詩と弁別できるほどの特徴を備えていなかったのである。
端的に言えば、八〇年代の女性詩は伊藤比呂美から始まる。女性詩と聞いて吉原幸子・新川和江を編集人とする女性作家のための詩誌『ラ・メール』(昭和五十八年[一九八三年]~平成五年[九三年])を想起される方も多いだろうが、大勢を言えば『ラ・メール』は伊藤の登場によって巻き起こった女性詩ブームを後追いしたメディアだった。
また伊藤は『ラ・メール』創刊号に寄せたエッセイで、『ラ・メール』は流行遅れの「往年のフェミニスト風」だと批判した。女性詩という呼称についても男たちによって作られた隔離的概念に過ぎないと拒絶している。この伊藤の批判はおおむね正しい。女性作家が集っただけで新たなムーブメントが起こるはずもない。究極を言えば詩史的に女性詩と呼ばれる新たな表現は、伊藤一人によってもたらされたものである。
伊藤は生理、セックス、出産、堕胎・子殺しなど、それまで女性詩人が取り上げなかった主題を正面から描いた。露悪的と批判されることもあったが、伊藤の意図はそこにはなかっただろう。簡単に言えば能力の差はあれ男ができる仕事は女にもできる。しかし出産に至る一連の事象は女性のみの属性である。伊藤はそれを自らのアイデンティティとした。またそこから社会との接点を探った。それは極私的に自らの表現基盤を把握しようとする試みであり、松浦の思考と深く通底している。
同人詩誌「書紀」の平出、稲川は昭和二十五年(一九五〇年)、二十四年(四九年)生まれである。「麒麟」の松浦、朝吹は二十九年(五四年)、二十七年(五二年)生まれで、女性詩を代表する伊藤は三十年(五五年)に生まれた。生年から言えば六年しか違わないこれらの詩人たちは、八〇年代にそれぞれのやり方で時代の変化を感受していた。
その内実はどうであれ、ポスト戦後詩・現代詩人の姿勢を見せた平出、稲川、松浦らの俊英が、思想的にも詩法的にも次代の詩の共通パラダイムを見出せなかったのは確かである。しかし現代の詩はやはり彼らの試みの延長線上にある。極私的でセルフィッシュな詩法である。
現在、詩の世界には思想や詩法面での共通パラダイムは存在しない。しかし極私的でセルフィッシュな姿勢はどの詩人にも共通している。詩人たちは個々に切り離された場所で各々の詩の表現基盤を探っている。詩〝壇〟や文〝壇〟が作家たちの共通パラダイムを指すとすれば、現在、詩壇・文壇は存在しない。戦後文学のパラダイムが霧散してしまった現代ではそれはますます加速している。
詳細に検討すれば、それは八〇年代を代表するイデオローグである平出や稲川、松浦の作品でも確認できる。だがそれを最初に鮮明に打ち出した詩人は伊藤と朝吹である。作品に限定すれば、八〇年代を代表する詩人は伊藤と朝吹だろう。
朝吹は文字どおり極私の詩人である。言語はそれ自体社会的コードであり、その歴史や時代状況と無縁の表現者は存在しない。朝吹もまた初期には戦後詩や現代詩の影響を受けている。しかしまったくと言っていいほど評論活動を行わなかったことからもわかるように、朝吹の視線は常に自己の内部に注がれていた。ただこの詩人の試みは重要である。極私は非私に繋がるのである。
季節ごとに方位さだめ、滴り
くちびるに無言の笑いがわたされる
都市ごと沈んでゆく横揺れから、鳥は飛びたち
人々は吊され、昂まった話と消される花々
燃えてゆき(・・・・燃えてゆくのだ)王国の
断片から断片と
十字路を過ぎれば夜の終わりだ、雪、降り過ぎ、その時
ひとりの女のかたちをした爪へ、雪
舞踏しわたし、ひとつの祝いものが
星/草になる
(詩集『終焉と王国』 序詩全篇 昭和五十四年[一九七九年])
朝吹文学はおおむね三期に分類できる。第一期は処女詩集『終焉と王国』(昭和五十四年[一九七九年])から第二詩集『封印せよ その額に』(五十七年[八二年])、第三詩集『opus』(六十二年[八七年])までの期間である。第二期は第四詩集『密室論』(平成元年[八九年])の時期に当たる。第三期は第五詩集『明るい箱』(六年[九四年])、第六詩集『まばゆいばかりの』(二十二年[二〇一〇年])から現在までの期間になる。単純化して言えば朝吹は〝密室〟の詩人であり、その詩は密室に入りそこから出るための軌跡だと言える。それ以外の夾雑物はほとんどない。
朝吹は日本の現代詩、もう少し踏み込んだ言い方をすればシュルレアリスムの詩法から大きな影響を受けている。引用は処女詩集『終焉と王国』の序詩だが、言葉は通常の意味伝達内容を保持したまま内面化され、日常とは異なる方法で使用・連結されている。
ただ冒頭の「季節ごとに方位さだめ、滴り」という詩行は、朝吹がまだ自らの方向性を確信していなかったことを示唆している。だから詩人はどの方角にも行ける「十字路」に辿り着く。しかしそこで「夜」は終わる。「雪」が「女のかたちをした爪」に変わり、さらに「わたし」となるのである。「夜」の〝黒〟から「雪」・「爪」の〝白〟にイメージが変化するわけだが、この「わたし」はさらに「ひとつの祝いもの」「星/草」でもあると語られる。
詩集『終焉と王国』を上梓した時期に、朝吹がなにごとかの終わりを感受していたのは確かだろう。都市は沈み、鳥は飛び去って人々は吊される。花々も消え、王国は断片へと解体されてゆく。ただそこから新たな「わたし」が生まれてくるのだと朝吹は予感している。この「わたし」は清らかな純白のイメージに包まれたなにものかであり、寿がれた「祝いもの」である。
しかし「わたし」を朝吹の自我意識とイコールだと捉えることはできない。それは「星/草」の喩で語られる無機物でもある。「わたし」は天(星)でもあり地(草)でもある新たな世界像そのものだということだ。従って『終焉と王国』という詩集タイトルは古い王国の終焉であり、新たな王国(世界)の始まりを意味していると読み解くことができる。
王国は見えず泡立つつぶやく
山は火、島は離れ
誰れの乳か夜に青い鎖をはり
脳の末端から星々の空隙
王国の裏から広大な砂の星の漠とした
流れ、その微動へと
終わりが始まろうとして
止まない
(詩集『終焉と王国』より「始まりおわらない・・・」最終部)
散乱する死の
海、古い磁気の海の
表層に
(雪)文字を降らせて溶かす
円環を閉じ
封印せよその額に
(詩集『封印せよその額に』より「死へ向う空隙・・・」最終部 昭和五十七年[一九八二年])
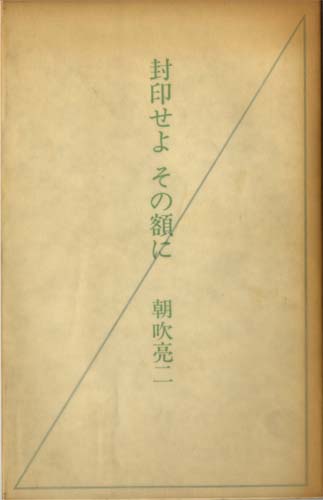
だが朝吹が求める「わたし」の「王国」はなかなか見えてこない。処女詩集『終焉と王国』の最後に置かれた詩篇「始まりおわらない・・・」は、「終わりが始まろうとして/止まない」で締めくくられている。朝吹の試みは振り出しに戻っている。第二詩集『封印せよその額に』の最終詩篇「死へ向う空隙・・・」も同様である。その最終行は「円環を閉じ/封印せよその額に」である。詩篇は堂々巡りを繰り返す。
新たな世界像は、朝吹によって『星』や『草』といった具体物として捉えられている。しかしそれは言語化しようとすれば溶けてしまう「(雪)文字」なのだ。このように内実は確かにあるが直截に表現できないなにかを抱え込んだ場合、人はそれを可能な限り純粋に捉えるために、外界の影響を受けない隔離された場所に閉じ込めて描写するしかない。朝吹の王国は不定形の内実を「封印」するための容れ物を必要としている。
ここにひとつの名を抹消することから始まる
それはひとの名であるか、物語の名であるか
(詩集『〈opus〉』より「00」冒頭部 昭和六十二年[一九八七年])
ここに物語はない、物語の
名はない、さんざめく潮のみちひきのように
閉ざされるものも
ない
(詩集『〈opus〉』より「99」最終部)
第三詩集『〈opus〉』は00から99までの番号が振られた連作詩である。タイトルの「opus」は作品番号という意味である。読者に特定観念を植え付けないために無機的な表題が選ばれたのだと言うことができる。それを反映するように、詩篇は「ひとつの名を抹消することから始まる」。抹消されるのは「ひとの名」でも「物語の名」であってもよい。朝吹はそれまでの「わたし=星/草」や「王国」といった観念(の物語)を白紙還元している。
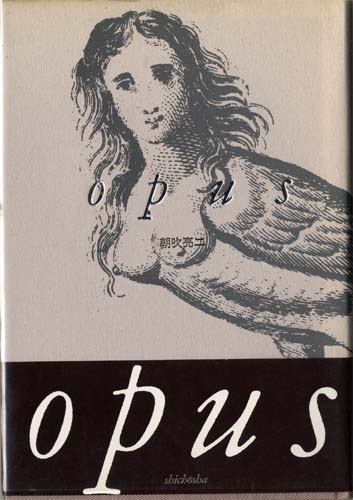
この試みは「ここに物語はない、物語の/名はない」という一応の帰結に達している。だが詩篇は「さんざめく潮のみちひきのように/閉ざされるものも/ない」と続く。観念あるいは物語的求心点を失っても溢れ出して止まないなにかがあるということだ。『〈opus〉』は観念や物語の枠組みを取り外したのちに、なにが溢れ出すのかを見極めるために書かれている。
[話し方おしえてください、どのように話していいのかよくわからないのです、アナタの文法が、アナタの語彙が不明です、おんなことばで話したらいいのでしょうか、あいうえおであれば知っています、でもそれでつうじるのでしょうか、通信からさきの回線はぼくにはわからない、(中略)光りのさきの回路について話したいのです、話し方おしえてください、アナタの文法おしえてください、あいうえおであれば知っています]
(詩集『〈opus〉』より「49」部分)
「話し方おしえてください、どのように話していいのかよくわからないのです」という詩行から、朝吹が抱える内実が、わたしたちが使用する日常言語では表現できないことが示される。それを表現するためには「通信からさきの回線」、「光りのさきの回路」が必要だ。しかしそのような回路=言語は存在しない。そのため朝吹の言葉は最も単純なレベルにまで遡行・解体し始める。子供が言葉を覚えるように、「あいうえお」から記述を始めるのである。それは言語習得のゼロ点にまで立ち戻って、その用法を変えようとする試みである。
べつの/うまれ/をいき/よ/とこえは/め
いれいす/る/べつ/のよ/くぼうを/よみ
/と/けとか/たり/かけるこ/のくう/げ
き/いく/つも/のよみ/ち/がいがあた/
らし/いし/ょくよ/くをうな/がす/しょ
/くよく/とかし/たくう/きのような/お
ん/なはあむ/とた/べ/る/あむあ/むと
もじ/を/たべそ/し/ゃくし/のみこ/む
のみこ/まれた/き/じゅつか/ら/なに/
がう/まれ/るか/な/にも/うま/れぬと
/はだ/んげん/す/るな/くう/きおん/
な/く/うきね/こ/くうき/あ/たまから
べつ/の/せいが/かた/られ/て/ゆ/く
こと/もあ/る/ひ/とつ/ふた/つみ/っ
つ/くう/きお/んな/のし/ょく/よく/
だけ/やせも/せず/じょうご/をと/お/
ってな/がれで/るねく/たー/え/りくし
―/るあ/たらし/い/さけ/あれさ/わぐ
だけのあた/ら/しいき/じゅ/つをは/き
だす/く/うき/おん/なの/いぶ/く/ろ
(詩集『〈opus〉』より「92」全)
読みやすいように漢字混じり表現にすれば、『〈opus〉』92は「別の生まれを生きよと声は命令する。別の欲望を読み解けと語りかけるこの空隙。幾つもの読み違いが新しい食欲を促す」で始まる。やがて「空気のような女」が現れる。女は「あむあむと文字を食べ咀嚼し飲み込む」。そして「荒れ騒ぐだけの新しい記述を吐き出す」のである。
端的に言えば、朝吹が抱えている内実はこの世には存在しない新たな言語への希求である。それは日常言語に「空隙」を、「読み違い」作ることでしか垣間見ることができない。そこから生み出される「荒れ騒ぐだけの新しい記述」は文字どおりの意味で受け取っていい。朝吹は形式的にも意味伝達内容的にも、日常言語を破壊間際のところまで追いやるのである。
鶴山裕司
*1 『常同性について-朝吹亮二論』 夏夷 第十号 平成十四年(二〇〇二年)五月
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■




