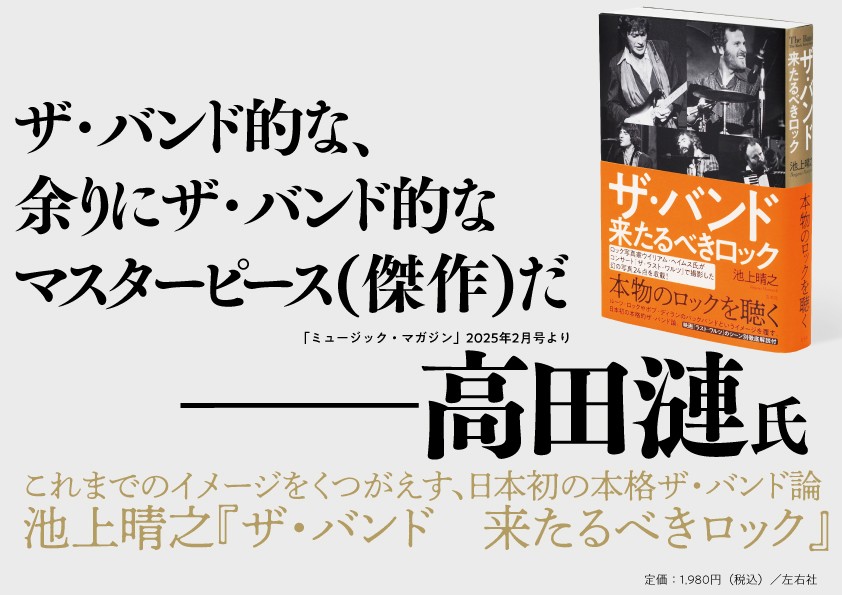自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。
自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。
by 金魚屋編集部
池上晴之(いけがみ・はるゆき)
一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。
鶴山裕司(つるやま ゆうじ)
一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。
■黒田三郎の戦後思想■
池上 黒田三郎は、「荒地」派では鮎川信夫と双璧をなす知識人ですね。戦前(一九三九年~一九四〇年)に北園克衛の詩誌「VOU」に掲載された「戦争とハヴナットの世代に関する覚書」というエッセイを読むと、当時の「現代思想」であった人類学者のマリノウスキや社会学者のレヴィ=ブリュールの著作まで読んでいることがわかります。
このエッセイというか評論が書かれた時の「戦争」というのは、具体的には第一次世界大戦や日中戦争のことを指しているのですが、「プロパガンダは戦争における最有力な武器の一つである。今後ともそのために多かれ少なかれ芸術家は必然的に動員されるであろう。即ち彼等は意識的に或いは結果的に多かれ少なかれ各々の技術をひたすら戦争という目的の為に捧げるのである。そしてまたプロパガンダの為のみでなく、反対に運動後の砂糖水として芸術が利用されることも考えられる」という、まるでその後すぐに太平洋戦争中に日本の詩人たちが歩んだ道を予言するような鋭い認識を示しています。クラウゼヴィッツの『戦争論』にも言及しながら若い世代の詩人の視点で現代における戦争の本質を考察していて、若干二十歳の青年が書いたとは思えない文明批評とも言える内容です。
この後、黒田三郎は東京帝国大学に進み、一九四二年九月に戦争のため半年繰り上げて経済学部を卒業したのですが、もちろんマルクスも読んでいるし、戦前の「荒地」のメンバーの中でいちばんの教養人だったと言っても過言ではないでしょうね。
鶴山 切れ者ですね。それは初期評論を読んでいるとよくわかる。でも鮎川のようにそれを社会批評に援用しなかった。田村隆一のように詩で社会批判することもなかった。彼の視線は常に昨日から今日へ、明日へと続く日常に注がれていた。
黒田自身の具体的な生活実感から人間を捉えるとしたら、社会構成員の平均水準におけるサラリーマンすなわち市民として自己を捉えることになる。そこでは単独者的あり方における詩人という考え方は抽象的観念的で、生活実感における市民との間にギャップが生ずる。彼はこのギャップに敏感だった。「たかが詩人だった」という自嘲とともに「詩人」を絶えず「市民」へ溶解吸収し、自己を市民として捉えながらも、その「市民」に安住していたわけではないから、どうしても「市民」をはみ出る「詩人」に彼はつきまとわれた。(中略)そこに彼の詩の本質があったと、私には考えられる。「市民」は彼の理想ではもちろんなく具体的な日常のあり方だったし、「詩人」もまた彼の逃れえぬ具体的なあり方だったが、ひそかにいつも衝突と軋轢がそこにあって、酔うとあばれ回るものが生れて顔を出す。それは充たされざる彼の自我の狂態的自己主張といえようか。
三好豊一郎「黒田三郎」
「荒地」で最も黒田三郎の詩を理解していたのは三好豊一郎です。文中に出てくる「たかが詩人」は『ひとりの女に』に収載された詩の一節です。後半部だけ引用します。
欲しがってならないものを欲しがった後の
子供のように
僕は夜の道をひとり
風に吹かれて帰ってゆく
新しい航海に出る前に
船は船底についたカキガラをすっかり落すという
僕も一度は船大工になれると思ったのだ
ところが船大工どころか
たかが詩人だった
恋愛を経て普通の生活者になれるはずなのに「たかが詩人」にはそれができない。黒田さんはごく普通の市民であることにこだわった。しかし一方で単独者の詩人であることに引き裂かれていた。だから「田村隆一のようにその無意味な(生活)平面を垂直に断ち切る内的な意味の発見ないしは発見の姿勢にも、また鮎川信夫のように詩作の根底に「想像力の聖なるものとの遭遇」(W・H・オーデン)を求めて日常現実への否定的態度に徹するゆき方にも、従い得な」かったと三好さんは書いている。
黒田さんの中での市民と詩人の葛藤が厳しい現実的抒情詩を生んでいるのは確かです。現実に即したリアリズム抒情詩は黒田三郎が最初です。
池上 黒田三郎は昭和五十五年(一九八〇年)に六十一歳で亡くなっているから、鶴山さんが「現代詩手帖」の編集をやられていた頃にはもう亡くなっていたわけですよね。大正八年(一九一九年)生まれで鮎川信夫より一つ年上だから初期の主要な「荒地」派のメンバーでは最年長で、最も早く亡くなったわけですね。
ぼくは晩年の黒田三郎さんに「無限アカデミー」の現代詩講座で何回か会ったことがあるんです。昭和五十三年(一九七八年)のことで、ぼくは高校二年生、田村隆一さんにお会いした年ですね。中学校の国語の先生だった黒田さんのファンの方が皆に声をかけてくださって、毎回講座が終わった後に数人で黒田さんを囲んで喫茶店でお茶を飲んだんですよね。
その時の黒田さんの印象はとても穏やかで、紳士的な方でした。歩きながら話をしていても「もうこの歳になるとね……」みたいなことをおっしゃって、高校生のぼくから見ると老人でした。だけどその頃黒田さんはまだ五十九歳だったわけだから、いまのぼくらよりずっと若かったんだよね(笑)。喫茶店でも主に話をしていたのは国語の先生で、黒田さんは「うん、うん」と聞いている感じでした。
でもいまでも忘れられないのは、ぼくの書いた詩を黒田さんに読んでもらった時のことです。田村隆一篇で言いましたけれど、ぼくが「高二コース」という雑誌に投稿した詩を選者の田村さんが特選に選んでくれたんです。その詩を喫茶店で黒田さんにも読んでもらったんですよね。ぼくは内心で黒田さんも誉めてくれるかなと期待していたんですけれど、読み終わるとフンという感じで「要するにいまの若い人たちの詩はイメージなんだ。だけどぼくたち「荒地」は違うんです。イメージじゃなくて、言葉を意味として使ったということ、そういうことなんです」と、誰に向かってでもなく、ひとり言のように、ちょっとうんざりしたように、しかし毅然とおっしゃいました。
ぼくは「荒地」派の詩が好きだったから、それなりに「荒地」派の影響を受けていると自分では思っていて、詩における「意味」についても考えているつもりでした。だけど黒田さんのその言葉を聞いてはっきりわかったんです。黒田さんから見ると、ぼくらの世代の詩は、もう言葉を意味じゃなくてイメージとして使っているわけです。「荒地」派の詩人たちが言葉を意味として使ったようには、自分たちは言葉を使うことができない。言葉の繰り出し方が、世代的にも表現史的にも変わってしまっている。もう「荒地」派の詩法には戻れないんだな、ということがその時よくわかりました。田村さんに「詩人になんかなっちゃダメだ」と言われたことに加えて、黒田さんの言葉を聞いて「荒地」派のような詩はもう表現史的に書くことができないんだ、イメージとして言葉を使う現代詩しか書けない時代に自分はいるんだと気づいたことが、結局その後ぼくが詩作を続けなかった内的な理由なんです。
あと黒田さんがぼくの詩を読んで言葉を発する前に、詩のコピーをポンとテーブルの上に投げた時のちょっと虚無的な態度が強く印象に残っています。いつもは穏やかな黒田さんの素顔を垣間見た気がしました。それは「荒地」派以降の現代詩と自分たち「荒地」は違うのだという矜持でもあり、同時に言葉をイメージとして使っている若い世代の現代詩に対する批判でもあるように感じましたね。
鶴山 「荒地」の詩人たちは〝現代詩〟を春山行夫、村野四郎、北園克衛以降のモダニズム詩としています。モダニズム詩最大の功績は『月に吠える』の萩原朔太郎ですら晩年の『氷島』などで回帰してしまった、〝短歌的抒情〟と絶縁したことです。島崎藤村『若菜集』、北原白秋『邪宗門』、朔太郎『月に吠える』、西脇順三郎『Ambarvalia』と自由詩は何度もそれまでの表現を否定する形でアイデンティティの更新を行っていますが、モダニズム詩の登場によって自由詩は日本文学におけるほぼ完全なアイデンティティを確立した。朔太郎高弟の吉田一穂は「詩は短歌的原罪を負っている」と書きましたが、モダニズムの出現によって自由詩は短歌的抒情と完全に切れた。
ただモダニズム詩の弱点はその功績と表裏一体だった。言語表現としては斬新でしたが思想表現を失ってしまった。「荒地」派戦後詩は戦後思想という強烈な意味を詩で表現した。黒田さんが意味の詩にこだわったのは当然でしょうね。またモダニズムを通過した意味伝達方法は単純なものではなかった。だから戦後の詩人たちは戦後詩と、ある意味極端なモダニズム詩のような修辞的実験だった現代詩をマージできたのだと思います。
池上 黒田三郎は戦前に書いた詩を編集した『罌粟に吹く風』『影の狩猟者』『悲しき女王』という三冊の詩集を一九四二年に刊行しようとしていました。しかし結局その詩集は刊行されることなく、詩集用の原稿は戦災で焼けてしまいます。一九四二年に南洋興発株式会社に入社して、一九四三年にはジャワに赴任し、一九四五年二月に現地招集され、戦後の一九四六年五月にようやくジャワのプロボリンゴ港から出航して帰国の途につくことができたのですが、ジャワを離れる前に戦中に書いた詩や日記をすべて焼却しています。
戦後に出版された黒田三郎の第一詩集は一九五四年の『ひとりの女に』ですが、焼け残った戦前の詩稿を集めて詩集『失われた墓碑銘』を翌一九五五年に刊行しています。さらに十年後の一九六五年になって、『ひとりの女に』以前に書かれた一九四六年末から一九四八年の作品をまとめた『時代の囚人』という詩集を出しています。つまり詩集は詩が書かれた順番で出版されたわけじゃないんですよね。一九七一年の『定本黒田三郎詩集』で、ようやく『失われた墓碑銘』、『時代の囚人』、『ひとりの女に』と作品が書かれた時代順で詩集が収録されます。
ここで興味深いのは、『失われた墓碑銘』というタイトルから戦前の作品が失われたように思ってしまうのですが、実際に本当に失われたのは戦中にジャワで書いた詩や日記なんです。なぜ自ら戦中に書いた詩を焼却したのか、その理由はわからないのですが、『時代の囚人』の「あとがき」では「一九四二年から一九四六年に至る空白」と書いています。ぼくは戦前にモダニズムの影響を受けながら抒情詩を書いていた黒田三郎が、戦後に「荒地」派の戦後詩人として出発した理由を知る鍵は戦中に書いた詩にあるんじゃないかと思っているのですけれど、こればかりは実証しようがないですね……。
道はどこへでも通じている 美しい伯母様の家へゆく道 海へゆく道 刑務所へゆく道 どこへも通じていない道なんてあるだろうか それなのに いつも道は僕の部屋から僕の部屋に通じているだけなのである 群衆の中を歩きつかれて 少年は帰ってくる
これは『失われた墓碑銘』巻頭の「道」という詩です。この詩は戦前に書かれた作品で、原題は「少年」ですが、モダニズムの影響は感じられず、黒田三郎の抒情詩人としての資質が現れていると思います。この「道」というテーマには思い入れがあったのでしょう、『時代の囚人』でも巻頭に「道」という題名の詩を掲げています。
それは美しい伯母様の家へ行く道であった
それは木苺の実る森へ行く道であった
それは夕暮ひそかに電話をかけに行く道であった
崩れ落ちた町のなかに
道だけが昔ながらに残っている
いそがしげに過ぎてゆく見知らぬひとびとよ
それぞれがそれぞれの中に違った心をもって
それぞれの行先に消えてゆくなかに
僕は一個の荷物のように置き去られて
僕は僕に与えられた自由を思い出す
右に行くのも左に行くのも今は僕の自由である
戦い敗れた故国に帰り
すべてのものの失われたなかに
いたずらに昔ながらに残っている道に立ち
今さら僕は思う
右に行くのも左に行くのも僕の自由である
鮎川信夫の「橋上の人」にも戦中版と戦後版がありましたが、黒田三郎の「道」には戦前版と戦後版があるわけです。戦前版では、どこへも通じているはずの「道」は「僕の部屋から僕の部屋に通じているだけ」で、「群衆の中を歩きつかれて 少年は帰ってくる」。しかし、戦後版の「僕」は「戦い敗れた故国に帰り/すべてのものの失われたなかに/いたずらに昔ながらに残っている道に立ち」、「右に行くのも左に行くのも僕の自由である」と思うわけです。二つの作品を読み比べると、戦前の抒情詩人が、戦争体験を経て「荒地」派の戦後詩人となったことがよくわかります。
鶴山 黒田さんが『定本黒田三郎詩集』などで書いた順に詩集を収録したのは彼の詩業を論じる上で重要ですね。戦前の「道」では閉塞感が強いのに戦後作では「右に行くのも左に行くのも僕の自由である」となっているのは、戦後一瞬であれ黒田さんが戦後日本に自由を感じたからでしょうね。しかし『時代の囚人』前半は「自由」の考察に当てられています。
そしていまは
与えられた喜びと
自由のなかで
あなたはあなたに何を語るのか
「時代の囚人」
隙間風のように忍び寄るものよ
あてのない恐怖よ
鏡のなかに僕は僕を見る
逃亡は失敗であり逃亡はついに失敗であるのであろうか
「歳月」
僕が僕の故郷を捨てて
遠い海の彼方に行ったことに
どんな意味があったろう
かれこれ言うのがあなた方の自由であるならば
かれこれ弁解するのは
僕の自由というものであろうか
(中略)
「放埒のあげく人眼を恐れて脱走したのである」
「然り」
「機械的なあまり機械的な生活のなかから
海の向うの安逸と無為に憧れたのである」
「然り」
「思想と生活の迷路で
つきまとう自らの影を見つめるに耐え得なくなったのである」
「然り」
あなた方は非常によく理解する
ああ ほんの数歩が
僕に僕の自由を放棄する勇気を与える
「自由」
『時代の囚人』では詩が「道」「時代の囚人」「歳月」「自由」の順に並んでいて、一作ごとに自由の考察が深まってゆく。「道」では「右に行くのも左に行くのも僕の自由である」とあったのが四作目の「自由」では「僕に僕の自由を放棄する勇気を与える」になる。この延長上に『ひとりの女に』がある。黒田は結婚を選択した。「自由を放棄」が黒田さんの戦後の出発点です。
自分自身を可能性として、いついかなる時でもあらゆる方向へ出発出来るような態勢におくことは遂に、無意味でしかない。結婚しないことによって、人間は常に結婚を可能性として持つ者ではない。戦わないことによって、人間は常に戦いを可能性として持つ者ではない。そういう所には、可能性はあり得ないのである。むしろ、ひとりの人間として他の人々と同様に決定的な選択をする所に、詩人や芸術家の可能性は懸っており、その点においてのみ、詩人や芸術家は、人々の胸に生きる人間となるのである。
昭和二十二年(一九四七年)に書かれた「自由の使途」という評論には黒田さんの〝市民思想〟が非常によく表れています。彼は絶望を抱えて野垂れ死にするはずだったのに結婚した。それは彼の自由を狭める選択だった。一方で自由意志を行使した市民の選択でもあった。そして最低限かもしれませんが彼はその責任を取った。酒乱で大暴れした話が面白おかしく伝わっていますが黒田さんは「荒地」の誰よりもマイホームパパだった。常に断念を伴う生活上の「決定的な選択」が黒田の詩の強烈なリアリズムになっています。
池上 黒田三郎の恋愛と結婚に関する複雑な心情は、詩集『時代の囚人』に収載された「一人の女に」というタイトルの詩に初めて現れます。この詩が書かれたのは一九四八年、「自由の使途」の翌年ですね。
人生は過失である
戦い敗れた故国の美しい山河に
生き残り
罌粟の花よりも散りやすいひとよ
あなたはなお
あなたの過失を愛する勇気を失わないだろうか
これは最初の一連です。戦争を生き延びた「あなた」の「過失」が何を指しているのか、この詩を読んだだけではわかりませんが、黒田光子さんの『人間・黒田三郎』には、黒田三郎と光子さんが出会った一九四七年の頃について「彼には既に婚約者があって私にその人の写真など見せましたし、私の方にも学生時代から四年越しの恋人がいました」と書いてあります。黒田三郎と光子さんの恋愛はお互いに「過失」だったわけです。
この後、紆余曲折があり、一度は婚約を解消しながらも一九四九年六月に二人は結婚するのですが、後の詩集『ひとりの女に』に収載された詩は、「一九四八年冬から翌四九年春にかけて書いたもの」と黒田三郎は「あとがき」で書いています。引用した「一人の女に」は一九四八年の四月に詩誌「詩学」に発表した作品ですから、この詩を書いたことで、『ひとりの女に』という詩集に結実するコンセプトを黒田三郎は見い出せたのだろうという気がします。
詩集『ひとりの女に』は一九五四年、黒田三郎が三十五歳の時に第一詩集として出版されたんですよね。この詩集はいまでも誤解されていると思うんですけれど、いわゆる恋愛詩集じゃないんですよ。恋愛や失恋をテーマにしているわけではなくて、「結婚」を選択する心的葛藤がテーマなんです。黒田三郎自身も「詩集『ひとりの女に』は恋愛詩集と言われながら、「愛」ということばは一語も出て来ない」と書いています(「詩集『ひとりの女に』の出版」)。鶴山さんが指摘されたとおり、黒田三郎にとっても光子さんにとっても「結婚」は「決定的な選択」だった。その意味で『ひとりの女に』は倫理的な詩集だと言ってよいとぼくは思っています。
あと、話はちょっと変わりますが、今回黒田三郎の詩を改めて読んで気づいたのは、『ひとりの女に』の頃まで、「罌粟」という言葉がよく出てくることです。これはどこから来ているのかなぁ。
鶴山 ジャワかな。
池上 いや、それが戦前の詩から出てくるんです。一九三七年に「VOU」に「罌粟」というタイトルの詩を発表しています。詩の内容はモダニズムで「罌粟」とは関係ないんですけれど。『失われた墓碑銘』にも「罌粟」という題の別の詩が収載されています。こんな一節があります。
ああ
何時かとおい日に
私は立っていたことがある
ただひとり
白い果しない野の中に
真昼
微かに罌粟が匂っていた
先ほど取り上げた「一人の女に」には「罌粟の花よりも散りやすいひとよ」という詩行がありました。同じく『時代の囚人』に収められている「跫音」という詩にも「一輪の罌粟の花のように 胸のなかで燃えているものがある」という表現が出てきます。最後に出てくるのは詩集『ひとりの女に』の中でも重要な「突然僕にはわかったのだ」という作品です。
罌粟に吹く微かな風や
煙突の上の雲や
雨のなかに消えてゆく跫音や
恥多い僕の生涯や
何もかもがいっぺんにわかったとき
そこにあなたがいたのだった
パリの少年のように気難しい顔をして
僕の左の肩に両手を置いて
これは詩の最後の二連で、「罌粟に吹く微かな風」という表現がありますが、戦前に出すはずだった第一詩集のタイトルは『罌粟に吹く風』でした。こうやって並べて見てみると、「罌粟」は恋愛感情を表象している詩語なのかなと思えます。そう考えると、『ひとりの女に』より後、つまり結婚後の詩集に「罌粟」が出てこない理由もわかる気がします。実際、次の詩集のタイトルは『渇いた心』です(笑)。
ちなみに先ほど挙げた「VOU」に掲載された「罌粟」は、こんな詩です。
ビイチパラソルの横で自殺する勇気を計算することは咳をする和蘭皿よりも嫉妬深い。たとえば女学生などはアネモネを食べすぎるとウソつきいじけた晴雨計は瞼の上に白い受信函を置いた。日曜日は決闘のテイケツトをとり落とし不調法な鵞鳥や春のG・P・V・などがランデブに流行する。雲のない中古るの海峡を疾走する無蓋貨車。文化的な農夫は匂わない。灰皿の縁に神います。
最初期の黒田三郎の詩には北園克衛的モダニズムや西脇順三郎的シュルレアリスムの影響が明らかですね。
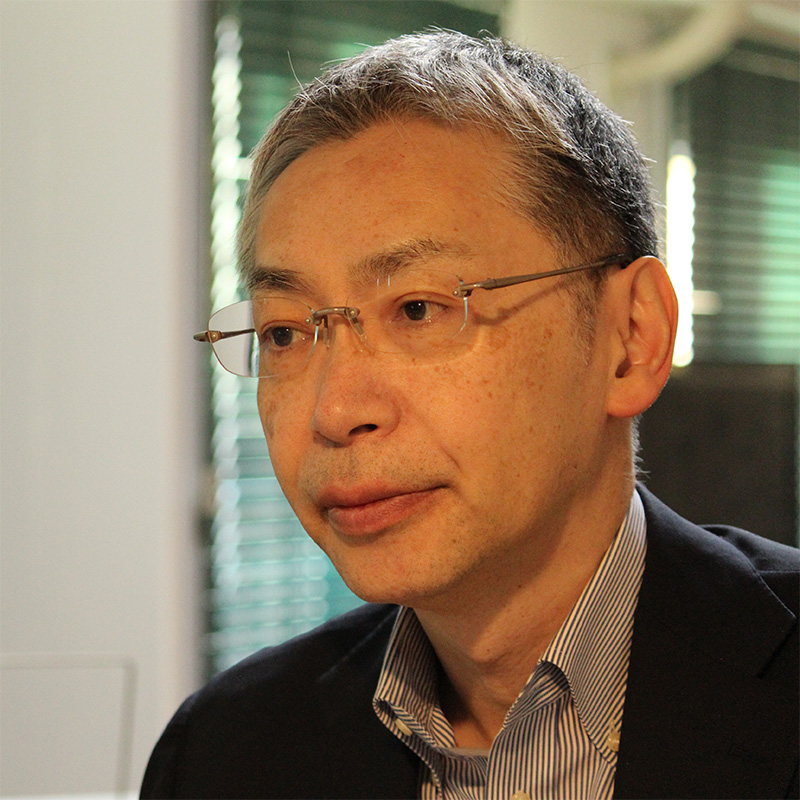
鶴山 「荒地」の中では黒田さんと木原孝一さんが「VOU」同人だったわけで、黒田さんは自分の詩の師匠は北園克衛だとハッキリ書いている。戦後道は分かれたわけだけど。正直に言えば僕は北園詩をあまり評価していません。でも北園主宰「VOU」は戦後に少なくとも黒田三郎、木原孝一、白石かずこ、藤富保男という優れた詩人たちを輩出した。村野四郎や春山行夫門から詩人が出たという話は聞かないので突出している。前から気になっていて藤富さんにインタビューしたいとお電話したらお亡くなりになった直後で果たせなかった。北園さんの詩もデザインもほぼ欧米前衛芸術の直輸入でうーんと思ってしまうんですが、その乱暴なまでの段差の付け方は強い衝撃と影響力を持っていた。近代詩論になってしまいますが一度ちゃんと考えてみなければなりませんね。
池上 確かにそうですね。寺山修司だって二十歳の頃は北園克衛に才能を見込まれて「VOU」に作品を発表していたわけですしね。黒田三郎も「荒地」派の中ではわかりやすい抒情詩を書いた詩人と見られていますけど、よく読むと詩の技法は高度で、陰影のある作品を書いた詩人だと思います。
■抒情詩の原理と変遷■
鶴山 一方で思い切って単純な詩も書いている。黒田さんは『ひとりの女に』に続く『小さなユリと』で不動の抒情詩人の地位を確立した。
コンロから御飯をおろす
卵を割ってかきまぜる
合間にウィスキイをひと口飲む
折紙で赤い鶴を折る
ネギを切る
一畳に足りない台所につっ立ったままで
夕方の三十分
僕は腕のいい女中で
酒飲みで
オトーチャマ
小さなユリの御機嫌とりまで
いっぺんにやらなきゃならん
半日他人の家で暮したので
小さなユリはいっぺんにいろんなことを言う
「ホンヨンデェ オトーチャマ」
「コノヒモホドイテェ オトーチャマ」
「ココハサミデキッテェ オトーチャマ」
卵焼をかえそうと
一心不乱のところに
あわててユリが駈けこんでくる
「オシッコデルノー オトーチャマ」
だんだん僕は不機嫌になってくる
味の素をひとさじ
フライパンをひとゆすり
ウィスキイをがぶりとひと口
だんだん小さなユリも不機嫌になってくる
「ハヤクココキッテヨォ オトー」
「ハヤクー」
癇癪もちの親爺が怒鳴る
「自分でしなさい 自分でェ」
癇癪もちの娘がやりかえす
「ヨッパライ グズ ジジイ」
親爺が怒って娘のお尻を叩く
小さなユリが泣く
大きな大きな声で泣く
それから
やがて
しずかで美しい時間が
やってくる
親爺は素直にやさしくなる
小さなユリも素直にやさしくなる
食卓に向い合ってふたり坐る
「夕方の三十分」という詩ですが何の謎もない。そのまんま。でも抒情詩を書き始めたからにはいわばバカみたいに単純な詩も書かなければなりません。だけど言語表現の平明さは技巧です。作家が自分の中に意図的に、非常に微妙な心的空隙を作り出さないと「夕方の三十分」のような単純で切迫感のある詩は生まれない。
黒田さんは中原中也が好きでしたが、「『中原中也詩集』を読むとき、非常にすぐれた少数の詩を除いては、風変りな作者のその場その場の思いつきに終っているように感じられる詩が、決して少なくないのである」(「日本の詩に対するひとつの疑問」)と書いています。萩原朔太郎についても「朔太郎が思想的にどんなにボロボロの衣服を着て粗暴であったとしても、社会や人間性や道徳に対する識見の高さという点からは、彼は一頭地を抜いた人物であった」(「三好達治論」)と書いている。
中也や朔太郎という敬愛する詩人について論じても黒田さんはその〝欠落〟に注目しています。中也は小林秀雄、河上徹太郎らの超インテリに囲まれていましたが彼らは「なんで中也みたいなヤツがあんないい詩を書けたんだ」と首をひねっている。小林秀雄は詩人中也に強いコンプレックスを抱いていた。また多くの同時代詩人たちが朔太郎の〝感覚欠落症〟を指摘している。感覚だけではありません。知識面でも朔太郎には欠落が多かった。思い込みが激しく論理的に考えるのが不得意だった。
ただそういった欠落が中也や朔太郎に傑作を書かせた面がある。高い知性が優れた作品を生むとは限らない。抒情詩も同様で日常言語を使いながら日常言語をはみ出す表現を生むためには逆接的に非―日常的心性と視線が必要になる。黒田さんは戦前に鹿児島から帝大経済学部に進学した超エリートですが娘のユリに自分のことを「ヨッパライ グズ ジジイ」と言わせている。この部分は恐らくフィクション。黒田の心の声だな。幼稚園児のユリちゃんにこんな批判、できるわけない(笑)。だけどそこまでどうしようもない市民を描かなければ読者の共感を得られない。
表現史は残酷で読者は一瞬で『ひとりの女に』や『小さなユリと』の表現に慣れてしまったわけですがこれらの詩集を書くのは相当な勇気がいる。俗な言い方をすれば、ちょー恥ずかしい(笑)。尊敬します。
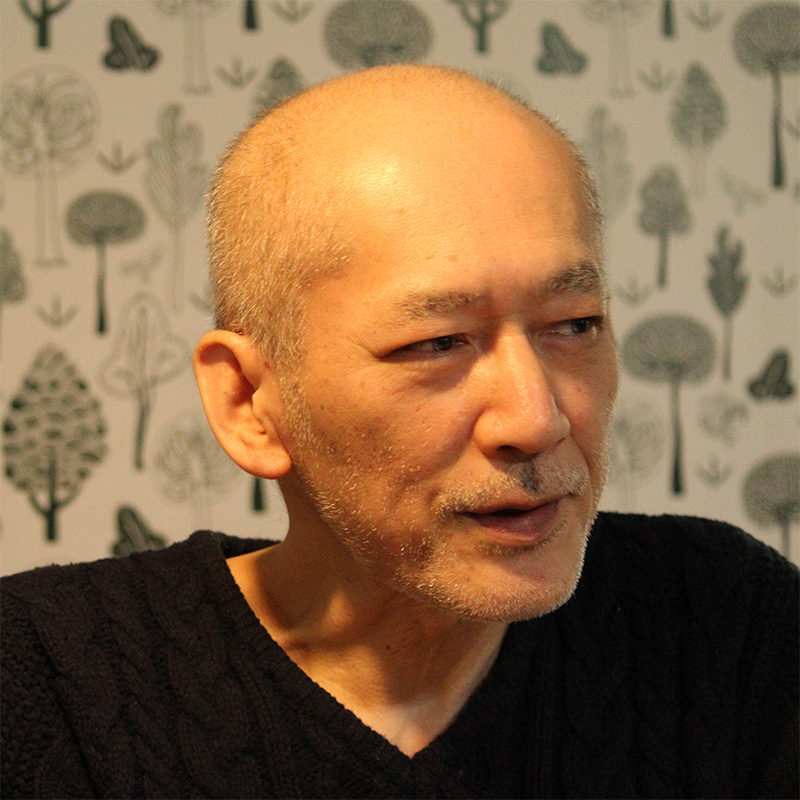
池上 『小さなユリと』は、鮎川信夫が『荒地詩集1954』に掲載した「小さいマリの歌」にインスパイアされたのではないかとぼくは推測しています。「小さいマリの歌」の一部を引用してみますね。
小さいマリよ
どんなに悲しいことがあっても
ぼくたちの物語を
はじめからやり直し
なんべんもなんべんもやり直して
気むずかしい人たちに聞かせてあげよう
小さいマリよ
さあキスしよう
おまえを高く抱きあげて
どんな恋人たちよりも甘いキスをしよう
まあお髭がいたいわと
おまえが言い
それならもっと痛くしてやろうと
ぼくが言って
ふたりの運命を
始めからやり直せばいいのだよ
この詩は鮎川信夫の作品の中でも異色作で、「小さいマリ」は当時一緒に暮らしていた詩人の佐藤木実の連れ子だとか、「小さいマリ」に仮託した恋愛詩だとか、いろいろな読み方がされているんですけれど、ぼくが注目したのは「小さいマリ」という言い方です。これは日本語としてはかなり不自然ですよね。翻訳調というか。黒田三郎の「小さなユリ」のほうはさほど違和感はありませんが、しかしこれも普通自分の子どもを「小さなユリ」なんて言わないですよね。しかし、どちらの作品もここが重要なポイントで、「小さいマリ」とか「小さなユリ」と作中の子どもを呼ぶことで、私小説的ではない、ある種ファンタジーのような世界を成立させているのだと思います。もうひとつ特徴的なのは母親の不在ですけれど、このことについては改めて考えてみたいですね。
それから、若い頃の黒田三郎はボードレールやエドガー・アラン・ポーがすごく好きなんですよね。『失われた墓碑銘』の元になった未完の詩集の『影の狩猟者』や『悲しき女王』というタイトルにも現れていると思います。『失われた墓碑銘』には「群衆の人」という題の詩もありますし。しかし、一方で北村太郎は「『失われた墓碑銘』には、後の黒田三郎のすべてがあるといってもいい」(「『失われた墓碑銘』前後を主として」)と書いているように、『失われた墓碑銘』は多面的な詩集です。
何も秘密なわけなんかありゃしません
僕が紺のハンティングを被って街を歩く
何も秘密なわけなんかありゃしません
僕が蒼い顔をしてくりかえしスタンダァルをよむ
何も秘密なわけなんかありゃしません
僕が空罐をけっとばす
何も秘密なわけなんかありゃしません
高慢ちきなお嬢さん
ああ
それにしても
自転車の上で風に吹かれている
あなたの髪の毛は
ひどく美しくみえる
この戦前に書かれた「風」という詩なんか、すでに『ひとりの女に』的な抒情詩になっています。だから、黒田三郎が戦後にわかりやすい抒情詩を書いたのは、本来の資質だったのかもしれませんね。だけど、一九七〇年代ぐらいまでは『ひとりの女に』は有名な詩集で、特に詩に詳しくない人にも黒田三郎という名前は知られていたのに、どうして読まれなくなっちゃったんだろう。
鶴山 茫漠とした存在だった女の子を『ひとりの女に』で、名前は出していませんが読者がハッキリ実在の女性だと感じ取れるように書いたわけですね。そういう形で言語像が変わってゆく。もっと長い目で見ると大正時代の三好達治、中原中也、戦前戦後の黒田三郎の抒情詩を並べてみればどう言語像が変わってきたのか直観把握できます。じゃあなぜ今黒田の詩が読まれていないのかと言えば言語像が変わったからです。
おかあさんのなぐさめも うるさいだけ
おとうさんのはげましも うっとうしいだけ
だから いまは ただひとりにしておいて
ほんのすこしだけ しんでいたいの
ほんとにしぬのは わるいことだから
おんがくもきかずに あおぞらもみずに
わたし ひとりで もくせいまでいってくるわ
先頃お亡くなりになった谷川俊太郎さんの「ひとり」という詩の後半です。ペルソナ手法でいじめにあっている女の子の心情を詠っている。俊太郎さんの息子の谷川賢作さんと高瀬麻里子、大坪寛彦さんのグループDiVaが素晴らしい楽曲にしています。
表記的にも内容的にも黒田よりも単純な詩なんですが最後の一行「わたし ひとりで もくせいまでいってくるわ」で詩が虚空に、観念レベルにまで抜けている。谷川俊太郎はそれまで地上にあった抒情詩を天上にまで持っていった。それが『二十億光年の孤独』の俊太郎詩の大きな特徴です。黒田の詩と比べると俊太郎詩の方が新しいと感じる読者の方が多いのではないか。
ただ俊太郎的抒情詩の言語像も必ず古びてくる。二十一世紀社会が求める言語像と合わなくなってくるはずです。
池上 なるほどね。だけど黒田三郎の書いた戦後詩はいまでも本質的に古びていないと思うな。詩集『時代の囚人』に収載されている「死のなかに」から引用してみますね。
死のなかにいると
僕等は数でしかなかった
臭いであり
場所ふさぎであった
(中略)
死は異様なお客ではなく
仲のよい友人のように
無遠慮に食堂や寝室にやって来た
床には
ときに
喰べ散らした魚の骨の散っていることがあった
月の夜に
馬酔木の花の匂いのすることもあった
(中略)
戦争が終ったとき
パパイアの木の上には
白い小さい雲が浮いていた
戦いに負けた人間であるという点で
僕等はお互いを軽蔑しきっていた
それでも
戦いに負けた人間であるという点で
僕等はちょっぴりお互いを哀れんでいた
(中略)
いたわりあったり
いがみあったりして
僕等は故国へ送り返される運命をともにした
(中略)
ひとりは
昔の仲間を欺いて金を儲けたあげく
酔っぱらって
運河に落ちて死んだ
ひとりは
乏しいサラリイで妻子を養いながら
五年前の他愛もない傷がもとで
死にかかっている
(中略)
死 死 死
死は金のかかる出来事である
僕の知らない男や女が吊皮にぶら下っているなかで
僕も吊革にぶら下り
魚の骨の散っている床や
馬酔木の花の匂いのする夜を思い出すのである
そして
さらに不機嫌になって吊革にぶら下ってるのを
だれも知りはしないのである
この詩は「荒地」派の戦後詩を代表する作品の一つだと思います。「死」をモチーフに、戦争中のジャワでの体験、現地で敗戦を迎えた日本人の姿、帰還して来た人たちのその後の人生、戦後の日常生活になじめない黒田三郎自身の心情を平易な言葉で重層的に描いているすぐれた詩ですね。
鶴山 途中で「僕のお袋である元大佐夫人は/故郷で/栄養失調で死にかかっていて/死をなだめすかすためには/僕の二九二〇円(当時の黒田の給料)では/どうにも足りぬのである」と書いているところが黒田さんだよね。黒田は敗戦一年後に帰国したわけですが綜合雑誌を読んで「言葉への不信」を抱いた。「言葉だけでは信用できない。目の前に一杯の御飯が出なければ」(「詩人と言葉」)と書いています。そんなところに市民であることを選択した黒田さんの肉体的思想がある。昭和二十年(一九四五年)八月十五日ですべてが変わったわけだけど黒田さんは戦前の傷も含めて生活者としては何も変わっていないと捉えている。
池上 黒田三郎が戦後詩人と言えるのは、『時代の囚人』と『渇いた心』だけだとぼくは思っています。『ひとりの女に』や『小さなユリと』の黒田三郎はもう戦後詩人ではなくて抒情詩人ですね。一般的にはこれらの詩が黒田三郎という詩人のイメージになっていますけれど、ちょっと「黒田三郎」という詩人を演じている感じがしちゃうんですよね。
鶴山 『ひとりの女に』と『小さなユリと』で身を削ったんだからもうちょっと評価してあげましょうよ(笑)。
池上 もちろん、こういう詩は現在に至るまで黒田三郎以外に書いた人はいませんね。どちらも極めてユニークで、すぐれた詩集であることは間違いないと思います。
鶴山 詩集『もっと高く』の「紙風船」は黒田三郎の代表作の一つでいいと思うな。フォークグループ赤い鳥が楽曲にしてヒットしたのでよく知られていますが。
池上 うーん、ぼくはあまり黒田三郎らしい詩だとは思っていないんですよね。
鶴山 すんごい短い詩ですよね。
落ちて来たら
今度は
もっと高く
もっともっと高く
何度でも
打ち上げよう
美しい
願いごとのように
この詩は三好達治の短詩「雪」みたいなものだと思います。「太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。/次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。」ですが短詩「雪」を記憶している人は案外多いんだ。
三好さんは西脇順三郎と年が近かったこともあってしばしば並べて論じられますが古い文語詩人のイメージであまり評価が高くない。でも代表作がある詩人は偉大です。ほとんどの詩人がすぐ口にのぼるような代表作を書いてないからね。黒田さんは三好さんに倣ったわけではないでしょうが、後期の衰弱体の詩に移行する間際の美しさがある。
池上 そうかもしれないけれど、ぼくは昔から「美しい願いごと」という表現に違和感があるんですよね。「美しい」願いごとなんてあるのかな。願いごとって切実ですよね。「家族の病気が治るように」とか「子どもが受験に受かるように」とか……屁理屈と言われそうだけど(笑)。『もっと高く』の中の短い詩なら「不思議に鮮やかな」のほうが黒田三郎らしい気がします。
木枯の吹き寄せた
落葉の下から
思いがけないなくし物が
出て来た時のように
それは不意に
忘却の底から姿をあらわす
遠い日のある一瞬の
不思議に鮮かな記憶
それが何故なのか
それにどんな意味があるのか
ささやかと云えば
あまりにささやかなこと
ひとり旅の汽車の窓から見た
真夏の人影もない白い田舎道
空襲のあとのプラットフォームできいた
明るい口笛の一節
霧の夜の谷間ですれ違ったひとの
ほのかな香水の匂い
「霧の夜の谷間ですれ違ったひとの/ほのかな香水の匂い」という詩行は、少なくとも田村隆一や中桐雅夫には書けないと思うな(笑)。
鶴山 「不思議に鮮やかな」は国木田独歩の『忘れえぬ人々』みたいだなぁ。柄谷行人さんが『忘れえぬ人々』を題材に「風景の発見」という評論を書いていますが読んだ時に「そうかぁ、風景が発見されてるかぁ、単なる衰弱じゃん」と思ったのを覚えています(笑)。
黒田さんの詩業に即せばこのタイプの詩はハッキリ衰弱体の始まりだと思います。彼は中期に私小説的な詩を書いて抒情詩人として高名になった。しかし実生活でそうそう恋愛や子育てといった〝事件〟は起こらない。光子さんによると結婚後も女性たちとのアフェアはあったみたいだけど。
あんまり言っちゃいけないかもしれないけど谷川俊太郎さんは三回離婚してますね。非常に圧の高い抒情詩が生まれる背景には詩作品で表現された以上の生活上の苦しみや葛藤があったのは間違いない。黒田さんは後期になると『ふるさと』とか風景描写詩が増えてゆく。ドラマチックな詩で黒田三郎の詩を記憶した者にはどうしても衰弱に見えてしまう。
池上 一方、『荒地詩集1952』に掲載された「妻の歌える」は問題作としてよく取り上げられますよね。
1
あなた方は
正義のために
と仰言います
あなた方は
祖国のために
と仰言います
あなた方は
平和のために
と仰言います
私から
この貧しい
ひとりの妻から
ただひとつの願いを奪い去ろうとして
あなた方は
大声疾呼なさいます
あなた方の
美しい言葉
あなた方の
重々しい身ぶり
あなた方の
悲壮な決意
あなた方の大声疾呼する声は
裏通りのよどんだ空気をふるわせ
たてつけの悪い硝子戸をふるわせ
食器棚の上の一輪ざしをかすかにふるわせ
隙間風のように
私の耳を襲います
再軍備
再軍備
再軍備
(中略)
8
あなた方は
正義のために
と仰言います
あなた方は
祖国のために
と仰言います
あなた方は
平和のために
と仰言います
だが
あなた方は
今迄何をなさったのですか
夕暮れの町をゆき交う無数のひとびとのなかで
私は考えます
雨のふる日も風の吹く日も
つくろい物の洗濯 食事の用意
編物の内職に追われとおしの私のために、
いや私だけではありません
その日暮しのすべての妻や子のために
私達の小さな幸福と
私達の小さな平和と
私達の小さな希望のために
あなた方はいままで何をなさったのですか
(後略)
8章から成る長い詩の「1」と最後の「8」の前半ですが、鮎川信夫が「おそらく彼に欠けているのは「小さな幸福、小さな平和、小さな希望」をまもるという自己の生活体系を、現実の発展的エネルギーに結びつけるといった努力であろう」「根本的には、やや概念化された素朴な自然主義の立場から文明批判をやろうとする態度であって、その有効性はかなりせまいものであると言えるのではないだろうか。これが黒田の社会詩のぎりぎりのところで、振子がゆれ戻るように、彼はすぐもとの日常性の世界へかえってしまうのである。社会詩人でもあり、同時に抒情詩人でもあるが、その振幅の小ささは、むしろ驚きとするに足りよう」(「詩人と民衆」)と詩人としての黒田三郎を徹底的に批判したために、その後二人は疎遠になってしまったんですよね。
鶴山 成功作かどうかは別として意欲作だと思います。鮎川さんは戦後詩を代表する詩人でいわば〝男根主義〟の権化だから、彼の立場や資質からの読み方では中途半端で狭隘な文明批評詩に写っただろうね。
でも世の中の半分は女なんだ。古井由吉さんがどこかで書いていたけど、男を一番うろたえさせるのは女の言葉です。戦時中の男たちの多くはそれこそ「お国のために」と「大声疾呼」していたわけだけど、どんどん戦況が悪くなっていった。そんな時に女房に「あんたどうすんのよ、食べる物がないじゃない、どうやって暮らしていくのよ、どうすんのよどうすんのよ」と言われた時の男のうろたえ方は見物だった、というようなことを書いておられた(笑)。追い詰められても頭でっかちのまま虚勢を張り続けている男に女は結局はそれがなければお国もなにもありゃしない具体的生活をぶつけてくる。その肉体性の前では崇高な理念なんか吹き飛ぶ。世の中を動かすのは女たちの声だというのはある程度本当です。
黒田さんは市民を選択したわけで昨日から今日、明日へと続く生活を表現の基盤にした。それが彼の肉体的思想だった。女性的な生活思想を持っていた。実際黒田の傑作詩集は光子さんやユリちゃんを媒介に生まれている。黒田にとって女性はイデアであると同時にアポリアでもあった。もっと言えば抒情詩は女性的な側面が強い。特に男の詩人は自己の中の女性的な部分を意識的に掘り起こさないと抒情詩は書けないところがある。「妻の歌える」は社会批判詩だけど女性の目で社会問題や矛盾を捉えようとしている。あんまりこういった詩は書いていないけどもっと女になり切って作品を書いてもよかったんじゃないかと思います。
池上 確かにタイトルが「妻の歌える」では、「夫」が「妻」のことを書いている詩のように読めてしまいますね。
鶴山 そうですね。思ったより黒田さんの話が長くなりましたねぇ。黒田三郎は大物なんだな。そろそろ急いで茨木のり子篇に移りましょう。
(金魚屋スタジオにて収録 「黒田三郎篇Ⅱ」了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■