 月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
by 小原眞紀子
第十二幕(前編)
「それで都大病院は結局、キャンセルしたってわけ?」
入院はね、とわたしは月子に答えた。
「だって、帰って三日目には食事が摂れるようになったのよ」
寝室の二つのベッドに、姉とわたしは向い合って腰掛けていた。
寝間着代わりの楽なワンピース姿だったが、もう普段と変わらずに動き回れる。スツールに置いた盆の紅茶も、自分で用意した。
「夾子が病院の帰りに様子を見にきてくれてたの。それがまた、ちょうど宅配ピザを頬ばってる最中だったりしてね」
「夾子がねじ込んで、都大病院のベッドを空けさせたんでしょう?」
やれやれと、開業医の姉は息を吐く。
「さぞ人騒がせと思ったろうね」
「うん。で、検査ぐらい受けないと悪いから、昨日ちょっと都大病院に行ってきた。夾子がここで採血したのを、聖清会の方に持って行ったばかりだったけど」
「まあ、退院した途端に回復されたんじゃ、聖清会病院も形無しね」
「転院じゃなくて、まだよかったでしょ」わたしは言い張った。
「夾子が診ていたことに変わりはないし。小康状態を得て帰宅、自宅療養で回復、ということよ」
実際、そういう場合もあるわね、と姉は苦笑する。
「転院したらよくなったって、患者は言いたがるけど。それまでの治療効果がその頃になって上がってきた、と思しき例はしょっちゅうよ」
では、自分もそうなのだろうか。
以前の状態を振り返ろうとしても、拭ったように思い出せない。
ただ、家に戻ったときの安心感、身体から怠さが一気に抜けていった感覚だけが鮮烈に刻まれている。
「最初っから、たいしたことなかったんだろ」
文彦は電話口で、そう言って笑っていた。
「ストレス過剰で回復が遅れてたんだよ。そもそも神経を使うような場所にいたこと自体、患者として間違ってる」
理屈は通っていた。が、落ち着け、立場を考えろと言ったのは自分じゃないか、と多少は腹立たしかった。
「要はそういうこと。神経性の部分もあったんじゃないの」と、月子までが言い出した。
「夾子も気が利かないこと。あんな騒ぎの最中の病院に運ぶなんて」
「なにしろ急に倒れたから」と、わたしが言い訳するはめになった。
「そのまま入院するとも、思ってなかったろうし」
「ま、最初に、知り合いの病院に行ってしまうと、なかなかねえ」
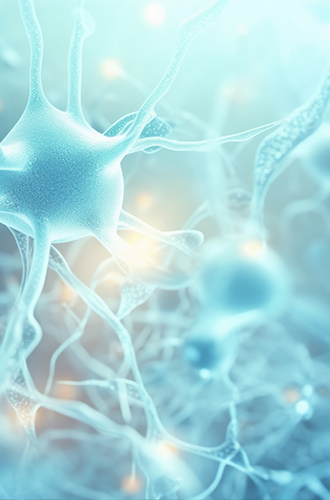
わたしたちのほか、家には誰もいなかったが、月子は囁き声になっていた。危険に敏感なのが適性ならば、まさに医者の鑑だろう。入院中にも、一度も見舞いに来てくれなかった。
「月子姉さんも、渦中の病院には足を踏み入れられなかったんだよね。テレビカメラに映ったら、大変だもん」と、わたしは嫌味を吐く。
「だって、どうせすぐ退院って、夾子が言ってたし」と姉は強弁する。
「あなたの顔を見て、転院しろって勧めたくなっても困るし」
この姉には、検査の数値が改善せず、しびれを切らして退院してきたと話してあった。恐怖に駆られ、裸足で逃げ出して警官を呼ばれたとは、とても言えない。
わたしは立ち上がると、壁際のワードローブを開いた。
病院から帰ったときに着ていたジャケットのポケットを探る。
「ねえ。これを見てもらえないかな」
シートを折り取った二つずつのカプセルと白い錠剤、一袋の粉薬を姉に渡した。
「聖清会病院で飲まされていた薬なんだけど」
「夾子が処方したんじゃないの?」
処方はね、とわたしは言う。
「だけど退院して、あまりにも劇的に改善したもんだから」
月子は慎重な手つきで、錠剤をシートごと裏返した。
「普通の肝機能改善薬だと思う。うちでは使ってないけど」
わたしは頷いた。「そっちの錠剤は、家でもずっと飲んでる。カプセルの方はどう? 朱色と黄色の二色使いよね。これが今、夾子がくれているもの。赤と黄色でしょう」
姉は顔を上げ、上目遣いで見た。年齢とともにやや垂れてきたが、一重瞼の目は相変わらず鋭い。
なぜ夾子に訊かないの? と言いたげだった。
が、無言のまま、再び視線を落とす。
「これもどうやら肝臓の薬ね」
病院の事態がやっと収拾されかかっている今、わたしの口から夾子に投薬を問いただしたりできないのだ、と察したらしい。
「赤と黄色のは、よく知られた越中製薬のやつよ。あまり効かないとも言われてるけど、安いし、副作用が少ないみたい」
すると脱走騒ぎで懲りた夾子が、意識混濁の怖れが少ないものに変えた、ということだろうか。
「病院では、ナースがシートから出して飲ませることもあったけど」
「別の薬にすり替えたとでもいうの?」
姉は肩でなく、首をすくめたように見えた。最近、太ったせいだろう。
「看護学校じゃ、そんな技は教えないわね。だいいち、自分で飲むからよこせと言われたら、どうするのさ」
ぶつぶつ呟きながらも、月子は粉薬の袋も破き、掌に少量を取って嘗めた。
「ただの胃薬ね。昔とは違って器械で密封されているから、何か混ぜるとしても、医師やナースには無理。薬剤師を抱き込まなきゃ」
姉は掌の粉薬をゴミ箱にはたいた。
「あんた、聖清会病院の薬剤師に恨みを買った覚えは?」
わたしは首を横に振った。
「まあね。夾子の彼氏が拘束されている間に、別の真犯人があんたを狙ったというのは、とってもサスペンスドラマっぽいけど」
「そんなこと、決めつけたわけじゃないわ」
月子は再び首をすくめた。
「だいたい毒を盛るような真似が、病院ほど出来にくいところはないんだから。薬をはじめ、口に入るものは大勢の手を経るし、残した食事、排便の量まで記録されるし」

医者ほど脱税しづらい商売はない。
と、昔、父が言っていたのを思い出した。医者がしょっちゅう税務署に挙げられるのは、保険診療の管理で発覚しやすいからに過ぎない。
「そうよ。最悪の場合には、資格剥奪の危険にもさらされるし。普通の医療関係者って、すごく小心なのよ」
「でも、もし過失だったら?」
聖清会病院の経営状態は、すでに普通ではない。
そう言いたかったが、この姉には余計な先入観を与えず、意見を聞くべきだった。
「細かいミスは、一般に考えられている以上にごろごろしてるって、お父さんも言ってた」
「細かいミスは、ね」一音ずつ区切るように、月子は応える。
「だけど、めったに死ぬもんじゃないし。最近は、大きなミスの事例は医師や病院が自ら公表するでしょう? 結局、長い目で見ればその方が、」
「三和子さんでも?」わたしは姉を遮った。
「おっちょこちょいで、目先のことしか考えないんでしょ?」
「あの人は、そうね。認めはしないでしょう」
月子はふんと鼻を鳴らし、冷笑を浮かべた。
「それでも医療ミスのリピーターには手を出させないとか、お目付役のナースを付けるとか、組織的に対策が講じられるものよ。病院内ではまず、劇的事件なんて起きないの。起きないようにしてるんだから」
ああそう、とわたしは頷いた。
姉の分別は、いつからこんな保守的な頑迷にすり替わったのか。
「医療組織ってものを、それほど信じてたんだ。だったら夾子たちのために、病院の言い分の肩を持ってやってもよかったんじゃない?」
姉は不快そうに眉を寄せた。
「なんでわたしが。冗談じゃない、あんたのことを心配したのとは、わけが違うわ」
「どう違うのさ」
月子は肩をすくめた。今度は首でなく、ちゃんと肩をすくめたように見えた。
「逮捕されたのは、あの看護師だもの。わたしたちは関係ないでしょ?」
「夾子の夫よ」
夫。そんな言葉を持ち出すのは無論、本意ではなかった。
認めないわ、と姉は言った。
「会う気もないし。夾子にもそう伝えてちょうだい」
「それはわかってるんじゃないの?」と、わたしも肩をすくめる。
「会えば、印象も変わると思うけど」
「もう、たくさん」と、月子は我慢ならないように頭を振る。
「わたしを巻き込まないで。ああ、お父さんが再婚なんかするから」
「夾子も生まれてこなけりゃよかった、ってわけ?」
「いなけりゃ、そのぶん面倒は起きない」姉は躊躇もなく言い放った。
「で、あんたは。好女子とはどうなの?」
別に、と答えざるを得なかった。「絶縁状態のままだけど」
「じゃ、美希はどうしてるの?」
さあ、と首を傾げた。
釈放以来、夾子宅に蟄居中の彼との折り合いがつかず、家と病院の間を行ったり来たりさせている、としか聞いていなかった。

「ごらん。所詮は縁無き衆生じゃないの」
「だけど腹違いだから、って理由じゃないもの」
「同じことよ」
「同じじゃないわよ」
「元の根はあの女でしょ?」
「それこそ根に持ちすぎ」
こんな姉妹喧嘩は久しぶりだと、思わず苦笑が漏れた。
「何がおかしいのさ」
「姉さん。お嫁入り道具のことは確かにひどかった。でも、お母さんも若かったんだし」
「後妻だもん。そりゃ若いわよ」
「姉さんの母親としては、ね。だけど考えてみたら、もう老人じゃないの。あのね、聖清会の介護施設を見学して気がついたんだけど、もしかしてお母さんは、」
「お母さんって、呼ばないでちょうだい」
突然、月子は耳を覆った。「反吐が出るわよ」と、叫ぶ。
その思いがけない子供じみた仕草に、わたしは苛立った。
「姉さんったら。他人呼ばわりするなら、非難する権利もないでしょ?」
「あるわよ。被害者の遺族だもの」
月子の視線はわたしをも憎み、突き放すかのようだった。
「何のこと? 被害者って誰さ?」
「お父さんよ」
二階のダイニングテーブルで、わたしはひたすらフレンチドレッシングの瓶を振っていた。
キッチンには分厚いステーキが三枚、冷蔵庫から出してある。
「お父さん。何で死んだと思う?」
一昨日、そう呟いた姉の言葉を脳裏から一掃すべく、とっくに乳化したドレッシングを振り続ける。
「心臓麻痺でしょう。違うの?」
「それまで発作なんか一度も起こしてない。高血圧はあったけど、たいしたことはなかったわ」
顔を掌で覆っていた月子は、ふいに目を上げた。
「誰にも言うまいと思ってきた。墓まで持っていこう、と」
わたしはただ黙って、その顔を眺めているしかなかった。
「あんたのせいよ」
姉は諦めたかのような笑みを浮かべた。
「もう忘れようとしてたのに。薬がすり替えられた、みたいなことを言い出すから」
「心臓麻痺じゃなかった、ってこと?」
心臓麻痺よ、と姉は答えた。
「広司さんの診立ての通り」
父の急死の報に駆けつけ、死亡診断書を書いた医師は、たまたま学会で福岡にいた月子の夫だった。
亡くなったのは医者、その娘婿の医師が立ち会った検死で、病死と断定されるのに時間はかからなかった。
「わたしだったら、異変に気づいたかもしれない。父に高血圧があるなんて、広司さんに聞かせていたのがまずかった」
「まさか毒を盛られたとでも? それも、お母さんに」

月子はゆっくりと頷いた。
「劇的事件なんて、起きないんじゃなかったの」
「病院では、ね」と姉は唇を歪めた。
母が、なぜ疑われる?
父の急死に、母はひどい混乱に陥っていた。集まった親戚、近所の目を気にした好女子が、慌てて奥の間へ隠そうとしたほどだった。
「悲しみのショック、とは限らない」月子は硬い声で言う。
「やったことの大きさに気が動転したのよ」
「あのとき、お父さんが死んだときから、そんなふうに考えていたの?」
いいえ、と姉は首を振った。
「あの女が逃げる少し前よ。講演会で聞いたの。ある薬物と別の成分の反応で心臓麻痺を起こす危険性について」
「だって、お母さんがそんなこと、」
「知らないとは言えないでしょ?」月子は正面から見返した。
二十一で後妻にきた母が、それまで勤めていたのは町の薬局だった。
薬剤の卸問屋の知人を通じ、二人の娘を抱えて妻に先立たれた父に紹介されたのだ。
「その危険性自体は、ありふれた注意事項よ。医者なら周知だし、単なる薬局の手伝いでも知っていておかしくない。わたしが講演会で聞いて耳を疑ったのは、その場合の見分け方。お父さんの死に顔が妙に赤黒いって、記憶に残っていた」
(第25回 第十二幕 前編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『幕間は波のごとく』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


