 月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
by 小原眞紀子
第十幕(下編)
目が覚めたとき、時計は二時半を指していた。
フットライトと非常灯だけの、暗い病室の隅で身じろぎした。
頭の芯が痺れていた。その気になれば、また眠れるだろう。
がらんとした病室で、朝までまんじりともせずにいるのは辛かった。かといってスタンドを点け、本を読む気力はない。
と、サイドテーブルを見た。白い封筒が置かれている。
入院費の請求書だろうか。
布団の中から手を伸ばした。封筒の口は開いている。取り出した便箋の薄い手触りに、嫌な予感が走った。
人殺しの家族め。
ナースコールを手探りで掴んだ。
廊下は静まり返っていた。手応えのないボタンを狂ったように押し続けた。誰もいない、ということがあるだろうか。
明るい廊下に黒い人影が覗く。自分で呼んだナースだと頭ではわかっているのに、反射的にぞくっと震える。
「どうなさいました?」
ベッドの端に封書を押し込んだ。
暗がりを抜け、近づいてきたのは小久保ナースだった。
「誰か来たかしら?」
「お膳を引きに、わたしが」
そうだ、お膳。廊下の光で、床がきれいに拭き取られているのが見えた。始末を頼みもせずに寝てしまうなんて、どう思われたろう。
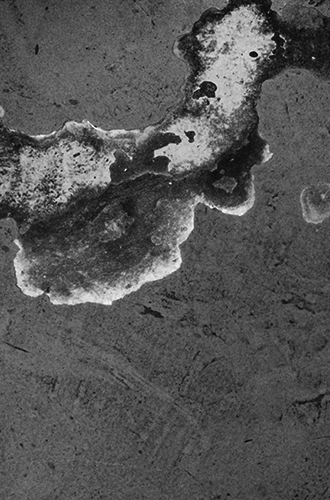
「その後は」と訊いた。
「院長代理がいらしたりしなかった?」
「いいえ」
答えながら、小久保ナースの目が泳いだ。担当といえども、病室への出入りをすべて確認できるわけはなかった。
「変な夢を見たみたい」と、わたしは言った。「床を汚したのも、片づけさせちゃって」
彼女が床を拭いたとき、サイドテーブルにすでに封筒はあったのか。
もし、中を見られていたら。
小久保ナースといえども、下手に尋ねるわけにいかなかった。
「ずっとお休みになってましたから。明朝、早くから検査ですし、軽い導眠剤でもお持ちしましょうか」
大丈夫、と大急ぎで首を横に振った。
ナースは立ち去った。
わたしは封筒を引出しの奥に仕舞い込んだ。
闇の中、廊下の薄明かりから目が離せない。
人殺しの家族め。
以前はゴミ袋も切り裂かれていた。植木鉢が割られ、ポストに石を詰め込まれた。そのことは町内会長、郵便屋も知っている。
が、あの封書のことは文彦にも話していないのだ。捨てずに取っておくべきだったが、便箋もワープロの文字の位置も、前と同じで間違いない。
別人が真似たなど、あり得なかった。
誰なのか。病室の中にまで入ってきたのは。
しかし神経が高ぶっていたのは、しばらくの間だった。病室の入口を見張る格好のまま、わたしは再び意識を失うように眠り込んでいた。
「さあ、検査に行きますよ」
喉が乾き、上顎がひりひりする。起こされたのは十時をまわり、朝食の時間はとうに過ぎていた。
お水を、と頼んだ。その声が掠れていた。
消化器の検査でも水は構わないはずだ。が、見知らぬナースは面倒そうに躊躇し、ずいぶん経ってからコップを持ってきた。
「あのう、夾子は?」固まった舌がやっと動く。
「主治医なら、検査室にいらっしゃいます」
ナースは三〇代半ば程度か。名札を読もうとしたが、二重にぼやけていた。足がもつれ、ストレッチャーに載せられた。
運ばれた先は脳MRI検査室だった。
「どうして、」
こんな検査をするのかと訊こうとしたが、ナースは無視する。
朝食を抜いたからには、消化器の検査ではないのか。どうして足がもつれるのか。それになぜ、こんなに喉が乾くのか。
何かおかしい。と、横たわった視界の下部に白衣の裾が見えた。どうやら夾子らしい。
「あっちに着くやいなや倒られたら、義兄さんに言い訳できないもの」
念のためだから、という妹の声に、やっと安堵する。
「脳ドッグのつもりで。保険でやれるしね」
では個室料代わりの、単なる保険点数稼ぎと思っていいのか。確かに、足がもつれるのは脳疾患症状だ。が、それを訴えた覚えはまだない。
「ねえ、夾子」
黙って、と妹は叱った。
「閉所恐怖で不安な場合は手を挙げてください」
白いドームの中へ頭から吸い込まれてゆく。周囲には専門医、技師やナースがいる。閉所恐怖。この不安感がそうなのか。夾子の姉として、手を挙げて助けを呼ぶわけにはいかない。
固く目を閉じ、終わるのをひたすら待つしかなかった。

ドームから出されると同時に、検査室の扉を開けている妹の姿が目に入った。
「夾子、眩暈がするの」
「特に異常ないみたいだったわよ」
振り返った妹は事務的な表情だった。
「お部屋で専門医の先生から説明を聞いて。今流行っている風邪、三半規管に影響が出るみたい。六人部屋に一人でいるんだもん、空調の温度を上げた方がいいかも」
「文彦さんがね、」
何を、自分は言い出すのか。こんなとき亭主を持ち出す女を、軽蔑していたはずではないか。そう思いながら止められなかった。
「肝機能の数値について、セカンドオピニオンを求めたらって。東京の大学病院に転院するようにって」
もの思わし気に、夾子はちらりと見やった。
「わかった。後ほど」と、他人口調で答える。
検査室から出てゆく白衣姿は、少女めいた赤い頬の妹ではなかった。
わたしの方は、心配する必要もないのに言い募っている患者だった。そんな厄介な患者の悪口を、さんざん聞かされて育ってきたのに。だが患者が感じる気後れとは、こんなものなのか。
残ったナースと検査技師が立ち働きはじめ、自分の身が再びストレッチャーに載せられたとき、妹の表情の意味にやっと気づいた。
少なくとも彼らの前で、あんなことを言うべきではなかった。
やはりどうかしている。
病室に戻り、ナースが空のストレッチャーを転がして立ち去ると、自己嫌悪に陥りつつ、ベッドの上の天井を眺めていた。
と、急いで身体を起こし、サイドテーブルの引出しを開けた。
転院の理由を思いついたのだ。
悪意を持つ誰かが、この居場所を知っている。
だが手紙はなかった。確かに引出しに入れたはずの封書は、跡形もなく消えていた。
夢でも見たのか。
わたしは自分自身を疑いはじめていた。
(第22回 第十幕 下編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『幕間は波のごとく』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■





