 女優、そして劇団主宰でもある大畑ゆかり。劇団四季の研究生からスタートした彼女の青春は、とても濃密で尚且つスピーディー。浅利慶太、越路吹雪、夏目雅子らとの交流が人生に輪郭と彩りを与えていく。
女優、そして劇団主宰でもある大畑ゆかり。劇団四季の研究生からスタートした彼女の青春は、とても濃密で尚且つスピーディー。浅利慶太、越路吹雪、夏目雅子らとの交流が人生に輪郭と彩りを与えていく。
やがて舞台からテレビへと活躍の場を移す彼女の七転び、否、八起きを辻原登奨励小説賞受賞作家・寅間心閑が Write Up。今を喘ぐ若者は勿論、昭和→ 平成→ 令和 を生き抜く「元」若者にも捧げる青春譚。
by 文学金魚編集部
その回の台本を渡されたのは、四季の事務所だった。台本を渡してくれたのはマネージャーだったが、実は彼女は三人目。自分が前例のない立場だから、四季としても体制を整えるのが大変なのだろう。そう考えていたので、短期間での交代には驚かなかったけれど、三人目のマネージャーが昨年秋に亡くなった金森馨さんの奥様と知った時には驚いた。
更に驚いたのは、あれから半年くらいしか経っていないということ。参宮橋のご自宅で浅利先生と二人、金森先生の御遺体に付き添っていたあの夜、帰ろうとしたおチビちゃんに「そばにいてくれないか」と浅利先生が沈痛な面持ちで訴えたあの夜からたった半年……。
もっと長い期間に思えるのは、テレビの世界の流れが早いからかもしれない。四季の舞台に立っていた時は、街で知らない人から顔を指されることなど一度もなかった。それがどうだろう、たった数ヶ月で何度もそんな経験をしている。
やはりテレビの力は凄いと思う。その波を乗りこなすことなど到底出来ないが、こうして揺られているだけでも十分に楽しい。知らなかった景色が次から次へと現れる。だからその台本を読んだ時、おチビちゃんは素直に嬉しかった。とうとう自分がメインの回が来たのだ。もちろん緊張感はあるが、それよりもワクワクする気持ちの方が強い。
この数ヶ月、日々新しいことを吸収してきたという自覚がおチビちゃんにはある。共演者の方々とのコミュニケーションも取れているし、スタッフさんとの連携にも問題はない。もう右も左も分からなかった初日とは違う、私はこのチームの一員なんだ。そんな強い気持ちで、当日おチビちゃんは撮影に臨んだ。
初めて関わった患者である、車椅子の少年に対して献身的に接する早苗。少年も心を開いてくれた為、日が経つごとに離れ難くなっていく。最後はより良い治療を受ける為に転院していく彼を、早苗は寂しさや辛さを堪えて送り出す。残ったものは、患者への過度な思い入れはいけないという教訓――。
このストーリーはしっかりと頭に入っているので、あとは早苗の心情の移り変わりを丹念に見つめ、自分の全身に行き渡らせていけばいい。ただ、ここは舞台の上ではない。幕が上がる代わりに、カメラが撮影を始める。映された自分の姿や動きが、そのままテレビで流れることはなく、監督以下スタッフの方々による様々な編集作業が必要だ。何度も同じ場面をやり直すこともあるし、カメラがベストのポジションを探し当てるまで静止していることもある。必要なのは、演じ続ける集中力より、すぐに演じられる集中力。
――求められているものが違うのよね。
漠然とではあるが、おチビちゃんの中ではひとつの答えが出ていた。
もちろん実際の現場は、良くも悪くも様々な可能性に溢れている。事前の考え通りに物事が進むことは少ない。今回、少年と二人のシーンでそれは起こった。

「ちょっと今のところ、もう一度かな」
監督さんの天の声がする。何か難しい動きがある訳でもない、ごくごく普通のシーン、しかも撮り始めて間もないタイミングだったので、おチビちゃんは意外な感じがした。もう一度スタート。でもまたすぐに天の声がする。
「うーん、もう一度、やってみようか」
またすぐに止められた。何かがうまくいっていないのは確実だけれど、それがどこなのかさっぱり分からない。まさか少年に尋ねるわけにもいかず、またやり直す。
「はい、その部分、もう一度やっておこう」
まただ。おチビちゃんは密かに焦り始めていた。どこがどうと訊けないまま再び、いや三度やり直す。
「うん、あのね、やっぱりもう一度かな」
何がダメなんですか? と訊けないまま撮り直して、また止められた。今度こそちゃんと尋ねてみよう、と決めた瞬間、ディレクタールームから女性がひとり下りてきた。武敬子プロデューサーの助手さんだ。
「ちょっと」
「……」
「ちょっとこっちへ来て」
ぐいと手を引っ張られ、セットの奥へ連れて行かれる。驚いて声が出なかった。
「あなたね、これテレビなんだから、舞台上みたいなお芝居してどうするのよ!」
小声で怒鳴る彼女に返す言葉はない。その迫力もさることながら、言葉の意味がうまく掴めなかった。
「分からない? あなた無意識でやってるの?」
喉がひっついたようで声が出しづらい。何度か小さく咳払いをして、ようやく「すみません」とだけ伝えられた。
「どうして笑ってるの?」
「?」
「一番最初のところよ。あなた、何で笑ってるわけ?」
そのことか、とすぐに思い当たった訳ではなかった。ちゃんと思い返してみる。確かにカメラが回り始めた瞬間は笑顔だった。フフ、と声が出ていたかもしれない。でもそれは……。
「理由、ある?」
はい、とは言えなかった。
「何か面白い出来事があった? だったら笑ってないとおかしいわよね。どう? あのシーンの前に、何か笑えるようなことがあった?」
間髪入れずに「いいえ」と答えたのは、ふてくされたからではない。彼女の言葉に納得できたからだ。
多分、雰囲気で芝居をしていたんだわ。そう思えた。子どもが一緒のシーンだから楽しくした方がいい。そんな簡単なイメージで笑ってしまっていた。「舞台上みたい」なんて言われたけど、あんなこと、浅利先生が一番嫌がる芝居だ。もちろんそうやって言い返すことはできず、おチビちゃんは何度目かの同じシーンに臨んだ。結果は一発OK。
すいませんでした、と周囲に頭を下げながら「ちょっと慣れすぎちゃったかな」と反省する。この現場に、共演者に、スタッフさんに慣れてきたから、変な感じで調子づいてしまったんだ……。おチビちゃんは病室のセットの縁に片足を乗せながら、そっと身を引き締めた。

その話は夏目雅子さんから舞い込んできた。
「ねえ、早苗ちゃん?」
こういう悪戯っぽい表情の時は何かある。用心というほどではないけれど、一応覚悟して近寄ると顔をぐっと近づけて凄いことを呟いた。
「一緒にコマーシャル、やりましょうよ」
え、と思わず変な声が出る。商品はカネボウのヘアカラーだという。
「カネボウ?」
「そう! この間歌舞伎の帰りに行ったじゃない? あれがきっかけみたいなものよ」
はい、と答えてみたものの、頭の中ではようやく「コマーシャル」という単語を理解し終えたところ。どうしよう、という動揺がやっと顔に現れる。
「ちょっと、早苗ちゃん、聞いてる?」笑いながら夏目さんに肩をポンポンと叩かれた。「なんて顔してんのよ」
いきなりこんなこと言われたら誰だって、という気持ちをつんのめりながら伝えると、また笑われる。
「ごめんごめん。まあ落ち着いて、ね?」
コマーシャルに出る時の役柄は、いわゆる本人役。先輩後輩のふたり、というイメージらしい。そこまで聞いて、やっと実感が湧いてきたおチビちゃんは「ええ、どうしよう……!」と落ち着かなくなる。
「大丈夫よ。私がしっかりと推薦しておいたんだから」
おどけて胸を張る夏目さんが頼もしい。初日の撮影の記憶がふと蘇った。本当に会えてよかったと思う。変なタイミングで「ありがとうございます」と頭を下げて、「もう、やめてよお」と肩を抱かれた。
「あと、ちゃんとOKもらったからね」
「……え?」
「武さんもすごく喜んでたわよ」
反応が一瞬遅れたのは、OKを出したのが浅利先生だと思ったから。そうか、こういう話が来た時に確認をするのは武さんなのか、と感心する。少し前なら考えられなかったことだ。やっぱりテレビの世界は話が早い。そしてスケールが大きい。
それから数日目立った動きは無かったけれど、おチビちゃんは焦らない……ように頑張っていた。平静を装うのは意外と難しかったが、今ジタバタすると、あの素敵な話が消えてしまいそうで怖かった。
ちっとも落ち着かなかったけれど、夏目さんがいるから絶対うまくいくと信じる日々。事態が動いたのは一週間を越した頃だった。夏目さんが別のコマーシャルの撮影をしているスタジオで、スタッフさんも交えて打ち合わせが行われるという。マネージャーの金森さんが不在だったので、慣れない場所にひとりきり。でも心細さを感じる暇などなかった。おチビちゃんの衣装やヘアスタイルをどうするか、についてスタッフさんたちが意見をぶつけ合った後、実際に触って髪質をチェックされたり、顔を色々な角度から観察されたり、と息つく暇もない。驚いたのは容姿についても、相当率直な意見が飛び交うところ。鏡を見るよりも、自分の外見が分かりそうな気がした。
そのうちサラサラと絵コンテが描かれる。全部で三パターン。それ自体はとても簡素なものだったが、おチビちゃんの頭の中には、ふたりで共演している姿が鮮やかに浮かんでいた。例えば「ユーモア編」と題されたパターンでは、素敵な「先輩」夏目さんの言葉に、「後輩」のおチビちゃんが「はい!」と素直な返事を繰り返すというもの。
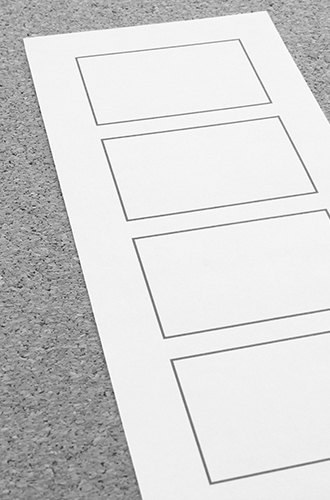
「私、女にとって髪は、自分を表現できる唯一の場所だと思うの」
「はい!」
「色とツヤ、それは健康の証」
「はい!」
「このファッションカラーなら、無理なく穏やかに染め上げてくれる。決して無理はしないこと」
「はい!」
「……恋と同じよ」
「……そちらの方は無理が目立ってますよ」
そんな自分たちのやり取りが映像になったことを想像するだけでも嬉しくて、何か一仕事やり終えた様な気持ちでおチビちゃんは家に帰った。
いよいよ本格的に、夏目さんとのコマーシャルの話が動き出した。言うまでもなく大きな仕事だ。数ヶ月前には、自分にそんな仕事が来るなんてこれっぽっちも思っていなかった。あの頃に戻って「あと少し経ったら、カネボウのコマーシャルやるんだよ」と教えてあげたいが、きっと数ヶ月前の自分は信じないだろう。今だって信じられないのだから無理もない。
次にやることは本番の撮影だけ、という状態で「野々村病院物語」の収録を続けていた。実は新しい仕事の話も入ってきている。今度はフジテレビの昼の連続ドラマらしい。あとは映画のオーディションが一本。あんな大きなスクリーンに自分が映るなんて、まったくピンとこないけど、受けるからには選ばれたい。ただ、金森さんから先の仕事の話を聞く度に、ワクワクだけでは言い表せない感情が混ざり合う。
もっと新しい場所で、もっと大きな仕事をしてみたいが、このまま舞台から遠ざかってしまうことへの不安もやはりある。いや、舞台というより四季かもしれない。このまま四季へ、浅利先生のところへ戻らなくてもいいのかしら?
なかなか答えは出ない、というか、今はまだ出したくない。答えが出るのは、もう少しこの新しい世界で自分の力を試してからだと思う。
次に金森さんから仕事の連絡が入ったのは、待ちに待ったコマーシャル撮影の前日。夏目さんや武プロデューサーたちと、撮影折り返しの「納涼ビアパーティー」へ行く直前のタイミングだった。
もしもし、という彼女の声が心なしか暗い。
「あ、お疲れ様です。今日はこれからビアパーティー、行くんですよ」
「そう……」
「?」
「あのね、残念なことに、あれ、キャンセルになっちゃった……」
「え、フジテレビのドラマですか?」
「いや、カネボウのコマーシャルの方」
鳥肌が立った。どうしてですか、と大きな声をぶつけたが返事はない。しばしの沈黙の後、金森さんはこう告げた。
「浅利先生の方から、ストップかかったから」
(第34回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『もうすぐ幕が開く』は毎月20日に更新されます。
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■






