 「世に健康法はあまたあれど、これにまさるものなし!」真田寿福は物語の効用を説く。金にも名誉にも直結しないけれど、人々を健康にし、今と未来を生きる活力を生み出す物語の効用を説く。物語は人間存在にとって一番重要な営為であり、そこからまた無限に新たな物語が生まれてゆく。物語こそ人間存在にとって最も大切な宝物・・・。
「世に健康法はあまたあれど、これにまさるものなし!」真田寿福は物語の効用を説く。金にも名誉にも直結しないけれど、人々を健康にし、今と未来を生きる活力を生み出す物語の効用を説く。物語は人間存在にとって一番重要な営為であり、そこからまた無限に新たな物語が生まれてゆく。物語こそ人間存在にとって最も大切な宝物・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、かつてない物語る物語小説!
by 遠藤徹
3.エコバッグ(前編)
いつものようにスーパーで買い物を終えた真田寿福は、ひとりアパートへの道をたどっていた。午前中は執筆にあて、昼食後軽い昼寝をしてから散歩をするのが日課となっている。散歩する場所は日によって異なるが、いくつかのルートがある。川沿いの道を歩く日もあれば、少し足を伸ばして町外れの山に登る日もある。そのあと、喫茶店で一服して本を読み、スーパーに寄って帰宅するというのが、真田の日常なのであった。夜も早々に寝てしまう。奇天烈な小説を書く人間だから奇天烈な生活をしていると思われがちだが、真田の日常はごくごく平凡、かつ判で押したように似たようなものだった。むろん、真田にいわせれば、そうした単調な反復のなかにこそ至福が潜むということなのであろうけれども。たとえば、喫茶店でいつもの席に座っていつものコーヒーを啜りながら、真田は先日のセミナーでひとりの中学生がしてくれた話を思い出した。
「コーヒーカップと受け皿。受け皿の上には、白い象とコアラとライオンがいる。受け皿に描かれた絵というわけじゃなくって、ほんものの白象とコアラとライオン。小さな小さな白い象と子熊とライオンだ。プラスチックのおもちゃでよくあるようなサイズ。象は鼻をぶらぶら振りながら歩いている。コアラはユーカリの木がなくて不安なのか辺りをきょろきょろうかがっている。ライオンは、さすがの貫録で寝そべたまま惰眠を貪っている。ただし、生きている証拠に呼吸に合わせておなかががゆったりと膨らんだりしぼんだりしている。

「最初に象を入れてみてください」
マスターに言われて、そっと白い象をつまみあげた。軽い。象は鼻を持ち上げ、耳をぱたぱたさせて、上目遣いにこちらを見た。
「いいんですか?」
「ええ、どうぞ」
象をコーヒーに落とした。みるみる溶けていく。白い輪が広がり、やがてコーヒーの黒さを、おちついた焦げ茶色に変えた。
「飲んでみてください」
「ああ、まろやかになりましたね」
「そうでしょ。最初の一口目は、そのままで飲んでいただきました。うちのブレンド独特のいろんな部分がとんがった味を堪能していただいたわけです。次には、白象によって、それらが一つにまとめられた融和感を味わっていただく、そういうわけです」
「うん、おいしいよ。最初の口の中があちこち刺激される感じも面白かったけど、この落ち着きはどっしりして満たされるね」
「あと、二、三口お飲みになったら、次はコアラですね」
「へえ、コアラですか」
「ええ、背中から上手く掴んでくださいね。こいつ意外に爪が鋭いんで」
なるほど、背中から摘まみ上げたが、少し暴れた。鋭い爪でひっかこうとする。
「ちっこいくせにこいつ」
コーヒーの上で、思わず指を放してしまった。手足をばたばたさせながら、コアラはコーヒーの中に落ちていった。
「あれっ、このコアラなかなか、溶けないですよ。水面で、助け求めてアップアップしてますけど」
「混ぜてください。スプーンでぐるぐると、渦を起こしてください」
「なんか、溺れさせてるみたいだな」
ちょっと気が引けたが、思い切って混ぜた。アップアップしながら、コアラは渦に呑み込まれていった。
「ではどうぞ、ご賞味ください」
「おお、これは!」
思わずうなってしまう。また味に大きな変化があったからだ。そこはかとない甘みが加わっている。砂糖や、合成甘味料の甘みではない。爽やかな、なんというのかかそけき甘み。コーヒーの味を損なわない、かすかな、上品きわまりない甘みだった。
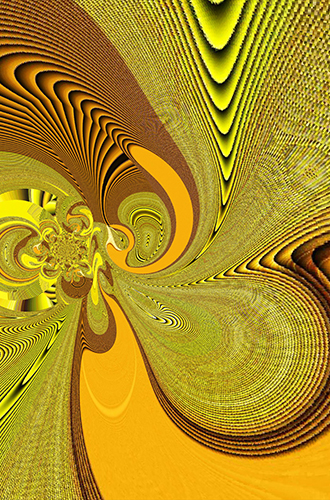
「おいしいですね。苦くてまろやかでほのかに甘い。なんというのか未体験の味です」
「でしょう」
このまま、最期まで飲みきっても良かった。ライオンはお代わりにとっておこうという気にもなった。それほど、その味が気に入ったのだ。
「もちろん、それでもかまいませんが」
髭面のマスターは、いつものようににこにこ微笑んでいた。
「もし、冒険をお好みでしたら、最期はライオンをおすすめしますね」
「へえ。冒険かあ。そこまでおっしゃるなら」
「あ、だめだめ。さすがに相手は百獣の王です。これを使ってください」
マスターは、角砂糖用の小さなシュガートングを渡してくれた。
「なるほどね。怪我した人もいるんですか?」
「いや、さすがにお客さんは大丈夫ですよ。わたしが気をつけてますからね。でも、わたし自身は、以前油断してて噛まれました」
マスターは親指を、ほらっと見せてくれた。そこには、ライオンに噛まれた痕がくっきりと残されていた。けっこうな出血量で、医者にかかったほどだったという。
「どんなに小さかろうと、やっぱり猛獣は猛獣。油断は禁物ってことですよ」
「ちょっと、怖いな」
なるほど、こいつは喫茶店の冒険だ。そう思いながら、シュガートングで眠っているライオンをそっと掴んだ。途端にライオンは目覚めて暴れ始めた。
「しっかり掴んで、そう、あと少しです」
咆哮も上げた。小さいくせに、なかなかの威嚇力だった。それに、全身の筋肉の躍動ぶりも見事だった。まさに筋肉の塊である。
「よし、そこで落として」
ぽちゃっと音を立てて、吼える猛獣が半分ほどに減ったコーヒーの水面に落ちた。驚いたことに、そこからでもライオンはジャンプして、縁を掴もうとした。
「気をつけて、スプーンで落とすんです。そうです。そう。あと二、三回」
カチャッ、カチャッと、スプーンがコーヒーカップのへりに当たる音が響いた。下手するとライオンは軽々とコーヒーカップの縁を飛び越えそうだった。けれども、ジャンプするごとに、その力は衰えていった。痩せていくようにも見えた。
「そう、こいつはコーヒーに溶けやすい体質なんですよ。だから、もう大丈夫。ほらね」
やがてジャンプする力を失ったライオンは、ぐずぐすと崩れて、コーヒーと一体になった。
「さあ、残りをご賞味ください」
「おおっ、これは」
がつんときた。シナモンの強烈な匂いがまず鼻腔を突き、喉を刺激した。さきほどまでの落ち着きが、またざわめきに変わった。ぐいっとそれを飲み干すと、全身がぽかぽかした。脳がぴりぴりと目覚める感覚があった。心がゆったりと満たされる感覚があった。
「うん、なるほど、もう十分ですね」
いつもなら、お代わりを頼むのだが、もう十分という感じがした。というより、なにもかもが満たされたという感覚になっていた。
「これで、当分は、コーヒー飲まないでも大丈夫ですよ」
「というと?」
「いまお感じになってる感覚が、一ヶ月くらいは続くってことですよ。どうです、一杯はそこそこの値段だけど、試してよかったでしょう」
「そうですね。これを試さない手はないですね、まったく。次はまた別のを頼みますよ」
「いいですよ。次は蛇なんてどうです。コーヒーカップをぐるっと取り巻く、ボアコンストリクターとか」
「ボアだけですか、蛇は?」
「いえいえ、コブラとかハブもありますよ。でも、こっちはかなり上級のコーヒー通向けっていうかね」
「ああ、いろいろあるんだ」
「ええ、そうなんです。また、その時の体調や気分をお伺いして、調整させていただきますよ」
「うん、ありがとう。じゃ、また」
「ご来店、ありがとうございました」
店を出て振り返ったが、そこにあるのは理髪店だった。やっぱりだ。いつだって行ける喫茶店ってわけじゃないんだ。ほんとうに必要になったときにだけ、目の前に現れる。だから、もしかしたら、もう二度と行けないかも知れない。でも、また次があると期待しよう。それに、当分はこの喫茶店の力を借りないでも大丈夫そうだし。この店に入る前とはすっかり打って変った前向きな気持ちになって、歩き出した。」

うん、あれはなかなか面白かったな、と真田はふっと微笑む。中学生にして、こんな物語を醸せるというのは、ほんとすごいなあ。そんな風に、一杯のコーヒーだって、呑むたびに真田にとっては新しい体験となるのだった。
「あの」
買い物帰りの真田に呼びかける者があった。それはほんとうに珍しいことだった。かなり有名人であるにもかかわらず、真田寿福はまったく目立たないからだ。変装しなくても、ほとんど声をかけられることなどない。有名人によくあるようなオーラのごときものは、一切感じさせない。むしろ見えないとすらいえた。カメレオンの擬態能力的なものがあるというわけではない。そもそも彼自身が、自分のことを特別だと一切感じていない。それこそが、彼が人目につかない最大の理由なのであった。
「はい?」
少し戸惑ったように振り返る真田。そこには、一人の少女がいた。学校帰りなのだろう。高校の制服姿だった。にこにこ笑っている。ただし、真田を真田と認識しているのかどうかはわからなかった。
「よくお見かけするんで前から気になってたんですけど、お買い物ですか?」
なるほど、まだ明るい時間にいい年をした中年男性がスーパーで買い物をしている。しかもそれが毎日なのだ。下校時にその姿を見て、ちょっと興味をもったということなのだろうと真田は考えた。
「ああ、うん。豚肉とジャガイモとニンジンを買ったよ。家にタマネギがまだあるから」
「肉じゃがですか?」
「うん、そうだね。それとカレーもいっしょに作っちゃうつもりだよ。明日は帰りが遅くなりそうだからね」
明日は金曜だから、夕方から定例のセミナーが開催される予定になっていた。ほとんど外食しない真田は、その日の分の食事も今日のうちに作っておく予定のようだった。

「なるほど、その素材だとシチューもいけますよね。あと、ポトフとか?」
「ああ、ポトフもいいね。でもぼくは基本ご飯派だから」
「いいえ、シチューもポトフもご飯でもオッケーですよ。家はいつでもそうです」
「なるほど、まあご飯は適応力抜群だからね」
「三食自炊なんですか?」
少女は驚いているようだった。
「そうだよ。ほんとはもっと田舎に引っ込んで、自分の食べるものは自分で作りたいくらいさ。いずれはそうするつもりだけどね。まだ、いまはいろいろこっちでやらなきゃいけないことがあるから」
「自給自足ですか?」
「そう、人間誰しもそれが理想だよね」
「誰しも、ってわけじゃあ無いと思いますけど」
じゃあ、わたしはここで失礼しますと、少女はお辞儀をして去って行った。まあこれで、彼女の疑問も解けたことだろう。どうやらこの界隈には、三食自炊している暇そうなおじさんがいるようだということ。どういう職業でそれが可能になるのかというようなことを聞いてこないのが、まあ奥ゆかしいところではあると、真田は考えた。
(第10回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







