Interview:三浦雅士インタビュー(1/2)
三浦雅士:昭和二十一年(一九四六年)青森県弘前市生まれ。思想家、文芸批評家、舞踊研究家、編集者。四十四年(六九年)に青土社創業と同時に入社。四十七年(七二年)より「ユリイカ」編集長、五十年(七五年)より「現代思想」編集長を歴任。五十七年(八二年)に退職後、本格的文筆活動を始める。『メランコリーの水脈』でサントリー学芸賞、『身体の零度』で読売文学賞受賞。現代文学と思想のみならず、お能、日本舞踊、バレエなどの舞台芸術にも精通している。
■ポスト・モダンについて■
金魚屋 一九八〇年代頃から日本の文学界・思想界にポスト・モダン思想が流れ込み、わたしたちも多大な影響を受けました。ただどうも額面通りには受け取れないところがあります。とても刺激的な思想で従来の考え方の枠組みを壊す役割はあったと思いますが、やはりその先を考える必要があると思います。三浦先生はポスト・モダン思想の旗手のお一人だったわけですが、演劇や舞踏など肉体的な核のある表現と、ポスト・モダン思想を出会わせている、繋ぎ合わせておられるように思うのですが。
三浦 ポスト・モダン思想の一番のポイントは、起源というものは全部怪しいということなんです。みんな昔の方が古いんだ、昔に起源があると言うけどそうじゃない。そういった思考を疑う必要がある。簡単に言うと、たとえば今が一番古いんだという発想への転換が必要です。大昔というのは、むしろ君自身の中にあるんだよ、ということです。古さ・新しさというシステム自体が言語によって作り出されている。
二十世紀になって新しい学問がダーッと出てきましたね。たとえば動物行動学、エソロジーです。動物行動学を例にすると、それ以前までは犬や猫の起源を調べるには、解剖すればいいと考えていた。これを積極的に行ったのはドイツの学者たちです。解剖してみれば、哺乳類はほぼ同じ身体構造を持っていることがわかる。解剖である本質に行き着くという考え方です。でもよく考えてみれば、生きている生命体でなければ意味がないんじゃないか、という考えが芽生えてきた。生きていることに生命の本質があるんじゃないかという新しい考え方です。この考え方を敷衍してゆけば、生きているものたちの諸関係の方が、解剖なんかよりも重要だということになる。関係性を意味づけてゆく行為の方が遙かに重要だということですね。そこで犬のことを知るには、犬と実際に生活してみなきゃならないということになった。それが動物行動学です。
この考え方は芸術の方面にも広がってゆきました。音楽や美術が、今現在どういうふうに享受されているのかを調べてゆくわけです。一個一個の対象を事細かに分析していってもしょうがない、関係性を見なければ本質はわからないんだという発想の転換です。この考え方を適用して、最初に学問的成果を出したのが美術史です。ヨーロッパだと昔の礼拝堂では、今のテレビと同じようなことが起こっていた。教会に礼拝に行くには違いないんですが、子どもたちにとっては映画やテレビドラマを見に行くような側面があった。イエス様が生まれて布教を始めてと、ステンドグラスや壁画を読んでゆくわけです。つまり読んでゆくことが享受だった。それが何を語るかというと、今現在の僕たちの享受の仕方が起源そのものだということです。物があって享受が生まれるんじゃなくて、享受があって物が生み出される。それは考え方の逆転ですね。どこかに行って、あるいは何かだけを一生懸命調べるんじゃなくて、自分自身の中にあるシステムを分析していった方が起源に辿り着きやすい。
金魚屋 時間軸を遡るんじゃなくて、関係性の中に起源を見ると。

三浦 そうですが、関係性の中から時間軸も発生しています。時間軸と空間軸という座標の中にあなたがいるわけではなく、あなた自身が座標を作っているということです。歴史的な時間・空間軸が絶対化されてしまう理由は言語にあります。犬や猫は言語を持っていないからあまり悩まないでしょう。人間だけが悩むのは、言語を持っているせいです。そのことを忘れてはいけないということを、個々の現実事象に当てはめていったのがデコンストラクション(脱構築)です。人間は様々なところで矛盾を発見しますが、なぜ矛盾として認識されるのかというと、それはすべて人間が持っている言語に原因がある。このフレームというか構造は、ルネッサンスの後のバロック――マニエリスムとも呼ばれますが――の時代にすでに見られます。
ヨーロッパではルネッサンスが昔を振り返る最初の自覚的運動でした。ルネッサンス期の人々はギリシャやローマを模範にしていた。それを反復していって、クラシック=古典というジャンルが生まれた。新たなクラシックを作ったんですね。でもそれに対する疑いが出てきた。スタティックに絵解きができる映画やテレビドラマじゃなくて、スターが出てきて活躍することそのものに注目しようとしたのがバロック・マニエリスムなんです。このバロック・マニエリスムの担い手になったのはスペインです。なぜスペインかと言えば、金が集まっていたからですね。
中世のヨーロッパでは、イタリアのヴェニスとジェノバにまず金が集まった。地中海貿易ですね。当時は東ローマのコンスタンティノープル、今のイスタンブールが交易の拠点だった。コンスタンティノープルがイタリア商人の富の源泉だったんです。ヴェニスとジェノバは都市自体が株式会社みたいなものでしたが、この交易ルートをもっと拡大して効率化したのがオランダ東インド会社、次いで現れたイギリス東インド会社です。そして東インド会社が出現するまでの繋ぎの役割を担ったのが、カトリック国のスペインとポルトガルです。
イタリア商人は地中海貿易だけをやったわけですが、それはコンスタンティノープルに行けば南インド洋、南シナ海の様々な商品が簡単に手に入れられたからです。ところがスペインとポルトガルは、喜望峰を回ってダイレクトに南インド洋、南シナ海のエリアと関係しちゃった。それによって膨大な富を得た。そうなるとスペインやポルトガルに画家を始めとする文人たちが集まるようになります。特にコンスタンティノープルが陥落した後はそうです。グレコなどの画家が代表的ですが、彼らがスペインで始めたのがバロック・マニエリスムです。だからバロック・マニエリスム研究はスペインで盛んになった。この研究の成果を、ごっそりもらって新しい芸術を生み出したのがレンブラントでしょうね。だからレンブラントを研究すれば、ルネサンスからバロック・マニエリスムまでの流れがだいたいわかる。またこの段階でゲルマン語の時代が来ます。美術史がスペイン語からドイツ語で分析され、語られるようになるんです。最初はイタリア語、次にスペイン語、ドイツ語という順に美術史を語る言葉が変わる。そうすると、これは言語自体の中に、ルネサンスからバロック・マニエリスムへの流れを探った方がいいんじゃないかということになってくる。
レンブラントを始めとする画家や美術史家たちは、当時アムステルダムが一番お金を持っていましたから、アムステルダムで探求を始めた。スピノザやデカルトといった哲学者たちも集まってきた。そこからルネッサンスからバロック・マニエリスムへの移行とはなんだったんだろうという研究が出て来たわけだけど、これが十九世紀になって歴史学などの形で大学などで研究されるようになる。歴史学の成果をも応用してバロック・マニエリスム論を研究しましょうということになった。
この学問的探求の流れが、二十世紀に入って一九五〇年代のヨーロッパの学会を占拠してゆくようになります。バロックとマニエリスムは同じなのか違うのか、あるいはバロックやマニエリスムはルネッサンスからの堕落した形態なのか、それとも発展系なのかといった議論ですね。それが二十世紀中頃の学問的フォーカスでした。ルネッサンスはクラシック=古典で普遍だと考えられていましたが、本当にそうなのか。古典の起源は案外あやふやで、更新され続けているんじゃないかということです。このルネッサンスとバロック・マニエリスムの関係は、モダンとポスト・モダンの関係にそっくりなんですね。

『孤独の発明 または言語の政治学』
講談社刊 2018年6月30日
金魚屋 確かによく似ています。
三浦 このことは、僕以外、まだ誰も言ってない。ということは大いに怪しいということです(笑)。とはいえ、ルネッサンスからバロック・マニエリスムへの移行があれほど話題になって、エウヘーニオ・ドールスとかスペインの学者が盛んに論じたけど、美術史の専門家しかこの議論に参入していない。もちろん一般の人がルネッサンスからバロック・マニエリスムへの移行を面白がったことが、美術史の議論が盛んになった理由なんですけどね。簡単に言うと絵の読み方が変わった。ルネッサンスが映画やドラマの筋を面白がるものだったとすると、バロック・マニエリスムは誰がどういう衣装で登場したのかに注目したんです。劇の筋の面白さよりも、着物や登場人物の微笑み方の違いなど、細部の違いに関心が移った。細部を見てゆけば、起源は常に更新され続けているのがわかる。文化だけじゃなく、建築だってルネッサンスからバロック・マニエリスム様式に変わっていきました。それがロココに繋がってゆく。
■概念の衝撃について■
ラモーナ 全体像よりも、細部の微細な差異に人々の興味が移っていったわけですね。
三浦 それがイコノグラフィーからイコノロジーへの学問の推移です。イコノグラフィーはざっくり図像の種類を捉えますが、イコノロジーではもっと目を働かせて細部まで検討する。このイコノロジーによって視覚の研究も出て来ました。視覚研究からさらにゲシュタルト心理学も生まれた。人間が見ること自体の中に持っている心理作用の研究です。イコノグラフィーからイコノロジーへの推移もまた、僕の考えではモダンとポスト・モダンに対応していると思います。これはもっと突き詰めて考えなければならない問題ですが、あまり探求されていない。なぜかと言うと、アメリカがモダンとポスト・モダンを主導してるからね。インターネットの言語は英語が主流でしょう。英語の基準が強すぎるんだな。学問の探究は言語と深く関係しています。英語自体は底の深い言葉なんだけど、ネットなどで使われている英語はすごく底が浅い。それがポスト・モダン研究に影響してしまっている。
ラモーナ そうなんです。英語自体は豊かですが、ネイティブではない大勢の人が使いますから、あっさりした言語になってしまっていますね。
三浦 アメリカ人が作ってきたシステムの底が浅いことも影響しています(笑)。
ラモーナ みんな共通の言語を探していて、それが英語になってゆくという意味では、ポジティブな側面も持っているわけですが。
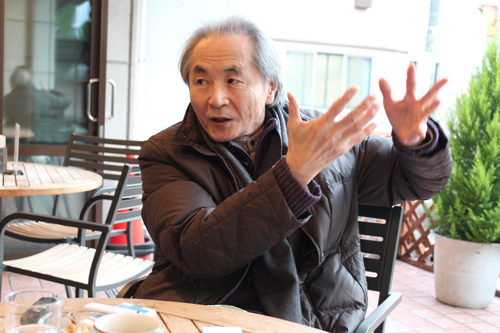
三浦 それと同時に、たとえばルーマニア語の独特の言い回し、日本語のこの微妙な言い回しはとても英語に翻訳できないと主張する人たちも出て来る。今みたいにナショナリズムが強くなった時期は特にね。でもそれは嘘です。必ず伝わる。英語の言語としての奥行きが浅いから翻訳できないといった問題ではない。翻訳可能かどうかというのは、そこに概念の強さ、外国人があっと驚くような概念があるかどうかなんです。今僕がしゃべっていて、それによって視点が変わった、違う何かが見えてきたとするなら、その体験は非常に強烈です。その強烈さは概念が変わった強さです。そのパワフルな力を各国言語に翻訳すればいい。
お能を例にすると、お能のこの部分がルーマニアのフォークロアのある部分に対応している、共通点があってなおかつ違う部分があると指摘すれば、それはお能研究にもルーマニア文化にも影響を与え得る概念になります。だからネットを始め、国粋主義的になっている人たちは、本質的には自国の言語にしがみついているということなんだな。日本語、ルーマニア語、英語が素晴らしいと言い出す人たちは、概念を伝えることができる言語能力がないからそうしているだけなのかもしれない。だけど他者に新鮮な驚きと発想の転換をもたらす概念は、どんな言語にでも翻訳できます。
ただ今一番問題なのは、世界経済の中心であるアメリカでは、違う文化の概念によって驚く、見方を変えるといった謙虚さが足りないことです。二十世紀初めまでのアメリカは、ヨーロッパに対するコンプレックスで動いていました。アメリカ人は王族とか天皇に弱いでしょう。『ローマの休日』とか『ハリー・ポッター』なんかでも、アメリカでヒットするコンテンツには王族が登場するものが多い。ボストンのキヨスクに行くと、イギリスよりもたくさん王室のポストカードが置いてあります。自分たちで王室をカットアウトしちゃったんだけど、それだからこそ郷愁があるんだね。だからかつてのアメリカには、ヨーロッパの学問に対する敬意があった。ナチスが台頭してきてドイツで居場所のなくなった学者を受け入れたりもしました。戦前までは、ヨーロッパ文化を敬意をもって受け入れていたんだな。
金魚屋 美術でもアメリカの美術館のヨーロッパ絵画コレクションはすごいですね。
三浦 金のあるところに美術品が集まるのは世界中同じだけどね。スペインに金が集まった時は、先進文化だったヴェニスとジェノバに憧れて絵画なんかを集めたでしょう。で、ヴェニスやジェノバはコンスタンティノープルの真似をしていた(笑)。
ラモーナ ルーマニアにとって、コンスタンティノープルは非常に大きな存在です。
三浦 コンスタンティノープルの文化はルーマニアに流れています。ルーマニアの文化もコンスタンティノープルに流れ込んでいますね。ビザンチン文化の影響範囲は広いですから。それが陸路と海路を伝って西ヨーロッパに伝わり、最高に洗練されたのがパリです。そういうヨーロッパに対する敬意と憧れが、かつてのアメリカのアイヴィ・リーグの学者たちにはあった。しかし戦後世界経済を支配するようになってから変わってしまった。アメリカだけでやっていけると思っちゃったんだな。謙虚さがゼロになっている。戦前の作家はT・S・エリオットであれヘンリー・ジェイムズであれ、みんなパリやロンドンに行きたがった。帰化した文学者も多い。そういう憧れを持っていた最後の文学者はヘンリー・ミラーかな。
ただ実利的な観点から見たアメリカの文明論はすごくいいんです。アメリカの分析哲学はヴィトゲンシュタイン以降の伝統を受け継いでいて、それを受容した後はアメリカ独自でやっていけると思い込んでいる。全くの間違いだけどね。それに薄々気がつき始めたのが文学畑の連中で、彼らはフーコーやデリダを読み始めた。フーコーやデリダの学問は分析哲学とは正反対ですから。だけどこれも問題があって、禅問答のようなわけのわからない神秘思想に傾いている傾向があります(笑)。アメリカではなんでも理屈でわかると思っている連中が分析哲学をやり、いやそうじゃないと考える連中がポスト・モダニズム思想をやっているという構図です。それはそれでアメリカ固有の問題だけど、アメリカで一番面白い学者たちは動物行動学や生物学、遺伝子工学などをやっている人たちなんです。
彼らは最初は文明論を書く意図はなかったけど、動物行動学や生物学、遺伝子工学の成果を援用して文明論を書き始めた。ギリシャ文学に対するローマ文学のようなものですね。ギリシャ文学はプラトンとアリストテレスに代表されますが、ローマ文学が生んだ中にもキケロなど素晴らしいものがある。ギリシャを受け継いだローマは独自の文化を持っているんです。そういう独自の文化的な達成が、どの点にあるのかアメリカは気がついていない。哲学じゃなくて動物行動学や生物学、遺伝子工学などの発想から生まれた文化論にアメリカ文化の一番いい部分が表れているとはそういうことです。だけどトランプ大統領の時代になったから、当分アメリカバンザイの風潮が続くんでしょうね(笑)。

『メランコリーの水脈』(講談社学術文庫)
講談社 2003年5月10日
■表現の自由と知的所有権■
金魚屋 アメリカという国は、トランプ大統領のような人がトップに立った方が、特に経済的にはうまく行くようなところがありませんか。
三浦 それはどこの国でも同じだろうね。はっきり言うと、バカな人がトップに立っている時は、周りの人間がなんとかしなくちゃと頑張るからね。結局は首を切られるんだけど(笑)。宋代の中国もまさにそうで、暗愚の王様がいる時の方が国が活性化しますね。
金魚屋 文学や芸術と経済は切り離せないところがあります。国はもちろん、文化ジャンルでも経済力のあるところに優秀な人が集まってきます。経済を切り捨てて、いわゆる文学的な小綺麗な観念だけで文学を語ってもしかたがない。
三浦 だから批評家たちは、みんな経済の話をしているでしょう。ただ経済というものも、実は文学的なものがコアになって動いている面がある。決して綺麗に分けて考えることはできない。
金魚屋 これから数十年ですら、社会が本当にラディカルに変わると思います。なお文化と経済を切り離して語ることはできませんね。
三浦 ネットがもたらす変化に対して、客観的な研究が行われていないことは問題ですね。アメリカは盛んに知的所有権を主張しているでしょう。知的所有権というのは要するに、一度何かを考えついたら、ずっとそのアガリで食べてゆけるという制度です。これをアメリカが強力に推進しようとしている。物を作るよりも、アガリで食べてゆくことを重視し始めているんですね。これはとても危険な兆候だね。
本来誰の物でもない土地に所有権を認めて値段を付けちゃったように、インターネットなりなんなりの発明に対しても、アメリカは値段を付け始めている。だけど知的な発明は、社会全体に受け入れられた時点でみんなのものなんです。昔は知的所有権などありませんでしたね。素晴らしい詩を作りみんなが口ずさむようになっても、何十億円寄越せということはなかった。みんなのものになったという誇りだけで、生み出した人は十分だったんです。だからこれだけ知的所有権の権利主張が盛んになると、知的所有権を、昔のようにみんなのものにしようという動きも出て来るでしょうね。それがいつかはわかりませんが。誰も彼もが知的所有権を主張し始めるとにっちもさっちも行かなくなる。何をするにも課金される。それが言語の世界にまで広がれば、創作も不可能になる。
知的所有権は工業とかソフトウェアの世界で盛んだけど、ネットでは有料課金というヤツがある。一方でYouTubeやウィキペディアとか、無料でコンテンツを提供して、広告などで収益を上げる仕組みもある。ここにも確かに経済システムはあるわけだけど、無料で提供されるコンテンツの方が遙かに強い影響力を持っています。知的所有権と利益の仕組みはいずれ飽和に達して見直しされる時期が来ると思います。ソビエトが崩壊したのは重工業から情報化時代に対応できなかったからですが、今の中国も、インターネット中心の情報化時代によって揺らぐだろうなぁ。だけどインターネットは人類にとってなんなのかという本質的な問いかけはまだない。ラモーナさんはお能の研究者だそうですが、今はルーマニアにいても研究できちゃうでしょう。

ラモーナ そうですね。十年前はYouTubeもなくて、映像を見ること自体難しかったです。でも今は簡単に見られます。文章資料についても主要なものは比較的簡単に読めます。
三浦 知的所有権との絡みで、映像はすぐ消されちゃうことがあるけどね。だけど君が作ったものは、君を育ててきた文化の所有でもあるわけで、君だけの物じゃないんだという思想がもっと出て来れば、社会はまた変わるでしょうね。そういうふうになっていくんじゃないかな。というのも、社会全体でアナーキズムに対する関心が高まっているでしょう。アナーキズムは反体制と言われますが、管理を嫌う思想でもあります。今は管理を嫌う思想が強まっているし、重要になっている。コミュニズムは徹底した管理でしたが、その管理に抗う思想がアナーキズムです。
日本に限らず戦後の知識人は、みんな共産主義に憧れていたでしょう。資本主義より共産主義の方が素晴らしいと思い込んでいた。それは日本でも韓国でもまだ残存しています。だけど本心から共産主義はダメだと考えていないから、総括が十分に行われていない。共産主義の一番ダメなところはプロレタリア平等とか言いながら、一皮剥けばものすごく権威主義なところです。そういった現実制度の弊害を取り除けば、マルクスの思想などは非常に優れた所があるのだから、そういうことを考えれば、共産主義と資本主義の対立とかといった問題ではなく、両者とも行き詰まっているときに次はなんなのか、なにが重要になってくるのかという本質的問題がクローズアップされてくると思う。そのきっかけになるのがアナーキズム思想だと思います。
アナーキズム思想の一番の要点は、管理を嫌うことです。管理は人間のイマジネーション、クリエイティヴィティを奪い抑圧するんです。アナーキズム思想が盛んになって、関連本の出版が盛んになっているのは、管理社会に対して自由であろうという人間の本質的欲求の表れです。この管理を嫌うアナーキズム思想とネットが連動すれば社会は変わる。ネットはアナーキズム思想の最良の部分を実現する力を持っているんです。今はその手前の段階ですね。
■母性という表現基盤■
金魚屋 現代社会の未来に対する興味と同時に、三浦先生は一方で文化の伝来ルートやそのオリジンに対して強い興味をお持ちですね。文化は様々な形で、しかも今ではちょっとその伝来経路や影響関係がわからなくなってしまった形で伝わっています。例えば『源氏物語』の『須磨・明石』の構造は、シェイクスピアの『テンペスト』とそっくりです。元々ユーラシア大陸にあった古い伝承を、遠く離れた日本とイギリスでシェアしていたのかもしれません。
三浦 一つは今おっしゃったような古い伝承が伝わったケースね。もう一つは洪水神話が、人類にとって非常に古くて重要な文化的影響力を持っていたことが考えられます。シェイクスピア作品自体、完全なオリジナルではないでしょう。イタリアの古い物語なんかをどんどん取り入れている。シェイクスピアは古いヨーロッパ伝承を組み合わせて、その最終バージョンを作った人だとも言える。その完成度が高かったから、シェイクスピア作品に敵うものはないとなっている。日本で言うと近松門左衛門がそうだな。いいとこ取りをしています。
ただ元々嵐とか風雨が持っている、根源的な力は無視できません。雨が降ってきた、風が強くなった、嵐がやってきたということが、人間の身体に直に語りかける何かを持っているということです。嵐などが主題になっている神話や物語の起源は、元々人間が身体の中に持っていたものだとも言えます。

『私という現象』(講談社学術文庫)
講談社 1996年10月9日
星 神々や自然現象などに対して、人間が同じようなリアクションを取るから、違う文化圏で似たような物語文化が生まれてくるということでしょうか。
三浦 ある意味で言えばそうですね。その祖型は、僕はお母さんと子どもとの関係にあると思います。人間とお母さんの関係は普遍的です。なぜかというと、おっぱいを飲むからです。人間はおっぱいを飲まないと生きられないんです。少子化にはなりましたが、その分、お母さんが子どもにおっぱいを飲ませる時間、子どもと対峙している時間が長くなっているでしょう。その時間の長さによって、現代人の表情がどんどん洗練されてきているところがあります。
笑いには様々な種類があります。嬉しくて笑っている場合、苦笑いしている場合、ちょっと起こった笑いなどがある。それは言語とほとんど同じです。言語の獲得と表情の獲得は同じ質のものなんです。それを人間に与えるのは父親じゃなくて母親でしょうね。まず母親の微笑みが子どもの微笑みをもたらす。子どもは自分から笑ってるわけじゃない。お母さんが赤ん坊がこんな動作をしたから、可愛いからと笑う。それにつられて赤ん坊も笑うんです。この笑いの往復を繰り返すと子どもは笑うことを習得する。同時に母親も、子どもの笑いを見て笑いを習得している。それを覚えると、泣くとか怒るとかの表情も読み取れるようになります。これは鳥や犬や猫といった動物にまで適用できるようになる。お母さんのある種の表情と同じだから、コイツは今不機嫌なんだなとわかるようになる。ここで起こっているのは概念の獲得ですね。この概念はいろんなところに適用できる。違う言語でも同じ概念が当てはまるんです。三歳児くらいまではこの概念を簡単に習得できるでしょうね。固まっちゃうと最初から習得しなければならなくなる。マザー・ランゲージ以外の言語の習得が大変になるのと同じです。

だけどマザー・ランゲージで習得した概念は、様々に活用できる。外国人だろうと動物だろうと、これは親和的な表情だな、拒絶的だなとわかるようになる。自然現象に対しても、通常は危機とかいう感じで受け取るわけですが、表情として言えば、これは自然が自分に敵対している、危うい顔をしているという解釈になる。この概念によって形作られる感覚を鋭敏に受け取ってゆけば、シェイクスピアの『テンペスト』や『源氏物語』の『須磨・明石』のような作品が生まれてきたりします。
突き詰めてゆけば、お母さんには優しさがあります。子どもに対してあなたが生きていることはとてもいいことだ、それだけでお母さんは嬉しいという肯定がある。この肯定感をどう文学とかの表現に流し込んでゆくのかは大きな問題です。それが文学や音楽が人を感動させる一番重要な要素になっています。だから幼い頃に母親から拒絶された子どもは、その後非常に厳しい人生を歩むことが多い。母子関係が人間にとって決定的な要素であるのは確かです。それは人類史や生命史にも繋がってくるような大問題です。
哺乳類とは、お母さんが子どもにおっぱいを与える動物という意味でしょう。でも対面哺乳、子どもの顔を見ながらおっぱいを与えるのは人間だけですね。犬や猫はそうじゃない。それと同時に対面性交をするのも人間だけです。表情が決定的に重要な要素になっていったのと、対面授乳、対面性交は深く関係しています。また対面して喋るのも人間だけです。人間が対面して喋るのは、性的行為にすごく近い部分がある。会話は極めてセクシーな部分を持つと同時に、極めて厳しい行為でもあるでしょう。無駄口を叩いちゃいけない、知らない人と話してはならないといった会話にまつわる禁則は、性的な禁則と対応関係があります。お母さんから習うことは、そういうことも全部含んでいます。生物学的な関係が、文化的関係にまで反映されているんです。(後編に続く)
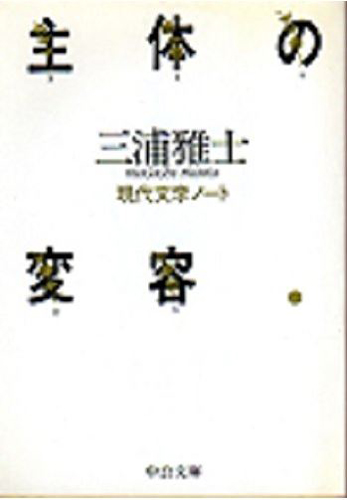
『主体の変容』
中央公論社 1988年2月1日
(2018/12/21)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 金魚屋の本 ■











