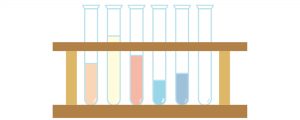 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
第04回 (一)象の鼻
手にしたそれは、まぎれもなく馬の脳を思わせる宝石、すなわち瑪瑙だった。女子であるわたしにわからないはずはない。
「でも、悪いです。こんなものいただいちゃったら」
種山の、つぶらな目がわたしを見つめた。
「いえいえ、わたしの方こそ、申し訳ないと思っているのですよ、こんなものをお渡ししてしまって。少しやりすぎたかななんて思ったりしてるんです」
「やりすぎって?」
「ええ」
ここで少し置かれたためが、意味深だったりするので、わたしはごくんと唾を飲んだ。
「つまりは、これが古代生物に由来するものだからなのです」
そんな! さっきの、白茶けた石が視野の片隅で動いたような錯覚に陥った。
「まさか、あの生きた化石といわれる・・・」
「いいえ、それは違います。ゴキブリではありません」
きっぱりと否定してくれた。これには感謝なのだが、つづけて種山はこんな風に正体を明かしたのだった。
「恐竜なんです」
なんだ、恐竜か。どこが、申し訳ないことなのかわからないという顔をしているわたしを見て、ほんのかすかに種山がほくそ笑んだような気がした。
いまのが、錯覚でありますように。わたしはそう願った。
「これは、そのぉ、まず恐竜が食事をしてですね、その帰結として産み落としたものがですね、珪素などを溶かしこんで、長い年月をかけて変性した結果としてできあがったものでして」
「それってつまり」
「ええ、そうです」
「生きとしいけるものが」
「ええ」
「食べたら出すといわれている」
「ええ」
「お米とは異なる、って書く感じの」
「ええ」
しれっと、うべなう種山。
うぎゃっ。
わたしは、瑪瑙を投げつけていた。種山に。
恐竜に由来する、お米とは異なるものを!
あろうことか、こいつめこのわたしにお米とは異なるものを握らせたのだ!

にんまり微笑んだまま種山は猛速度で飛来するそれを、さらりとキャッチした そして、、何事もなかったかのように宝石箱に戻した。
ぷんとむくれて部屋を出るわたしであった。とはいいながら、その実、わたしはすでに次の部屋を楽しみにしていた。
無念だけど、ちょっと姉貴の、
「きっと気に入るわよっ」
という言葉の意味がわかってきてしまったりしていたのだ。
「あなたならねっ」
という、語尾の「っ」が気になる皮肉も含めてだ。ちょっと悔しいけど。
第三展示室、いやいやもとい、一○三号室のテーマは「アルジャーノンの末裔」です、と種山は語った。
確かにその部屋には小さなケージが置かれてあって、白いネズミが飼われていた。
「これがアルジャーノンですか」
「いえ、ゴンサクです。権力の権に、工作の作と書きます」
ご丁寧にどうも。白いネズミの権作は、ケージの隅で何かを考え込むようにうずくまっていた。ちょっと沈思する哲学者風だったりした。
「もしかして、頭がどんどん良くなっていってるんですか」
「いや」
種山の声には少し陰りがあった。
「その逆です。日に日におかしくなっていってるんですよ」
「どういうことです?」
「ちなみにあなたは、遺伝子操作という言葉をご存じですか?」
唐突な質問。
「ええ、もちろん」
単語としては知ってますよ、中身はともかく。
「クローン羊のドリーちゃんとかでしょ」
「そうですね。じゃあ、君はドリーの母親が誰だったかは知ってますか」
「母親ですか? いえ、そんなのニュースでもやってなかったんじゃないですか。高校の授業とかでも習わなかったと思うし。なんか有名な方なんですか。っていうか、有名な羊さんなんですか?」
「ある意味ではね」
さっきまでとちょっとテンションが違った。なんだか、この部屋に入ってからの種山はちょっとばかしローな感じなのだった。
「どの意味で、ですか」
うん、とちょっとためをおいてから、解説の種山さんが登場した。
「ドリーの母親はトレイシーと言って、ベンチャー企業の製薬会社PPLが所有する動物工場だったんですよ」
「動物工場?」
初耳な単語だった。工場でつなぎを着て働く羊の姿を妄想してみた。
「うん、トレイシーは、乳腺の遺伝子を組み替えられた羊だったんですよ。製薬会社に必要なタンパク質を生産するためにね」
にわかには理解しがたい話だった。
「生きてる動物を薬を作るための工場にしたっていうわけですか」
残念ながらね、とうなずく種山。

「でも、そんな乳腺をもってる動物は一頭しかしかないわけですよね? そこで、同じ遺伝子をもった羊を再生産するために着手されたのが、クローン羊の作成計画だったというわけです。ドリーが最初だったわけだけど、その後にもたくさんのトレイシーが作られた。彼らはいまもなおPPL社で、嚢胞性線維腫症の治療薬を作りだしつづけてるっていうわけなんです」
ガツンと来た。これには、ちょっとやられてしまった。
クローン動物誕生! ってなんだかすごいことになってるぞ的なニュースだったのは、知ってるけど、その裏にそんな、なんていうのか金もうけがらみのひどい話があったなんて初耳だった。
「で、権作の話に戻るわけですが、彼はいまとても苦しんでいるんですよ」
「どうしてですか」
「特定の遺伝子の発現を抑制された結果、いわゆる統合失調症を発症しているからなんです。症状が進行してくるとすぐそばにある食べ物が見つけられなくなったり、広い場所にでるとパニックに陥ったりする。こうしてじっとしているいまだって幻覚や妄想に苦しんでいるのかもしれないんですよ」
怒りがわいた。
「なんてことするんですか、先生は」
「いや、ぼくがやったわけじゃありませんよ。これは商品ですからね。れっきとした企業の所有物で、研究用に販売されているんですよ。ぼくの大学で遺伝子工学やってる友人から借り受けているものなんです」
「実験っていったって」
生まれつき統合失調症を発症するように作られたなんて。いったいなんのために生まれてきたことになるのだろう。
「人間のためってことですか?」
「つづめて言えば、そういうことになります。人間を救うための犠牲ってことですね」
「なんだか、わりきれません」
さらにね、と種山は話を続けた。
「ネズミの受難はこれだけにとどまらないんです。たとえば、ガンを発現する遺伝子を組み込まれたネズミだっているんですよ。そして、これまた商標登録ずみってわけです」
「すみません、先生。この部屋出てもいいですか」
わたしは、アルジャーノンの末裔たちが、いまだに悲劇から抜け出せていなかったことにかなりのショックを受けていた。扉を開く音に反応して、白いネズミがバタバタとケージのなかで暴れる音を聞きながら逃げるようにして部屋を出た。
「悪かったですね」
素直に種山は謝った。
「じゃあ、お口直しに」
そんなわたしの気持ちを知っててなのか、わからずになのか、種山はすでに次の部屋の前に立っていた。
「今度はきれいなものをお見せしますよ」
「ほんとでしょうね」
「ほんとですとも」
扉を開くと、かぐわしい匂いがこぼれ出てきた。
「うわあっ」
思わず目を見張った。
それはテラスにあった。開け放たれた窓から、芳香が漏れてきていたのだ。赤紫のきれいな花がテラス一面に咲き誇っていた。

「きれいな花ですね」
「でしょ」
種山が、ベッドの横を通りぬけてテラスへと向かった。
「近くに来て見てみてくださいよ」
「はあ」
なぜ、近くに来てというのか、わたしには計りかねたけど、まあこういうものならいいかと思って近づいた。近づいても、ちゃんときれいな花だった。塔のような感じで、小さな花が下から上までびっしりと咲いている。
「どうです」
尋ねる種山。
「ええ、きれいですよね」
「よくご覧なさい」
「ご覧になってますよ」
「もっとよくご覧なさいって。見ようとしてないものがあるんじゃないですか」
「見ようとしていないもの?」
何を言っているんだこの人は? しげしげと見ると、プランターの土の上に黄色く枯れた背の高い植物が横たわっていた。先っぽに、毛が伸びだした穂のようなものがある。
「もしかしてトウモロコシですか? 枯れて地面に倒れてるのって」
「そうなんです」
もじゃもじゃ頭が揺れた。
「このプランターにはまずトウモロコシを植えたんですよ。それがある程度まで育ったところで、この花の種をまいたところ」
「こうなったっていうんですか?」
「ええ、そうです。まず名前から申しますと、この植物はウィッチウィードとよばれているんですよ」
「ウィッチウィード? ってことは『腕時計の草』?」
「それはウォッチでしょ。これはウィッチつまり魔女です。つまり、魔女の草」
「魔女の草?」
かわいらしい見かけのくせに、ずいぶんとおどろおどろしい名前だこと。
「ええ、そうです。なにしろ、これはアフリカやアジアでサトウキビやトウモロコシや小麦畑を全滅させてきた歴戦の猛者ですからね。そして、一九五〇年代以降は、おそらく輸入されたトウモロコシにくっついてだと思われるんですが、アメリカにも進出した。ブリティッシュ・インヴェイジョンならぬ、アフリカン・インヴェイジョンってわけです」
「どういう仕組みなんですか?」
「たいそうよくできてるんですよ、これが」
ここで、嬉しげな表情になるのが種山ならではである。
「まず、種の数が多い。一つの花がおよそ五万にも及ぶ小さな種を作り出すんです。畑一面のウィッチウィードとなると、その数は莫大なものになります」
「子だくさんなんですね。マンボウみたい」
「しかも、小さいから見つけて拾うというわけにもいかないわけです」
「確かに、気が遠くなりますね」
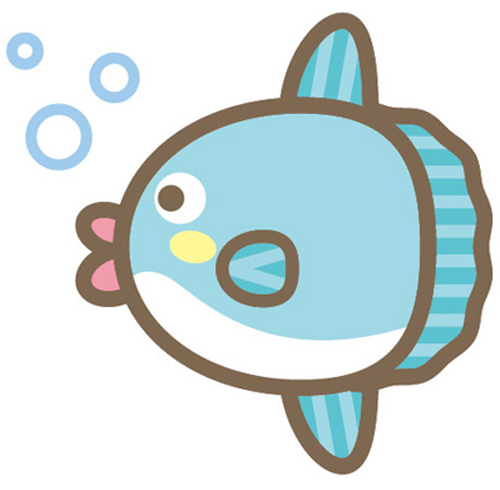
「しかも、辛抱強いんです」
「って、種がですか?」
「ええ、種がです。発芽に適した条件が整うまで、この種はじっと土の中で休眠して待っていられるんです。最高で一〇年も我慢した種があると聞いています」
「じっと、十年間待ち続けるわけですか」
「できますか?」
「もちろん、できません」
「でしょうね。ぼくもです。で、そうやって待っているうちに、たとえばトウモロコシが畑に植えられたとする」
「はい、そうしましょう。このプランターみたいにですね」
「すると、この種がはっと目覚めて、吸器と呼ばれるひげ根のようなものを出して、トウモロコシの根っこに入り込むわけです。魔女草はりっぱな寄生植物なんですよ」
りっぱな、っていう形容はどうかなって思うけど。
「でまあ、土の中で四週間過ごして、いよいよこうして地上に姿を現し、あでやかな花を咲かせる。と、まあそういうわけです。多くの場合、農家の人たちはこの時点でようやく、寄生に気が付くわけですが」
「時すでに遅しというわけですね」
「ええ、そうです。一面のトウモロコシ・プランテーションが、赤紫に変わった眺めは壮観ですよ。あまりにも美しく、そして同時にあまりにも甚大な被害を意味しているわけですからね」
「全滅ってわけか。フィールド・オブ・ドリームスならぬ、フィールド・オブ・デスってわけですね」
確かになかなかの猛者である。
「そんな感じで寄主であるトウモロコシを生かさぬように殺さぬように保ちながら、この美しい娘はあなたのような無邪気な鑑賞者からの賞賛を独り占めするという、まあそういう流れなわけです」
「先生」
「はい、なんでしょうか」
種山が、笑顔で振りむいた。
「もしかして、わたしのことを馬鹿にしてますか?」
「えっ。どうしてです?」
「だって、こんなのちっとも心やすらがないじゃないですか。どこがお口直しなんです」
「いや、この見事な生存戦略に、あなたもきっと感銘を」
「残念ながら、どちらかというと」
あれ、どっちだろう。とここではたと言葉に詰まってしまった。
確かにわたしは驚いていたからだ。ひどい話だとは思うけど、それなりに刺激的ではあった。ここに来てからの数十分で、わたしの脳は、そして感受性みたいなものは、これまでにないほど目を覚まして、なんだかわからないものを理解しようとあがき始めていた。
「どっちかっていうと、なんですか?」
急に押し黙ってしまったわたしの顔を、種山が興味津々で覗き込んできた。
「あ、そうだ」
わたしは、突然自分の使命を思い出した。思い出したのだが、その思い出し方があまりに突然であったために、そのことと目の前にあるものへの驚きとがごっちゃになってしまった。結果、自分でもわけのわからないことを種山に問うていた。
「象はこの花を食べるでしょうか」
「えっ、象? どうだろうな」
口にしてしまってからわたしは慌てたが、種山の当惑顔が面白かったのでそのまま放置することにした。
「そりゃ、通り道にあれば食べるかもしれませんけど、それがどうかしたんですか」
「すみません、先生。大事なことを忘れてました」
「大事なこと? それは」
ようやく合点がいったように種山がうなずいた。
「象と関係があるわけですね」
「ええ、それこそ、わたしが今日お邪魔した理由なんです」
(第04回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



