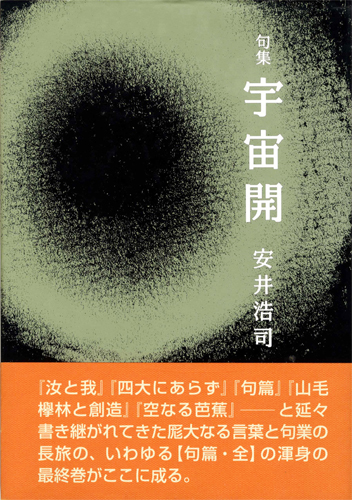
安井浩司新句集『烏律律』(うりつりつ)
発行 平成二十九年(二〇一七年)六月五日
定価 三千九百円(税抜)
発行所 沖積舎
『えくとぷらすま』は、加藤郁乎の難解、多彩なエッセンスの混入している句集であろう。(この辺から、いち早く高柳重信が郁乎の〈作品〉に組みしなくなったのは、当然というべきかもしれない。それは俳句の認識論においてきわめて重要なことであり、その両者の裂けに、俳句の本質にかかわる大切な問題がたっぷり入っていたということだ)。
(安井浩司「放物線の行方」)
安井さんの加藤郁乎論「放物線の行方」は、戦後に書かれた最も重要な俳句評論の一つである。俳句が生きた芸術として常に変化してゆく文学なら、戦後で最も重要な俳句評論だと言ってもいい。安井さんが書いているように、第二句集『えくとぷらすま』によって、郁乎と重信の間に「裂け」が生じたのは間違いない。それは文学的な裂け目である。
重信は基本的に新興俳句の継承者である。新興俳句は相対化して言えば、俳人が明治維新の近代以降で、初めて〝作家の自我意識表現〟を正面から取り入れた文学運動である。新興俳句弾圧事件が起こったのは、それまで花鳥風月に終始して来た俳人たちが、作品で社会思想を表現し始めたからであるのは言うまでもない。
この新興俳句的〝自我意識文学〟の流れは、戦後になって二つの新たな俳句運動を生んだ。一つは金子兜太に代表される社会性俳句である。もう一つは重信の前衛俳句運動だ。両者はコインの表裏だと言っていい。社会性俳句の方がストレートに新興俳句を継いだと言えるが、重信は芸術至上主義者として、多行俳句という新たな俳句形式の創出によって強い自我意識を表現しようとした。以後、重信的前衛俳句に共感した俳人たちは、それぞれに異なる独自の俳句形式を創出してゆくことになる。
ただこれも相対化して捉えれば、兜太の社会性俳句と重信の前衛俳句は、維新以降の日本の近・現代文学(主に自由詩や小説)がすでにその表現基盤としていた自我意識を、従来の俳句伝統の上にあからさまに付加した運動だったと言える。しかし郁乎の『えくとぷらすま』はその表現の審級(質)がまったく違っていた。
「落丁一騎対岸の草の葉」で始まる『えくとぷらすま』は、作家・郁乎が〝これは俳句である〟と宣言しなければすでに俳句ではない。『えくとぷらすま』は、ほぼ完全な作家独自の表現であるという意味で自我意識的俳句文学の極北である。しかしもっと重要なのは郁乎が重信門の俊英であり、『えくとぷらすま』で重信的自我意識俳句の限界を突破しようとしたことにある。『えくとぷらすま』は自我意識的俳句文学の極北だが、その作品生成システムは非-自我意識的である。
安井さんは処女句集『青年経』の冒頭に「渚で鳴る巻貝有機質は死して」を置いた。俳句文学において〝形式〟は絶対だということだ。中身(有機質)はなくても、俳句形式に風(言葉)を吹き込めばそれは鳴る(俳句ができあがる)。そしてこの俳句形式は調和的完結世界として、ぼんやりと、だが確実にその外形を認識できるが、実際の姿は可変的である。五七五に季語定型がすべてではない。山頭火や放哉のような無季無韻でも、重信の新たな俳句形式によっても俳句は簡単に成立する。俳句形式は俳人個々の様々な試みをあっさり飲み込んで俳句を成立させてしまう。俳句文学では俳句形式が常にその表現主体なのである。
つまり俳句文学はずっと、俳句形式に作家の自我意識が交差することで作品を生み出してきた。俳句形式が〝主〟で作家の自我意識が〝従〟なのである。短歌が百人一首など作家中心に成立し得るのに対し、俳句が元禄俳句、天明俳句と集団的営為としてまとめられる理由がそこにある。重信は強い作家の自我意識を〝主〟と措定し、それによって俳句を〝従〟としてねじ伏せようとした。しかし安井さんが指摘したようにそれは必敗の試みだった。ただ重信が「俳句史の一本道に繋がる本格的俳人」(「放物線の行方」)だったのは確かである。
しかし、それ以上に俳句史を震撼させたことは、『えくとぷらすま』が、とりあえず句と呼ばれる〈作品〉化をもって、俳句形式の磁場としての共同体、いわゆる俳句の内と外が限定しあうことで成り立ってきた規範としての共同体母型を突き破ったことであるだろう。すなわち、共同体における〈意識〉の装置としてではなく、限りなく他者へと浸透していく〈霊〉の装置としての俳句である。(中略)加藤郁乎において、はじめて「不在」の中に〈他人〉=〈他者〉性を獲得したと言ってよい。また俳句は、そこに全き〈他者〉を所有しうる形式として、自らの虚構性において自覚したと言ってよいかもしれぬ。
(同)
『えくとぷらすま』は「霊的昇華現象」というオカルティズムの用語である。「加藤郁乎において、はじめて「不在」の中に〈他人〉=〈他者〉性を獲得したと言ってよい」「また俳句は、そこに全き〈他者〉を所有しうる形式として、自らの虚構性において自覚した」という安井さんの言葉は難解だが、郁乎が〝俳句形式に作家の自我意識を交差させて俳句を生む〟という、俳句発生以来の作品生成原理(共同体母型)を打ち破ろうとした、初めての俳人だと論じていると理解してよい。
郁乎は「えくとぷらすま=霊的昇華現象」を〝別自我〟とも呼んでいる。別自我とは強い自我意識を剥ぎ取られた〝空虚な自我〟のことである。安井さんの言葉で言えば「私性の否定として(中略)「不在」そのものが主を演じる」ということになる。この設定が重要なのは、俳句形式と作家自我意識の相互依存関係を暴くことができることにある。俳句形式は存在としては認識できるが、その姿形は不定形である。俳句が有季定型、無季無韻、多行といった固定的形式として認知されるためには、作家の強い自我意識が必要なのだ。作家の自我意識が消え去れば俳句形式はその外形を失うことになる。
比喩的な言い方になるが、郁乎は俳句形式に〝別自我=空虚な自我〟を対峙させて、鏡のように俳句形式を写し取ろうとした。それがどれほど無残な姿なのかは句集『えくとぷらすま』を読めばはっきりわかる。『えくとぷらすま』で表現されているのは俳句形式の内蔵のようなものだ。またそれゆえ『えくとぷらすま』の作品群は郁乎のものであって郁乎のものではない。俳句形式の側から言えば、その〝虚構性〟が露わになったと言うことができる。形式(外形)はあっても内実は希薄だ。ガラクタが詰まっている。内実は俳人の自我意識がなければ充填されない。
もちろん郁乎の試みは、ほかの俳人が試みれは別の言語成果を生むはずである。しかしそんな人は現れないだろう。郁乎の『えくとぷらすま』は、俳句文学を知り尽くした俳人による文字通りの〝秘儀〟だからである。またこの秘儀の意味を正確に理解していたのは、結果として安井さんだけだったと言える。
郁乎は重信的自我意識俳句の限界を敏感に察知して、別自我による俳句創作を模索したわけだが、そこで見た無残な光景は、かえって俳句形式の重要性(俳句形式と作家自我意識の相互依存関係)を強く意識させることになった。『えくとぷらすま』以降、郁乎がウルトラ保守派として江戸俳句に回帰していったのは、転向ではなく一つの必然だった。しかし安井さんはポスト・えくとぷらすまの道を選んだ。それはポスト・高柳重信(前衛俳句)ということでもある。
俳句形式は自らが書くものではなく、けっきょくは書かれるものだ。(中略)俳句形式が書かれることで成り立つかぎり、文体化はひとつの必然であるだろう。それでもなお形式の添いとおぼしき文体化に抗いつつ、それを消去しようとすれば(中略)俳句形式を私的にとらえ、そこに私自身を認めない場面、という劇場的なものが、いわゆる念願の俳句形式の虚構が完璧に成立すれば、そこをもって俳句生成史は終熄するはずである。
(同)
安井さんが論じているように、俳句文学において俳句形式は〝主体〟だが、それは作家(の自我意識)によって「書かれるもの」である。両者は相互依存的なのだ。ただ俳句形式は存在し、かつ不定形である。そのため俳句形式は作家によって書かれることで一つの「文体化」、具体的に言えば俳人個々の〝俳風〟を生み出す。新興俳句はもちろん、重信や郁乎も結局はこの道筋をたどった。安井さんは郁乎の『えくとぷらすま』の試行を踏まえて、この俳句文学の絶対的作品生成原理を変えようとした。
安井さんの方法は「俳句形式を私的にとらえ、そこに私自身を認めない場面」という言葉で表現されている。俳句形式に作家自我意識を交差させれば、相変わらず俳句形式が主体の「俳句生成史」が続くことになる。それでは新興俳句から兜太・重信に至る、自我意識俳句の試みがすべて無駄になる。しかし郁乎の方法では俳句形式が空虚な「虚構」だと明らかにできても、そこから新たな「俳句生成」システムを生み出すことができない。俳句形式を解体・崩壊に追い込むことなく、あくまで作家が主体の俳句文学を成立させることが安井さんのアポリアである。(下編に続く)
鶴山裕司
■ 安井浩司さんの本 ■
■ 鶴山裕司さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■







