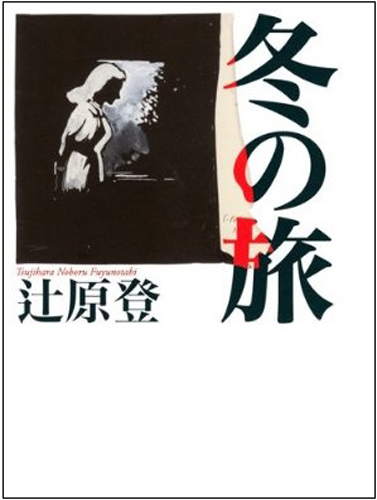長いあいだ私を呪縛してきた「よい文学」の定義がある。
──ほんとうの文学は、人間というものがいかにおそろしい宿命に満ちたものであるかを、何ら歯に衣着せずにズバズバと見せてくれる。(略)文学はよいものであればあるほど人間は救われないということを丹念にしつこく教えてくれるのである。そして、もしその中に人生の目標を求めようとすれば、もう一つ先には宗教があるに違いないのに、その宗教の領域まで橋渡ししてくれないで、一番おそろしい崖っぷちへ連れていってくれて、そこで置きざりにしてくれるのが「よい文学」である。(三島由紀夫『若きサムライのために』)
定義を知ったのが高校二年の春、二十代はとことん信奉しきり、三十代で疑いが兆し、四十代で抜け出した。脱け出さなければ、文芸の受容幅が極端に狭くなり、現実の文芸世界との共存が困難になるからだ。今は読者も書き手も、三島とは正反対に、希望を語るのに忙しい。希望はわかりやすければわかりやすいほど好まれる。
ところが、辻原登の『冬の旅』に出遭って、忘れかけていたものへ引きずりもどされた。『冬の旅』はまがうことなく三島の定義に合致する、「よい文学」だったからだ。
主人公・緒方隆雄は悪漢ではない。とりたてて美質もなければ、欠点もない。ただひとつ、著者はそうと明記はしないが、繰り返し現われる「被害のパターン」のようなものがあった。
緒方は姫路網干の高校から専門学校へすすみ、たまたま勤めた中華料理チェーン「包子 マダム楊」で店長からあらぬ疑惑をかけられ、辞表を書かされる。次に勤めた「さにわ真明教」のPR誌編集部時代には、妻が失踪してローンのみ残り、経費の水増し請求に手を出して失職する。次に住み込み働きをしたおでん屋「ふなき」では、店によかれと思いついたことを実行したのが仇となり、火事に見舞われて仕事と棲家を失う。門真の携帯電話部品工場に短期採用されると、作業中に感電火傷して入院。布施のクニーリング工場ではカンボジア人留学生を妊娠させて解雇。治験のバイトで食いつなぐも、薬の副作用で昏倒。釜ヶ崎の花売りになれば、やくざにからまれて廃業。天王寺公園南門の柵ぞいにたむろするホームレスの一員に加わると、強盗殺人の共犯に巻き込まれ、懲役八年の実刑。滋賀刑務所から出ると、ドヤ街でホームレスに襲われて所持金を奪われる。緒方は何かに引きずられるようにして天王寺から紀勢本線に乗り、鳳・日根野・和歌山・箕島、そして切目で無賃乗車がばれて飛び降り、夜道を駆けて紛れ込んだ家の、仏のように柔和な老夫婦を包丁で刺し殺す……。
意志的な選択というよりは偶然の複合によってそうせざるをえないところへ押し流され、最後は死刑判決しか待つもののない袋小路に立たされる。袋小路で彼は自問する。意志的な選択でこうなったわけではないが、とはいえ、別様に自分は生きることができたであろうか? 答えはすぐに出る。否、やはり、このようにしか生きられない。この酷い認識が骨髄に徹したとき、彼はようやく何かから自由になったと感じる。最後から二行目はこうである。
──緒方は、生きる気力が身内から湧いてくるのを覚えた。
この一文に触れて『金閣寺』を想起する読者は少なくないはずだ。主人公の溝口は、父から金閣寺がいかに美しいか、聞かされて育つ。美の観念は自己増殖し、ついには彼の現実生活を阻害する。溝口は追いつめられて金閣寺を焼いて死のうと決意するが、いざ焼いてしまうと、心に変化が生じる。最後の有名な一文は、
──一ト仕事を終へて一服してゐる人がよくさう思ふやうに、生きようと私は思つた。
未来には刑務所の房しかない。しかし、溝口を憐れむのは、おかど違いというものだ。溝口は刑務所の中に究極の自由を発見する。それは世間の希望の範疇には到底収まらないが、まぎれもなく希望だった。
『金閣寺』は美の形而上学的議論によって溝口を崖っぷちへ追い込むが、まあ、何と無理の多い小説だろう。無理を糊塗するために、過剰に華麗なレトリックが必要になった。しかし、『冬の旅』はことごとしい形而上学議論など一切なく、わかりやすく平明な文章と個別具体的事実の積み上げによって、無理なく緒方を崖っぷちへ追い込んでいく。ただし、どんづまりで形而下と形而上とが接触発火して煙をあげる。緒方本人はまったく気づいていないが、個別具体に徹して今ここに生きるしかないという形で死を受け容れた瞬間、個別具体を超える何ものかが彼に忍び寄る。私はその足音をはっきり聴いた。その何ものかに対して希望という語を当てるのは、ほとんど冒瀆であろう。
三輪太郎
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■