 宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
宋(ソン)美雨(メイユー)は民主派雑誌を刊行する両親に育てられた。祖国の民主化に貢献するため民主派のサラブレッドとして日本に留学するはずだった。しかし母親は美雨を空港ではなく高い壁に囲まれた学校に連れていった。そこには美雨と同じ顔をしたクローン少女たちがいた。両親は当局のスパイだったのか、クローンスクールを運営する当局の目的は何か。人間の個性と自由を問いかける問題作!
by 金魚屋編集部
エピローグ
異例中の異例だった。
朝のコーヒーが効くまえに呼び出されることなど、これまでは一度もなかった。宋徳(ソンデェァ)は、コンソールボックスに入れてあったサンドウィッチを掴み、信号待ちのタイミングで頬張った。
気持ちが急いた。午後一番で外務省の定例会見がおこなわれる。それまでに長年の友人である男と会っておくつもりでいた。彼は通信社の北京特派員として活動している日本人で、表向きは大手のメディアしか相手にしない。
宋が編集長をしている『常言』は、官製メディアとは対極の存在だ。普通なら会おうと思っても見向きもされない。先方の事務所で翻訳や通訳として働く現地人スタッフは、すべて外交人員服務公司から派遣され、外国人記者の監視と報告が義務づけられているのだ。公然と給与をもらうスパイである。宋と連絡を取り合っていることが知れれば、十年選手の特派員という貴重な立場を棒に振る。
ただでさえスケジュール調整は難しく、連絡手段も限られるため、密会できるチャンスは極めて少なかった。ひと月以上もまえから予定を組んだ。昼食時の混雑に紛れ、市中にある大衆飯店で会おうということになっていた。その同じ時間帯に定例会見がねじこまれたのである。
特派員なら職務として会見場に行かなければならない。そうかといって希少な機会を逃すのも痛かった。どうにかして今日中にスケジュールをアレンジしようと考えたが、自宅にある固定電話はもちろん、携帯電話も盗聴の対象になっている。インターネットを使った通信も常に監視の目が向けられてきた。すべてのやり取りがバレるわけではないものの、ネット上の「会話」に頼るのはギャンブルが過ぎる。平素はじっくり監視の有無を確認するが、今回はあまりに時間が足りなかった。そこで彼は驚くべき手段に出た。宋の自宅アパートにやってきて、郵便受けに封書を入れておいたのだ。
自宅近辺が張りこまれていたのは美雨を入校させるまで、だった。約束どおりに学校へ届けてからは、盗聴だけを気にすればよかった。張りこみから解放されたことで、妻の雨欣(ユーシン)も気兼ねなく外出できるようになっている。そんな話をしたことを特派員は記憶していたのだろう。もちろん、美雨は日本に留学したことになっているが。
封書を見つけたのは、宋が朝の散歩に出る直前のことだ。特派員の体温が残っているかのように感じられた。そこには密会場所と時間の変更について書かれてあった。
彼のほうが定例会見の変更を早く知るのは必然だ。日本のメディアは、各国の通信社から多くのニュースを買っている。大枚をはたき、情報を漁ってきたのだ。一方で『常言』は、カウンターイデオロギーの記事で成り立つ雑誌だ。外国人記者との質疑応答が伝わってきた段階で、省のスポークスマンが発信する教科書的な言葉の裏に潜む真意を分析していく。そこには、一読するだけでは探知し切れない意味深さがこめられている。知らず知らずのうちに国民を取りこむという壮大な企てが実践されていた。
七時。朝市から帰る人の群れがこちらへ向かってくる。そのあまりの多さにたじろぎ、宋は、トレーラーやトラックが何十台と並べられているパーキングを抜けることにした。猿のように笑っていた運転手たちの視線が、部外者である宋を追いかけてくる。会話が途切れるたびに問い質されるのではないかと冷や冷やさせられた。約束の時間を五分ほど過ぎ、なんとかテントが居並ぶ場所まで出ることができた。みな片付けで忙しい。確かにここなら、と思えてくる。
宋は海産物を扱う店のそばで待った。たらいや木箱を洗う女が引きも切らずにやってくる。生臭い汚水は足元に用意された排水溝へと流れこむ。転落防止用の金網には鱗がびっしりと貼りついていた。いつもなら朝陽を受けて煌めくのだろう。今日は雨曇りだ。店仕舞いの手を急がせているのも、驟雨の気配が漂っていたからだ。そんなことを考えているうちに、アスファルトについた小さなシミが重なり、広がりはじめた。
一部の地域では雷雨になるという予報も出ていた。見上げると、西の空が瞬いている。若い女が短い悲鳴を漏らした刹那、空を切り裂かんばかりの轟音が響いた。巨大な蓋で押さえつけられたように、男も女も頭を低くしはじめた。ここはだだっ広い。目立つのは、車のほかは彼らだけだ。早く、早く、と声をかけ合いながら、彼らは二倍速の動きで片付けを終えてしまった。
宋は、車に避難する彼らのあとについていった。来た道をもどるしかなかった。あのまま突っ立っていれば目立つし、特派員の姿はどこにもなかったからだ。道中、トラブルが発生したか。あるいは、予想よりも早く天気が崩れはじめると感じ、ここに近づくことを止めたか。いずれにせよツイていない。外務省の会見が変更されたことに加えて、懸命に調整した密会さえ実現できなかった。

上着の内ポケットが振動した。連絡手段として携帯電話を使うことは自重すべきと確認し合ってきたというのに。宋はパーキングの外へ出た。大泣きしそうな空を見上げながら幹線道路まで走った。雨宿りする場所を探している哀れな男を演じつつ、小路に停められた車を検めた。どれも無人。不審な車両は見当たらない。往来に変わりはなく、目が合った通行人はみな傘を差し、ずぶ濡れ確実の男に優越感と同情心を向けている。バイブレーションは途切れたが、間を置かずにまたかかってきた。三度も繰り返された。ようやく見つけたコンビニの軒下で、宋は、濡れそぼった肩をハンカチで拭いながら携帯電話を掴み出した。ディスプレイに明滅していたのは特派員のカバーネームではなかった。妻だった。
未明の散歩は日課である。出かけるときは、いつも妻と一緒だ。体をほぐしながら一日の予定を確認し、この国の未来について意見をぶつけ合うのが常だった。そうやって何年も関係を維持してきた。
毎晩、酒が入ると議論は沸点に達したものだ。同じ民主派の旗を掲げていても、個人のレベルでは温度差があるからだ。熱意の高低ではない。民主的な社会を実現するためには何を先に解決しなければならないか。その着眼点に相違があるということだ。望遠鏡と顕微鏡。優先して使う道具が違えば必然的にそうなる。演繹法と帰納法。好んで用いる論法が異なれば目指す理想が同じでも火花を散らすことになる。夜のうちに解決できれば問題ないし、熱した感情が熟した愛情に転じる効用もあった。が、そんなことは月に何度もない。ほとんどは持ち越しになる。ふたりで朝の散歩に出かけるようになったのは、出勤前に妥協点を見つけるための苦肉の策だった。
今朝は宋のほうから散歩を拒んだ。ひどい二日酔いに襲われたときでも欠かさなかったというのに。昨夜の議論はこれまでにないほど激しいものだったのに。
妻としてはどうしても感情を均しておく必要があった。当然だ。言葉を生業としている者としての務めだった。使い方を間違えば、相手を貶め、生涯癒えないような傷さえ負わせるのだ。感情を鎮めておくことは、優れた議論することよりも重要である。
散歩を拒む理由を訊かれ、宋は上手く返せなかった。出かける間際に封書を見つけてしまい、自身の動揺を鎮めるだけで精一杯だったのだ。相手が何者なのか、どうして日課をキャンセルしてまで会わなければならないか、妻に告げれば済んだはずだ。しかし、できなかった。日本人特派員は、妻が有していない情報提供者の一角だ。夫と妻、編集者と部下という役回りを保つには欠かせないメンツだった。
肩透かしを食らった妻は宋に苛立ちをぶつけた。気まずい空気は濁りに濁り、居た堪れないほどの密度になった。宋は窒息寸前の金魚のように家から飛び出していた。
少しは冷静さを取りもどしたのだろう。このままの精神状態では仕事場へ向かえないとあらためて思い直した。仕事先では嫌でも顔を合わせなければならないのだから。きちんとした決着をつけたいはずだ。
雷鳴を待ってからコールした。理性と理論に基づいて妥協点を見出す。そんなときの妻の声は低く変わった。
しかし。
どの道を選んで帰ったのか思い出せない。気がつけばドアのまえで汗を滴らせていた。妻の気丈さは出版社の誰もが認める。『常言』が差し止められたときも、横暴な監査が乱入してきたときも、夜道で襲われかけたときでさえ毅然としていた。理念に殉じるなら、という開き直った思いがあったからだ。その彼女が声を震わせていたのだ。最悪の事態が起こったとしか考えられなかった。電話口で詳しい話をしなかったことがその証拠だ。彼女のことである。誰かに脅されていたとしても、夫の身を案じて叫んだはずだ。
それなのに。
宋はドアに耳を押し当てた。物音ひとつ聞こえない。妻が置かれた現状を物語っていた。無抵抗を余儀なくされている。足掻いても無意味だと思い知らされたのだ。
玄関には見覚えのない靴があった。紐を弛めたものだが、女性モノには違いない。汚れが目立っていて、踵を潰した跡も気になる。
訪問客は日常に溶けこんでいる人物だ。雨のなか、宋を哀れんでいた通行人とは違い、存在そのものを消すことにすべてを捧げているような女なのだ。呼び鈴を鳴らされ、妻は警戒したはずだ。こんな早朝から訪ねてくるのは出版社のスタッフしかいないはずなのに、ドアスコープの向こうに見えたのは野暮ったい服装をした女だった。それでもドアを開けてしまったのは、警戒の鉄柵を簡単に破られてしまったからだろう。相手にはそうできるだけの腕力があったということだ。国権という剛腕が。
居間に入った。ガラステーブルには豪勢な菓子が並べられてあった。少々の客人ならば、あれほど華やかに盛りつけることはない。万にひとつでも、というときのために蓄えておいた品々なのだ。たとえば『常言』への投資を望む善良なスポンサーが現れたときなどに。それをすべて費やしているではないか。
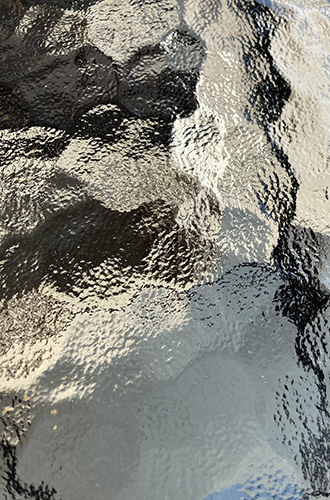
ソファのカバーも取り換えられていた。座っていたのは、冴えない服装をした若い女だ。着崩したというより、生活のレベルがそうなのだからと諦めているような姿に見えた。
妖術だろう。この国には居民委員会という組織が現存する。市民の相互扶助に尽力する一方、公安局の下請けも担った。反党・反政府的な活動を監視している。委員会のリーダーは退職した党幹部だが、市井の景色に馴染むような容姿を心掛けていると聞いていた。
一見しただけでは一般人そのものだが、女の存在感のなさは際立っていた。どこを切り取っても特権のにおいがしないのだ。存在を隠すことに関しては、随一の芸当を身に着けている。誰に訊いても目撃情報が得られないような空気感だった。
妻がようやく宋に気づいた。零しかけた涙を指の腹で拭っている。
ついに。そんな思いが胸をかき乱した。宋は妻の肩を包み、椅子に座らせてやった。こんなにも小さいと感じたことはなかった。
「お嬢さんが禁を破りました」
女が平たい表情のまま切り出した。
「おふたりの処分につきましては、後刻、担当者から具体的な指示が入ります。今日、わたくしが伺ったのは、簡単なアンケートに答えていただくためです」
女が質問しはじめた。思いついた言葉で端的に答えてほしいと付け加えて。宋は従った。閃きに頼りながら、しかし首を傾げたくなった。些細な項目ばかりなのだ。波打つ感情を鎮めるためのクッションなのだろう。本題は先に待っている。
しかし。
「以上です。ご苦労様でした」
拍子抜けしたのだろう。妻の涙も止まってしまった。
女は、テーブルに用意された菓子の包み紙を外した。金箔で覆われたチョコレートを口に放ると、白い頬を綻ばせた。夫婦の感情を覗き見ることに、この上ない爽快感を覚えている。それを巧みに隠しながら、ふたつ目の菓子を飲みこんだ。
「参考までに、ですが」
来た。
妻が宋の手を握った。凍傷寸前のように血の気を感じない。
「お嬢さんを育てようとした理由は」
焼き菓子を齧りながらそう言った。何気ないトーンでカモフラージュさせていたが、クローン計画の根幹をなす質問に繋がるはずだ。
「十八になれば手放すことがわかっていて、どうして」
嘘は効かない。通じない。自分たちが受け入れ先の候補に挙げられたとき、すでに素っ裸にさせられていたと考えていい。そうでなければ、あれだけの計画を反体制派市民に漏らすはずもないのだ。
「受け入れなければ無期限で出版を差し止めると言われていたことは確かです」
宋は女の口元を見詰めながら答えた。四つ目の菓子が手元から消えている。
「それ以上に、彼女を母親にしてやりたかった」
妻の手を握り返した。体温がもどるようにと擦りもした。
「不妊治療のつらさは当人にしかわからない。わたしは理解者のつもりですが、それでも」
妻が首を振った。充分に理解してくれている。揺れる瞳がそう伝えていた。
「治療を止めることにしたのは、年齢的に限界だと感じたからです。担当医から暗に告げられていましたし。正直なところ、安堵しました。これ以上、彼女の苦しむ顔を見なくて済むと。でも、それ自体がわたしの我儘だということも気づいていました」
妻が「え」という顔をした。
「苦しまなくて済むのは、わたし自身です。そうでしょう? 彼女が味わわされた挫折感はこれからも続くのですから」
「同志を裏切った気持ちにはなりませんでしたか」
「子供のことは夫婦の問題です。彼らに助けを求めたところで、我が子を授かるわけでもないでしょう?」
「十八で引き離される。そんな子供の気持ちについてはどう感じていますか」
「すべて親のエゴです。申し訳ない気持ちでいっぱいです。なんとかして卒業してもらいたいと思っていました。決して能力のない子ではありませんでしたから」
女は黙って聞いていた。
「あの子には感謝しています。だから、親の責務について説明があったときも納得できました」
妻が顔を上げて言った。宋が言おうとしていたことだった。
「なんでもします、あの子のためなら」
妻が怯えていたのは、美雨のこれからのことを案じていたからだ。自分たちは八つ裂きにされても構わない。美雨が助かればそれでよかった。
「あの子は、娘は」
「生きてはいます」
女が口を動かしながら平然と答えた。宋は、それ以上の質問ができなくなるほどのショックを受けた。神経がどうにかなりそうだった。
「では、指示を待つように」
女は腰を上げ、立てかけてあった松葉杖を手にした。
かろうじて玄関まで見送りに出た夫婦に、女はメモを渡した。
「外出しなければならない場合は、ここに連絡すること。許可を得てから出かけるように」
女が去ったあとも、宋たちはしばらく玄関から動けなかった。
生きてはいる。妻の頭のなかにも同じ言葉が残響しているに違いない。
「無事、という意味だよ」
宋は言い聞かせながら妻の腰に手を回した。卒倒しないのが不思議なくらいだ。女の余韻が消えたときこそが本当に危ういと思った。
「何も口にしていないんだろ」
居間にはまだ菓子を並べてある。見るのもつらいだろうが、緊張を持続させるには必要な毒でもあった。一番カロリーが高そうな菓子を摘み、妻に渡した。無意味だと彼女は拒んだ。確かにそうかもしれない。体力と気力を回復したところで、処分のときが迫っているのだ。
足元にメモが落っこちた。拾い上げ、宋は、ますます空しさを感じた。妻の様子では、ここから一歩も動けそうにもない。外出許可など必要ないのだ。捨てようとしたが、手が震えていたせいで狙いが外れた。テーブルの角にあたり、メモが口を開いた。
目が釘づけになった。そこに記された文字列を理解するまで、相応の時間がかかった。
『おふたりの気持ちは必ず伝えます』
路面に膜をつくるほどの水煙だ。雷雨は弱まる気配がなかった。視界が悪いせいか、方々から車のクラクションが聞こえてくる。古い街並みだ。歩道は狭く、みな傘をぶつけ合いながら歩いている。
松葉杖を使って歩くのは不慣れだったが、しっかり固定されたおかげで痛みは半減している。応急処置の延長とはいえ、さすがは医者の手際だと感心させられた。
1―30は、アパートの軒下からタクシーを拾った。乗りこんですぐ、通りの反対側に現れた中年の男女が気になった。先を急ぐ者たちとはあきらかに違う。目的地がそこにあるからだ。定まった視線は、宋夫妻が住むアパートへと向けられていた。

残された時間は少ない。迷いや躊躇いは命取りになるということでもある。このままじっとしていても死に神のほうから近づいてくるのだから。
だからこそ曾の言葉に興味が湧いたのかもしれない。これまでどうしても理解不能だったことだ。いまなら知っておきたいと思えた。
培養組のそばにいたのはいつでも教師たちで、知識や技術や戒めを教えるに過ぎなかった。外組の生徒が親のことを口にしても、それがどういう意味なのかわからなかった。親の心を肌で感じたことのない自分たちには、理解する糸口さえなかった。
なんでもします――。
曾は培養組の心を読み、ここへ足を運ぶよう焚きつけた。事実、そそられる提案だった。しかし、彼女が読み誤ったこともある。
子は、親が想像している以上に早く、逞しく成長する。まして培養組は諦めるということを習わなかった。高い次元を目指すことだけを教わった。何かを達成すれば、その先にあるより高い欲求を叶えようと挑む。
いま、親とは何かを知ることができた。つぎに目指すべきものはすぐに見つかった。
22に届けることだ。あのふたりの言葉は彼女のものだ。
自分も行く。22が目指す日本へ。
命を繋げばどこかで会えるだろう。お互い、裏通りという狭い界隈で生きることを余儀なくされるのだ。
なぜ、そこまで日本行きに拘るのか。1―30は、装甲車を降りる間際の背中に訊いた。22は即答した。日本人の心には実直さと高潔さがあるからだと。
彼女は両親から聞かされたと言っていた。
たったいま会ってきたばかりの、あのふたりから。
嘘を吐くような人たちには見えなかった。しかし、娘を失望させないように、日本という国の優れた面ばかりを伝えたのではないだろうか。いずれは手放さなければならなかったのだ。せめて十八年間だけは夢のなかで暮らして欲しいと願ったのではないか。
実直さと高潔さは美しい心から生まれる。教師からはそう教わってきた。しかし身近に感じたことはない。22の昂った瞳から伝わったのは、命を懸けても触れる価値があるということだ。
実直さと高潔さが本当に存在するのなら、目で耳で指先で感じてみたい。
幻想を探すことになるのかもしれない。それでも気持ちは昂っていた。
日本という国に触れてみたいという思いが、心の芯まで根を張っている。
1―30は鎮痛剤を打った。曾がポケットに押しこんでくれたものだ。
この足が役に立たないのなら、連れて行ってくれる誰かを探せばいい。カネさえ手に入ればなんとでもなる。なんでも揃う。叶う。この国では、美徳と悪徳に違いはない。
学校から逃亡したあと、嫌気がさすほど「地下」を歩いた。身を隠すために、胡が用意した部屋を転々としなければならなかったからだ。「地下」で生きる女たちがすぐそばで暮らしていた。彼女たちは、ときに蝶であり、蜘蛛であり、虫けらだった。その逞しさに打たれたことも一度や二度ではない。体ひとつで生きていくことの難しさは意義深さに等しいと気づかされた。唇を染めるだけで、あらゆる望みが手に入ることも教わった。思えば「地下」の女になりかけていた。割れる寸前の蛹だった。いまこそ羽化するときなのだ。
ポケットに手を入れ、馴染みはじめた新しいリップを取り出した。
「どちらへ」運転手がミラーのなかで行き先を訊いた。
「あなたが好きなところなら、どこでも」
鮮やかな紅を引きながら、1―30はつぎの言葉を選んだ。
それに似合う微笑み方は、タクシーを拾う間際に決めてあった。
(第17回 最終回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『クローンスクール』は毎月15日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


