 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十六、『三四郎』第六章 帝国大学運動会(中編)
d:帝国大学大運動会
翌日、三四郎は運動会に出かける。参加するためではない。『野々宮さんの妹といっしょに美禰子もそこにいるだろう。そこへ行って、こんにちわとかなんとか挨拶をしてみたい』からである。
「あくまで女性目当てなわけだね」
「この言い方だと、よし子は、美禰子をその場にもたらす媒介物みたいじゃない」
「まあ実際、そういう都合のいい思考なんだろうね、三四郎は。母親的存在は、普段は不要なんだよ。困ったときだけいてくれればいいんだ」
「でも、行ってみて三四郎は失望するのよね」
「そう、ひとつには『婦人席が別になっていて、普通の人間には近寄れない』からで、もうひとつは『フロックコートや何か着た偉そうな男がたくさん集まって』いるために、自分を小さく感じたからだ。お目当ての女には近づけないわ、男として駆け出しの身、まだ何者でもない自分を思い知らされるわで、二重にへこんじゃうわけだね」
「やっと一安心するのは、お目当ての二人の女の居場所がわかってからなのよね」
「そう、そのために三四郎は『よく見渡す』ということをしたのであり、つまりは女性陣をじろじろと見つめ倒したわけだね。そして、『目のつけ所がわかった』と安心するわけだ。見渡すのも、目をつけるのも、運動会じゃなくって、とにかく美禰子だけが目当てなわけだよね。そんな三四郎の女目当ての視線を遮って運動会が邪魔をする。つまり、競技者たちが現れて美禰子たちの姿を覆い隠してしまうわけだ」
「すごくさりげないけど、とても皮肉な描写よね」
読書=体験してるからこそ、女を見ていた眼中に、男たちがぞろぞろわいて出たときの違和感、疎外感、そして後ろめたさが伝わってくる。十二、三名もいる競技者たちが、美禰子とよし子のまん前にぞろそろと現れるのだから。これもまた人間の盾である。
「一番になった学生は、昨夜最初に演説をした男に似ているのよね。種目は二百メートル走で、記録は二五秒七四。これは当時としては世界的に見ても結構いい記録だったのよね。この年の夏に行われたアテネ五輪で、優勝したアメリカの選手が出した世界記録が二十一秒六。だから、それには及ばないとしても、一般の学生が出す記録としては悪くないことになる」
「でも、これって一九〇四年でしょ。もう百分の一秒まで記録がはかれるようになってたのね」
「そこなんだよ。「蘊蓄」によると、これは田中館博士と田丸節郎博士が考案した計測器を用いたものだったらしいよ。百分の一秒まで計測するのは、そうすることで、世界基準の記録となるからなんだ。そして、この運動会で、田中館博士の助手を当日勤めていたのは寺田寅彦だったようだ」

「野々宮のことね」
「そう、これはだから帝国主義と軌を一にしたできごとでもある。科学力、それが可能にする公式な記録、それを世界に発信することで、他の強国と初めて互することができる。そういう世界基準のスポーツの場でもあったわけだ」
「でも、三四郎にはそんなことはぜんぜん見えてないわね」
「そうだね。計測係を勤めていた野々宮が美禰子に近づく。すると『美禰子は急に振り返った。うれしそうな笑いに満ちた顔である』と三四郎は『遠くから一生懸命に二人を見守って』いるだけだものね。競技なんかそっちのけ、その背後に隠された帝国主義的な意図もそっちのけで、ただただ女のことに意識を集中しているだけなんだ」
「この生々しい凝視の視線は、読書=体験してみないとわからないわよね」
e:サッフォーの池
三四郎は運動会に退屈する。『運動会はめいめいかってに開くべきものである。人に見せべきものではない』と考える。女たちがそんなものを『熱心に見物』していることが気にくわない。これが、世界に「見せるべく」行われている記録会であることはまったく意識に上っていないわけである。我慢できなくなった三四郎は、会場を出て丘を登り、高い崖に腰を下ろして眼下の池を眺める。それは、三四郎が美禰子と初めて出会った森の池である。
丘を降りようとした三四郎は、登ってくるよし子と美禰子に遭遇する。
「ここで、二人の目が比較されてるわね」
「うん、よしこの目は『どんな陳腐なものを見ても珍しそうな目つきをするように思われる。その代わり、いかな珍しいものに出会っても、やはり待ち受けていたような目つきで迎えると想像される』とあって、その目つきに三四郎が癒されることが記されている。その目は、『大きな、常にぬれている、黒い眸』を持っている」
「ところが、うるおったよし子の目に対して、この日の美禰子の目は『この時にかぎって何物をも訴えていなかった』とあるわ。『火の消えたランプを見る心持ち』を三四郎は感じるのよね」
「うん、ほんとに三四郎はとにかく女性のことはよく観察している。だって野々宮や与次郎や広田についてこういう描写はいっさいないだろ?」
「美禰子の目から光が消えているのはなぜかしら」
「もしかしたら、兄が結婚することを知ったとか、あるいは前から出ていた話が本決まりになったとかそういうことが、この日の前にあったという推測はできるね。いよいよ、里見家がなくなる危機が訪れたわけで、自分はもはや誰かと結婚する以外に生きていく方法がないという状況に追い込まれているということかもしれない」
「三四郎には当然わからないわね、そんなこと」
「崖から池を見下ろしたよし子は、『「サッフォーでも飛び込みそうな所じゃありませんか」』という。すると美禰子が『「あなたも飛び込んでごらんなさい」』とけしかける。よし子は『「飛び込みましょうか」』とは答えたものの、水が汚いからと言って引き返してくる」
「サッフォーは、情熱的な恋の詩を作り、恋に破れて投身自殺したとされてるみたいね。今では恋に破れて身投げっていうのは作り話だってことになってるみたいだけど」
「いずれにせよ、恋もしていないよし子に死ぬ理由はないわけだ。むしろ飛び込みたい気持ちだったのは美禰子の方だったろうね」
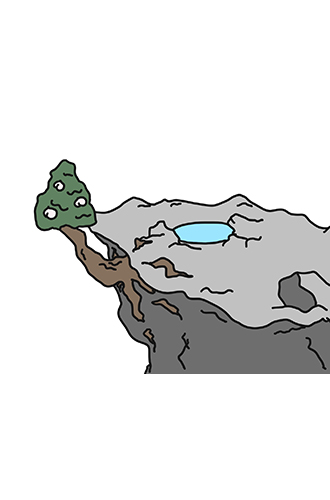
「サッフォーといえば、あの事件よね」
粗暴がレオタードを着てあるいているような高満寺の口から、珍しく感慨深げな言葉がもれた。とはいえそれもやむをないことではある。
どれだけ数多くの少女小説が書かれたとしても、吉屋信子の存在が霞むことはない。そんなことがよく言われてきたが、VRの時代になって、それが事実であることがはっきりとしめされた。
吉屋信子の小説には、ほとんど男性が登場しない。登場するとすれば、少女同士の恋愛、あるいは疑似恋愛を妨げる存在としてのみである。つまり、吉屋信子の小説世界は、徹頭徹尾、少女と少女との密接な関係を、アールヌーヴォーにも比される美文調で描き出した一種の異端耽美世界なのである。
彼女が活躍した大正から昭和にかけての時期、そういう少女たちはエスと呼ばれたが、これは今日でいうところのレスビアニスムに近い意味である。ただしエスの場合は、そのほとんどがプラトニックな恋愛感情によるつながりであることが多いのが違いといえば違いであろうけれど。そして、サッフォーといえば、ギリシャ時代にレスボス島に女学校を建て文芸・音楽・舞踊などを教えるとともに、そこの生徒たちのために女性への愛を謳った詩を多く残したことでも知られている。つまり、このレスボス島に、レスビアニスムという言葉は由来しているわけだ。
「ってことで、だいたいの想像はつくわよね」
「そうだね。吉屋信子の小説世界の体験者には、だからエスに憧れる女子、あるいは実際にそういう体験をしたことがある女性が多かった」
「でも、別の輩も出てきたのよね」
そうなのだ。吉屋信子の美しい世界をかつてのAV的なノリで楽しもうとする男性読者が徐々に増えてきたのである。
「なんせ美少女ぞろいだし、ちょっとロリ系でもあったりするからなあ」
まあ、なんにせよ、単に読者=体験者として楽しんでくれる分には、エス系女子でも、キモオタ男子でも、もっと危ない系男子でも関係なかった。いずれもわが社にとってはお客様であり、それぞれがそれぞれの楽しみ方をすることに文句のあろうはずはなかった。そう、なんせ文学作品とは、開かれたテクストなんだもんね。どんな楽しみ方にだってあけっぴろげの御開帳ってわけだ。
「問題は、読者のなかに、作品に入れ込むあまり、違法な原典侵入を試みるものが出始めたことだったよな」
「そうね、自分の嗜好に合うように作品を改竄しようとしたり、描写をもっと過激にしようとしたりする輩だよね」
「で、〝『花物語』の乱〟が起こってしまったと」
そう、『花物語』は、吉屋信子のデビュー作にして代表作であり、少女小説を定義づけた記念碑的作品でもある。『初夏のゆうべ。七人の美しい同じ年頃の少女がある邸の洋館の一室に集うて、なつかしい物語にふけりました』という書き出しで始まる作品で、七人の少女たちが順繰りに自分の身の回りで起こった出来事について語る形式を取っている。「鈴蘭」「月見草」「白萩」など、どの物語も花の名前がタイトルとしてつけられている。
少女同士の悲恋の話が多いが、なかには『日陰の花』のように、もろレスビアニスムを思わせるような作品も混じっている。
「事件が起きたのは『燃ゆる花』だったわね」
「大金持ちの家に嫁いだものの、そこから逃げて雪深い北国のミッションスクールに逃げてきた人妻ミセス片岡と、彼女を崇め侍女のように仕えるみどりという少女の物語だよね」

大金持ちは、ミセス片岡を取り戻そうとして『焦茶のモーニングコートを着た肥大な紳士』を送り込んでくる。院長を買収しようとして断られた、『無礼で高慢な来客』は、『「後悔するなッ、こっちは命知らずの人間を金で買って、どんな事でもやらせてやるぞッ」』と捨て台詞を残して去る。その言葉通り、ある日の明け方、ふいの火事が起こる。避難した生徒たちのなかにミセス片岡とみどりの姿が見えないことに気付いた院長は、燃える校舎の焔のなかにたたずむ二人に気づく。助けようとする院長を拒み、『「焔は汚れたものを浄化させてくれるでしょうものを!」』と言い残すミス片岡。二人が燃え尽きるシーンは、『紅蓮の焔のなかに咲く真白き花よ! かくて匂い高くも葩を散らして焔の中に!』と描写される。そう、吉屋信子の世界において、美しい乙女は無残に焼け焦げて死んだりはしないのだ。格調高く耽美なる隠喩がすべてを埋め尽くし、死すらもがあくまでも美しく描き出される。客観描写など必要ないといわんばかりである。
「全部で五十二あるエピソードのなかでも、人気の高い逸話よね」
「でまあ、エス系、あるいは百合系大好き少女が好きが昂じてダイブしてみたところ、とんでもない改竄をしようとしてるオタク系男子に気が付くのよね」
「そう、そいつはまずみどりの衣装をロリ系に変えた。それに飽きたらず、院長が、買収に屈してミセス片岡を売るという筋書きに変えようとしていた。つまり、ミセス片岡がミッションスクールから、よほど嫌な思いをした大金持ちの家へと連れ戻されるっていう話にしようとしてた」
「それで、彼女はあわてて戻って仲間を連れてきた。そして、その改竄野郎を取り囲んで詰問し始めたわけよね」
「すると、そこに、このオタク系男子のシンパを名乗る一味が現れて、エス系少女軍団VSオタク萌え萌え軍団の諍いが始まったわけだ」
「でまあ、「キモオタどもが」「信子さまの作品を穢すな」「白豚どもは退散しろ」と一方が甲高くわめけば、「単為生殖しか生きる道が残されてないブスども」「男には見えない種類の女ども」「ひらひらフリルのロココ調時代錯誤」と他方は吼えるという感じになったのよね」
「元にもどせよ」「いやだ」「なんでミセス片岡を売らせるんだよコラ」「そっちの悲劇が見たいんだよ。みどりちゃんとミセス片岡の引き裂かれる涙がよ」「残酷野郎が」「火事で焼け死なす方がよっぽど残酷だろうが」「でも二人は一緒なのよ、そして焼け死ぬんじゃなくって『紅蓮の焔のなかに咲く真白き花』になるのよ」「馬鹿か。洗車場で脳みそ洗ってこいよ」「それに、金持ちの家で、一度逃げたミセス片岡がどんな目に遭わされるかって考えるとよお。たまんないねえ」「この変態どもがあ」っといったどうしようもない展開になって、しまいには取っ組み合いになった。
「そんで活字は倒れるは、文脈は崩れるはの大混乱になって、俺たちが緊急出動したんだったよなあ」
そう、あのときは高満寺が大活躍だった。おそらく数十人はいたであろう、双方の派閥の猛者たちをあっという間になぎ倒し、一網打尽にひっ捕まえて連れ帰ったんだから。
で、活字を元通りに直した俺たちは、振り返ってとんでもない光景をみてしまったわけだ。そう、『紅蓮の焔のなかに咲く真白き花』をもろに見てしまったってわけだ。
「あれはまいったなあ。何ともいえない美しい悲劇だった」
「そうね。活字で読んでるだけだと、美し悲しいんだけど、体験として実際に見ちゃうと悲し哀れが先にきて、それから美死いって感じだったわよね」
とはいえ、いっしょにそんな思い出にふける相手が高満寺というのは、あまりにも場違い感が強すぎると思うのは俺だけだろうか。そのせいで、さっさと感傷から覚めることができた。さあさあ、任務に戻らなきゃねえ。
「ほらそこのでっかいの! 柄にもなく乙女チックモードに入ってんじゃねえよ!」(もちろん、口に出しては言えないセリフである。命あっての物種だからだ。ブレイン・バスターとか、コズミック・バーストとかいった、致死性の技かけられたくないからな。というわけで、ささやかな心の叫びに留めておいたのはいうまでもない)。
(第25回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月14日に更新されます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


