 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十五、『三四郎』第五章 迷へる子(ストレイ・シープ)(下編)
f:ストレイ・シープ
さらに先の橋まで歩いた二人は、古板を渡しただけの橋を越える。美禰子は平気で不安定な橋を渡る。『この女はすなおな足をまっすぐに前へ運ぶ。わざと女らしく甘えた歩き方をしない』と三四郎は感じる。さらに、着物が汚れるのも気にせず彼女はきたない草の上に腰を下ろす。
「ここで小川と空の対比があるでしょう?」
「うん、二人の前を流れている小川を三四郎は眺めるんだよね。すると水が次第に濁ってくる。それは川上で百姓が大根を洗っていたからだとわかる」
「それに対して、美禰子は空を見つめている。澄んでいた空も色を変える。『ただ単調に澄んでいたもののうちに、色がいく通りもできてきた。透き通る藍の地が消えるように次第に薄くなる。その上に白い雲が鈍く重なりかかる』と言う具合にして、藍色の地が徐々に白い雲にグラデーションしていくのよね」
「『「空の色が濁りました」』という美禰子の言葉で初めて三四郎は顔を上げるわけだから、読者=体験者は、小川の水の濁りを三四郎の目で、空の色の濁りを美禰子の目で見ていることになるね」
「この対比はなにかしら。下を向いている三四郎と上を向いている美禰子」
「現実とつながろうとしている三四郎と、空想に逃げようとしている美禰子」
「あるいはまた別の何か。決して釣り合わない二人の関係の象徴とか」
「なんだか気になる場面よね。この大理石の空は」
「三四郎が奇妙なことを言うよね。『「こういう空の下にいると、心が重くなるが気は軽くなる」』って。その理由を説われて三四郎は『「安心して夢を見ているような空模様だ」』って説明し、美禰子が『「動くようで、なかなか動きませんね」』という」
「もう、あれは雪だとはいわないのよね」
「そうだね、美禰子が『「大理石のように見えるでしょう」』と聞き、三四郎が『「ええ、大理石のように見えます」』と答える。これはまるで、同語反復だけど、ここで二人が協同して雲を大理石に仮託したことがわかる」
「大理石は動かないから、不安で揺れ動く心に安定をもたらしてくれるってことかしら」
「そうだね。自分を根無し草と感じている美禰子にとっても、美禰子の思いが見えず(ほんとうはわかっているのだけれど、わかることが怖いからわからないままでいることを選んで)悩んでいる三四郎にとっても、安定した大理石のような雲を見ることは心を落ち着かせてくれる体験となる」
「でも、雲だから動くわよね、実際には」
「そうだね。これはだから、二人のはかない希望でしかない。でも、ここで二人が同じく雲を見るっていうのは、広田の引っ越し先で同じ人魚の絵を見た、あの行為の繰り返しにもなっている。まだ一学生に過ぎず、結婚対象としてはとても考えられない三四郎だけれど、そんな三四郎が自分に夢中になっていることは、美禰子にとってちょっとした心のより所にもなっているのかもしれない」

「自分には魅力がちゃんとあるんだっていう確認ね」
「大理石のようではない二人、あとでわかるように社会的に不安定な立場にある美禰子と、まだ将来も決めかねていて、美禰子、よし子、お光の三人の女性を天秤に掛けるようにふらふらしている三四郎とは、不安定なところが似ているんだよね」
「だから、迷子なのね」
「そう、そういうところはとてもうまくできている」
読書=体験すればわかることなのだが、乞食と迷子のエピソードはそれだけで終わらず、ちゃんと後半の流れとつながっている。たとえば、遠くに聞こえる菊人形の客寄せの声を聞きながら、美禰子は自分を『おもらいをしない乞食』にたとえる。
「つまり、経済的に困っているわけじゃないけれど、誰かの助けを求めている存在っていうこと。人の助けを借りなければ生きていけない存在っていうことね」
「そう。この時代でいえば、結婚する以外にアイデンティティを確保する手段がなく、しかもその結婚を急がねばならない境遇にある自分。それで野々宮に求愛のサインを出しているのに、答えてもらえない自分。答えてくるのは、可能性のない三四郎でしかないという自分。大声を出す乞食のように、あれこれ関心を引こうと自己演出を繰り出すしかない自分、そんな自分を乞食にたとえているわけね」
そこに、三四郎が冗談で引用した、広田が口にした「場所が悪い」という言葉が現実となって現れる。『洋服を着て髭をはやし』た広田くらいな男が近づいてきて、二人を憎悪の目でにらめつけるのである。ここには、結婚前の男女が、人目を忍ぶようにして、人気のないところで二人でいるということが当時の道徳観から大きく外れているということが示されている。未婚の女性は、親や夫以外の男性と出歩いてはならなかったのである。美禰子の行動はそういう意味でも大胆であり新しかったということができる。
「そして迷子の話になる」
「そうだね、三四郎が自分たちが迷子になったから、広田先生たちが捜したにちがいないという。それに対して、美禰子が『「責任をのがれたがる人だから、ちょうどいいでしょう」』という。三四郎が、それは広田先生のことか、それとも野々宮のことかと問うが、美禰子は答えない」
「そうね、さっき迷子に対する人々の対応について広田が批評的に述べた言葉を、今度は広田たちに投げ返していることになるわね」
「人を評した言葉が自分に返ってくるってわけだね」
「でも、それが広田という意味なのか、野々宮という意味なのか、あるいは両方ということなのか美禰子ははっきり言わないのよね」
「たぶん、両方、特に野々宮のことを批判しているんだろうけどね」
「で、迷子の話になる」
「『「迷子の英訳をしっていらしって」』と美禰子は三四郎に問い、『「迷える子(ストレイ・シープ)ーーわかって?」』というわよね」
「でも、これってよく考えるとちょっと変だよね。ふつうに迷子の英訳となると、ロスト・チャイルドとかでしょ、ストレイを使うとしても、ストレイ・チャイルドとかいうはずじゃないかな」
実際「蘊蓄」ボタンで、迷子の英訳を調べると、そういう訳しか出てこない。
「つまり、英語のみならず、聖書の知識も持ち合わせている美禰子が、自分の言いたいニュアンスを伝えるのにもっともよい言葉を宛てたということよね」

「そう、聖書でストレイ・シープといえば、神や救世主あるいは牧師などに導かれなければ、自分の進むべき道がわからない衆生を指すわけだからね。つまり、これはさっきまでの話とつながっているわけだ。寄る辺ない自分に対して、誰も責任をとってくれないという現状を指していることになるよね」
「兄恭助は、父母のない家で自分が先に結婚したら、妹の美禰子が寄る辺を失うという現実を顧みない。恭助の兄の友人であった広田も、そういう状況の自分を助けてはくれないし、結婚という形で自分を救える野々宮は、経済的事情を理由にそこに踏み切ってくれない。そして、大混雑の菊人形展でも、この二人は、自分をほったらかして議論に熱中しているばかりだ」
「当然、三四郎には、『この言葉を使った女の意味』がわからない。なぜ迷子に、彼女がこの英語を宛てたのかがわからないわけよね」
「ここで三四郎は、美禰子をまた見失ったと感じただろうね。三四郎がストレイ・シープとなったわけだ。だから、景色が『寒いほど寂しい』と感じられるわけだ。つまり、この風景は、三四郎の心の中を表現しているわけだよね。
帰り道、二人は泥濘を越える。泥濘の真ん中にある不安定な石を足がかりに三四郎がまずわたる。三四郎が手を貸そうとするのを、美禰子は断るが、わたったときにバランスを崩し、『美禰子の両手が三四郎の両腕の上へ落ち』ることになる。美禰子はもう一度「迷える子(ストレイ・シープ)」と口の中で言い、三四郎はその呼吸を感じ取る。
「二人が接触するのは、この一回切りよね」
「うん、二人の迷える子同士が手を取り合ったってイメージだね」
「同士的な関係かしらね」
「落ち着きどころを見つけられない二人のつながりであって、色恋的なつながりではない。でも、三四郎が錯覚するには十分だな」
「そうね、同じ人魚を見つめ、同じ雲を見つめ、ついに手と手を取り合ったわけだからね。距離が縮まったと錯覚しても無理はないわね。なんだか、哀れだわ三四郎ちゃんが」
「しょうがないよ、そういう道化的な役回りなんだから。一見与次郎が道化的役回りに見えるけど、こうしてみると三四郎の方がよっぽど道化的だよね」
では、第五章を整理するとしよう。
兄の不在時に、一人でいるよし子を尋ねた三四郎は、彼女の口から、美彌子の兄恭を媒介として、自分の知人たち(美彌子、野々宮、広田)らがつながっていることを知る。菊人形展に向かう途中、野々宮と美彌子の間では空中飛行機をめぐる言い合いがある。次いで、一行は、乞食と迷子の少女に遭遇するが、いずれに対しても彼らは冷淡で人任せである。菊人形展に入ったものの一人取り残されている美彌子を連れて、三四郎は谷中、千駄木を抜けて根津方面へと向かう。一緒に空を眺めたり、未婚の二人が並んで座っているところを中年の紳士に睨まれたりした後、美彌子が一行から離れて迷子になった自分たちをストレイ・シープと呼ぶ。
「まあ、収穫といえるのは、ふたたび被害者恭助の名が登場したことと、彼が三四郎の知人たちすべてとつながっていることが分かった点くらいだよな」
「そうね、このことを逆にいえば、すべての登場人物が彼を殺す動機を持ちうるということだともいえるものね」
「全員が容疑者か。とはいえ、その動機がなんなのかは、まったく見えてこないけどね」
「強い感情といえば、野々宮と美彌子の結婚をめぐる確執、それを見守る三四郎の嫉妬、くらいしかないものね」

「でもここで、三四郎は美彌子とアバンチュールしたわけだよな。一時的に野々宮の元から美彌子を連れ去ったわけだから」
「まあ、三角関係よね。でも、どう考えても恭助はその三角形の外にいるわよね」
「この三角関係が殺人の動機につながるとはちょっとかんがえにくいなあ」
というわけで、再び暗礁に乗り上げる俺たちの舟なのであった。
「実はさ」
なかなか光明が見えてこないことにいらついていると、不意に、巨大な筋肉の塊が、告白めいたことを言いだした。
「え、何?」
俺はたじろいだ。何だ。いったいこいつは何を告白しようとしているんだ。やはり、人を殺した過去でもあるのか? そうだとすれば、たぶん素手でだ。などと恐ろしい推測に凍りつきかけていたとき、
「ストレイ・シープって、わたしにとっても思い出深い名前なんだよね」
「え、まさか。リング・ネーム?」
ごつい顎でうなずく高満寺。
過去にこのレオダードで筋肉を包み込んでいる女が、女子プロのレスラーだったという噂は聞いていた。とはいえ、高満寺が自分からその話をしたことはなかったし、俺も聞きたいと思ったことはなかったから、噂は噂のままだったのだ。
「でも、ちょっとあれじゃない?」
「あれって?」
「いやその、うまく言えないけどその、なんていうか、体格と名前が一致しないっていうか」
怒りの琴線に触れないように、言葉を懸命に選ぶ俺。刑事ドラマで、時限爆弾の赤い線と青い線のどちらかを切断しようとしているときの主人公の気分。はらはら、どきどきだ。失敗したらばらばら、どっかんだからな。
「ああ、わたしのじゃないわよ」
「やっぱりね」
「やっぱりってどういう意味かしらね」
「いや、そのあんまり強そうじゃないでしょ、ストレイ・シープって」
「そうね。さんざんいたぶってやったもんだわ。その子、マリー・マグダレンとペアを組んでてね。二人そろって、セクシー・ダイヤモンズなんて呼ばれててさ。童顔のかわいらしい子たちで、おっぱいどっかん、腰きゅっ、お尻どっかんって感じだったからね。リングの外じゃ、マスコミに騒がれて、写真集だとかイメージビデオだとかいって浮かれてたけどね」
「でも四角いジャングルじゃ・・・」
高満寺の妖しい笑み。やめてくれ、俺の背中に氷を流し込むのは。
「餌食だった・・・と?」
「そうね。わたしたち、極悪姉妹にとっちゃ、いびりがいのある獲物だったわよ」
でたわ、極悪姉妹。まさにヒールの極みだね。似合ってるよ、高満寺、その名前。
「それに、わたしたちがエスカレートすればするほど観客も喜んだり心配したりで大騒ぎになったもんだから、興行主ももっとやれもっとやれって感じだったしね」
恐るべし、ショービズの世界。
「ダブル・ムーンサルト、ブラッディ・サンデー、ブラック・サーズデー、波動拳、エンズイギリ、ブレインバスター、恐怖の大魔王、アポカリプス・ナウ、コブラボアハブツイスト、ダイヤモンドカッター、サバト・スペシャル・・・」
「え、なにそれ?」
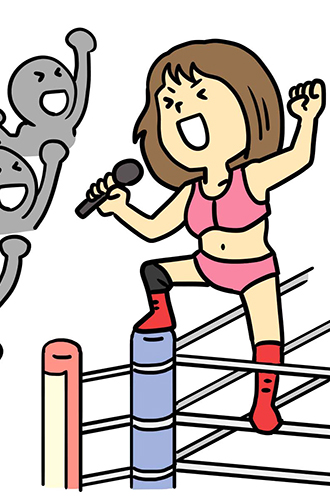
「大技よ。わたしが、相棒の死神女子と繰り出した技の数々。ストレイ・シープったらもう、ああああ~んとか喘ぎ声がセクシーでさ、『もっとやれ、昇天させちまえ!』って、最初は同情してた観客もどんどん興奮してくって感じでさ」
うう、もう聞きたくない。なにこれ? なんでこんな話俺いま聞かされてるんだっけ。なんで聞かなきゃいけないだっけ。
「で、君のリングネームは何だったわけ?」
「スマイリング・エンジェルよ」
「はあ?」
ありえない。ほんとだとしたら、ブラックすぎる。
「信じた?」
「ぜんぜん」
「でしょうね」
高満寺も、苦笑して修正した。
「ほんとは、アングリー・デビルよ」
かくして、怒れる悪魔を引き連れた俺は、今日も世界の破壊にいそしむのであった。ってなわけにはいかないので、かつてリングで大暴れしたらしい悪魔とともに、俺は再び明治文学の世界へと入っていくのであった。
(第23回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月14日に更新されます。
■ 遠藤徹新刊小説 ■
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


