 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十五、『三四郎』第五章 迷へる子(ストレイ・シープ)(中編)
c:空中飛行機
「で、いよいよ翌日になる。菊人形を見に行く日だ」
俺はまず、三四郎に同化して情景を体験してみた。三四郎=俺は広田の家について中に入ろうとするが、そこで野々宮と美禰子の会話を漏れ聞いてしまう。話題がなんなのか不明なのだが、
『「そんな事をすれば、地面の上へ落ちて死ぬばかりだ」』と男がいい、
『「死んでも、そのほうがいいと思います」』と女が答える。
『「もっともそんな無謀な人間は、高い所から落ちて死ぬだけの価値は十分ある」
「残酷なことをおっしゃる」』と続く。三四郎には、なんのことを話しているのかわからない。
広田、野々宮、美禰子、よし子、三四郎の五人で出かける。与次郎は、大論文を書いているからと一緒に出かけない。いっしょに歩きながら、三四郎は、学問の世界と、女の世界が統合されたこの集団に、自分も織り込まれていると感じるが、同時に『どこかにおちつかないところがある。それが不安である』といった心持ちになる。そしてその原因がさっき漏れ聞いた二人の会話にあると気づく。
すると、野々宮と美禰子がさっきの会話の続きを始める。『飛べるだけの装置を考えたうえでなければ』高くは飛べないという野々宮と、それでも飛びたいという美禰子の対立であるらしい。何の話なのかと問う三四郎に、野々宮が『「なに空中飛行機の事です」』と種明かしをしてくれる。
「ここはいろいろ考えさせる部分だなあ」
「まず、野々宮と美禰子の飛行機をめぐる立ち位置が、理学と文学、あるいは科学と詩の対立として示されているわよね」
「そうだね、それが実は二人の結婚観とも重なっているってことだろう。ちゃんと経済的基盤を整えた上でなければ結婚は無理だと考える野々宮と、結婚したければそんなことは二の次だと考える美禰子の対比でもある」
「つまり、この二人が相容れないっていうことの表示でもあり、結局は結ばれずに終わるということの予兆でもあるわよね」
「それに、野々宮の言い様は美禰子がいうように結構残酷だよな。つまり、科学のもつ非人間性と、詩の背後にある人間性の対比でもあるようだ」
「空中飛行機はこのころ結構話題になってたのかしら」
「いや、「蘊蓄」によれば、ライト兄弟の初飛行が一九〇三年のことであり、日本で広く話題にされるのは一九〇九年頃からであったということだ。つまり、この小説は世の中より少し早くこの話題を取り上げていることになる」
「徳川好敏大尉が、日本で初めての動力飛行を行うのは一九一〇年だから、小説が連載されてた一九〇八年の時点では空を飛ぶことはリアルではなかったってことになるわね」
「でも、海外通の漱石は逸早くこの話題を知っていたってことだよね。それで俺が少し気になるのは、ライト兄弟と三四郎のつながりなんだ」
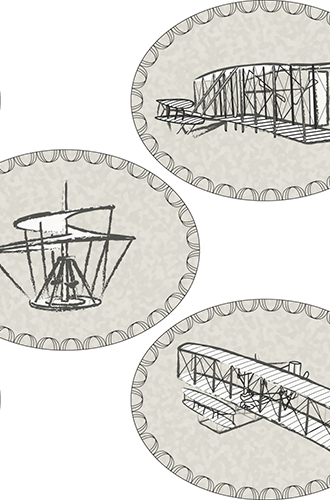
「何かつながりがあるの?」
「うん。オーヴィルとウィルバーは実は三男と四男なんだよ」
「あら、奇妙な符号ね」
「動力飛行機を発明したことで、この二人は、長男と次男を見返したわけだろ」
「兄弟の順位を飛び越えたってことね」
「そう。そして、三四郎には、まだ将来が定まらないがゆえの楽天的な未来像がある」
「長男野々宮が代表する学問の世界、次男恭助が代表する政治や実業の世界、その両方を飛び越えようとする三男と四男のイメージなのかな」
「どっちにしようか迷ってて三と四に引き裂かれているのと同時に、三と四のペアとなって一と二との順位を覆そうともしているわけね」
「うん、そういう複雑な三四郎の立ち位置みたいのを、この名前が代弁しているともいえなくはないように思うんだよね」
「美禰子とよし子の間で引き裂かれ、野々宮と美禰子の関係性への疑いに動揺している落ち着きのなさとも関係ありそうね」
「まあ、ちょっとこじつけめいてるけどね。でも、こう考えることで、漱石が主人公に三四郎っていう奇妙な名前をつけた意味がはっきりするような気がするんだよな」
d:乞食と迷子―責任を逃れる人たちー
菊人形展へと向かう途上、一行は、団子坂で乞食と迷子に遭遇する。
乞食は、大観音の前で『額を地にすりつけて、大きな声をのべつに出して、哀願をたくましゅうしている』が『誰も顧みるものがいない』し、五人も平気で行きすぎる。
よし子は、ただ『「やる気にならないわよね」』といい、美禰子は、『「ああしじゅうせっついていちゃ、せっつきばえばしないからだめですよ」』といい、広田は場所が悪いのだという。ここは人通りが多すぎるからだめなのであって、山の上の寂しいところでこの乞食に出会ったらだれでもやる気になるという。野々宮はしかしそういう場所だと今度は一日待っても誰も通らないかもしれないと言う。
「よし子は、都会人の感覚を代表しているんだろうね」
「個人主義ってやつかしら」
三四郎は彼らの批評を聞いて『自分が今日まで養成した徳義上の観念を幾分か傷つけられるような』気がする。
「共同体感覚で、皆が支え合っている田舎の道徳では、互助の発想がベースにあるんだろうね。それに対して、資本主義の論理が徹底した都会では、働かざる者は食うべからざるってことになる」
「でも、逆説もなりたつわ。都会のような人の多いところで物乞いをするからこそ、それなりの実入りがあって、乞食でも生きていけるっていうわけでしょ。だから、あんな人通りの多いところで物乞いをしているわけでしょ」
そう、俺たちにはいま、光源寺の大観音の前で大声を上げている乞食の姿が見えている。汚い手ぬぐいで頬かむりをした、破けた衣服を身に付けた初老の男だ。靴もないのか裸足である。それが、いかにも哀れを誘う身振りをしながら、大声で喜捨を乞うている。その映像は、「薀蓄」で見たいくつかの画像が元になって俺たちの脳内で合成されたものである。

「都会だからこそ余剰の貨幣があり、それが乞食にも付与される可能性が高まるって事だね」
「美禰子の言葉の意味はあれでしょ、演出過剰ってことでしょ。慈悲を象徴する観音像の前で、大袈裟に物乞いをする姿に嫌悪感すら感じてるみたいだもの。後で自分を『物乞いをしない乞食』にたとえる彼女は、この乞食に、自分の姿を重ねてるんじゃないかしら。人の注意を引こうと一生懸命演出しているけれど、それが過剰すぎて逆に実入りがない自分の姿と映っているんじゃないかしら」
「そうだろうね。そして、広田は、思想的な視点から利他主義と利己主義のことを言っている。都会化、資本主義化は利己主義とペアになってる。資本家と労働者の存在を前提とする資本主義は、群衆のいるところでしか成立しない。貨幣によって人間関係が媒介されるのは、有象無象の群衆がいるからなわけだ。相手の顔が見えないから、貨幣を使わざるを得ないってこと。
それに対し、人が少なければ、自分と他者との関係はより水平的になる。共感的になる。間に貨幣の媒介を必要としない。逆に言えば貨幣の価値まで水平化される。だから、山の中で乞食に会えば、自分と乞食の一対一の関係のなかで、利他的になれるってことじゃないかな」
「それに対して、野々宮はあくまで科学者的な客観性で応じているわけね」
「確率論だよね」
たとえ、広田が言うとおりに山の中では人の財布はゆるくなるという公式が成り立つとしても、その前提としての人が通るという可能性が、確率論的には極端に低くなるという事実について語っているわけだ。
「そして、そういった無責任あるいは不道徳な言動、この小説の言葉を借りれば『批評』が可能になるのは、ここが都会だからだということになる。なぜなら、批評というのは自分と相手を切り離すことで初めて可能になるものだからだ。他者に対して無責任になるから客観的になれるっていうことかな」
「迷子のエピソードも同じね」
その迷子は『七つばかりの女の子である。泣きながら、人の袖の下を右へ行ったり、左へいったりうろうろしている』とあり、おばあさんを探している。通行人たちは心を動かされはするものの、誰も助けようとはしない。読者=体験者たる俺たちには、その女の子の姿がリアルに見えるから、哀れさがいっそう際立って伝わってくる。
けれども、彼らは批評家のままである。野々宮は場所が悪いのだという。いずれ巡査が助けるだろうから、とみな『責任をのがれる』のだと広田がいう。そばまでくれば助けるが、追いかけてまでたすけるのはいやだとよし子がいう。このことを広田が『「やっぱり責任をのがれるんだ」』と追求する。結局巡査が助けたと美禰子がいい、よし子は安心する。
「『責任をのがれる』というのは、心のままに直接行動する勇気を持たないということと同じ意味で使われている感じね」
「そう。だから、この後で美禰子が同じ言葉を口にするときに、その意味が生きてくるわけだ」
e:菊人形展―助けなき苦痛―
かくして五人は、大混雑している菊人形の展示場に入る。顔や手足は木彫りで、菊で衣装をこしらえられた人形が曽我の討ち入りのような史実を再現するかたちで並んでいる。

ちなみに、「薀蓄」で探してみたところ、宮本百合子に『菊人形』という短い作品があることがわかった。そこに日露戦争直後に行われた団子坂の菊人形のことがわりと詳しく書いてあった。
『葭簀ばりの入口に、台があって、角力の出方のように派手なたっつけ袴、大紋つきの男が、サーいらっしゃい! いらっしゃい! 当方は名代の(何々とその店の名を呼んで)三段がえし、旅順口はステッセル将軍と乃木大将と会見の場、サア只今! 只今! せり上り活人形大喝采一の谷はふたば軍記! 店々で呼び合う声と広告旗、絵看板、楽隊の響で、せまい団子坂はさわぎと菊の花でつまった煙突のようだった。』
『戦争ものでない菊人形と云えば、あのどっさりの菊人形の見世ものの中で何があったろう。常盤御前があった。小督があった。袈裟御前もあった。』
つまりは、時事ネタであった日露戦争時における水師営の会見などを題材にしたものと、もっと古い伝統的な主題を再現したものの二種類があったことがこうした描写からうかがわれる。三四郎たちが見たのは、こんな菊人形たちだったわけである。
広田と野々宮は、菊の培養法などをめぐる議論に夢中になって皆から遅れる。美禰子は先にいて、野々宮の方を振り返るが、野々宮は広田との話に夢中になっている。三四郎は美禰子の後を追う。名を呼ぶが美禰子は答えない。
「そして三四郎は、美禰子の二重瞼に『霊の疲れがある。肉のゆるみがある。苦痛に近き訴えがある』のを認めるってあるわね」
「うん、三四郎の目線に沿って読書=体験すると、三四郎が美禰子ばかり追いかけてるのがよくわかるね。ここでも三四郎の眼は、菊人形じゃなくて、美彌子を子細に見物しているわけだ。美禰子の心の動きを読みとろうと懸命になっている。そしてここでも、心の代替物として目の周囲が描かれているっていうところがおもしろい。」
「そういえば、この下りではよし子の事が完全に無視されてるわね」
「そう、菊人形に入った途端、よし子の描写がなくなる。この章が終わるまでまったく姿を現さない。菊人形展の群衆のなかに置き去りにされたままになる」
「そうだね。個別には両方に関心のある三四郎だけど、二人が同時に存在すると、美禰子の前に完全によし子は見えなくなるってことだよね」
「よし子は、三四郎にとって母親の代替物だからね。母親はいつだっていてくれるから、あえて顧みる必要を感じないわけよね。都合のいいときだけ帰る場所であり、そんな扱いを許容してくれる存在だ。そんな母親的なあり方を、三四郎は完全によし子に見ていることになるわね」
「そう、それに対して美禰子はわからない。追いかけていないと、目線を据えていないとどこに行ってしまうかわからない。そういう不確定性、あるいは不安定性が、三四郎をいても立ってもいられなくさせるんだろうね」
心持ちが悪くなった、という美禰子のなかに『三四郎は往来の真ん中で助けなき苦痛を感じ』る。静かな所へいきたいという彼女といっしょに、菊人形展を出て、谷中と千駄木の出会う谷沿いの小川にそって根津へぬける石橋をとおって二人は歩く。そして人の通らない広い野にでる。
「こんなにたくさん人がいるのに、ほんとうに彼女が求めている人は振り向いてくれない、そういう苦痛よね」
「近づいてくるのは、どうでもいい三四郎っていう若造だけなのよね」
「教育のない下等な人間の間にいたせいで、失礼な目にあったりして疲れているのではないかと三四郎は言う」
「ひどい言いようよね。自分は母親がかりで大学まで行かせてもらってる遊民の身であって、実際にはさして勉学に励んでいるわけでもないのに、エリート意識だけは半端ない」
(第22回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹新刊小説 ■
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


