 さやは女子大に通う大学生。真面目な子だがお化粧やファッションも大好き。もちろんボーイフレンドもいる。ただ彼女の心を占めるのはまわりの女の子たち。否応なく彼女の生活と心に食い込んでくる。女友達とはなにか、女の友情とは。無為で有意義な〝学生だった〟女の子の物語。
さやは女子大に通う大学生。真面目な子だがお化粧やファッションも大好き。もちろんボーイフレンドもいる。ただ彼女の心を占めるのはまわりの女の子たち。否応なく彼女の生活と心に食い込んでくる。女友達とはなにか、女の友情とは。無為で有意義な〝学生だった〟女の子の物語。
by 金魚屋編集部
0 螺旋階段(後編)
*
「急死に一生じゃけえ」
親戚一同が、どっと笑った。夏休みは、祖母の実家に行くことになっている。今年も祖父が飲酒運転をして、ガードレールに突っ込み、外車をオシャカにしたのだ。死にかけたのに、本人もへらへらしている。
「やんちゃじゃねえ。少年の心を持っちょる」
祖母が言った。実家に帰ると、方言が出る。
私は、台所へ向かった。お茶をいれているふりをすればいいのだ。ポットに水を入れ、スイッチを押す。

「東京のお兄さんは元気かね?」
声が大きいから、こちらまで聞こえてくる。
「毎日、クロスワードと釣りよ。見てるだけでこっちがくさくさしてくるわ。物も捨てないし」
「姉さんも大変じゃねえ」
「家だって、私が建てたようなもんよ」
その場に祖父がいないと、滅茶苦茶を言う。
「姉さんじゃないとできんね」
明美さんの声。
「ほんとうよ」
だれかが言った。
「おい、明美。だらだら喋っておらんで、お茶持って来んかい」
叔父がお嫁さんに茶碗を差し出す。
「今、持って行きます」
かわりに返事をする。
「悪いねえ。まったく、明美は気がきかんわ」
人数分の茶碗を並べ、パックの煎茶を空けて、お湯を注ぐ。のれんを上げて、茶卓に戻る。
「ええ娘さんになったじゃないか」
叔父がこちらを見て言う。
「これが、気難しくてねえ。最近、やっと明るくなったのよ。一時はどうなるか心配したわ」
いつものやり口だとわかっていても、つい腹が立ってしまう。
「人のこと、精神病みたいに言わないでくれる?」
「ところで、兄さんの妹さんたちはどうしてるの?」
明美さんが話題を変えた。
「姿子さんだけはさあ。美人の中の美人じゃけえ」
叔父がまた余計なことを言う。
「見た目はどうだか知らないけど、性格がね」
こういうとき、祖母は決して黙ったままでいない。
「あのひとは人を逸らさない雰囲気を持っているよ」と叔父。
「目立ちたがりよ。女は控えめじゃないと。ちょっとあの人は強いからね。びっくりするわ」
「姿子さんが西洋風の美人なら、姉さんは和風美人じゃけえ。そりゃあ、お互いに意識し合うね」
またしても、明美さんがすかさずフォローする。丸く収まった。
帰りの新幹線で、私はずっと眠っていた。
秋になり、再び東京での生活が始まった。
いつもの時間に、いつものバスに乗る。
――おはよう。
挨拶する声が聞こえる。第二外国語の授業で一緒の子だ。歩き方がスチュワーデス風。素早く手を振り、口角を上げる。あなたのことを無視していませんよ。というサイン。大学生が寄り集まるこの時間帯の車内では、あちこちで同じジェスチャーが繰り返される。視線を規定の位置に戻す。バッグの中身を移動させて、整理する。窓の外を眺める。今日は雨だから、到着が遅いかもしれない。もっと早く家を出ればよかった。ガラス越しに、様々な様式の家が並んでいる。
「空想するのが趣味なのよ」ドイツ語の先生が、外を指さしながら言った。半年以上も前のことだ。今は同じバスに乗ることはない。離婚して、引っ越したらしい。私は興味がなかったけど、一応「なにをですか?」と聞いた。そうしたら「たとえばね、素敵な家を見つけてあの家の住人だったら、って考えるの。通学の時間が楽しくなるわよ」って。どうしてそんなことを教えてくれたのかは、わからない。先生は私が軽く孤立しているのを、知っていたのかもしれない。
――つぎは女子大前
アナウンスとともに、入口付近に人が集合した。急がなくても、どうせ出られるのに。列に並ぶ。押し出されるようにして、外に出る。単位を取りに来てるだけ。そう言い聞かせたら、自分が自立しているように思えてきた。
「パートツーがいる」
「どこどこ?」
「前歩いてる」
パートツー、というのは私のあだ名らしい。由来はわからない。二重人格とか? とにかく良い意味ではないということは口調からも確認できる。勝手に名付けないでほしい。嫌われているほどではないけれど、違和感を持たれているのだと思う。興味がある分野の先生と、積極的に接触したがる。嫌味を言ってくる人には近寄らない。一人で行動していても平気。他の子と違うところがあるとすれば、そのくらいだと思う。共学だったら、たぶん普通。けど、この閉鎖的な環境では許されないらしい。授業だって、自分の基準でとる。
教室のドアを開ける。はじっこに座り、自分の持ち物でテリトリーを包囲する。縄張りをつくっているのだ。お腹が空いたから、バッグからおにぎりを取り出した。かつおぶしと、梅干ししか入ってないシンプルなやつ。食べているところを人に見られるのが嫌だから、ちぢこまりながら口に運ぶ。今日は一コマだけ。授業と、バイトと、家。その繰り返しで、日々が過ぎていく。たまに友達と映画に行ったりする。合間に図書館とか、公園にもいる。若い時期を無駄に過ごしている、という観念があるから、デートもする。でも、なにも変わらない。トンネルを抜けたら一般道だった、的な。とにかく退屈で、イライラしていて意味もなく焦っている。

一つのことに全体重をかけたくない。上手くは言えないけど、後ろで扉が閉まってしまうような気持ちになりたくない。どんなことにも深く関わらないようにして、精神のバランスを保っている。喪失感を味わうのが怖くて、いつも身構えている。私は、器用ではないのだ。
「ねえねえ」
となりから話しかけられた。ピンクと黒が半々のワンピースを着ている。
「なに?」
「そのバッグ、ガルシアマルケスでしょ?」
興味の対象は私ではない。
「うん。原宿で買った」
「お店の場所がわからないんだけど。よかったら案内してくれる? お願い」
手を合わせている。そんなに重要なことなのだろうか。
「なんで?」
「忙しい?」
切迫しているようだ。
「まあまあひま」
そういう流れで、だれかと街をぶらぶらすることもある。
目的を終えたあと、私は一人で表参道を歩いていた。
「あらまあ」
大きな声が聞こえる。振り返ると、初老の女性が立っていた。ベージュの服に、ワインレッドのマフラーをしている。スウェードの鞄を持っていた。見覚えがなかった。私のさらに後ろに、知り合いがいるのだろうか。女性はさらに続けた。
「大きくなって。背格好が、お母さんとまるで同じね」
私に向かって話しているようだ。どう反応していいのか、戸惑った。すこし警戒した。
「あらー。忘れちゃった? 遥子よ。利蔵の妹。もうおばさんになったから、わからなかった? 小さいころ、抱っこしたのよ。今もあの時の面影があるわね」
揺子という名前は、聞いたことがある。ということは、姿子さんと姉妹になるのだろうか。
「すみません。ぼーっとしてて」
「いいのよ。この近くに、息子の事務所があるの。たまたま来てただけだから、びっくりしたわ。お茶していかない?」
勉強しない大学生には、時間なんていくらでもある。
「あっ。はい」
私はノコノコ付いていった。

「ごめんね。いきなり声かけて。身内に偶然会うことなんて、なかなかないでしょ? ロイヤルミルクティーでいいわよね? ここでは一番おいしいわよ。なんか食べる? お腹空いてない?」
座るなり、遥子さんは話しはじめた。
「はい」
「今栄養とらないと、育たないわよ。サンドイッチも必要よね。私は、ドリアにするから」
「ありがとうございます」
勝手に決めてしまう。
なにを話したらいいのだろうか。
「だいぶ前ですけど、姿子さんに会いました」
少々強引かもしれない。
「あらー? あの子もああ見えて損な性分だからね。元気だった?」
「ご主人が入院されたって聞きました」
「そうなの。ここのところずっと熱っぽくて疲れが抜けないって言ってたらしいの。真面目な人なのに珍しく気力が湧かないってこぼしていたらしいわ。夏バテにしても長いし。このへんで一度ゆっくり休んでちゃんと治したらってことになってね。あそこは妹も体が弱くて、仕事も何度も辞めさせられてるし。なんとか再就職してるけど、なんだかんだ大変だわ」
「え? そんなに弱いんですか?」
「まあねえ。生活を支えるために、美容部員やってたこともあったわよ」
「姿子さんがですか?」
「売り上げは凄く良かったみたいだけど。そのせいか虐められてね。泣きながら電話をかけてきたこともあった。どこでも目立ちすぎるのね。だけどなにを言われても、自分のことを反省するのよ」
「祖父からは、全然聞いてませんでした」
「ほとんど没交渉でしょ。姿子とは。昔から、仲が悪かった。姿子が「けど、兄貴」って言うと、兄が怒りだすのよ。何度くりかえしても、話し合おうとするのよね。姿子は話せばわかると信じてるから」
あきらめたような表情をしている。
「どんなときにですか?」
「数えきれないわよ」
「考え方が根本的に違ったんですね」
「そうなのよ」
「祖母と祖父は、まともに話し合っててるところ、見たことがないです」
「でも、結局最後は姉さんの思い通りになってるでしょ?」
片側で手を組んでいる。放心状態に見える。
「なんとなく」
「兄さんには、うまく誘導することしか、できないのよ。他にやりようがないの。それが現実よ。嫌われたら、元も子もないよ」
揺子さんは、ため息をついた。
*
授業のない日。ベッドから起きると、湿度の高い空気が漂っていた。除湿機のスイッチを入れて、パジャマからワンピースに着替える。頭にさわると、寝癖が付いていた。激しくリーゼを吹きつける。この世に存在する生活感を全て一掃したい。汗もかきたくない。煩わしいことから逃れて生きていたい。できることなら、一生。
階段を降り、洗面所に向かう。顔を何度も洗った後、居間に戻って冷蔵庫を開ける。昨日のおかずの残りが、タッパーに入れてある。パンと牛乳を取り出す。朝はこれだけで充分。パンをトースターで温めて、再び上に戻る。
私の部屋には、不必要だけど必要不可欠なものが並んでいる。木製の本棚には、海外の幻想文学。その引き出しには、ビー玉とか、天然石が小分けされて入っている。気が向いたときに眺めるのだ。特に意味がないけど、パンはお盆ごとサイドテーブルに乗せてから食べる。ベッドに腰掛けながら。お行儀が悪いことをするのが嬉しい。ただ、それだけ。パンくずが床に落ちていると思われるので、箒で掃いてチリをゴミ箱に入れる。ほとんどの時間、私は私の世界に生きていて完結している。
下の階から話し声が聞こえてきた。祖父が電話しているのだ。「いやいや」とか、決まりきった相槌を打っている。受話器に向かってお辞儀をする姿が目に浮かんだ。たぶん相手は会社時代の上司だろうな、と思った。定年退職した後なのになんでわざわざ連絡を取り合うのかが理解できない。階段を降りる。玄関で、キタムラの靴を履いた。
顔を合わせないようにこっそり外に出ようと思ったのに、祖父はいつのまにか庭に移動していた。ちっぽけな植木鉢を見つめている。中には、松が植えられている。
「おい。どこに行くんだ?」
気づいているとは思わなかったから、驚いた。背中に目でも付いているのだろうか。
「出かけてきます」
質問することが重要で、答えは聞いていない。いつものことだ。門を閉めた。背後で、金属が触れ合う音がした。
「次、いつ会える?」
彼が言った。いつ見ても、背が高いと思う。
「土曜日」
「長いな」
「ふーん」
「本当だよ。疑うなよ」
「私のほうが、好きだと思う」
文脈を無視して、言いたいことを言う。
「今となっては」
足音だけが聞こえる。
「なに?」
「妹よりも大切だよ」
平気でそんなことを言えるなんて、冷たい人だと思った。
「優秀なんでしょ? 慶應に行きたいんだって?」
「まだ中学生なんだけど」
「知ってる」
「勉強ばっかりしてるんだよ。このまえ、お茶淹れてって言ったら、無視された」
どう反応していいのかわからなかったから、口角を上げてみた。
「一人で帰れる?」
「と、思う」
「このまえ、山手線で一周して、もとの駅に戻ってただろ」
「大丈夫」
「やっぱり、送っていくよ。」
そう言って、彼は私の手を握った。
次の日も休みだった。つまり、学校もバイトもない日。
――妹よりも大切だよ。今となっては
彼の言葉が、頭の中をよぎった。本心だとは思えないけど。たしかに、私は彼から、妹みたいに扱われてる。出来が悪くて、甘ったれな妹。一人っ子の私には、それが嬉しかった。自分でも、なんでこれほど依存心が強いのか理解できない。誰かが、関心を持って世話をしてくれる。それだけで、相手に支配されてしまいそうだった。他人なのに、身内以上に大切に感じることなんて、あるのだろうか。
机の引き出しを開けて、ビー玉をひとつ、手の平に乗っける。赤の波模様。そっと、転がしてみる。何度も反復しているうちにことん、と音がして床に落ちてしまった。もう、どうでもいい。
本棚から、本を一冊選ぶ。趣味が変わらないから、同じ本を何度も読む。というよりも、変な読み方をしている。一度目はストーリーを追う。二度目以降は、作者の影を追うのだ。具体的には、嗜好をあぶりだす。描写が綿密なところに目を付けて、検討するのだ。友達に話したら、意味がないって言われたけど。実は目の前の人に関心を持つことだって、充分不毛だと思う。人が本当の気持ちを話しているかなんて、本人にしかわからないし。サイドテーブルに付箋とシャープペンシルを置く。怪しいと思われるところに、線を引く。目を付けた作家とは、絶対に接触しない。握手会とかに行って、「ヨーロピアンシュガーコーンが好きでしょ?」なんて言うのは犯罪行為だし。これは、けっこうおもしろい。勝手に、相手のことを知った気になれる。なにより、身近な人への執着を断ち切れる。依存心がなくなる。自立できる。という境地を目指している。
こんなことばかりしていると自己評価が下がるので、翻訳の練習をする。『中級者のためのフランス語翻訳練習帳』。わかりやすいタイトルである。
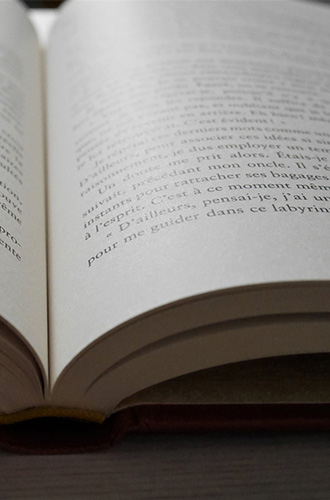
ドアをノックする音がした。
「入っていい?」
母の声。
「どうぞ」
「昨日、何時に帰ってきた?」
エプロンのポケットに、手を突っ込んでいる。
「そんなに遅くなってないけど」
「どこ行ってたの? 電話くらいしなさいよ」
「メールした。渋谷」
「あらそう。なんにも言わないんだから。横浜にも勝手に行っちゃうし」
「ごめんね」
「そういえば姿子おばさん、元気だった?」
「まあまあ。でも、おじいちゃんにいつも存在否定されまくりだったらしいよ」
「なんで嫌うのかね。あの人には、おじいちゃんは良くしてもらったことしかないのに」
「おばあちゃんに気をつかってるんじゃないの?」
「あるかもね。でも、そこまでは必要なくない?」
「なんだろう。罪悪感があるとか?」
「どんな?」
「考えてもわからないわね」
疑問を投げかけたあげく、母はどこかに行ってしまう。いつもそうだ。
祖父はどうして、祖母の言うなりなのだろう。姿子さんが嫌いな理由は? 頭の中で、同じ言葉がエコーする。祖父の性格を、私はよく知らない。特徴といえば、学歴信望者なことくらいだ。「学歴の高い人間は、人格的にも優れている」それが、口癖だった。しかし、彼の妻は中卒なのだ。
ひとつ、思い出したことがある。高校生のときだったと思う。私は喉が渇いていて、下の階に降りた。蛇口を捻って、水を飲んだ。日本は住宅事情が悪い。というより、狭い。襖をへだてて、その向こうに祖父と祖母が寝ている。
冷蔵庫のモーター音が響いていた。一度起きてしまうと、なかなか寝付けない。椅子の下に丸まる。
「なあ」
祖父の声。
「疲れてるのよ」
「なあ、なあ」
しつこい。
「疲れてるの」
祖母は嫌そうだった。
なにも聞かなかったふりをして、私は部屋に戻った。話題にもしなかった。母も、知っているだろうということは予想がついた。つぎの日、祖父は機嫌が悪かった。テレビの音量が大きく聞こえた。朝食がまずかった。
「新聞、とってきて」
祖母が言った。祖母は部屋で、手にクリームを塗っていた。私は顔を見れなかった。
金箔が入ってるのよ、こうすると、艶が出るの。シミも薄くなるのよ」
「前と変わってないように見えるけど」
返事はなかった。
祖母の神経は手の甲に集中していた。
「色が黄色いわね、あんた」
祖母はよく、私に言っていた。普の容姿だが、肌だけはとても美しいのだ。
記憶は連続して蘇る。
同じ年の、私の誕生日。父は深夜に帰ってきた。
「見せたいものがあるんだよ」
笑顔で話しているが、様子がおかしい。酔っているようだった。
玄関には巨大なペコちゃん像が置かれていた。たぶん、店頭に配置してあったものだ。
「かわいいだろ? 気に入ったか?」
父は得意げだった。どうしていいのかわからなくて、私は下を向いた。母が出迎えにきた。
「どうするのよ、そんなもの持って帰って」
母がつぶやいた。そして、顔を覆って静かに泣きはじめた。
「なにが悲しい? なあ、なにが悲しい?」
父は怒りはじめた。周辺の住人が寝ている深夜、母と私はそれをひきずって駅前の店に戻しに行った。帰ってきたとき、父は居間でうつぶせに寝ていた。
祖父は
「人として恥ずかしくない行いをしろ」
と言って父を叱った。それを聞いて、父は一週間ほど帰ってこなかった。
昼、私と母は居間で紅茶を飲んでいた。談笑する母と私に、祖母が言い放った。
「女が二人いて、男一人引き留められないの? 情けないね。あんたらは」
母は笑った。私も続いた。笑ってしまえば、全てが喜劇だった。私は普通の馬鹿として、高校を卒業した。非難されることは、なかった。なにもかもがどうでもよかった。角砂糖に水が侵食するみたいに、私はなにかをなくしていった。
母は買い物が趣味で、気が向くと私に服を買ってきてくれた。空を見上げれば、鳥が飛んでいた。瞬発的に面白いことを追い求める。私はそれ以外の生き方を知らない。
*
「横浜のおじさんのお通夜に行ってくるから」
祖母が、髪の毛をとかしながら言った。あれから、二年以上が経過していた。
「おじさんって?」
「姿子さんのご主人よ」
「なんで?」
「白血病だったからよ」
「知らなかった。夏風邪じゃなかったの? なんで言ってくれなかったの?」
「はじめは高熱が出てだるさが抜けなくて病院に行ったんだけどね。なかなか良くならなくて心配して大きなところで精密検査したら見つかったのよ。入院していたのは話したでしょう? 私たちも後で聞いたのよ。それに、あんたに言ったって何もできないでしょうが」
「夏風邪だって聞いた」
自分でも馬鹿なことを言っていると思う。けど、納得できなかった。
「だったら、あんなに長く入院するわけないでしょう。お金がかかるのに。最後は民間療法にまですがってたんだから」
それから、二ヶ月くらいして姿子さんが倒れた。お見舞いに行ったとき、姿子さんはゆっくり私の頭を撫でた。やせてしまって、指輪が重たそうに見えた。それから三回、病院に行った。息子にも会った。つぎの月の六日、家に電話がかかってきた。祖母が受話器を取る前から、姿子さんが死んだのだな、と思った。なぜかはわからない。たぶん、親戚だからだろう。
「横浜が、亡くなったのよ」
祖父は新聞から顔を上げなかった。けれども、葬式には出た。私たちは並んで収骨をした。
「美人だったね」
三重が言った。
「とても」
神戸が答えた。
それからしばらくして、横浜の息子が来た。「売り食いをしていたから、ほとんどまともなものが残っていない」と言って紙袋を手渡してくれた。近鉄松下と印刷された袋を開けると、小さな箱が現れた。中に入っていたのは、大粒のルビーの指輪だった。
(第02回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『学生だった』は毎月05日にアップされます。
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


