 女の人がいる。古い羊と書いてコヨウさん。弟がいて名前は詩音。詩音は結婚して家を出てゆき、古羊さんは実家に一人で住んでいる。孤独なわけではない。寂しくもない。お勤めに出かけ、淡々と日々を送っている。それでも事件は起きる。とてもささやかな。そしてまた日々が過ぎてゆく。第6回金魚屋新人賞授賞作家、片島麦子さんによる〝じん〟とくる女の人の物語。
女の人がいる。古い羊と書いてコヨウさん。弟がいて名前は詩音。詩音は結婚して家を出てゆき、古羊さんは実家に一人で住んでいる。孤独なわけではない。寂しくもない。お勤めに出かけ、淡々と日々を送っている。それでも事件は起きる。とてもささやかな。そしてまた日々が過ぎてゆく。第6回金魚屋新人賞授賞作家、片島麦子さんによる〝じん〟とくる女の人の物語。
by 文学金魚編集部
#1(後編)
「オネエサンはどう思います?」
リサに声をかけられて、古羊さんはわれに返った。オネエサン、と云われるたびに、自分の他に誰かいるんじゃないかと思って首を巡らしたいのをどうにか我慢する。初対面なのにこの人は、わたしのことをオネエサンと云う。古羊さんは戸惑っていた。自分のことを姉と呼んでいいのは詩音だけなのに。
リサが古羊さんをそう呼ぶのは、それ以外、呼びようがないからである。リサは詩音の婚約者で、挨拶と式の相談をかねて古羊家を訪れていた。未来の旦那の姉なのだから、お義姉(ねえ)さんと呼ぶのが当たり前と信じきっている。
「今はレーザーでね、あっという間なんですって。結婚式までにきれいに治るって先生も太鼓判を押してくれているし。女性同士だからこの気持ち、判っていただけますよね、オネエサン」
さっきからリサが熱心に訴えているのは、左目尻の下にある泣きボクロを除去するレーザー治療を受けるかどうかということだった。式の相談といっても、すべて資産家であるリサの実家がお膳立てしてくれていて、要するに古羊さんに相談することなど何もないのである。
「でも万が一ってこともあるだろう? 傷でも残ったら大変だよ。せっかくの結婚式に浮かない顔の君を見るのは忍びないな」
「あら、平気よ。パパの昔からの知り合いのお医者さまだもの。信頼できるかたよ。詩音はいいから黙ってて。あたし今、オネエサンとお話ししてるの」
やれやれという風に、詩音は肩をすくめて口を閉じた。リサの父親の存在は、詩音にとってありがたくもあり脅威でもある。大手製薬会社の研究部に所属するエリート研究員である詩音の義父となる予定のその人は、会社の大株主のひとりでもあった。つまり、そういうことすべてをひっくるめて、詩音はリサとの結婚に踏み切ったのだった。詩音にとってのしあわせとは、そういうこと、に他ならない。

「ホクロも似合っていると、わたしは思うけれど」
古羊さんは控えめに答えた。でないとどこを見ていいのやら、目のやり場に困ってしまうからだ。古羊さんはリサと向かい合ってからずっと、彼女のホクロだけを見ていた。顔にはまったく興味がなかった。よくできた顔だとは思う。いろいろな技を駆使すれば、こういう顔ができあがるのだろうとも。次に会った時には判らないかもしれない。だったら目じるしに、ホクロは残しておいてほしかった。
「そうですかあ? でも泣きボクロって、あんまりいい意味ないみたいなんです。前からずっと気になってたんですけど……助平っぽいし」
「助平って、リサ、云いかた」
呆れたように詩音が口を挟む。
「だって他に、どう云うの?」
「セクシーとか、もう少し何かあるだろう」
「まあねえ。けど、自分で自分のことをセクシーって表現するのって何か変じゃない?」
「でも、それじゃあんまり……」
この二人は一体何をもめているのだろう。
古羊さんは眉間のしわを深くした。もめるのならば、もっと他にもめることがある筈だった。オネエサンと呼ぶなんて、わたしは全然聞いていない。わたしの家族は詩音だけ。あなたと家族になるなんて、誰もひとことも云ってはいない。
そう云いたいのだけれど云えない古羊さんは、ひたすらリサの泣きボクロを凝視した。こうやってずっと見続けていれば、もやもやとした思いが収斂されて、ホクロのひとつぐらいなら焼き切れるような気がした。
新郎控室に入ると、詩音の他には誰もいなかった。
「リサさんは?」
「あっちの控室でまだ準備中だよ。女の人はいろいろと大変だよね」
「詩音もよく似合っているわよ」
「ありがとう」
古羊さんは静かにドアを閉め、詩音の前に立った。
新郎用の控室は新婦のに比べればずいぶんと手狭で、小さな会議室のようにあっさりしたモノだったが、そのシンプルさがかえって詩音の美男子ぶりを強調していた。背の高い詩音に合わせた銀色に光るロングタキシード姿は、どこか知らない国の王子さまに思えて、古羊さんはほれぼれと自分の弟を見直した。王子さま、などというのは少女じみた陳腐な表現だと判っていても、そうとしか表現できないほどにこの日の詩音は輝いてみえた。
「それ、もしかして母さんの?」
詩音が指さすのは、古羊さんの黒留袖だった。教会式に留袖が似合うかどうか少し悩んだけれど、古羊さんは結局着ることにした。大事な詩音の晴れ舞台なのだからと、苦手な美容室で髪もアップにしてもらった。レンズのない眼鏡はそのままである。
「ええ。きっと母さんも父さんも、喜んでくれてるわね」
「そうだといいな」
「そうよ、絶対にそう」
古羊さんは力を込めて云った。そうでないと困るのだ。詩音のしあわせを古羊家のみんなは祈っている。とりわけ古羊家の女たちには切実な願いだった。詩音がしあわせであることが自分たちのしあわせであるのだから。

「姉さん」
「なあに?」
詩音は照れ臭そうに頭をかきながら、「こういう時になんていうかな」と前置きし、一歩前に出る。
「長い間お世話になりました。父さんと母さんがいなくなってから今までずっと、面倒みてくれてありがとう」
そう云って深々とおじぎした。
古羊さんは思わず絶句した。今の今まで面倒をみてもらっていたのは古羊さんのほうではなかったか。
「……って、これ、ふつうは花嫁さんが云うものなのかもしれないけど」
爽やかに笑う詩音を見て、古羊さんは悲しくなった。よく判らないけれども、詩音の感謝の言葉が古羊さんの耳には永遠の別れの言葉に聞こえたのだ。
「そんな、風に、云わないで」
途切れ途切れの声しか出てこない。自分は一体どうしてしまったのだろう。混乱する古羊さんを詩音は微笑んで見つめている。感極まった姉の態度と捉えているのだ。
清々した笑顔を浮かべる詩音の前で、古羊さんは曖昧に微笑んでみせた。完璧な弟の晴れの舞台を自分が傷をつける訳にはいかないと思う。笑って送り出すことがつとめであると、柄にもなく決意する古羊さんであった。
「姉さん、そろそろ」
「え」
「行かないと。時間が」
壁の時計にちらちらと目をやりながら、詩音が申し訳なさそうに切り出した。
「ああ、そうね」
「じゃあ、いってくるよ」
「はい、いってらっしゃい」
いつも家の玄関で送り出すように古羊さんは云った。詩音は古羊さんのわきをすり抜け、ドアに向かっていく。古羊さんはそのうしろ姿を見送った。けれど、すぐにドアの向こうに消えていく筈のうしろ姿はいっこうに遠のかない。詩音はためらいがちに半分振り向いた。
「姉さん、あの」
「なあに?」
「悪いけど、離してくれないかな」
云われて詩音の視線の先に目をやると、誰かがタキシードの裾を握りしめていた。それが自分の手であると認識するまでに数秒が必要だった。血の気が失われるほどに握り込まれた右手を、古羊さんは慌てて離した。
「ごめんなさい。どうしよう、しわになってる」
「大丈夫だよ、これくらい」
微妙に裾から目を逸らして、詩音は明るく云った。
「気にしないで。ごめんだけど、ほんとうにもう行かなけりゃならないんだ」
「判ってる。いってらっしゃい」
「いってきます」
詩音は快活な声を残し、さっと身をひるがえしてドアから出ていった。
式がはじまるまで、古羊さんは詩音のタキシードの裾のしわが気になって仕方なかった。完璧な弟に傷をつけてしまったと嘆いたところで、古羊さんの他には誰もそんなことを気にする者などいなかったのだが。
晴れたうつくしい陽光が教会のステンドグラスを通しておごそかに降り注いでいた。神父さまと詩音の待つ十字架の前に、父親に連れられたリサのウエディングドレス姿がしずしずと近づいていく。リサの左目尻の下に泣きボクロはなかった。
パイプオルガンがひときわ高く鳴り響く。列席者から拍手が沸き起こった。

親族のひとりとして最前列に立つ古羊さんには、向こうからやってくるリサの姿がぺらぺらした紙のように見えている。白く塗りたくった顔にまっ白いウエディングドレス。全身白いばかりの薄っぺらい紙人形が上体を揺らしながら一歩ずつ、また一歩ずつ、詩音を白い世界へ誘いにやってくる。
白くて光り輝く場所が詩音にはよく似合う。
古羊さんはそう思うことにした。そこに行けば、詩音はしあわせになれると云う。だったら悪いことじゃない。思う存分、しあわせになればいい。それがわたしの望むことだったんじゃないかしら。
父親から、白い手袋に包まれたリサの手が詩音の手へと移る。向きを変え、壇上に向かう二人の手はしっかりつながれたままだ。リサの頭を覆うベールにかすみながら、どこまでも流れる白いドレスのレースの川に阻まれて詩音が半分隠れてしまっても、古羊さんは、平気だ、と思った。
銀色の魚になって詩音は泳いでいく。いってらっしゃい。うんと遠くまで泳いでおいで。光り輝くひれの一端を自分が握り潰してしまったことを古羊さんは思い出す。でも焦りはしない。もし疲れ果て、泳げなくなったとしても大丈夫、あなたの還る場所はきちんとあるのだから。
神の御前で、二人は誓いの言葉を口にしている。
次の日曜日、新居にお呼ばれされる予定の古羊さんは、結婚祝いと引っ越し祝いをかねて何かプレゼントをしようとデパートの食器売り場を見てまわった。
最初はガラス製品のあたりを一周してみたけれど、なかなかしっくりくるモノが見つからない。西洋食器や銀製のカトラリー、そういうモノもあのマンションには似合いそうだが。
想像通り、新婚の二人は白を基調とした明るく清潔な高級マンションに引っ越した。リサの両親が費用のほとんどを肩代わりしたようである。だから古羊さんも新居の雰囲気に合わせたプレゼントをと考えていたのだが、いざ選ぼうとすると、もう同じモノがすでにあの部屋にはある気がしてためらってしまうのだった。
案外難しいものね。
古羊さんはつい眉間にしわを寄せ、むむむ、と唸る。
険しい顔つきの古羊さんに売り子は声をかけることができず、黙って見守った。もう一周まわって古羊さんがその場を離れた時にはちょっとだけほっとした。よほどの目利きか、ただの気むずかし屋か、どっちにしたってあまり話しかけたくないタイプの客であることは間違いなさそうだったからだ。
次に古羊さんは隣の和食器のコーナーに移動した。やっぱりこういうほうが落ち着くのだ。古羊さんは眉間の力を抜き、ゆっくりひとつひとつを見てまわる。
ふと目を奪われて立ち止まった。
それは有田焼の夫婦湯呑みで、どちらもやわらかい筆づかいで桜の絵つけが施されたモノだった。男性用の大きな湯呑みには淡い藍色の、女性用の小ぶりの湯呑みには薄紅色の桜の花が描いてある。仰々しくない控えめな色合いが上品で、古羊さんはいっぺんで気に入ってしまった。それから他の食器も見てまわり、もうひとつ、白磁に黒鉄色の水玉がぼつぼつと浮いてる、大きな盛り鉢を手にとった。こちらはどちらかというと軽薄で下品な模様でありながら、何ということもなく心惹かれるものがあった。
しばらく考えてから、古羊さんは近くの店員に声をかけた。落ち着いた感じの男性店員は、古羊さんが指さす夫婦湯呑みと盛り鉢の両方をレジに運び、訊ねた。
「どなたかへの贈りモノでしょうか」
「ひとつは結婚祝いの品なんです。もうひとつは自宅用で」
「さようですか。でしたらお祝いの品のほうは、プレゼント用のお箱にお入れいたしましょう」
「お願いします」
古羊さんは軽く頭を下げ、店員が準備してくれている間、ぶらぶらと他の商品を眺めて待とうとした。
「あの、お客さま」
行きかけたところを呼び止められる。
「一応、お箱のご確認と、あと包装紙をお選びいただけますか」
「あ、すみません」
意味もなく謝った古羊さんはレジ横の台に店員が用意してくれた箱を見て、わずかに眉をひそめた。
「その大きさで入るかしら?」
「ご心配には及びません。これはそちらの夫婦湯呑み専用のお箱でございますから、ピッタリの寸法にしてあります」
自信たっぷりに答える男性店員を見て、古羊さんは「いえ、違うんです」と困惑した様子で小さく頭を振った。
「ごめんなさい。そっちじゃなくて、こっち。ええ、こっちが贈りモノなんです」
古羊さんが指し示したのは、白磁に黒い水玉模様の盛り鉢のほうだった。
店員が丁寧に包んでくれた二つの箱を両手に抱え、古羊さんはよろよろと家路についた。けっこうな重さである。帰る道すがら、盛り鉢のほうを指さした自分を瞬間、奇妙な表情で見返した店員の顔を古羊さんは思い出していた。
何かわたし、変なことをしたかしら?
考えてもよく判らない。盛り鉢を結婚祝いにするのはいけなかったのだろうか。それならそうと教えてくれてもよかったのに。
でももう買ってしまったのだから仕方がない。次の日曜日にはこれと、何か気のきいたお茶菓子でも持参するしかあるまい。
「結婚って、いろいろ面倒よね」
思わず口からもれる。自分がした訳でもないのに、面倒なモノが何より苦手な古羊さんは「結婚」にまつわるもろもろを、「ご免」な範疇に属する中でも最上級の位置に据えることに決めた。
気のきいたお茶菓子、というのがまったく思い浮かばなくて途方に暮れる。盛り鉢は目にした途端、これにするべきだと何かが自分に囁いたのだ。ふだんの古羊さんは優柔不断なほうだった。
どうしてあれを選ぶことにしたんだっけ。
お茶菓子について悩むのが嫌になって、古羊さんは盛り鉢について考えることにした。納得のいく答えが見つかれば、この両腕にかかる重量が少しでも軽くなる気がした。
突然、天啓のようにひとつの単語が閃く。
ホクロ。
そうか、そういうことか。白に黒の水玉模様。あれはリサのホクロだったんだ。へええ、そうか。古羊さんはちょっと嬉しくなった。理由が判ったからといって、荷物が軽くなることはなかったが、ホクロか、へえ、ホクロね、と考えているうちに思いのほかはやく家に到着することができた。
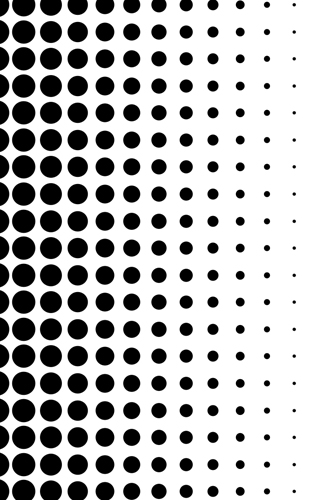
玄関のドアを開けて家に入り、お祝いの箱を六畳の部屋の畳の真ん中に置いた。一階の部屋はあと四畳半の部屋と小さな台所、二階は六畳の部屋が二つ。決して広いとは云えないが、詩音のいなくなった今、ひとりで暮らすには申し分ない広さだった。
古羊さんは買ってきたもうひとつの箱をさっそく開け、自分用の湯呑みをざっと水洗いし、ひとり分の湯を沸かした。待っている間に男性用の湯呑みのほうを取り出すと、大事そうに胸に抱き、それから茶箪笥にそっと閉まった。
緑茶を淹れた湯呑みを持って、縁側に腰を下ろす。そうして猫の額ほどの庭を眺めながら、いつもよりさらにゆっくりとお茶を啜った。
 横書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
横書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ふうらり、ゆれる』は毎月05日に更新されます。
■ 片島麦子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







