 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(九)象のお腹(下編)
「ハーイ」
まるでアメリカ人みたいな陽気さで、そのバックパッカーが呼びかけてきた。象の上から振り返った和也に、ワーオと青年は大げさなゼスチャーで腕を広げて見せた。あの山道を登って来たせいで、全身汗まみれだった。
「驚いたな、もしかして君日本人?」
「ええ、そうです。カズヤといいます」
和也もまた懐かしい気持ちにかられて答えたのだった。こういう場所で遇いたくない日本人というのもあるが、ハルはまったくそういうタイプじゃなかった、と和也は言った。たぶん、会った瞬間から吸い込まれていたんだと。
「そうかい、カズ。ぼくはハルだ。この近くにあるカレン族の村を目指してる」
青年は快活にそう言った。
「何を言っているのか」
と先生役の少年バボディが問うた。だから、君の村へ行きたいと言っているとたどたどしいカレン語で答えた。半年たってようやく、少しばかり言葉での意思疎通が図れるようになっていたのだ。
「乗せてあげよう」
バボディが言ったので、ハルを象に上がらせた。
「思えばあれがすべてを象徴していたんです」
和也が述懐した。
「だって、ぼくたち二人は、ウライの象に一緒に乗ったのでしたから」

象の背中に乗るや、ハルは歌を歌い始めた。聞いたことのない不思議で陽気なメロディだった。なんという歌かと尋ねたら、
「いま思いついた歌だからわからない」
そう答えた。
「そして、もう忘れちゃったから二度と歌えないだろうね」
さらにそういって笑った。その瞬間に、もう和也は落ちていたというのだ。恋というわけではない。友情というのでもない。ついに探し求めていたものを見出した。出会うことができたという歓びだったという。
カチリという音を立てて、何かがみごとに符合した。噛みあった。その時はそう思って疑わなかった。
実際、ハルの行動は破天荒で、気まぐれだったけれど、いつだって陽気で前向きなものだった。村の言葉も一か月もたたないうちに驚くべき速度で習得してしまった。身振り手振りを交えているとはいえ、自分にはまだ到底無理だと思われる冗談さえ口にして村人を笑わせているハルの姿を見ているだけで、和也は幸せな気持ちになった。
やがて、自分が思いを寄せていたウライもまたハルに惹かれていることに気付く。自分があてがわれたのよりずっと立派な高床式の住居に、ウライが夜昇って行くのを見たこともあった。奇妙なことに、ウライが家の中に入って行っても、歌声はやまなかった。かといってウライと二人で歌うというのでもなく、ずっと一晩中ハルの歌声だけが響いたのだった。それは奇妙なことで、和也はその秘密を知りたいと思った。
けれども、和也自身はどうしても、ハルの住居を訪れることができなかった。なんだかもったいないような、恐れ多いような気がしたのだ。
幸せな気分で半年ほどして一度帰国した。戻ってくるとハルはいなかった。和也はがっかりしたけれども、ある日ウライから、またハルがやってくると聞かされた。心のなかがポッと明るくなるのをはっきりと和也は意識した。そんな風にして一年半が過ぎ、和也にとってはラーオ村こそが世界でもっとも幸せを感じられる場所となったのだ。
奇妙なことに、和也のなかには、ウライとハルの仲を羨んだり嫉妬したりする気持ちは不思議と起こらなかった。むしろ、二人の幸せをこそ望んだ。二人が幸せになることこそが、自分の幸せだとさえ思えたのだ。
ところが、二度目の帰国をしてふたたび村に戻ったとき、ウライの表情は暗かった。和也は心配して声をかけたが、ウライは応じてはくれなかった。ハルの姿は村になく、和也は二人の間になにかよからぬことが起こったのではと心配した。
そんなある夜、ウライが困った顔で和也に告げたのだ。
「またあの人が来るわ」
「そうかい、それはよかった」
無邪気に喜んだ和也は、そう告げたウライの暗い目に戸惑った。
「どうしたの? 喧嘩でもした?」
ウライは首を横に振った。なおも問いかけていくと、ついにウライが意を決したような表情で和也に告げたのだ。
「お願いだから、あの人にもう村に来ないでと伝えてほしいの」
いったいどうして、と和也は問うた。
「わたしはあの人が好きだった」
「そうだね。ぼくだって」
「でも」
和也の言葉をウライの悲しみが遮った。
「あの人は裏切っていた。わたしを、いえわたしたちを」
そして知らされたのだ。和也が実はアメリカの巨大製薬会社の研究員だということを。和也がこの村に来たのは、ヒッピー的な放浪の旅の途上ではなく、明確な資本主義的搾取の意図(「実際、少数民族の村に暮らしていながら、ウライはこういう表現を無理なく使える人でもあったんです」、そういう和也の表情は夢見る人のそれのようだった)を持ってのことだったということを。

「あの人は盗もうとしている。わたしたちの大切なものを」
「どういうこと?」
「わたしたちの体の秘密を」
ウライはそう告げた。遺伝子工学の知識がなかった和也にはそれが何を意味しているのか分からなかった。けれども、ウライの表情からはそれが相当重大なことなのだということは想像がついた。だから、
「わかった。ハルが来たら聞いてみるよ」
「聞かなくてもいい。とにかく、追い返して」
ウライはそれだけ言うと、くるりと背を向けて去ってしまったのだった。けれど、少し歩いてからウライは振り返ってこう告げた。
「わたしは、わたしなりの方法で闘うから。このままにはしておかないから」
その眉の間に刻まれた皺が、彼女の強い決意を示していた。何かよくわからないけれど、ただならぬことが起きた、あるいは起きようとしているのだと、和也にはわかった。
やがて、その翌々日にハルがいつものように陽気な笑顔で現れた。村人たちは変わらぬ彼を歓迎し、和也も若干複雑な思いを抱えながらも、またハルに会えた歓びに胸が躍るのだった。
その夜、和也は意を決して、歌声が響くハルの家を訪れた。そして、初めて知ったのだ。歌声が、スピーカーから再生されるものだったということを。よほどよい機器を用いているのだろう、その声音は生音のやわらかさや響きを失うことなく部屋の外へと流れ出ているのだった。そして、
「やあ、来たね」
朗らかにそう口にしながらも、ハル自身は、簡易テーブルの上に設置した電子顕微鏡のような装置を熱心に覗きこんでいて振り返りもしなかった。

「君は微生物の研究者なんだって?」
ああ、ウライから聞いたか? なんでもないことのように、ハルは問い返し、和也はうなずいた。
「正確には、微生物じゃなくって、遺伝子だけどな」
「へえっ」
和也は感心した。
「そんなものが見えるのかい?」
「いや、これは違う。もっと別のお宝がないものかと、植物の細胞を見てたところだ」
でももう望み薄だなとハルは笑った。この村で手に入れるべきものはすでに手に入れた。だから、そろそろお別れのときだと。
「どういうことだ」
和也は問うた。
「そういうことだよ。ぼくは前回の滞在時に、この村で大変すばらしいものを発見した。いや、手に入れた。だけど、忠実な社員としてそれを会社に送ることはしなかったんだ」
「というと?」
「決まってるじゃないか」
当然だろ、という顔で春山が微笑む。
「交渉したんだよ」
「交渉?」
「ああそうさ。本国に帰って本社とやりあってた。この貴重な遺伝子を、社としてはいくらで買う意志があるかとね。誠意のある金額を示してもらえなければ、他社に持っていくつもりだって」
にわかには信じられない話だった。会社の社員が、自分の会社に対して脅迫まがいの交渉を持ちかけるなんて。親方日の丸的な、あるいは疑似家族的な日本的経営しか知らなかった和也には驚きだった。
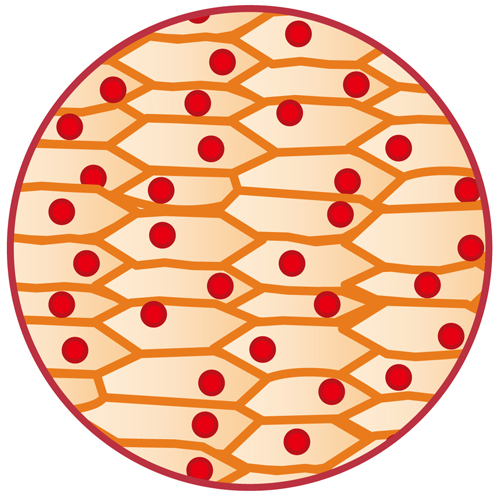
「それで?」
問うた和也にハルは答えた。
「むろん、うまくいったよ。ぼくは今や常識的には想像できないほどの金額を手にしている。一生遊んで暮らせるってレベルをはるかに超えたマネーをね」
「そうなのか」
和也のなかのハル像がぐらついた。こんな人間を自分は信奉してきたのかと自分を疑った。
「でもひとつ厄介ごとが起きたんだ」
「なんだい?」
そう問うた和也だったが、
「ああいや」
とはぐらかされた。
「失敬、カズ。今のは失言だ。ぼくはどうやら君に少し気を許しすぎたようだ。どうか忘れてくれたまえ」
自分の秘密を知られたことにも、何の頓着も見せずにハルはそういった。
「君とも短い付き合いだったけど、今後ともあれだろ、君はこの村に来るんだろ? まあ、楽しくやってくれたまえよ。気のいい、扱いやすい原住民たちだからね」
怒りがこみ上げた。今自分はこの男を殴るべきなのだと感じた。この男のスピーカーを破壊し、この男の顕微鏡を破壊し、この男が裏切りで手にした預金の通帳を引き裂き、そして村中にこの男の正体をバラすべきなのだと感じだ。
「でも、自分にはできなかったんです」
和也はそういって肩を落とした。
「どうしてなのかはわかりません。ここまで真実が露わになっても、わたしは彼を必要としていたのかもしれません。幻想の中の、彼が作り上げた虚構のイメージの彼こそがわたしが生きていくためのよすがとなっていたからでした」
なにもできぬまま、和也はハルの家を辞し、自分の部屋に戻って夜通し煩悶した。その結果、早朝に眠りに落ちてしまい、目を覚ますのが遅くなってしまった。
翌朝遅くに目を覚まして、広場に向かう途中、あの騒ぎが起こった。ウライが、自分が大切にしていた象の暴走で死ぬという事件が。
「そのとき、なにもかもが明確になりました」
和也が言った。
「もう得るもののない村に、ハルが何をしに戻ってきたのを悟ったのでした」
大学まで出ていたウライだからこそ、そしてハルの近くにいたウライだからこそ、ハルが何をしようとしていたかに気付いたのだ。そして、世界へ向けて告発しようとしていたのではないか? その動きがあることをいち早く察知したハルは、だからその張本人であるウライの口を封じるためにこの村に戻ってきたのではなかったか?
「わたしは激しく動揺しました。失ってはならないものを一度にすべて失ってしまったからです。途方にくれたわたしは一晩抜け殻のようになって過ごしました。そして夜明けになってやっと決意が固まったのです。ハルにすべてを問いただそう。そして謝罪してくれるよう願ってみようと」
そんな決意を秘めてはしごを降りた和也は知らされることになる。ハルが今朝早くに村を出たと。
「だから、わたしも村を出ました。追いつこうと。そして、何かを取り戻そうと」
けれども、ハルの行方は杳として知れなかった。
むなしく帰国した和也は、しばらく抜け殻のようになって過ごした。何もかもなくしたと思った。自分にはもう何も残されていない、と。
そこにふい打ちのように訪れたのが、直感の飛躍のような解決策だった。つまり整形である。探しても見つからないのなら、作ってしまえばいい。自分がなってしまえばいいじゃないか。自分がハルになってしまえばいいじゃないかと。
「理屈では説明がつかない。それはわかっています」
和也はそういった。
「でも、あの時のわたしにはそうするしかなかった。他に方法を思いつかなかったのです」
ハルの顔を獲得した和也は、その上に元の自分の顔を被せて暮らした。和也としての素顔の下に、ハルの顔を人知れず持っているということが和也の喜びとなった。
夜家に戻って一人になったときには、仮面を脱いだ。つまりハルとなった。そしてハルの顔となってウライのために作った仏壇を見つめた。仏式というのはおかしいかとは思ったが、日本ではこういうものしか手に入らなかったし、自分がウライを弔うにはこれが自然であるように思われたのだ。

「わたしは毎日ウライに謝罪しました。和也としてではありません。ハルとしてです。そして、こうささやきました。愛しているよ、ウライ、と。そのとき、わたしはどこにもいなかった。ふにゃふにゃの皮のようにめくれ返ったシリコンの仮面だけがわたしでした。わたしは、わたしを、床に無造作に投げ捨てたのです。当然でしょう。わたしにはなんの意味も価値もないのですから。どうでもいいわたしは消してしまって、わたしはハルとなった。ハルとなって、ウライが唯一見つめていたハルとしてウライを弔いそして、愛したのでした」
(第24回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







