 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(九)象のお腹(中編)
これは意外だった。種山がまだ何も言わないうちに、春山氏が状況を自ら説明したのと同じだったからだ。間違いない。春山氏は、種山の推理通りの行動を取ったのだ。
でも、それに対する種山の返答は、わたしの頭をぐらぐらさせた。まるで、怪力で持ち上げたお地蔵さんでぶん殴られたほどの衝撃だった。なんでお地蔵さんなのかはわかんないけど、なんかそれくらい違和感があったのだ。
「そうです、そしてあなたは殺されたのです」
「ええええっ」
でしょ、でしょ? わけわからんんんんんんん~~~~、でしょ? 気でも狂ったのかって、耳を疑うでしょ?
「先生、大丈夫ですか」
まったくもう、そんなわけのわからないことを、ってたしなめようとした。でも、言えなかった。だって、眼の前で、カメレオン現象が起っちゃったんだもの。まさにカメレオンが変色するみたいだった。春山の顔色が急激に変化したのだ。ざざざざあっと青ざめた。寄せる波のように。あれぞ、まさに「ディス・イズ・驚き」という表情だった。
なに、どういうこと? 殺された人がなんでここにいるわけ? ゾンビなのこの人もしかして? なんとか言ってよ種山あ。説明義務だよ、説明義務ぅ。でも、そんなわたしの混乱混戦混雑混沌混迷状態には無関心に、種山の口調はいたって平板だった。そう例の講義調ってやつ。
「春山さん、あなたはおそらくまず頭部を鈍器で殴られて気を失ったのでしょう。頭部ならば、後で切除してしまうことになるから、多少の傷が残っても問題なかったわけですからね。
あるいは、強力なスタンガンで電気ショックを与えられたのかもしれません。アメリカ軍の使用しているスタンガン等は、三十から四十アンペアも出るものがありますからね。百アンペアだと人は即死してしまいますが、三十から四十ならば、確実に意識を喪失させうるはずです。
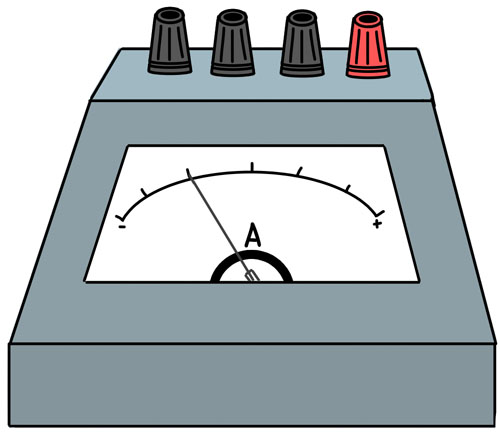
いずれにせよ、あなたは気を失った。気を失ったまま連れ出された。次いでどこか屋外の壁にでももたせかけられ、そこに象の足を前部に装着した車で刻印を押された。すなわち、腹部に象の足をめりこまされたのでしょう。それから、その車で三頭山まで運ばれ、和也氏の書斎に連れ込まれた。そして頭部を切断され、部屋のなかに放置された。フローチャート風に言えばそういう流れだったのではなかったですか」
春山氏は両手を膝の上においていたが、その両掌でがくがくする膝を懸命に押さえつけていた。どんなに強く押さえつけても、膝のがくがくは収まらないのだった。
「どうしてわかったのです」
春山が、震える声で尋ねた。心底驚愕していた。
「あなたがハルさんに心酔していたからですよ。ハルさんになりたいほどに。いや、むしろこう言った方がよいでしょうか」
そういう種山の顔は、どこかしら受容的な面持ちだった。
「あなたは元のままの自分でいることにもはや我慢ならなかったのではないですか。誰かほかの人にならなければ自分を保てないほどに」
「参りました」
春山ががくりと頭を垂れた。膝の震えが止まった。
「さすがです。よくわたしが和也だと見破られましたね」
うへえっ。わたしの頭の上には、急遽森が出現していた。もちろん、生えていたのは、ただの木ではない。驚きと桃の木と山椒の木である。以前中野の喫茶店で、和也氏が突然滋郎氏に変身したときも、確かにパンクっぽく髪の毛が逆立つほどに驚いた。でも、今度は驚きを超えてむしろショックだった。双子ならまあ、ありうるかとは思う。けど、似ても似つかぬ人間同士が入れ替わるなんて、ないでしょこれ、普通は。
「あなたたちは、体格がよく似ていた。顔つきは違ったけれど、今は医学が進歩していますからね。きっとどこかに大金を支払われて知らんふりを決め込んでいる整形外科がいるのでしょうね。
それだけじゃない。もう一人、協力者がいたはずです。シリコンかなにかで和也氏の顔を作った技術者がね。つまり、あなたは自分の素顔をまず春山氏のそれに成形した。その上で、成形した顔の上に元の自分の顔を重ねるという奇妙な重ね書きを行ったわけです」
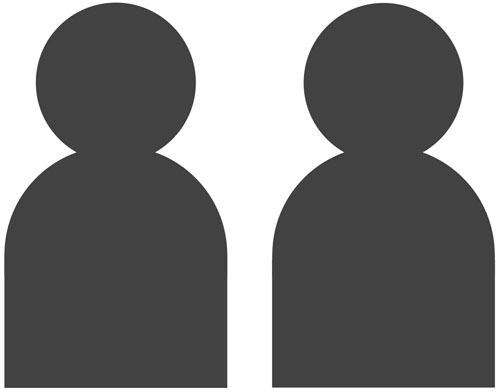
「そんなバカな。いくらなんだって」
わたしには意味がわからなかった。それなら、元の顔のままでいればいいじゃない。
「それに、仮面なんてしょせんは作り物でしょ。ばれちゃうに決まってるわよ」
でも、種山は落ち着き払っていた。
「いいえ、そうでもないんですよ。確かに、一昔前なら、こんな話は荒唐無稽なマンガ的設定だったかもしれません。でも現代の技術、たとえば立体写真造形技術などを使えば、毛穴までそっくりな仮面が作れるんですよ。実際アメリカで、これを利用した事件があったくらいなんです」
「どんな事件だったんですか?」
「銀行強盗でした。防犯カメラにはフードを被った黒人の顔が映っていた。でも、逮捕されたのは白人の青年だったのです。つまり、彼は黒人の顔そっくりなマスクを被って犯行に及んだっていうわけです」
「白人が黒人の仮面をかぶって犯罪を行うってことは、そこにさらに人種差別的なものが重ね書きされているってわけですね」
春山、いや和也氏、いや春山氏の顔をもつ和也氏が口を出した。
「そうです」
うなずく種山。
「いろいろ複雑なんですよ、顔を変えるってことがはらむ意味は。自分が自分のお面をかぶるとなるとそれはさらにややこしいんです」
確かにややこしやあ、ややこしやあ、って感じである。でも和也さん、あなたはなんだってそんなややこしいことを。
わたしは、いつの間にやら自分が種山の解説のつづきを楽しみにしていることに気付いた。なんてこった。こんな境地にまで連れ来られてしまったとは。
そんなわたしの感慨をやはりスルーして、種山は本筋に戻った。
「ワゴンを押してこの会社に配達に来たとき、あなたはすでに整形した後だった。そして、逆に和也氏の仮面をかぶっていたのではないでしょうか」
無言でうなずいた。種山に正体を暴かれたことで、完全に戦意を喪失してしまったようだった。

「お見せしましょう」
そういうと、さっきまで春山氏であった和也氏(だから、ややこしいって!)は、すっと立ち上がった。そして、机の引き出しからびろびろしたものを引き出してきた。
「これが、そうです。そっくりにしてもらうのに、ずいぶんと時間と金をかけました。昔映画の特殊効果を担当していたものの、CG全盛の時代になって失業してしまった職人のY氏という方がいるのです。でも彼は会社を立ち上げて、写真から3Dのリアルマスクを作り出す技術で今脚光を浴びているんですよ。ってまあここまで言うと人物が特定されてしまいますね。まあ、ここだけの話ってことにしておいてください。整形外科のU氏も、その方からの紹介だったんです。映画俳優や歌手などの芸能人を主な顧客としている方で、秘密厳守が第一という方でした。タイの村で一緒にとった数枚の写真をもとに、まずY氏がコンピューターを使って立体像を作成し、それを元にハルのマスクを作りました。そして、そのマスクをなぞるように、U氏がわたしの顔をつくりかえてくれたのです」
微笑む和也氏の口元に微妙に不自然な皺があるような気がしてきたけど、これはきっと先入見で見ているから。だって、この話を聞くまでまったく気になってなかったのだから。
「おわかりにならないでしょうけど」
和也氏がつぶやいた。
「わたしはほんとうにうれしかったのです。自分が春山になった瞬間。ついにほんとうになりたかった自分を手に入れたと感じたものでした」
「しかも、それはずいぶんと以前のことだったのではないですか」
種山がそう問うた。
「今回の事件とはまったく無関係なほど以前では?」
「ええ」
和也がうなずいた。
「もう二年以上前のことになります。ハルが事業を始めて成功しているのを知った時のことでした。わたしはもういたたまれなくなって、即座に整形を決めたのです。同時に、元の自分でいるためのマスクも同時に用意してもらったのです。表面は以前のままの和也でありながら、深層においてはハルである自分というのが一番落ち着くあり方だったからです」
ってことは、弟の滋郎氏と入れ替わったとき、すでに滋郎氏とそっくりな和也氏というのは存在していなかったということだ。本来そっくりであるはずのものが実はそっくりではなかったのだ。逆に、似ても似つかないはずのもの同士がそっくりになっていたのだ。なんという奇妙なねじれなんだろう。その意味するところは、ごめんなさ~い、わたしには到底測りかねるものでございます。
なるほど、と種山はため息をついた。
「つくづく、あなたという人のアイデンティティは、不確かなものだったと言わざるをえませんね。自分というものに、どこまでも自信がなかったのでしょうね。事業の経営には、兄のペルソナを必要とし、そこでの失敗からの脱却には春山氏のペルソナを必要としたのですから。つまり、あれでしょう? 元の自分とそっくりな仮面をつくったのも、元の自分を維持しようという意志のなせる業ではなく、むしろ弟さんに拒絶されまいという、あるいはまた、春山氏になりたいと願うのと同時に弟のようでもありたいという相容れるはずのない願望の表現だったのではないでしょうか」
「なるほど」
和也氏はしばし沈黙した。

「あまり深く考えたことはありませんでしたが、確かにそういうことだったのかもしれませんね」
「いずれにせよ、あなたは名実ともにハルさんになり替わって見せたということですよね。血が通っていて、見かけもそっくりな兄との関係を捨てて、赤の他人とそっくりになることを選択されたのですから」
「その通りです」
春山、じゃないや春山に化けた和也が語り始めた。
「わたしは、いつも兄と比較されて育ちました。実務能力にたけた兄と、空想癖があり、現実に興味の持てないわたしはダメなやつとさげすまれてきました。弟が堅実で冒険しないながらも、篤実な経営の才を示すほどにわたしは立場をなくしました。
いたたまれなくなったわたしは、ある時は歌手をめざし、ある時は釣りに夢中になり、あるときからは海外を巡り歩いて珍奇な品物を買いあさってはそれを日本で売りさばこうと企てました。けれど、どの企てもひとつとして実を結んだものはなく、わたしは限りなく自分という存在に対して不確かになっていったのです」
「そこでハルさんに出会ったわけですね」
いまやハルさんの顔を持つ男は、そこで朗らかに笑った。
「そうなんです。ラーオ村にいったのはもともとは象が目的だったんですがね」
「象使いですか?」
「ええ、ある本を読んでいて、象使いの技術が、いまやタイでも希少になりつつあることを知ったのです。その瞬間、象使いである自分をわたしはイメージし、そのイメージに吸い込まれた。そして、象使いの技術を身に着けたいと思ったのです。それも、昔ながらの技法を伝承している少数民族の村で」
「それは、実を結びましたか?」
「ええ、それなりに上達はしたと思います。特にわたしにとってうれしかったのは、よそ者のわたしに自分の象のモーヒッカを快く貸し与えてくれたウライとの出会いでした。流暢な英語を駆使してわたしにカレン族の言葉を教えてくれたのもウライだったのです。美しく、そして気高く優しい。そんな女性をわたしはそれまで見たことがなかった。たちまちわたしは彼女に惹かれたのです」
「でもそこにハルさんが現れた?」
「ええ、そうなんです」
ある日、カズこと和也氏は、先生役のバボディとともに象に乗って材木を運んでいた。使うのが象だけに、ゆったりとした時間が流れていた。そんな二人の背中に、ギターと巨大な荷物を背負ったバックパッカーがふいに声をかけてきたというのだ。
(第23回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







