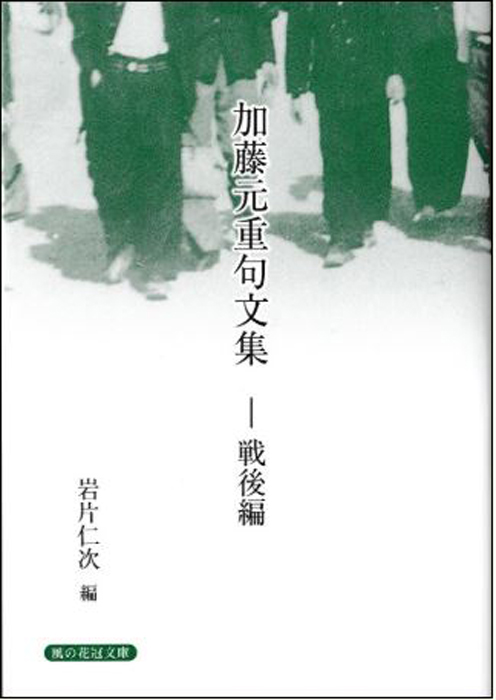
発行 二〇一八年三月十八日
定価 一五〇〇円(税抜)
発行者 鬣の会 代表 林桂
住所 〒371-0013群馬県前橋市西片貝町5-22-39
林桂さんが代表を務めておられる鬣の会から、風の花冠文庫の一冊として『加藤元重句文集-戦後編』が刊行された。加藤元重と聞いても、ほとんど誰もピンと来る人はいないだろう。僕もこの俳人の名を知らなかった。岩片仁次氏編の『重信表 私版高柳重信年表』は読んでいるから名前は目にしたことがあるはずなのだ。しかし高柳重信を巡る多くの文筆家の名前すべてを記憶しているはずもない。簡単に、かついささか乱暴にまとめれば、加藤元重は重信の早稲田大学時代の友人で戦後しばらく重信と俳句活動をともにしたが、やがて俳句からも文学からも離れてしまった群小作家の一人である。
こういった作家の文集がまとめられるのは珍しい。遺族が私家版で刊行しない限り、散逸して忘れ去られてしまうのが普通である。少なくとも自由詩や小説の世界ではまずこういった本は出ない。しかし俳句の世界は違うかもしれない。編者は岩片さんで巻末に「加藤元重略伝」を書いておられる。その中で「いつ頃であったか、『加藤元重集』を作ろうという思いがあって多少準備したが、そのまま歳月を重ねたためにいつしか散逸してしまった。よってやむを得ず現在資料として完備できる戦後諸篇によって本書を刊行することになった」と書いておられる。
言い添えておけば加藤元重は伝説上の人物などではまったくない。俳句からは離れたが重信晩年までかすかな交流があった。岩片さんも何度か加藤元重に会っている。しかしいつしか岩片さんとの交流も絶えた。『加藤元重集』を作ろうと思って連絡先を探したが、遺族がいるのか、いるとしてどこに住んでいるのかわからない。資料を探っても、加藤元重集の生年も没年も不明だ。岩片さんは「現時点では著作権継承者は不詳、故人・加藤元重集を著作権者として録しておく」と書いておられる。
ではなぜほぼ無名作家である『加藤元重集』が刊行されたのか。一つには重信前衛俳句の継承者である岩片さんや林桂さんの、重信研究の一環として必要だからである。また俳句文学の特性も影響している。前衛であろうと俳句は集団的営為である。仲間が寄り集まって作品と批評で切磋琢磨することで優れた仕事が生み出される。加藤元重は高柳重信が高柳重信となる若い時期に文学的行動を共にした人である。その記憶は重信の歩みとともに徐々に薄れてゆくことになるが、初期の仕事に影響を与えている。
優れた作家はみなそうだが、人生のある時期に知り合った文学上の友人知人を、言葉は悪いが踏み台にして自己の文学を作り上げてゆく。踏み台に、つまりは乗り越えるべき対象には当然年上の先行作家たちも含まれる。文学は同時代、あるいは先行作家の屍を乗り越えて先へ先へと進んでゆく営為である。特に詩の世界は死屍累々だ。優れた詩人など一世紀に数人しか出ない。では有象無象の有名無名作家の試みは無駄なのか。そうではない。ある時代を代表する詩人一人を生み出せばそれで良い。優れた詩人たちはそれを知っている。自分の仕事もまた、後進世代の踏み台になり乗り越えられるべきものである。ただできる限り良い踏み台であり、乗り越え甲斐のある仕事を残そうと願っている。
誤解を怖れずに言えば、加藤元重は反面教師として若い重信に影響を与えただろう。テキストを読む限り、若い頃の文学の同伴者としては十分魅力的な人だったと思う。人間的魅力があったと言っていい。だが悪魔のような文学者である重信は、この作家はいずれ脱落すると見切ってもいたはずだ。脱落者には脱落するだけの理由がある。文学者が仲間の屍を乗り越えて先に進むためにはそれを生活上の困難のせいにせず、文学の問題として捉える必要がある。
ようやくの東京住ひ迅雷
しやれのめすわがこのごろは夏暑し
むさし野のかなかなや若さ昂じるくる
真つ向を二百十日の大照日
東京の秋を呆乎と黙りゐる
町裏も雨後の気配や葉鶏頭
神よさらば桐の実冬の真昼月
早春の突風孤独日和かな
忘却もたまに地上へ流れ星
赤貧の唯一部屋の葦のずゐ
(「呆乎帖-昭和二十一年九月~二十四年十月」)
有季定型俳句ではないが、確信的な前衛俳句とも言えない。強いて言えば乱暴な句だ。その時々の感情の盛り上がりに即して吐き捨てたような手触りがある。当然だが句集以前の若書き作品ということになる。しかしこれらの句から若い文学仲間たちは、加藤元重の人間性をひしひしと感受しただろう。この作家には悪童の、悪ガキの雰囲気がある。それがある種の人間的魅力になっていたはずだ。しかし詩人としては繊細さに欠ける。詩人にとって最も重要な言語に対する美意識が不足している。
ほのほむら
(ひた恋う
恋う
来よ)
朱果実しなび
*
山 消えし
日の
こだまはつづく
*
しわがるる
そぷらの
しろい
橇
*
おかしの おばけ
おもちやの おばけ
ぱぱと
ままとの
なきべそ おばけ
(「回転木馬-昭和二十二年十二月~三十一年三月」)
これらの作品から、加藤が初期重信の多行俳句の同伴的実践者だったことがわかる。しかし多行俳句でも加藤の作風は乱暴だ。はっきり言えば多行〝俳句〟になっていない。俳句としての骨格が読み取れないのだ。多行になった途端、俳句文学の枠組みが崩れて溶け出してしまっている。これらは中途半端な自由詩だと言った方がいいだろう。骨の髄まで俳人である作家が書かなければ、多行形式は俳句になってくれないのである。重信は加藤の崩れを横目で見ながら〝俳人による多行俳句〟を模索してゆくことになる。
Ⅷ
ぐづで のろまで おたんこなす
ぼくの いふこと なんでもきいた
ぐづで のろまで おたんこなす
襟首 ふつと ゆらめいた
ちびで ぶしようで おばかちやん
ぼくの 身ぢかへ 来たがつた
ちびで ぶしようで おばかちやん
まあるい 胸で やつれてた
ぐづで のろまで おたんこなす
夜ふけの おはなし つづけたい
ちびで ぶしようで おばかちやん
もつと まぶたに きすしたい
ぐづで のろまで おたんこなす
ちびで ぶしようで おばかちやん
Ⅺ
ぼくは きゆんと だかれたい
乳房のあはひに 鼻をうづめ
ちえこの愛を 生かしたい
ひとりぼつちの ぼくなので
あんなに好きな ぼくなので
ちえこも どつかで 泣いている
生きているなら 化けといで
平気な顔しちや 死なれまい
ぼくをみつめて ふるへてろ
二人は 間抜けになつちやつた
(「もどかしい恋文」部分 昭和二十九年五月)
「もどかしい恋文」は加藤が最初の妻・千恵子を亡くした際に書いた追悼詩である。乱暴で悪ガキっぽい加藤の性格がよく表現された作品だ。その意味でストレートに読者の胸に響く詩である。しかしこれもまた素人の作品だ。絶唱ではあるが詩人として作品を書き続けるためのフレームがない。ただ加藤はそんな文学的骨格など、最後のところどうでもよかったのだろう。若い頃文学に親しんだ青少年が、皆最後まで文学に携わる義務などありはしない。より大切な何かを見つければ、多くの人が文学を捨ててそこに移ってゆく。その方が真っ当な人生だとも言える。加藤もそういった人の一人だ。ただこの優しく乱暴で愛すべき人の俳句からの脱落は、身近な人々に多くの示唆を与えたはずである。
おお、みなさん、おつたまげてはいけません。おつたまげたら、あなた方の負けです。(中略)
おお、みなさん、しかし笑つてはいけません。笑ったらあなた方の負けです。(中略)
おお、だが、みなさん、ウンチクを傾けてはいけません。(中略)マヌカンは模型人形、マネキン・ガール、転じて、案山子、デクノボウという意味のフランス語である。と多分述べたがるあなた方の唇を、芭蕉氏のハマグリのように固くとじなさい。そうすれば、マヌカンはマヌケの古代語であるとの悟りをひらいて嬉しくなることでありましょう。(中略)
おお、みなさん、けれど、愛しちやいけません。愛したら負けです。(中略)
おお、だが、みなさん、個独はいけません。個独は負けです。(中略)
おお、みなさん、さあ参りましよう。おひるを食べたら、「マヌカン」を買うんです。(中略)
おお、「マヌカン」をお買いになつたみなさん。「マヌカン」をショウガンする時には指をなめなめ、ページをめくることです。そうすればよだれを流す、さもみつともない姿をいんぺいすることができるでありましよ。
おお、しかし、みなさん。・・・・・・・・・
(「おお、みなさん、「マヌカン」を買いましょう」昭和二十八年九月)
「おお、みなさん、「マヌカン」を買いましょう」は、早川利康句集『マヌカン』の書評として書かれた。いかにも加藤らしい散文である。傲慢なほどの批評意識はあり、それに基づいて勢いよく走り出すのだが着地点が見えない。散文だけでなく俳句や詩でもそれは同じだ。早々と手をつけ書き出すのだが、作品はどこにも到達しない。彼の批評意識、というより不満は、いつしか最初の〝ではない〟という否定型に勢いよく戻ってきてしまう。この作家は少なくとも文学の世界で肯定すべき何事かを見つけられなかった。それが加藤の作家性と言えば作家性だろう。加藤元重が重信前衛俳句の渦中からいつしか消え、その朧な姿が今になって一冊の文庫本にまとめられることになったのは、なにかこの作家にはとてもふさわしい道行きであったように感じる。
鶴山裕司
■ 鶴山裕司さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

