 「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」
「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」
辻原登奨励小説賞受賞の若き新鋭作家による、鮮烈なショートショート小説連作!。
by 小松剛生
消防士の愛
アイロンをかけるということは、もしかしたら愛を語り合うことと似ているのかもしれない。それはただ単に僕が初恋の女の子に「アイロンの上手な男の人と付き合いたい」と言われた経験があるからというわけでは決してない、そう思いたい。
なぜなら僕はもう28歳で、アルバイトも含めれば3つ以上の違う職種についている過去があり、1年に1回しか会う事のない友人がいくばくか存在して、そのうち半分は入籍も済ませ、3分の1は子どもがいる。最近は自分が部屋を借りているアパートの、1階(僕は2階に住んでいる。そのアパートは2階建てだ)に住む年下の友人だってできた。彼は消防士で、去年の夏はアパートの屋上を囲う柵越しに、遠くにみえる花火を一緒に眺めた。
そういう人間、足跡を舐めれば一種の苦みを帯び始めるような28歳である僕は、初恋の女の子のことなんて忘れるべきなのだ。
少なくとも僕はそう思う。
「気にしなくていいですよ」
消防士はそう言って僕を慰めようとしてくれている。別に慰める必要なんてこれっぽっちもないのに、だ。気にしてなんかいないし、慰めが必要なほど疲労や消耗してもいない。なぜなら僕はまだ28歳だからだ。
「気にしなくていいですよ」
消防士の欠点がひとつ、ある。
彼は人の話を聞かない。
何をするにしても、最初のとっかかりが大事だと思う。
洗濯ロープに吊るして乾ききったお気に入りのシャツというのは、見る影もないほど無惨な姿になっている。シャツの死体、僕はこっそりそう呼んでいる。無数に切り刻まれた皺だらけのそれを僕は神聖な気持ちでアイロン台(28歳の独身の男がもつにしてはちょっとした代物だと思う)の上に横たわらせる。
まずは袖からアイロンを当てるのが僕のやり方だ。
最初のひと押しで、生地の焼けるような何とも言えない香りが部屋中に立ちこめる。その瞬間、僕は世界が止まったかのような錯覚を覚える。いや、たぶんあれは本当に止まっている。雪の降る午後よりも静かな瞬間だ。郵便夫の鼻の穴に雪の切片が潜ったときよりも静かだ。
彼女と最初にデートしたときもそうだった。僕はその頃いろいろと、髪型であったり体臭であったりファッションであったり、そういった諸々が気になる年頃で、自分専用の化粧ポーチが欲しかった。彼女にそれを告げると眉をしかめられ、古代ギリシャの哲学者のような厳かな表情を浮かべた。

「でもそれって、とても難しい」
「なんで」
当然、彼女は自分の化粧ポーチを持っていた。
「化粧ポーチとの出会いはね、奇跡みたいなもんなんだよ。探したからといって見つかるものでもない」
先輩の経験則というのは大事なアドバイスだ。
僕らは信号が赤になった横断歩道の手前で立ち止まっていて、彼女は肘組みをしながら僕を見た。哲学者に見られるのも悪くない、と僕は思った。
アイロンの1歩目はそんな風にして始まる。僕にいつも哲学者のことを思い出させる。
それは僕が28歳だからだ。
アイロンをかけるのは決まって晴れた日の休日だった。
その日が晴れてさえいれば、僕はどんなことよりもアイロンがけを優先させる。1度は選挙の投票日と時間が重なってしまったけれど、僕はアイロンがけを優先させた。民主主義でさえ、僕のアイロンがけをする時間を奪うことはできない。
「だめですよ、選挙には行かないと」
年下の消防士に叱られた。
ごめん、と僕は素直に謝った。
まるで郵便夫が自分の鼻の穴に雪の切片を散りばめさせるような時間を、基本的に僕はひとりで過ごす。アイロンがけを邪魔されるのは、他のどんな仕事を邪魔されるときよりも壮大な事件だ。世界は止まっている。だから僕はアイロンをかけるのだ。
けどひと息でシャツの皺をすべて取りきるわけでもない。物事には何にだって休憩が必要だ。
去年の10月、ある大学で行われた「DNAの形と、言語体系の構造が極端に類似している可能性について」という講義でも僕はそれを学んだ。話はあらゆるタンパク質の分子の結合から始まったのにもかかわらず、それはいつの間にか本道を外れていた。
「ロブスターには寿命がありません」
「それら甲殻類は脱皮をすることで、新陳代謝の低下を防いでいます」
「だからロブスターが命を落とす理由に老衰、というのはありえないんです」
「先日もカナダで巨大なロブスターが釣れたそうです。その年齢は推定ではありますが」
おかげで僕のノートにはDNAのことよりもロブスターに関する記載ばかりになった。
アイロンがけを再開しよう。
僕は今までいくつものシャツの皺を直してきた。
少し変な言い回し(なにぶん僕はまだ28歳なので許してほしい)になるけど、数えきれないほどの数を、だ。本物のランナーが人生の走行距離を数えないように、僕はそれらシャツの数を数えたことはないけれど、本当にたくさんの数になるとは思う。襟の部分にアイロンを当てるときは慎重に、それまでアイロン台に平行になるように動かしていたアイロンを少し斜めに傾げる。ランナーが接地する際の足裏を意識するように、僕はアイロンの爪先を意識する。

そういえば、彼女に贈ったプレゼントの数も僕は数えたことがない。
12月の寒い時期に誕生日が当たるので、マフラーだったり手袋を贈っていたりしたけれど、ある時ふと希望を聞いてみると彼女は言った。
「肉がいい」
それ以降、彼女への贈り物は近江牛のすき焼きセットになった。
「それで結局」
消防士は僕のグラスによく冷えた白ワインを注いでくれた。
「その女の子のこと、まだ好きなんですか」
いつも以上に彼は人の話を聞いていない。
たぶん、酔っているのだ。
僕がいつ初恋の女の子のことについて語ったのだろうか。
僕はアイロンについて、すなわち愛について語っていただけだというのに。
「いいじゃないですか、そんな意地にならなくても」
そろそろですよ、と彼は言った。
僕らは柵に寄りかかって、花火が上がるのをじっと待つことにした。
僕はまだ28歳だった。
おわり
漁師の孤独
ひとりの漁師がいた。
彼は魚を釣ってはいなかった。
でも他に彼を何と呼べばいいか、わからない。だからここでは便宜上、彼を「漁師」と呼ぶことにする。誰にだって名前は必要だ。
釣り糸を垂らしていたのは確かだ。でも彼の糸の先に「ウキ」は存在しなかった。彼が釣ろうとしているものはウキが動くかどうかで判断できるようなものではないからだ。
「釣れないねー」
隣に座っている女性がつぶやいた。
彼女は彼がまだ学生だった頃の知り合いだ。釣りに興味なんてないはずなのに、勝手についてきたのだ。追い返そうとも思ったが、今日の釣りは長期戦になることを覚悟していた。話し相手がいると気分がまぎれる。
「そんな簡単には釣れない」
「むー」
たぶん、彼女は釣りには明るくないのだろう。ウキがないことに何も言ってこない。周りに生い茂る枯れ草は朝露に濡れてどれも湿っていて、辺りの空気を冷やしていた。漁師の背筋が寒さで震えた。湿気は世界の敵なのかもしれない。湿度計は敵の動向を探すレーダーなのかもしれない。

「寒いね」
彼女はお尻をずらして彼に近寄ると、その肩に顔を埋めた。湿気が世界の敵だという可能性について、今は考えることをやめようと彼は決めた。判断は慎重にするべきだ。
テニス部にいた石原君、覚えてる?
うん。
結婚したんだって。子どもももうすぐ産まれるって。
そうなんだ。
実のところ、彼自身も自分が何を釣ろうとしているのか、具体的にはわかっていなかった。ただ自分が今は釣りをするべきだということはなんとなく知っていた。悲しいことに、人は自分のことをすべて理解できる生き物ではなかった。
「悲しい」
「え、なに」
「なんでもない」
見渡す限り、人影らしきものはどこにもいなかった。世界はふたりだけになったかのような気にもなる。彼女は立ち上がって水辺に近づいた。
「危ないよ」
「うん」
魚こいよー、と水面に向かって命令し始める彼女を漁師の彼は見ていた。彼女は自分の行動に疑問を持たないのだろうか。悲しいことに、人は自分のことをすべて理解できる生き物ではないらしい。
諦めて戻ってくる彼女に、彼は釣り竿を渡してみることにした。
「持ってみる?」
「いいの?」
彼女は嬉しそうに釣り竿を握りしめると、背筋を正してチベットに住まう高僧かのような神聖さで釣りを始めた。正座までしている。たぶんずっと持ちたかったのだろう。
真剣な彼女の表情を見ていると、なんだか少し申し訳ない気持ちになってくる。魚どころか、ザリガニだって釣れるはずがない。糸の先には何もついていない。餌すらない。
予想どおり、糸は静かに垂れるばかりだ。そのまますこし時間が経過した。
「釣れないね」と、彼は言ってみた。
「そんな簡単には釣れないよ」と言われた。
そのとおりだ、と彼は思った。
隈元君、引っ越したらしいよ。
へえ、どこに。
茨城だって。
なんで。
知らない。
「そろそろ行こう」
彼は道具を片付けることにした。
「まだ釣れてないよ、いいの?」
振り返ると彼女がじぃっとこっちを見ていた。丸い瞳にちょっと低い鼻がとてもチャーミングだった。

いいんだ、と彼はつぶやいた。
「もう釣れてた」
「え」
なに、なにが釣れたのとお尻を叩いてくる彼女を尻目に、彼は道具を片付け始めた。
「ねえなにが釣れたの」
「教えない」
帰り道、ふたりは駆けっこで勝負した。
彼女はサメのように走り、彼女が勝った。
「もう釣れてた」
負けた彼は、もう一度こっそりとつぶやいた。
おわり
勇魚
世界一、美しいくしゃみをする彼のなやみは、自分のくしゃみを見ることができない点にあった。
――悲しい。
彼はいつもそのことに心を痛めていた。
彼には確実にくしゃみの才能があったし、そのことを自覚もしていた。はじめのうちは、鏡に向かってくしゃみをして、その美しい瞬間をなんとかとらえてみようとしたものの、彼が鏡の中を覗くころにはその美しさはどこかに消えていた。ウェブカメラや、デジタルカメラでも無理だった。画素数の問題でもなかった。ある時から、彼は気づいていた。
結局のところ、くしゃみとはひとつの運動なのだ。
だからいくらデータ化しようとしても、肝心の本質はそこには残らずに「それっぽいもの」だけを残してどこかに霧散してしまう。
どこに。
どこかに、だ。
もうひとつ、気づいたことがある。
それは「1度として、同じくしゃみは存在しない」ということだ。プロ野球選手の投げる変化球だって、ひとくちに「フォークボール」と言ってもいろんな変化の仕方があり。いろんな握りかたがある。それと同じで、彼のくしゃみもするたびに、違う「落ち方」をした。
ある時はストライクゾーンからボールゾーンに激しく落ちるくしゃみだったり、またある時はよりバッター側に近い場所で急速に落ちたりもした。
快心のくしゃみをするたびに、彼は思った。
ストライク、バッターアウト。
スリーアウト、チェンジ。
*
彼は世界一のラッパーだった。
ラップを始める前から、なんとなく彼はそのことに気づいていた。
事実、六畳一間の彼が住むアパートの部屋の中では、彼は自由自在に韻を踏み、リズムを刻むことができた。
問題があるとすれば、彼はラップで世界を変えようと思うラッパーではなかったことにある。自分のラップを録音することはまずないし、そもそも彼は人前でラップをしたことなんてなかった。もちろんステージ上に立ったこともない。だから彼の友人たち(世界一のラッパーにだって友人はいるのだ)は、彼が自分のことを「ラッパー」だと言うたびに首を傾げていた。
彼には才能があった。世界を変える気もないのに、才能があったことだけは確実だった。
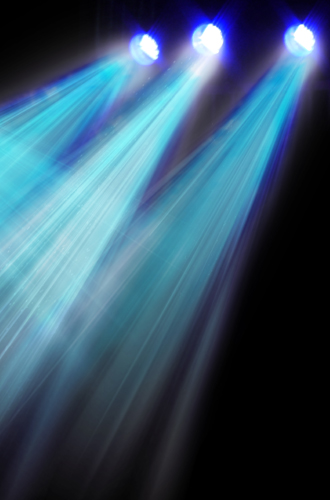
――悲しい。
世界を変えようと懸命に闘っている画面の向こうのラッパーを見るたびに、彼はそう思った。そしてそんな「彼以外のラッパー」のためにも、彼は自分が世界一であることを証明しなければならないと思うようにはなった。それは、進化とは言えないかもしれないけれど、変化と呼ぶには十分すぎるほどの代物だっただろう。
悲しいことがもうひとつ、あった。
彼のラップの良さは、ある種の臨場感にあった。
録音してしまうと途端に消えてしまい、それはどこにでもいるような凡庸なラップに成り下がっていた。なによりも孤独がその臨場感に絶妙なスパイスを与えていた。だから「ラップバトル」などで見られるような、大勢に見守られるなかで即興ラップを披露したとしても、味気ないものにしかならなかった。
つまり彼のラップは六畳一間という世界にしかいない、とても儚いものだった。ファウストの作った「ホムンクルス」という小人がフラスコの中でしか生きられなかったのと同じように、彼のラップは彼の部屋でしか生きられなかった。彼は自分のラップを「ホムンクルス的」だと分析することに成功した。
友人たちに、また首を傾げられた。
*
「古い映画を悪く言う奴は古い映画を観たことがないし、最近の映画をバカにする奴は最近の映画を観たことがないからバカにするんだよ」
「はあ」
彼は今、先輩と釣りに来ていた。
もっとも竿を握っているのは先輩ひとりだ。彼自身は釣り竿なんて持っていなかった。世界一の才能は持っていたけど、魚を釣る道具なんて買ったこともない。
「ほんとに釣れるんですか」
港には彼らの他に釣り人はもう1組だけで、その1組も遠巻きに眺める限り釣れる気配はみじんもなかった。
「勇魚」
「え」
「勇魚っていうサカナについて歌った曲があるんだ。不思議な曲でさ、たぶん歌詞を読むと勇魚を自分の恋人とか、たいせつな思い人に見立ててるんだけど、途中から人称が変化して、いつの間にか自分が勇魚になってる。そんな内容の歌詞なんだ」

「はあ」
「良い曲だよ、聴いてみろよ」
たぶんだけど。
先輩は僕を慰めようとしてくれているんだと、そう彼は感じた。
だから勇魚がクジラのことを指す別名で、だから魚というよりむしろ哺乳類なんじゃないかというような野暮なセリフを口に出すようなことはしなかった。
「勇魚、ですか」
「そう」
だからさ、と先輩は一向にアタリの来ない釣り竿を握りながら続けた。
「最近の映画、バカにすんなよ」
「はい」
「お前の才能をバカにする奴らと、一緒になっちゃうからよ」
「はい」
バカにすんなよな、と先輩は最後に小さくつぶやいて、それからふたりは海を眺めた。
*
さて。
先輩の隣にいる「彼」は果たして世界一美しいくしゃみをする彼だろうか、それとも世界一のラッパーだろうか。
僕はどちらでもいいと思う。
おわり
* この文章は、岩見拓馬さんの楽曲「勇魚」に強く影響を受けた結果、書くことができました。この場をお借りして、お礼申し上げます。
2016/10/21 小松
(第41回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
