 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
第05回 (二)象の頭
「姉からの伝言なんです」
そんな風にわたしは切り出した。真相は、伝言というよりはむしろ命令なのだが。まったく妹使いの荒い姉である。
立ち話もなんだなと思っていたら、ちょうどよい高さの場所が見つかった。ピンクのベッドカバーがかけられた回転ベッドである。わたしは躊躇なくそこに腰を下ろした。
「象が登場する事件、・・・ですか?」
「ええ」
指先で顎を撫でた。どうやら、少し興味が湧いたようだ。確認するように訊いてくる。
「もしや、犯人が象さんとか?」
「ええ、まあ」
種山は薔薇のつぼみが開くような笑顔になった。にっこおりとほほ笑んだ。
「うかがいましょう。なかなか興味を惹かれますね」
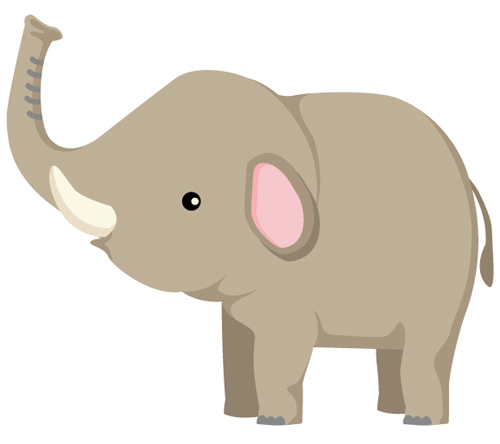
近づいてくる種山。そして、同じベッドの端に腰を下ろした。あれえ、先生それはちとまずいって。
「いいですか、先生」
「はい」
「まずは、密室です」
お約束ですかね、この辺りは。殺人現場となった小さな書斎は、窓にも扉にも鍵がかかっていた。おまけに、ご丁寧にも内側からからしか嵌められない閂までしっかり嵌められていたのだ。
「そして死体です」
やや平凡な組み合わせですなというコメントが、どこからか暗黙のうちに聞こえてくるような気がするけれど、きっと気のせいなのに違いない。
「被害者は会社経営の橘滋郎氏、四十歳」
「はいはい」
早く本筋に入れとせかす口調。
「場所は、東京都郊外の山荘。メモには東京都西多摩郡檜原村とありますね。三頭山という山の中腹にある山荘です」
「なるほど、被害者は温泉好きだったのですね」
「え、どうしてですか」
「その山にはラジウム温泉があったはずです。確か、日本一高い場所にある露天風呂とかもこの山にあったと思いますね」

「さては先生」
「ええ、温泉好きですよ。無類のね」
どうぞ、先を続けてとうながす風呂好きの大学教授。
「滋郎氏は、会社の経営にかかわる重大な決断を下す前には、いつも山荘籠りをされていたようです。なにしろ、仕事一筋で結婚もしていない自由な身でしたから、『ちょっと考え事をしてくる』とだけ秘書に言い残して、三頭山に向かったのだそうです」
「その重大な決断ってのが何かはわかっているんですか?」
「いえ、秘書にもはっきりとはわからないようです。ただ」
「なんでしょう」
「ここのところ、会社の経営が行き詰っていたというか、陰りが出てきていたのは確かだったようです」
「具体的には?」
「無理な拡大がたたったというか」
わたしは、面倒だなとは思いながらも、姉から聞いたことをかいつまんで話した。
橘滋郎は、本来は建築機材から結婚衣装まで幅広く貸し出しを行うレンタル会社であるユニヴァーサル・レンタル・ジャパンの経営者であった。昭和の初めに、祖父が建築機材のリース業を始めたことから今日へとつながるかたちの会社だったらしい。それが、二年前から新規事業として、ドローム・オブ・ヴイデオという名のCDやDVDさらにはゲームソフトやコミックスなどの娯楽用ソフトウエアのレンタルチェーンをオープンした。
「いまどきですか? ちょっと時代遅れでは」
と種山。そりゃそうだ。わたしだってそう思う。今やパソコンから音楽も映像も直接ダウンロードしてしまう時代なのだから、この時期に新しくソフト系のレンタル業を始めるなんて馬鹿げてると思う。
「でも、滋郎氏は、この時代だからこそ先行しているチェーン店から顧客を奪うチャンスがあるのだとみなしたようでした」
その商法がちょっとあざとい。それまでの堅実な事業機材や生活機材のレンタル路線とは打って変わった感がただよっていた。なにしろ、先行のビデオチェーンのある地域にわざと新店舗をオープンするというやり方なのだ。それでは競合してしまうはずなのだが、そこがあざといところなわけで、先行チェーンの半額以下の値段で商品のレンタルを行ったのだ。たとえば、先行チェーン店のTATSUYAがDVDを一枚一週間で三百円にしていたとすれば、ドローム・オブ・ヴィデオでは同じものを百円で貸してしまうというわけだ。
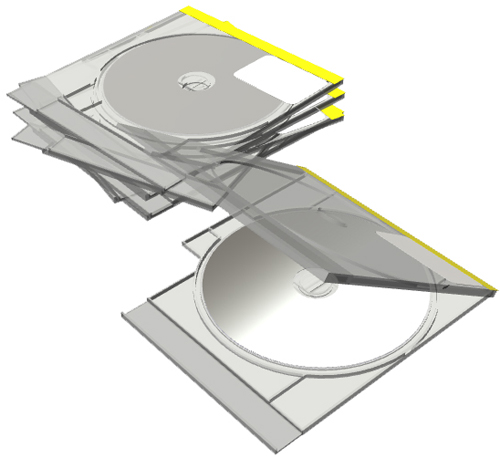
「まあ、回転さえよければ、それで収益はあがるでしょうけど」
と種山。その通りで、当初はそれなりに目論見が当たって顧客を奪ったかに見えたらしい。けれど、やがて先行していた店舗も値下げをしたり、商品の差異化を計ったりしてきた。結果、思ったほどには客を独り占めできず、店舗を増やしすぎたドローム・オブ・ヴィデオ部門は赤字に転化しつつあったのだった。
「他にも、スローフードの流行に眼をつけた飲食店もいくつか経営し始めたらしいですけど。まあ、こちらも最初だけ物珍しさで客が入ったものの、一、二店舗残したきりで漸次閉店の憂き目にあっていたらしいんです」
ああ、待って、ビジネスの神様。わたしを見捨てないでって感じである。
「ふーん、そういう場合に、相談できる人はいなかったのかなあ」
少し哀れに思ったのか種山がぼそりとつぶやいた。
「兄弟とか、親友とか」
「ああ、それはいたんですけど、だめですね」
「どういうことです?」
「なんというか、双子のお兄さんがいるにはいたんですけどね。でも、父親は、兄の和也さんではなく、弟の滋郎さんに経営を引き継がせた。まあ、そういうことです」
「つまり、経営の才覚がない人だった?」
「というか、それ以下ですね、お兄さんの和也ってのは」
びくりと反応する種山。もしかして、君も不肖の兄なのか? と問いたい気持ちをぐっと抑える。
「なんていうか、今風のヒッピーですね。、自分探しの人っていうか、あっちへふらふらこっちへふらふらなフラダンス的生き方だったみたいです。滋郎さんの所へ来ては金をせびり、その金でアジアへアフリカへ、そして最近ではヨーロッパなんかへ放浪の旅に出てしまうっていう感じの人だったようです」
「ビジネスに興味はなかった?」
「いえ、その辺はわかりませんけど、とにかく使えないというか、使いたくない感じの人だったようですよ」
「兄弟仲は」
「もちろんよくはなかったと思います。金をせびりに来るたびに怒鳴り声をあげる滋郎さんの声が秘書室まで響いていたといいますからね」
なんとなく、種山が気がひけた感じになっているのがおかしかった。いったい誰に感情移入してるんだか。わたしの推理では、絶対不肖の兄だよ、この人も。
「じゃあ、容疑者に上がったんじゃないの?」
「まあ、一応は。そりゃ、滋郎さんが亡くなれば経営権は和也さんのものになるわけですからね。でも、動機も成立しにくい感じなんですよ。だって和也さんは、むしろ現状維持で弟さんにたかってたほうが楽だと考えるタイプじゃないですか。その上、和也さんには完璧なアリバイがあったんです。その夜は、中野の自然食レストランで、スピリチュアル系の仲間たちとともに、世界の終末について論じあっていたようです」
「なるほど、いかにも週末向けの話題ですね」
「お店のオーナーから、他の客まで全員が証言しているのですから間違いありません。ちなみに皆で都合十本は開けたというワインはすべて有機ブドウから作られたものだったそうです」
「なるほど、孤独な経営者だったわけだね、滋郎さんは」
「よろしいですか、この話題については」
ずいぶん道草を食ってしまったと種山も気づいたようだった。
(第05回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



