Interview:ザ・ゴールデン・カップス インタビュー(2/2)

ザ・ゴールデン・カップス:1966年にヨコハマで結成されたロック・グループ。カップスはデビュー前に本牧のゴールデンカップというクラブで演奏していたが、メジャーデビューにあたりその名前をとってザ・ゴールデン・カップスとした。結成時のメンバーはデイヴ平尾(2008年に死去)、エディ藩、ルイズルイス加部、ケネス伊藤、マモル・マヌーの5人。その後のメンバー交代により、ミッキー吉野、林恵文、アイ高野、柳ジョージ、ジョン山崎がバンドに加わった。1972年に解散したが2003年に再結成し、映画『ザ・ゴールデン・カップス ワンモアタイム』(2004年公開)にそのライブの模様などがまとめられた。2017年3月3日にはデビュー50周年記念コンサートが行われた。
ザ・ゴールデン・カップスはコマーシャル的に言えばグループ・サウンズのバンドの一つだが、当初から他のバンドとは異質な本格的ロック指向を持っていた。また日本のロック・ミュージシャンやグループは、米軍基地があった横浜・横須賀のクラブなどから育っていった面があり、カップスはその代表的レジェンド・バンドである。実際、カップスのメンバーのほとんどがヨコハマ出身である。今回はデビュー50周年記念コンサートのリハーサルスタジオで、マモル・マヌー、ルイズルイス加部、エディ藩、ミッキー吉野、樋口 晶之氏にお話をおうかがいした。インタビュアーは小原眞紀子、寅間心閑、星隆弘氏である。
文学金魚編集部
■ミッキー吉野さん登場■
寅間 ミッキーさんがお出しになった本の中で、カップスのメンバーはそれぞれブレない自分のペースを持っているとお書きになっていたのが、とても印象的だったのですが。
ミッキー吉野 それはとても重要なことですよね。合わせようとすると、かえって合わなくなったりするから。僕はみんなより後にカップスに入ったメンバーだけど、今はどっちかっていうと、いかにバンドをまとめていくかっていう立場なんです。一番気をつけていることは、メンバーの顔を見て、たとえばある曲を誰かがやりたくない時は、それはやらないでおこうと気を遣うことです。一人でもやりたくないというエネルギーが出ていたら、それはやめておいた方がいいよね(笑)。だからカップスの基本はあまり強制しないことです。あくまで音楽は自由だというスタンスなんだな。ただ一番大きな妥協点は、お客さんからお金を取って演奏を見せるわけだから、そこだけはきちんとしなくちゃならない。
寅間 いろんな資料とか本とかを読むと、一九六〇年代から七〇年代にかけては、カップスの皆さんがやりたい曲と、シングル曲として発表する曲との間にギャップがあったとも書いてあったりするんですが、そのあたりはどうでしょう。
ミッキー それは好きでやっていた音楽と、仕事になる音楽との差のようなものだよ。それはいつの時代も変わらないんじゃないかな。ただ僕らの時代は学校で髪の毛の長さまで厳しく注意される時代で、そういう締め付けの強さは今の時代と違いますよね。お客さんがなんでいまだにカップスを見に来てくださるんだろうなぁって考えると、つまり彼らが一番何を求めているのかというと、カップスを見に来ると自分を解放できるからじゃないかな。昔からのカップスのファンの方が多いわけだけど、カップスを見に来ていた若い頃に、自分を解放できたという体験がベースになっているような気がします。それが当時のカップスの最大の存在意義だったんじゃないかな。カップスを見にいけば、騒げる、踊れる、心を解放できるってことです。まだまだ戦後で息苦しかった時代に、カップスが貢献したのはそういう自由な雰囲気、心を開く雰囲気を作り出したことだと思います。まあ本人たちは勝手に音楽をやってただけだから、結果としてってことになるけどね(笑)。

ミッキー吉野氏、ルイズルイス加部氏
星 ミッキーさんはカップスに加入される前に、バンドを外側から見ておられたわけですよね
ミッキー いつも見てたよ。だからリハーサルをやってる時でも、「これは昔こうやってたよね」とか言えたりする。そのくらい見てた(笑)。だから僕は一番客観的にカップスを見ることができるのかもしれない。
寅間 お客さんの前で演奏する時は、今と昔では違ったりするんでしょうか。
ミッキー 今見に来てくださるお客さんたちは、こっちが固くなって演奏してたりすると、かえって変に思ったりするんだよ。真面目にやってると、なに真面目にやってるんだよっていう雰囲気になってくる(笑)。
マモル 演奏し間違えた方がお客さんは喜ぶよ(笑)。
ミッキー まったくカップスを知らない人が見に来たら、なんてバンドだろうと思うだろうね(笑)。さっき言ったように、昔カップスを見ていた人が求めているのは心の解放だから、固くならないであるがままに演奏するのが今は一番大事だと思います。
寅間 今の方が、昔よりもやりやすかったりする面はないでしょうか。
ミッキー 昔の方が、今よりもっと戦いのような感じがしていましたね。テレビ局にしてもなんにしても、まず体制があって、いつも締めつけがある中でやっていたから、それと戦わされているという感覚はあった。
小原 ミッキーさんは若い頃はピリピリしてて怖かったから(笑)。
マモル 今はミッキーがバンドのメインだよ。リハーサルとかにしてもね。
ミッキー 演奏しててわかんなくなると、みんな僕の方を見たりはするよね。それはそれでいいんじゃないかな(笑)。
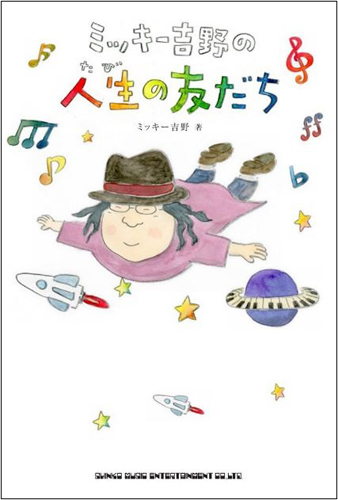
『ミッキー吉野の人生(たび)の友だち』
出版社:シンコーミュージック
発売日:2015/10/3
寅間 今でもなにかと戦っている感覚はありますか。
ミッキー それはないですね。カップスからゴダイゴの頃まで、ずーっと戦っていたという感じは確かにあります。なんで英語の曲を演奏するんだ、日本語の曲をもっとやれとか、そんなのはずーっと言われ続けてきたから。でも一番忘れちゃいけないのは、みんな音楽が好きでやってるわけだから、日本語の曲だとか英語の曲だとか、あんまりこだわっていなかったんだよね。たまたまみんなが気に入っていた曲が、英語の曲が多かっただけのことでね。それに対してプレッシャーをかけられるから、「なんだ」って感じで戦闘モードに入っちゃう(笑)。そういう時代だったんだよ。服だってそうでしょう。みんなお揃いのユニフォームを着て演奏する時代だよ。でもどっか切ってみたり、ちゃんとユニフォームを着たくないんだよね。学生の時だって、制服だとかにみんな何か細工したり工夫したりするじゃない。カバンをぺっちゃんこにしたりね。それと近いものがあるんだろうけど、社会に対する反発があったね。それはだけどロックンロールの基本だね。ロックンロールは親とか社会とかに対して、「なんだ」って反発するスピリットだから。
寅間 僕の感覚だと、二〇一七年の今の方が、どういう音楽をやるバンドなのかをきちんとわかって見に来るお客さんが、増えているように思うんですが。
ミッキー それはそうですね。昔はみんな同じテレビを見て、それに向かって世の中全体が盛り上がって進んでいったような時代でしょう。今はもっと個人個人が好きなものを選べる時代になった。そういう意味では日本が少しまともになった時代だと思います。でも今はまた少しおかしくなり始めているから、カップスをやるのもいいんじゃないかなと思います。今はなんか見えないプレッシャーが日本にかかってきたような気がするんです。カップスがやってるように、大事なのは心の解放なんだと(笑)。それをもう一回意識し直してもいいんじゃないかな。

『ザ・ゴールデン・カップス・リサイタル』
デビュー2周年記念の渋谷公会堂ライブ版(1969年7月20日)
マモル それがないとカップスらしくないね。
ミッキー あんまり政治のことは言いたくないけど、なんかわかんないうちにいろんなことが決まっていっちゃってる時代になってるよね。そうすると昔に逆戻りしているような感じがちょっとするんだよ。僕なんかは、本当に自由になりたいと思った昔の時代を経験してるからね。戦争は経験してないけど、ベトナム戦争とか、いろんな時代の雰囲気を知ってる。もしかすると、いきなりガツンとやられちゃう時代に向かってるのかもしれない。そういうことは、こういった機会をもらったときに、ちゃんと言っておかなければならないことなのかなと思いますね。
寅間 その世の中に広がっている抑圧的な雰囲気は、曲の歌詞に込めるとかということになるんでしょうか。
ミッキー それははっきり言ってダサイと思うんだよね(笑)。そういうことを歌詞に込めちゃいけない。音楽は自分自身の解放でもあるから、思い切ってやった方がいい。そこに政治であれなんであれ、社会的なメッセージを込めちゃうと音楽が小さくなっていってしまう。もっとワイルドになった方がいい。若いバンドがなんか狭く、小さくなって来ているのも、そういうところに原因があるんじゃないかな。バーンと破裂するようなバンドがいないじゃない。音楽が内にこもってきているような気がするね。それについても、もし僕なんかに発言権があるときは、言わなきゃならないのかな、警鐘を鳴らさなければならないんじゃないかなと思います。音楽はもっと自由なものだから。
星 そういう自由さを取り戻すために、必要なものはなんでしょうか。
ミッキー それはきっと、誰かが出て来て、証明というか、明らかにしてくれるよ。だから自由な音楽については実はあまり心配してないんだ。ただ世の中が、あまりいい方向に向かっていないことは、音楽を仕事にしている人たちも感じてるんじゃないかなと思います。また閉塞感のある時代にこそ、すごいエネルギーを持ったアーチストが出て来たりするものだから、それは期待していいんじゃないかな。

ミッキー吉野氏、マモル・マヌー氏
寅間 若いバンドのインタビューなんかを読んだり聞いたりすると、一九五〇年代、六〇年代、七〇年代の、いわゆるルーツ・ミュージックにあまり触れてきていないのかなと感じることが多いんですが、それについてはどうお考えですか。
ミッキー 僕はルーツ・ミュージックをちゃんと聴いている必要は、あんまりないと思うな。よく本をたくさん読まなきゃならないとか言うじゃない。でも読まないけど、タイトルだけ見ていくっていう学習方法もあると思うよ。音楽もそのくらいでいいんじゃないのかな。そんなの全部読んでたら、聞いてたら、一生は短いんだから無理に決まってよ。ジャズの世界ではスタンダードを全部演奏できなきゃいけないとかあるんだけど、それは本当に疲れるんだよね(笑)。
寅間 そういう学習と、楽器とかの技量を上げてゆくのはまた別の話だということですか。
ミッキー もちろんジャズにしろクラッシックにしろ、僕だってちゃんとやってないというコンプレックスはありますよ。でも気にしてたらきりがないからねぇ。それは飲み込んじゃうしかないかな。しょうがないじゃん(笑)。しょうがないじゃんってのは中国人っぽいかもしれないけどね。僕は見てていいなぁって思うだけど、中国の人たちには「しょうがないじゃん」っていうライフスタイルがあるんだよ。しょうがないって思い切って、できるだけ楽しく生きて行くしかないんじゃないかな(笑)。

『ベスト・オブ・ザ・ゴールデン・カップス ライヴ・バージョン』
ゴールデン・カップスのベスト・アルバムライヴ編
寅間 演奏なさっている時は、ご自身も解放されていますか。
ミッキー 一生懸命そうなるようにはしているけどね。でもすべてにおいてプレッシャーはかかるよね。ステージに立つときは緊張もするしね。だからいつも解放された状態になりたいという気持ちを忘れないようにはしています。解放はひらめきだからね。ひらめきがないと音楽は面白くないし、楽しくないよ。これでみんなに話は聞いたのかな。あとはマサユキ(樋口 晶之氏)か。彼が一番カップスを客観的に見ているかもしれないよ。
■樋口 晶之さん登場■
寅間 今ミッキーさんから、ステージで自分を解放することの大切さや、ほかのメンバーの皆さんからは、当時の洋楽とかについておうかがいしました。
樋口 晶之 昔の洋楽は、僕は実はそうとう好きなんですよ。ゴールデン・カップスに影響を受けてバンドをやり出した世代だから、今聞くとすごく懐かしいです。演奏しているときは、あんまり余裕がないですけどね(笑)。
寅間 カップスでプレイするときと、ほかでやる時は違いはありますか。
樋口 ほかでやるときは、やっぱり自分より年下が多いんです。カップスでは年上の方ばっかりだから、やっぱり緊張しますね。僕が小学生の頃に、カップスのメンバーはトップクラスで音楽をやっていましたからね。その頃見ていて影響を受けたバンドだから、演奏しててもなるべく迷惑をかけないようにしようと思っています(笑)。ハッピーなことだけど、プレッシャーもありますね。プレッシャーの方が大きいかな。誰でも子供の頃、見ていてうわーっと思った人っているでしょう。カップスは僕にはそういう人たちだからね。

樋口晶之氏
星 いろいろなミュージシャンの方と演奏されていると思いますが、ゴールデン・カップスの魅力とか、そういうものはありますか。
樋口 適当なんですよ(笑)。それがいいんですね。けっこうみんな適当なんだけど、本番になると気合いが入って、本番はばっちりなんです。僕が子供の頃も、ゴールデン・カップスはほかのバンドとは異質だったんですよ。洋楽が得意なバンドで、それで好きになったんですけどね。
星 五十年というキャリアを継続する秘訣ってなんでしょうね。
樋口 僕は四十五、六年のキャリアなんですが、カップスのみなさんはもう五十年以上やっていると思いますけど、なんだろうな、やっぱり音楽的なんですね。存在というか、人間のあり方がね。それが一番いいんだろうね。(リハーサル始まる)じゃあやります。
寅間 ありがとうございました。
(2017/02/20)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ ザ・ゴールデン・カップスのコンテンツ ■
■ ザ・ゴールデン・カップス『長い髪の少女』 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
