 「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」
「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」
辻原登奨励小説賞受賞の若き新鋭作家による、鮮烈なショートショート小説連作!。
by 小松剛生
ハンガーの話じゃないんだ
神様が新聞を読んでいる。
道端に捨てられた新聞紙を見つけたとき、空に向かって目一杯に広げられたそれらの紙片を、彼はそんな風に呼んだ。
「神様も政治経済に興味があるのかな」
「いや、神様は政治経済なんかに興味はないと思うよ」
わたしたちは今日、ハンガーを買いに街へ出てきた。
世の中にはハンガーを買うためだけに街に出る人たちもいるということを、みんなにも知っておいてほしい。
わたしたちがそれだ。
なぜそんなにも念を押すようにして言っておくかというと、わたしは彼と出会うまでハンガーを買うためだけに街へ出ることをしたことがなかったからに他ならない。
昨日の夜のことだ。
「出かけようか」
「いいよ」
「ハンガーを買いに行こう」
「うん」
「小さな弓みたいにくびれた、細いやつ、ポロシャツを吊るしておくのにちょうどいいやつ」
「いいよ」
わたしは彼の次の言葉を待った。
でも彼はわたしの返事に満足したように、さっきまで読んでいた本を再び開いて、狙撃手が狙撃用の銃に付けられたレンズを覗くかのように、一点に視線を集中させてしまう。
わたしは狙撃手を実際に見たことはないから、彼のその姿を見て、狙撃手を見たことにさせていただくことにする。
わたしだけの狙撃手。
「ねえ、狙撃手」
返事はなかった。
うちの狙撃手にはまだまだ自覚が足りないらしい。
その街にただひとつある博物館が、ハンガーの博物館だった。
そこには歴史上あらゆる場面で活躍したハンガーが飾られていて、偉人たちの使ったハンガーもあった。
例えばジョン・レノンが暗殺される前の晩に使ったとされるハンガー。それは木でできていて、彼の生前を思わせるようなパリッとした白いシャツがかけられていた。
例えばメルヴィルが使ったとされるハンガー。彼は『白鯨』を書いている間、ずっとこのハンガーを使っていたらしい。
例えばヴィンチェンツォ・ニバリのCM撮影用に背景として飾られたハンガー。彼のチームジャージと、彼が着たマイヨ・ジョーヌがそこに吊るされた過去もあった。
館内に人はほとんどいなかった。
静かで、わたしたちはそこで思う存分、たくさんのハンガーを眺めることができた。
人生の中で一番、ハンガーを眺めた日になったことだろう。
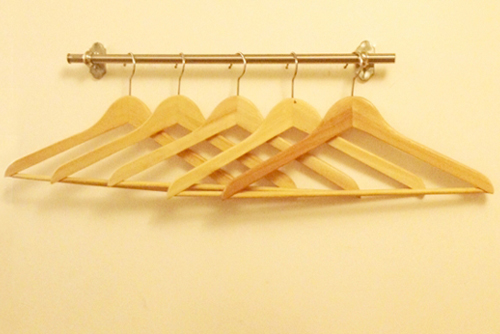
午後3時を過ぎたあたりで、備え付けの喫茶店に立ち寄ってコーヒーを飲むことにした。
彼はブラックを好み、わたしはミルク入りのやつをいつも飲む。
二人とも、砂糖を入れることはしなかった。
わたしはカップを斜めに傾けて、コーヒーを飲むことに集中している彼を思う存分、眺めることができた。
「なに」
「なんでもない」
わたしだけの狙撃手。
いったい、彼はレンズ越しに何を狙っているのだろう。
ハンガーのことだけを書いた小説というものがこの世には存在する。
作家の名前をジェールズ・バーン。
彼は1932年、当時イギリスの植民地だったセイロン島に生まれ、大学在学中に書いた長編『ほのかな光』にて一躍、世界から脚光を浴びた人物だ。
彼は住所を定めず、世界中のホテルを渡り歩く「ホテル・ライター」だった。
およそ自分の荷物をほとんど持たない彼が唯一、必ず持ち歩いていたものがセイロン島製のひとつのハンガーだった。
彼は自分と一緒に世界を渡り歩いたそのハンガーの物語を書いた。
原題を『It’s not about the hanger(ハンガーの話じゃないんだ)』というその作品は、執筆前から20カ国以上で発売が決められていて、あらゆる国の非凡な翻訳家たちは原文が渡される日を今や遅しと待っていた。
発売日は3度の延期と2度の検問をかいくぐり、ようやくにして販売解禁となったにもかかわらず、その3週間後にはありとあらゆる国で痛烈な批判を浴びることとなった。
ジェールズ・バーン最大の失敗作と呼ばれ、ジェールズ・バーンの小説に興味を示さなかった人たちまでがそれを手に入れることに奔走した。
皮肉なことに、ハンガーの小説はジェールズ・バーン最大の失敗作であると同時に、最大の売上部数を誇ることになった。
でも、僕はそれを失敗作だとは思わないんだ。
彼は博物館の売店に並べられた一冊の本を手にして、それをぱらぱらと眺めながら、わたしに言った。
「きっと、ジェールズ・バーンはハンガーを通して、どの言葉でもさし示せない領域や動向について、語りたかったんじゃないかなって、そんなことを思うんだ」
「ふーん」
「だから『ハンガーの話じゃないんだ』っていうタイトルになったんだ。そしてそれは決して駄作なんかじゃない。面白いかどうかはともかく、それはハンガー越しでしかできないことを、彼はやってのけたんだ」
彼はやけに熱心にそう語った。
冷静じゃない彼を見るのは、すごく久しぶりのことのような気がした。わたしは今日、ハンガーを買いに出かけて良かったと、心の底から思うことができた。
その人は。
「その人はハンガー越しに何を書きたかったのかな」
特に興味はなかったけれど、わたしはなんとなくそんなことを訊いてみた。
彼がわたしを見た。
わたしだけの狙撃手。
レンズ越しに彼が何を見ているのか、わたしは想像してみることにした。ひとつのレンズを二人同時に覗くことはできないから、わたしには想像することしか手段が残されてはいなかった。
その日、わたしたちは両手で抱えきれないほどのたくさんのハンガーを買った。
わたしは早くそれにシャツを吊るしてみたくて仕方がなかった。
ハンガーにシャツを吊るすためにわたしはさっそく洗濯機を回すことにした。世界中に存在するほとんどすべての服は、ハンガーに吊るされる前の服だということに今さらながら気づいた。
*
神様は言う。
「ハンガー、あれ」
そして最初にハンガーが生まれる。
ハンガーが生まれ、そして光が生まれ、光が生まれたことで影が生まれると聖書にはある。けれど、ハンガーと光の間にはきっと、服が生まれているはずだ。
ハンガーから作られたこの世界を、神様はどんな風に眺めているのだろうか。洗濯機から取り出した数枚のシャツを抱えて、わたしはベランダに出た。
空を眺めてみる。
誰かがレンズ越しにわたしを狙っているような気がした。
おわり
参考及び引用文献
『ただマイヨ・ジョーヌのためでなく』 著:ランス・アームストロング 訳:安次嶺 佳子(講談社 二◯◯◯年)
『フィンガーボウルの話のつづき』 著:吉田篤弘 (新潮社 二◯◯一年)
通話
彼女に電話をかける。
いま、いいかい。
「いいよ」
すると彼女は決まってその後に言う。
「いま、お風呂沸かしてるから、それまでならね」
僕も特に大した用事があるわけでもない。
ただ、彼女の声が聴きたくなった夜に電話をかけると、いつだって彼女はお風呂を沸かしていた。
偶然だろうか。
僕が電話をするたびに彼女はお風呂を沸かしているのだろうか。もしくは彼女がお風呂を沸かすから、僕は彼女に電話をしたくなるのだろうか。
勇気をだしてきいてみた。
「どっちなんだろう」
彼女は言った。
わかった、教えてあげる。
受話器越しの彼女の声はチェコのビールのように澄んでいた。
チェコのビールは飲んだことはないけど、そう思ってしまったのだから仕方がない。

「いい? わたしの家にはお風呂が24個あるの。それを1時間ごとにひとつ沸かしているせいで、あなたがいつ電話してきても、わたしはいつだてお風呂を沸かしていることができるの」
24個のお風呂。
「想像できない」
「でしょ」
彼女は言った。
「わたしがどれだけあなたの電話を待ちわびているか、これでわかった?」
「きみは」
「うん」
「いつもお風呂を沸かしてるんだ」
「そう、わたしはいつもお風呂を沸かしてるの」
彼女は言った。
「いつか冷めちゃうかもしれないけどね」
じゅうぶんだ。
おわり
さけるチーズに関する個人的なメモ
70日後のコーヒーを今飲むためにはどうすればいいか。
彼女はそれを考えながら、レシートがレジから出力されていく様子をだまって眺めていた。
目の前には彼がいた。
彼。
名前もわからないので、彼女はその男性のことをそう呼んでいた。
彼はいつも彼女の働いているこの時間にコンビニにやってきて、必ずビールの500ml缶をひとつ、さけるチーズをふたつ買う。
さけるチーズというのはさけているチーズのことを指すのではなく、そういう商品名で店頭に並んでいる商品のひとつだ。
彼女に言わせれば、およそすべてのチーズはそもそもさけるもののはずで、さけるチーズというのはチーズのことを言う。商品としてのさけるチーズは、世界中のさけるチーズの中のひとつに過ぎない。
でもそこにヒントが隠されているような気がする。
彼女は思う。
つまり70日後のコーヒーも、言ってしまえばコーヒーの一種にすぎない。コーヒーという大きな枠の中に70日後のコーヒーは存在する。
レシートが出力されてゆく。彼と一緒にレシートが出力されていくのを眺める。間抜けな顔だ、と彼女は思う。
そこに刻まれている細かい文字は、なんだかどこか別の世界への扉を開くための秘密の暗号のようにも思えるほどに小さいサイズを保っている。
店内を一日中冷やしている冷房には時を止める役割があるのかもしれない。冷たさは何かを保つための工夫で、それは時を止めるヒントだ。冷房が時間という概念に干渉するヒントになるのであれば、時間を超越するヒントも隠されているのかもしれない。レシートの出力は止まらない。彼は相変わらず間抜けな顔をしている。
さけるチーズに話を戻そう。
チーズはさけるチーズであり、さけるチーズと商品としてのさけるチーズは別のものとも、同じものとも言える。
それはメルヴィルの『白鯨』に残されたある定義に似ている。
いち、しとめ鯨は、しとめた者に属する
に、はなれ鯨は、だれにせよ最初にしとめた者に属する
あたかも二項対立かのように並べられているこれらは、ある種の状況を細分化させるために立てたれた定義にすぎない。
書簡だけ見ると、はなれ鯨とは、しとめ鯨と対を為す存在かのように並べられているが、ある種のしとめ鯨のことをはなれ鯨と呼ぶにすぎない。
はなれ鯨はしとめ鯨であり、はなれ鯨としてのしとめ鯨は別のものとも、同じものとも言える。レシートの出力は止まらない。彼は間抜けな顔をしている。
ここに冷たさの工夫を加えることで、70日後のコーヒーを今飲めるようになるのではないか。レシートに刻まれている文字、何かの暗号のような文字の羅列、そこにその方法が記されている可能性は高いのかもしれない。
缶ビールの値段が税込み271円。
さけるチーズがふたつで税込み381円。

それらの印字された言葉に冷房の冷たさが当てられることにより、どこか遠い海を泳ぐしとめ鯨ははなれ鯨になり、世界中のチーズはさけるチーズになる。コーヒーは70日後のコーヒーに変換される。彼は間抜けな顔をしている。
あれ、と彼女は首をかしげる。
何もかもが変換されたはずの世界で、彼だけが変わらずそこに立っていることを彼女は不振に思う。
「あの」と、彼が言う。
「はい」
「レシート、ください」
気づけば彼はビニール袋とお財布を片手に挟みながら、彼女がレシートを彼に渡すのをずっと待っていてくれたようだ。
「すみません」
彼女は頭を下げた。彼女にとってはもはやただの紙切れにすぎないそれを渡した。時が止まったはずもなく、ずいぶんと長い時間を彼は待っていてくれたようだ。
「いや、全然」
彼はそう言って、彼女が彼を待たせてしまったにもかかわらず申し訳なさそうに頭を下げながら店を出ていった。
彼女はひとり、カウンターの内側に立っていた。
よく見たら。
彼女は思った。
彼、そんなに間抜けな顔じゃなかったような気もする。
おわり
※この文章は、文学金魚さん主催イベントに際して公開された、ある女性の書かれた「リード小説」を元に、書いたものになります。この場所をお借りして、改めてお礼申し上げます。
(第22回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『僕が詩人になれない108の理由あるいは僕が東京ヤクルトスワローズファンになったわけ』は毎月24日に更新されます。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
