 その家は今から90年以上も前、大阪の外れに建てられた。以来、曾祖父から祖父、父へと代々受け継がれてきたのだが……39歳になった四代目の僕は、東京で新たな家庭を築いている。伝統のバトンを繋ぐべきか、アンカーとして家を看取るべきか。東京と大阪を行き来して描く、郷里の実家を巡る物語。
その家は今から90年以上も前、大阪の外れに建てられた。以来、曾祖父から祖父、父へと代々受け継がれてきたのだが……39歳になった四代目の僕は、東京で新たな家庭を築いている。伝統のバトンを繋ぐべきか、アンカーとして家を看取るべきか。東京と大阪を行き来して描く、郷里の実家を巡る物語。
by 山田隆道
第十七話
その夜、僕は大阪市内でロケを終えたあと、他のスタッフたちと食事をしてビールを二杯ほど飲んだところで、一人だけ先に帰ることにした。時刻はまだ午後九時を回ったところだが、とても二件目に繰り出す気分になれない。
御堂筋線に乗って終点の千里中央駅に着くと、駅構内のケーキ屋でエクレアを買った。このところ毎日のように来ているから、店員にすっかり顔を覚えられている。注文も聞かずに「エクレア五個ですねー」と言って梱包してくれた。
千里中央駅からモノレールに乗り換えて地元の駅に到着した。改札を出て帰路を歩く。二月も終わりだというのに、道路にはところどころ霜が降りていた。
やがて三丁目の交差点に辿り着いた。ここを左に曲がると昔ながらの古い一軒家が立ち並ぶ低層の住宅街に入り込むのだが、右側は比較的マンションやアパートが多い。僕の実家は左側にあり、僕が今から帰るアパートは右側にある。
去年の十二月、僕は妻子と一緒に実家を出て、現在の三DKアパートに引っ越した。築四十年以上にもなる古い木造物件のうえ、駅から徒歩二十分もかかる場所にあるから、家賃六万円と激安で、礼金もなしという破格の条件だった。
あのときはとにかく父から離れたくて、とにかく実家を出たくて、我ながら異常だと思うくらい焦っていたから、ひとまず緊急避難のつもりで引っ越した。ひとつだけ気がかりだったのは母を実家に残したことだったけど、それも近場だからなんとかなるという大雑把な理屈で自分をごまかしていた。
アパートに帰ると、今日も孝介の姿は見当たらなかった。実家のそれからずいぶん狭くなったダイニングでは、亜由美が一人でテレビを見ている。
それだけで状況がわかった。僕はダイニングから左右振り分け式につながった右側の部屋の襖を静かに開ける。薄暗い和室の中では、二つ並んで敷かれた布団の真ん中で秋穂が寝息を立てていた。このところの秋穂は孝介と同じ部屋で寝たがらない。まるで幼児返りしたみたいに亜由美にべったりする。
「今日も買ってきたの?」背後から亜由美の声が聞こえた。「エクレア」
「ああ。……なんかもう今さらやめられへんから」
僕は苦笑して、手に持っていたエクレアの袋に視線を送る。

「孝介、エクレア好きだったもんね」
「うん、幼稚園のころから一番好きやった。ケーキよりも好きやった」
「声かけてみる?」
「そうしたいけど……夕飯はどうやった?」
「いつもと一緒。ドアの前に置いてたら、いつのまにかなくなってた」
「そうか」
僕は溜息まじりに言うと、エクレアの袋を持ってダイニングを出た。子供用の洋室の前で立ち止まり、深呼吸してからドアをノックする。
「孝介」案の定、返事はなかった。「孝介」何度呼んでも一緒だった。
試しにドアノブを回してみたけど、やっぱりロックされていた。最初のころはこの事態に慣れなくて、強引にドアノブを引っ張ったり、ドアを強く叩いたりしたこともあったけど、今はなるべく刺激を与えないようにしている。
「エクレア買ってきたから、食べたくなったらドア開けろよ」
僕はそう言い残して、エクレアの袋をドアノブに引っかけた。

部屋の前から立ち去る瞬間は、いつも胸がざわざわする。本当にこれでいいのか。このままでいいのか。後頭部に鈍痛が走るくらい、あれこれ考えて、考え抜いた結果、孝介が好きなエクレアを毎日買ってくることしか思いつかない。
僕はどこでまちがったのだろうか。過去を振り返ってみると、あらゆるところに分岐点があって、そのすべてで誤った選択をしたのかもしれない。
別に我が子に高望みをしているつもりはなかった。学校なんか行きたくなかったら無理して行かなくたっていいとすら、今は思う。
アパートへの引っ越しは父に無断で進めた。僕はフリー稼業だから部屋を賃借できるかどうか不安だったけど、大家さんが理解のある人で助かった。「このアパートは古いから、ここんとこ空室だらけで困っててん。せやから、借りてくれてありがたいわ」とは大家さんの弁だ。保証人については保証会社を通した。
孝介と秋穂には詳しい事情を説明せず、ただ近場に引っ越すということだけを告げた。それでも、孝介はなんとなく状況を察したのだろう。「わかった。それでいいと思うよ」と短く言って、少し心配そうな秋穂の肩をたたいた。
「学校が変わるわけじゃないから大丈夫だよ」
「おじいちゃんとおばあちゃんには会えなくなるの?」
「すぐに会える距離じゃん」
「だったら、なんで引越しするの?」
「いろんな家に住んだほうが楽しいからだよ」
「え?」
「次はどんな家なのかなあって思うと、わくわくするだろ?」
「ああ、そっかー」
無邪気に笑う秋穂を尻目に、孝介はいたずらっぽく舌を出した。子供にとって三学年の差は大きい。これだけ大人の事情がよくわかって、適度に方便も使える孝介が、やがて不登校になるなんて、このときは夢にも思っていなかった。

父母への報告は引っ越しを済ませたあと、妹の典子が買って出てくれた。「お父さんとお兄ちゃんはしばらく距離を置いて、頭を冷やしたほうがええよ」と父に伝えたという。僕が入院して以来、典子には世話になりっぱなしだ。
さすがの父も落ち込むんじゃないかと思っていたけど、その予想は外れた。典子いわく、父は顔を真っ赤にして「そんな勝手なあれをする奴は知らん! 二度と帰ってくんなって、あれにしとけ!」と怒鳴り散らしたらしい。一方の母は事態をどこまで理解しているのかはわからないが、特に言葉を発することなく、沈んだ表情のままだったとか。僕としては、どちらの反応もショックだった。
あれから三か月弱、僕は一度も父母に会っていない。電話もしていないし、かかってもこない。母のことは典子からちょくちょく話を聞いている。父がいない間はデイサービスを頼んで、なんとか生活できているらしい。
正直、これで良かったとは思っていない。引っ越して以降、心の奥底から湧き起こってくる罪悪感は日に日に大きくなっている。去年の秋くらいは、父から逃げたら楽になるだろうなんて、そんな想像を働かせていたけど、きっと想像できていたということは、実感できていなかったということでもあるのだろう。
三月になっても孝介の不登校は続いた。最近は僕の外出中に限って、たまに部屋から出てくると、亜由美に暴力をふるうこともあるという。
その日も孝介は大暴れしたのだろう。夜遅くに僕が帰宅すると、キッチンの流し台の上に割れた皿やらグラスやらの破片が寄せ集められていた。
「また孝介か?」
僕の問いかけに、亜由美はげっそりした顔でうなずいた。
「さっきトイレで部屋から出てきたとき、ちょっと話があるって私が言ったら無視されたの。それで待ちなさいって腕を引っ張ったらもうダメ」
「今はどうしてるん? 二人とも寝たん?」
「秋穂は寝たけど、孝介は部屋に入ったきりでわかんない」
僕は溜息をついて、いつものように孝介の部屋に向かった。だけど、今夜は声をかけることもノックすることも控えて、エクレアの袋をドアノブに引っかけるだけにした。依然として具体的な対策はなにも浮かんでこない。
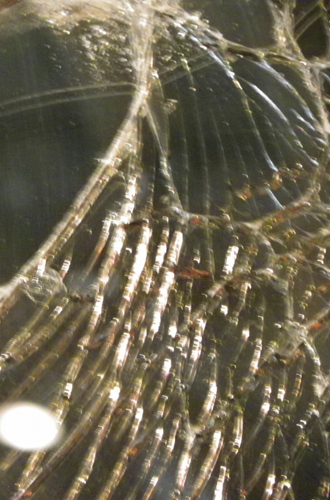
その後、風呂に入ってダイニングに戻ると、亜由美が珍しく食卓で缶ビールを飲みながらテレビを見ていた。僕も冷蔵庫を開けて缶ビールを取り出す。冬の寒い時期でも、なぜかビールだけはキンキンに冷えていたほうがいい。
缶ビールのプルトップを開けながら亜由美の対面に座った。なんとなくテレビ画面に視線を向けると、それがテレビ番組でないことに気づく。
去年の暮れ、家族四人で一泊二日の旅行を楽しんだときのビデオだ。中学受験が迫る孝介の最後の息抜きと称して、城崎温泉でカニを食べた。
「最近、こういうビデオをよく見てるんだ」亜由美がつぶやくように言った。「ほら、孝介も秋穂も笑ってんじゃん。この笑顔を忘れないようにって」
ビデオには城崎温泉までの車中の様子が映っていた。
後部座席に並ぶ孝介と秋穂に、助手席の亜由美がカメラを向けながら「十七条の憲法制定は何年?」と訊ねると、孝介が「労を知るだから……六〇四年」と答えている。その後も「じゃあ、大宝律令の制定は?」「七〇一年」「墾田永年私財法は?」「七四三年」と歴史の年号に関する一問一答が続き、「じゃあ、ちょっと飛んでペリー来航は?」という問いに、孝介が「開国はいやでござんす、ペリーさん……だから一八五三年!」と答えた瞬間、隣の秋穂が大笑いした。
「孝介、本当によくがんばってたよね」亜由美がビデオを見ながら言う。
「うん、親馬鹿かもしれんけど俺も感心してた」
ビデオの中の孝介は少しでも時間ができると、なにかしらの受験勉強をしていた。旅館の部屋に入るなり、テーブルに参考書を置く孝介の姿が映っている。

「今日くらいは勉強忘れてもええんちゃうか?」ビデオの中の僕が言う。
「ダメダメ。ちょっとはやらないと」孝介は参考書を読みながら抗弁した。「勉強は筋トレと一緒だから、一日休むと元に戻すのに三日はかかるんだよ」
「ほー、あの飽きっぽい孝介が立派なことを言うようになったもんや。前はプロ野球選手になりたいからって素振り五百回を毎日やるとか言うてたやん。あれは何日続いたんでしたっけ? 三日坊主で終わったんちゃうかったっけ?」
「ブー、不正解。二日坊主だね」
「もっとあかんやん」
「けど、飽きたからじゃないよ。実際ちょっと野球をやってみて、自分はスポーツではトップになれないってことを悟ったから方針転換したんだよ。ほら、スポーツって生まれつきの体格とか才能とかに左右されるところがあるじゃん」
「そんな悲しいこと言うなよ」
「いや、悪い意味で言ってるんじゃないよ。勉強だったら、一生懸命努力すればある程度は上まで行けると思うんだ。だってプロ野球選手になれる人は年間で百人もいないのに、東大生と京大生は年間で六千人近くも生まれるんだから」
ビデオに映る孝介の笑顔が、今の僕には痛々しかった。
本当に孝介は親が驚くくらい必死で努力していたのだ。志望校という具体的な目標ができてからというもの、学校帰りに進学塾に通い、夏休みや冬休みは朝から夕方まで講習を受け、家に帰ってからもあれほど好きだったテレビゲームや漫画に見向きもせず、毎晩遅くまで参考書や問題集と向き合っていた。
大阪でできた新しい親友も同じ学校を受験するから、いつも二人で切磋琢磨していた。受験をしない同級生たちからたまに遊びに誘われても、こちらが心配になるくらい強い口調で断り続けていた。これでもし受験に失敗したら、孝介は地元の中学でどんな目に遭うのだろう。受験に失敗した東京育ちの孝介を、小学校からそのまま進学した同級生たちは受け入れてくれるのだろうか。
だけど、親としては見守ることしかできなかった。息子がこれほどまで真剣に受験勉強に打ち込んでいたのだ。その姿が僕には頼もしくて、いじらしくて、とにかくこの努力が報われてほしいと神に祈るような気持ちだった。
亜由美がテレビを消した。部屋が一気に静まり返る。

「孝介、直前の模試でもA判定だったのよ」と亜由美。
「知ってる」
「受験って残酷だよね」
「うん、特に中学受験は厳しいわ。高校受験や大学受験とちがって、落ちたら公立中学に行くことになって、他のみんなに落ちたことがばれるんやから」
去る二月の初頭、我が家に届いた一枚の葉書。
それは孝介が受験に失敗したことを意味する不合格通知だった。
孝介は親が太鼓判を押せるくらい人生で一番の努力をして、人生で一番の勝負に挑んで、その結果、人生で一番の敗北を喫した。世の中には努力が報われないこともあるということを、わずか十二歳にして思い知ることになった。
一方、孝介の親友は合格通知を手にした。それが孝介の傷ついた心に追い打ちをかけたのだろう。以来、孝介は笑顔を失った。得意の屁理屈を並べて、大人を煙に巻くようなこともなくなった。やがて学校にも行かなくなった。
これを些細なことだとか、たいした挫折じゃないだとか、そうやって簡単に切り捨てるのは大人の理屈だ。受験が人生のすべてじゃないなんて、僕は頭でわかっていても、あのときの孝介の前ではどうしても口にできなかった。
小学校の卒業式が近づいてきたころ、孝介のクラス担任の先生から電話があった。なんでも家庭訪問がしたいという。もちろん、要件は孝介のことだ。
同様の家庭訪問は孝介が不登校になったばかりのころにもあったが、そのとき僕は仕事で同席できなかったため、亜由美だけが応対した。先生が言うには、孝介の受験失敗はあっというまに学年中に広まり、それ以降クラスメイトから笑われたり嫌がらせを受けたりするようになったらしい。その中心メンバーは受験前に孝介が遊びの誘いを断り続けていた連中だった。原因がそこにあるかどうかはわからない。ただ、親としては想定しておくべきことだったとは思う。
土曜日の夕方、先生が我が家にやってきた。三十代前半くらいの男性だ。
「今日、孝介くんと秋穂ちゃんは?」
狭いダイニングの食卓で、先生が切り出した。

「秋穂は習い事に行ってて……孝介は部屋にいます」亜由美が答えたあと、僕は補足するように言った。「まあ、いつもの感じです。トイレ以外はずっと」
先生は少し息を吐くと、おもむろに鞄から原稿用紙の束を取り出した。
「実は今日、これを持ってきたんです」
原稿用紙の束が食卓に置かれた。僕と亜由美が同時にのぞきこむ。
「孝介くんをからかっていた子たちが謝罪文を書いてきたんです。私が彼らを注意したり、根気強く諭したり、まあ、そうやって話し合いを続けてたら、彼らもわかってくれたみたいで……それで孝介くんに謝りたい、と」
おそらく謝罪文は本物だろう。四百字詰めの原稿用紙一枚一枚に、それぞれ特徴のちがう幼い文字で名前と文章が書き連ねられていて、なんだか生々しい。ざっと読んだ限り、これといって胸を打つような文面はなく、類型的なものばかりだったが、それでも孝介が学校で味わった苦しみを感じるには十分だった。
中でもショックが大きかったのは、孝介の親友の名前を発見したことだ。彼は孝介とちがって、中学受験に勝利した。そんな彼が謝罪文を書いたということが意味するもの。孝介にとっては、それが一番つらかったのではないか。
「孝介くんにこの謝罪文を見せてほしいんです。もう孝介くんをからかったりする子はいません。みんな温かく迎えてくれるはずです」
先生が真剣な顔で訴えてきた。いわく、孝介には今月中旬に控えている卒業式に参加してほしいという。このままフェイドアウトする形で卒業したら、地元の公立中学に進学してからも引きずることになってしまう、と。
ほどなくして、突然ダイニングのドアが開いた。
蒼白い顔をした孝介が入ってくる。
「孝介っ」亜由美の声が裏返った。僕は絶句して、孝介の顔を見つめる。
孝介は先生のもとに歩み寄り、遠慮のない口調で言った。
「早く帰れよ」
「えっ」先生の表情が曇った。
「なに勝手に来てんだよ、さっさと帰れよ」
「おい孝介、やめろ」僕が思わず言うと、孝介が声を荒らげた。
「家に来られんのとかマジうぜんだよ! どうせボロいとか思ってんだろ!」
ボロい――? 僕は耳を疑った。
「なにやっても無駄だから、あきらめろって!」
「ちょっと落ち着けっ」先生が血相を変える。
「出てけっつってんだろ!」
「みんな謝ってるから、もう大丈夫だぞ」
「うるさい、知るか!」
「おい、ヤケクソになんなよ」
「なってねえよ、馬鹿!」
そこで亜由美が割って入った。「やめなさい!」次の瞬間、孝介の右足が素早く上がる。「痛っ!」亜由美が腰を押さえてうずくまった。
「ええかげんにせえ!」僕は咄嗟に怒鳴り、孝介に歩み寄る。「おまえ、どこまで荒れたら気がすむんや! おまえ、どこまで……どこまで……」
だけど、そこで言葉につまってしまう。
孝介は黙って唇を震わせていた。潤んだ目で僕を見つめている。
「先生、すみません。今日のところは――」
僕は先生に目配せした。先生も察したようで、帰り支度を始めた。
そのとき、孝介の声が聞こえた。振り絞るような細い声だった。
「なんかもう、うるさいんだよ……。なんかもう、嫌なんだよ……」
「孝介」
「なんかもう、なんかもう……」
「どうした、孝介。なんでもええから言ってみろ」
「いや……だからもう、うざいっていうか……もう……」
孝介が目を伏せた。苦しいのだろう。親の直感でそう思う。
こういう時期は僕にもあった。胸の中に散らばっている思いをうまく言葉にできない。知っている言葉をいくら引っ張ってきても、時には辞書をめくって言葉を探してみても、どうしても覆い尽せない余地みたいなものが必ず残って、そこが一番大切なんだとわかっているから、じれったさを感じてしまう。もしかしたら、言葉の総数と気持ちの総数は気持ちのほうが圧倒的に多くて、だから既存の言葉だけですべての気持ちを表現するのは物理的に不可能なのかもしれない。
「わかった。もうええよ」僕は孝介の頭を撫でた。何度も何度も撫でた。「わかるから、孝介の気持ち。なんとなく、なんとなくわかるから」
孝介の反応はなかった。
「ほんまやぞ? お父さんも子供は一回やったことあるんやから」
帰り支度を終えた先生が黙って会釈した。僕も会釈を返し、亜由美に向かって顎をしゃくる。亜由美は先生を玄関まで見送ると、静かにドアを閉めた。
「どっか行くか」
僕はふと思いついたことをそのまま口に出した。孝介は黙っている。
「ごめん、ちょっと二人で出かけてくるわ」玄関から戻ってきた亜由美に視線を送った。「ほら、秋穂がいるから亜由美は家におったほうがええやろ」
「う、うん」
「なあ孝介、たまには男同士でうまいもんでも食べようや」

試しに孝介の腕を引いてみると、意外なほど簡単についてきた。これはもしやサインかもしれない。孝介も助けを求めているのかもしれない。
愛車のキューブに乗って、孝介の好きな大阪ミナミを目指した。
孝介は郊外ののどかな街よりも、にぎやかな繁華街を好むところがある。大阪に引っ越したばかりのとき、僕が「まずはどこに行きたい?」と訊くと、孝介は間髪入れず「道頓堀」と答えた。東京育ちの孝介にとって、グリコやカニ道楽の派手な看板がある、そういうステレオタイプの光景こそ大阪なのだろう。
行きの車中、僕は運転しながら必死で話題を探した。いきなり問題の核心をついたほうがいいのか、それとも他愛もない世間話をしたほうがいいのか、はたまた黙っていたほうがいいのか。いずれの案も頭に浮かんでは消去して、浮かんでは消去して、そういうことを繰り返した結果、僕が選んだのは――。
「ごめんな、孝介」ただ謝ることだった。「ほんまにごめん」
助手席の孝介を一瞥した。孝介は黙って車窓の景色を眺めていた。窓ガラスにぼんやり映る息子の顔。生気のない、人形みたいな顔。
「お父さん、孝介をさんざん振り回してきたよな」僕は続けた。「東京から大阪に引っ越したんも、おじいちゃんと暮らすことになったんも、学費のことで心配かけたんも、おじいちゃんの家を出て近場のアパート……ほら、今のボロいアパートに引っ越したんも、全部お父さんのせいや。お父さんのわがままや」
孝介が車窓から目を離した。そのまま下を向く。
「ほら、さっき孝介も言うてたやん。ボロいアパートがどうとか……。あれ、ちょっと気になってたんやけど、ひょっとして学校で笑われたりしてたんか? ボロいアパートに引っ越して、落ちぶれたとかなんとかって」
そのとき、孝介の声がかすかに聞こえた。「別に……」たいした言葉ではなかったけど、久しぶりに声を聞けただけでも少し安心した。
「ごめんな、ほんまにごめん」
何度も念押しするように言った。教育評論家とか心理カウンセラーとか、そういう専門家の人はもっと適切な言葉を選べるのだろうけど、僕にはまったく思いつかない。今の僕から「ごめん」を奪ったら、途端に沈黙に襲われてしまう。
ほどなくして、ケータイの着信音が鳴った。電話がかかってきた音だ。
だけど運転中のため、ひとまず放置することにした。
着信音が鳴りやんだころ、ちょうど信号待ちになったので、ケータイ画面を確認してみる。いったい誰からだろう、仕事のトラブルだったら嫌だな――。
画面を見た瞬間、僕は思わず目をむいた。体も固まった。
背後からクラクションを鳴らされた。信号が青に変わっていた。
慌てて車を発進させた。心臓が早鐘を打つ。苦しいほど大きな鼓動だ。
走っていると、再びケータイの着信音が鳴った。今度は運転しながら、こっそり画面をのぞいてみる。ああ、まただ――。やっぱり放置した。
「出ないでいいの?」
孝介が訊いてきた。不思議なもので、いつもの自然な口調に戻っている。僕はケータイの電源を落とした。平静を装いながら答える。
「あとでかけなおすからええわ」
「誰から?」
「おじいちゃんから」
孝介が目を丸くした。僕は右折すべき交差点を直進してしまった。
(第17回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『家を看取る日』は毎月22日に更新されます。
■ 山田隆道さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


