 イケメンチンドン屋の、その名も池王子珍太郎がパラシュート使って空から俺の学校に転校してきた。クラスのアイドル兎実さんは秒殺でイケチンに夢中。俺の幼なじみの未来もイケチンに夢中、なのか? そんでイケチンの好みの女の子は? あ、俺は誰に恋してるんだっけ。そんでツルツルちゃんてだぁれ?。
イケメンチンドン屋の、その名も池王子珍太郎がパラシュート使って空から俺の学校に転校してきた。クラスのアイドル兎実さんは秒殺でイケチンに夢中。俺の幼なじみの未来もイケチンに夢中、なのか? そんでイケチンの好みの女の子は? あ、俺は誰に恋してるんだっけ。そんでツルツルちゃんてだぁれ?。
早稲田文学新人賞受賞作家にして、趣味は女装の小説ジャンル越境作家、仙田学のラノベ小説!
by 仙田学
第一章 空から舞い降りたイケチン(後編)
だが。
だが。
超絶イケメン男(格好はチンドン屋)と超絶美白天使が至近距離で見つめあっている図は、映画かドラマのワンシーンのようだったのだ。
ひとことでいうと、お似あいだ。
認めざるをえない。
女子たちも男どもも、ため息を漏らすことさえ忘れて静まり返っている。
「もらっといてやる。てかこれ箸ついてないのかよ。お嫁にいけねえぞ、こんなんじゃ」
一瞬で教室のなかの空気が歪んだ。
片手で兎実さんの弁当を受けとると、イケメンチンドン屋はろくに見もしないでそのへんの机に置き、鼻で笑ってみせたのだ。

「ふらちゃん……かわいそ……」
「末代までバチが当たるぞ」
ざわめきが広がっていく。
兎実さんは男子からも女子からも愛されまくっている。
こんな扱いを受けたことは前代未聞だった。
「ごっめーん。用意してたはずなんだけど、家でるときうっかりして入れ忘れたんだぁ」
兎実さんはけなげにも耳まで赤く染めて、眉毛をハの字にしてみせる。
「しょーがねーなおめーは」
イケメンチンドン屋はアメリカ人のように肩をすくめた。
兎実さんはうなだれてみせたが、その唇にはうっすら笑みが浮かんでいた。
さきほどの青春女子のように、頭ぽんぽんされるのか。
誰もがそう思ったことだろう。
だがイケメンチンドン屋は目を逸らした。
それきり兎実さんには一瞥もくれない。
兎実さんは、棄て犬のように突きだしていた頭を微妙に震わせ、ひきつった顔をあげる。
「あぁん、ふらのばかばかばか。お昼休みにおうち帰っておハシとってくるね。ねえねえ甘いもの好き? デザートもあるんだょ」
「昼休み終わっちまうよ、ほんとバカだな。おっそれ『殺人教室』の新刊? 見して見して」
イケメンチンドン屋は兎実さんの質問を軽~く流し、近くの女子の鞄から覗いていたマンガに手を伸ばす。
バキッ。
ガチャッ。
机に突っ伏す格好でアントニオ小猪木のDVDに顎をすりつけながら、折れた鉛筆を両手に握っているのは、未来だった。
おれが夕べ削って筆箱に入れてやった鉛筆……。
折った勢いで筆箱が落ちたらしく、床にはなかみがぶちまけられている。
「映一。落ちた」
おれは反射的にしゃがみこんでいた。
長年の習い性だ。
ひとりで放っておくと、飲み物はこぼすわ、物は失くすわ、服は破れるわ、道に迷うわ、三歳児よりも目を離せないのが未来って女だ。
ゼロ歳児から一緒に育ったおれは、物心つく頃から、そんな未来の世話係におさまっていた。
「うう……」
四つん這いになって、散らばった文房具を拾い集めるうちに、おれの胸には悲しみが渦巻いた。
地位や名声や見た目のよさは、兎実さんの大好物だ。
よくよく肝に銘じていたつもりだった。
だが目の当たりにすると、どでかい金盥が脳天に激突したような衝撃に、めまいが止まらなくなってくる。
「それゴミ」
「うわおっ!!」
勢いよく腰をあげたおれは、机の裏側へ思いっきり脳天をぶつけた。
正真正銘のめまいにふらついたおれの目の前に、小さな白い顔が浮かびあがる。
重めのボブカットの髪にふちどられた顔の真んなかでは、牛乳瓶の底のようなぐるぐるメガネが光っていた。
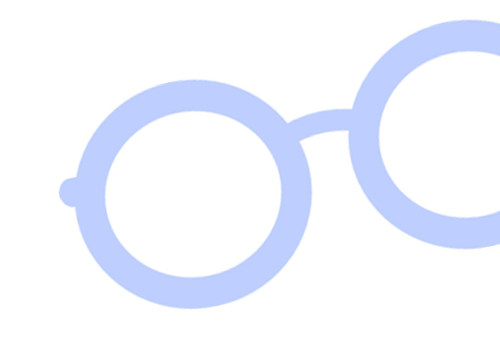
「羊歯」
羊歯灰汁美だった。
未来の鉛筆や物差しを両手に握っている。
「おお、ありがと。手伝ってくれんのか」
「それ、先週末からあった」
「ん?」
拾いあげた消しゴムがやけにぬめっていることにおれは気がついた。
ひんやりとして、ぬめぬめで、チーズ臭くて。
「ってかチーズじゃねえか」
裂けるチーズのプレーン味だった。
おれは手をブンまわして投げ捨てた。
誰だ誰だ裂けるチーズの食いかけを落として帰ったやつは。
やばいやばい、消しゴムと間違えて筆箱にしまうとこだった。
あとで未来にばれてみろ、血の雨が降るとこだったぜ。
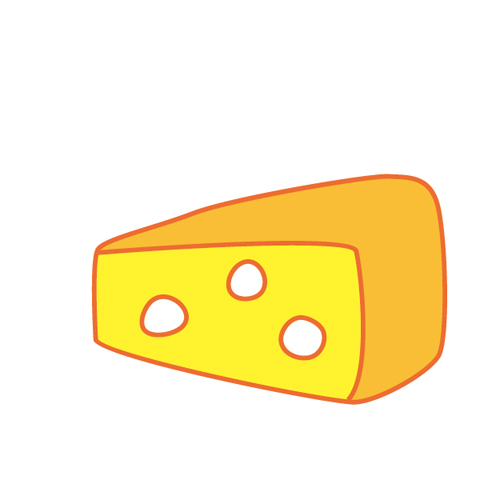
「いやあ助かったよサンキュー……あ」
ぐるぐるメガネにぴたりと張りつき、斜めに垂れさがっている白いものは。
「ごめんっ」
裂けるチーズだった。
おれは慌てて、羊歯のメガネから裂けるチーズのかけらをつまみとる。
おれの指が額に触れた瞬間、羊歯は野良猫のような素早さで身を引いた。
「ん?」
ふだんは固く引き結ばれている唇が緩み、ぐるぐるメガネの底で黒い瞳が揺れた。
白い頬が真っ赤に染まっている。
「羊歯、熱でもあんのか?」
とっさにおれの手は伸び、羊歯の額に触れようとした。
「おらおらおらっ」
野太い雄叫びが轟きわたったのはそのときだった。
同時に始業のチャイムが鳴り響く。
おれと羊歯は机の下から這い出し、かき集めた文房具を未来に渡すと、席に戻った。
教室の扉を開け放ち、できそこないの宝塚女優のように仁王立ちになっているのは、漆黒のパンツスーツに身を包んだ、背の高い女だった。
長い髪をひっつめにした、彫りが深く華のある顔。
隙のなさそうなきつい表情。
だが。
スーツの袖には、よく見るとご飯粒がカピカピになってこびりついていた。
シャツの胸もとはありえないほどダルダルで、巨大な乳の谷間が豪快に覗いている。
ひとことでいうと、だらしがない。
だらしのなさの極めつけは、下半身だった。
親の仇に叩っ切られたように、チャックが全開になっている。
裂け目から覗いているのは、ドドメ色のゼブラ柄の、破廉恥な下着だった。
「ゼブラ柄きたぁっっ」
「なんだよレースついてねえじゃねえか」
「きょうはおれの勝ち! 焼きそばパンおごりな」
「珍しくかわいー、でも色がなぁ」
「色違いあったら欲しいかも」
一気に空気が生ぬるく弛緩した。
「おまえらいつまでくっちゃべってんだぁっ! 全員まとめて追試だぞおらあっ」
両腕を振りまわし、全開になったチャックからパンツをもろ見せさせながら教壇へとのし歩いていくのは、担任の御殿場なたね、通称チャックだった。

伝え聞くところによると、これまでに受け持ったどのクラスでも漏れなく、最低五回はチャックを閉め忘れて登場しているとか。
校長や教育委員会から再三再四たしなめられているはずなのに。
宗教上の理由でもあるのかもしれない。
「はいはい」
「朝っぱらから数学かよ。だりー」
なたねがはじめてチャック全開で現れたのは、担任になった四月そうそうだった。男子たちは歓声をあげながらスタンディングオーベーションで出迎え、女子たちは絶叫しながら逃げ惑った。
だが慣れとは恐ろしい。
数ヶ月も経たないうちに、なたねのパンチラは日常風景に溶けこんでいった。いまでは稀に、パンツの柄をめぐって昼食のパンを賭ける者がいるくらいだ。
必要以上にチャックを気に留めているやつなど今ではひとりも……ん?
教壇に近づいていったのは、イケメンチンドン屋だった。
「おお! ちょうどよかった。自己紹介しなさい」
なたねの差し伸べた手をすり抜け、イケメンチンドン屋はその足もとにしゃがみこむ。
「……………………っっっっっっ!!」
息を呑む音が教室じゅうを駆け巡った。
しゃがんだイケメンチンドン屋の顔が、ちょうどなたねの股間の高さにあったのだ。
その鼻先は、ドドメ色のゼブラ柄のパンツにいまにも触れんばかりだ。
フケツっっ!!
女子たちの心の叫びが伝わってきた。
いや、ただひとり事態を把握できていない女がいる。他ならぬなたねだ。
「どうした。小銭でも落としたのか?」
なたねは心底不思議そうな声をあげる。
「先生助太刀いたすっ」
教室の奥から踊りでてきたのは、なたねと同じくらい背の高い女だった。
栗色の髪に、青い瞳。
ブラウスのボタンを弾き飛ばさんばかりに発育したボディ。
ロドリゲス蓉子だ。
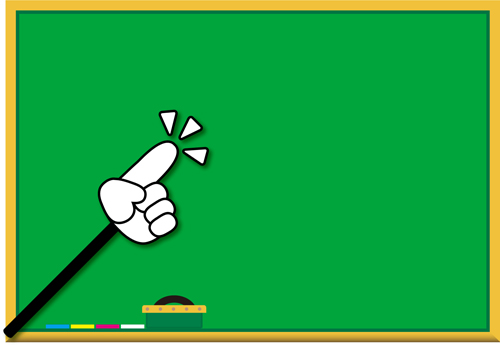
父親がイタリア人というだけあって、日本人離れした体格と抜群の身体能力の持ち主だ。
唯一残念なのは、友だちがいないこと。
同じく友だちのいないなたねと意気投合し、クラス委員長に選ばれてからは、なたねの片腕として活躍していた。
ロドリゲスがブレザーの背から勢いよく引きだしたのは、細長い棒だった。
棒の先端に取り付けられた手のひら大の円板には、力強すぎる字体で、
?
と大書されていた。
決死の形相で、ロドリゲスは?棒を、なたねの股間へ差し伸べる。
「先生っ!」
わずかな差だった。
ロドリゲスの?棒より先に、なたねの股間を覆っていたのは、イケメンチンドン屋がジャケットの内ポケットからとりだした、真っ赤なハンカチだった。
?棒を握りしめたまま、ロドリゲスバランスを崩し教壇の上ですっ転ぶ。
闘牛のように。
ロドリゲスの尻のたてた地響きに、口を半開きにして騒動をぼんやり見守っていたなたねは、我に返ったような顔をした。
「大丈夫かゲスっち! いまパンツ見えたぞ」
助け起こそうと、チャック全開のまましゃがみかたなたねは、
「おお。どうした、この赤いのは。落し物か?」
おのれの股間を覆っている真っ赤なハンカチに、ようやく気がついた。
たっぷり十秒ほどの間を置いて、なたねは全校じゅうに絶叫を轟き渡らせた。
「気をとりなおしていくぞー。ええ、きょうからうちのクラスに転入する、みんなの新しいお友だちだ」
黒板の上に巻きこまれていたスクリーン状の日本地図を引きおろし、その裏側へまわりこんで膝まで隠れてから、なたねはようやくイケメンチンドン屋を紹介する。
カラ元気丸だしの声だった。
そんなに嫌なら毎回厳重にチャックをチェックすりゃいいのに。
「どうも」
日本地図のど真んなか、なたねの姿を完全に遮る位置に、イケメンチンドン屋は陣どった。
教卓に両手を突き、クラス全員の顔を見渡していく。
「世のなかには、守らなきゃいけないものが、たったひとつだけある。なんだと思う?」
ことばを切ると、イケメンは唇の端を持ちあげた。
酷薄そうな、だが爽やかな笑みを浮かべてみせる。
「女性の美しさだ。それが失われそうになってるところを気づきもしないで見ている男なんて、言語道断。おれはどうかっていうと、全身全霊をあげて、女性の美しさを守るつもりだ。女性のみなさん。おれは絶対見捨てたりはしないから。ついてきてくれ」
早い話がアホみたいな自己紹介だ。
だがイケメンチンドン屋の、よく通るバリトンの声は、おれたちのエモーションを揺さぶった。

気がつけば、おれの頬には涙が伝っていた。
女子たちも胸の前で手を組み、目を潤ませ、ため息をつきながら話に聞き入っている。
やがてイケメンチンドン屋は静かに背を向け、黒板にチョークを走らせた。
池王子珍太郎
「よろしく。僕ってかっこいい?」
「さいっっっこ―――――――!!!!」
「珍太郎くんやばすぎ!!!」
「失神しそう!!!」
女子たちは耳をつんざくような黄色い声で絶叫する。
その声の海のただなかに、池王子は使用済みの真っ赤なハンカチを投げ入れた。
餌に食らいつくピラニアのように、女子たちは押し寄せる。
なにが悲しくて担任女教師の股間を覆ったハンカチを争い求めるのか。
おれには完全に理解不可能だ。
激しい接戦を経てハンカチは手から手へと渡っていき、最後に手にして微笑んだのは、
蛸錦だった。
(第03回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ツルツルちゃん 2巻』は毎月04日と21日に更新されます。
■ 仙田学さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


