 その家は今から90年以上も前、大阪の外れに建てられた。以来、曾祖父から祖父、父へと代々受け継がれてきたのだが……39歳になった四代目の僕は、東京で新たな家庭を築いている。伝統のバトンを繋ぐべきか、アンカーとして家を看取るべきか。東京と大阪を行き来して描く、郷里の実家を巡る物語。
その家は今から90年以上も前、大阪の外れに建てられた。以来、曾祖父から祖父、父へと代々受け継がれてきたのだが……39歳になった四代目の僕は、東京で新たな家庭を築いている。伝統のバトンを繋ぐべきか、アンカーとして家を看取るべきか。東京と大阪を行き来して描く、郷里の実家を巡る物語。
by 山田隆道
第十一話
「そんなもんな、どっかで親父にブチギレたったらええねん」
いつだったか、コンちゃんにそう言われたことがある。酒の席でのことだ。酔っぱらった僕が、父の横暴さについて愚痴をこぼしたときだったと思う。
コンちゃんいわく、父親というものは息子がおとなしくしているとどんどんつけあがっていく生き物だという。だから、どこかで強烈な反乱を起こして、我が息子はいつまでも子供じゃないということを思い知らせるべきだとか。
「安心せえ。なんぼ喧嘩しても親子の関係はなくならん。せやから、言いたいことは言ったほうがええんや。自分もスカッとするし、親父の態度も変わんで」
そのときは、コンちゃんの言葉に少し勇気づけられた。説得力も感じた。
しかし、実際に怒鳴ってみたら想像とちがった。鬱憤を吐き出したところで心が晴れるようなことはなく、それどころか余計にモヤがかかってしまった。
ああ、失敗だ。なんで父に激怒してしまったのだろう。情けないことに早くも後悔した。父と同居している以上、今日も明日も家で父と顔を合わせてしまうわけだから、このままでは気まずくてしょうがない。やっぱり最後まで我慢を通して、余計な波風を立てないほうが良かった。僕とコンちゃんでは、そもそもの性格だけでなく、置かれている状況もまったくちがうのだ。
仕事に戻る気になれず、ただただ適当に町をぶらついた。自分の意思とは無関係に回転する両足に行き先を任せているような、そんな感覚だった。
一時間は歩いただろうか。無意識のはずだったけど、結局は地元に近づいていた。彷徨の現実なんてこんなもんさと、訳知り顔になったつもりで苦笑する。
ほどなくして、小さな野池が見えてきた。小学校のころ、よくあそこでコンちゃんと一緒にザリガニ釣りをした。中学に上がってからは、お年玉を貯めて買った釣竿とルアーでブラックバスを狙ったものだ。釣れた記憶はないけれど。

野池の周囲はコンクリートで護岸されていて、さらにその周りには大人の肩くらいの高さの柵が設置されているけれど、子供のころの僕らはかまうことなく柵をひょいと乗り越えて、水際に近づいたものだった。
久しぶりに柵を乗り越えてみた。あれ、体ってこんなに重かったっけ。戸惑いながら護岸に着地すると、足がふらついて池に落ちそうになる。
ふと父の顔が頭に浮かんだ。そういえば、父はここに落ちたことがあった。
確かあれは僕が中二か中三か、それくらいのころ。
池に落ちたのは……僕のせいだ。
当時の父は祖父から受け継いだ霊園管理や石材屋などの事業をみるみる拡大して、現在のトータルエンディングサポートの会社を起ち上げたころだった。地元の人々の葬祭行事のほとんどを請け負うことで業績を伸ばしていたから、いつも自信に満ちあふれ、まるで町の実力者のように振る舞っていたものだ。
「新一、なんで人間が葬式や墓石みたいなあれに高い金を払うかわかるか? 結局やなあ、人間っちゅうのは忘れられたくない生きもんなんや」
あのころ、父は口癖のように言っていた。
「どんな金持ちでもヤクザでも、そこは一緒のあれや。いつか寿命があれするんはしゃあないって思っとっても、自分の存在が忘れられることは受け入れられへんねん。死を前にすると誰でもびびってまうからこそ、こんな石にすがってでも自分を残したいと思うんや。なあ新一、わかるやろ? 墓石っちゅうのはな、命が果てる恐怖に対する個人の戦いの証なんや。お父さんはそうやって恐怖と戦う人間をあれしてんねん。なあ新一、わかるやろ? 葬儀屋は人助けなんや」
わかるやろ――? 正直、父に何度そう言われても、当時の僕にはわからなかった。いや、正確にはわかろうとしなかった。どんな理屈をこねられても人の死で金を儲けているとしか思えず、とにかく不快だったのだ。
その不快感は、あっというまに父に対する嫌悪に変わった。葬儀屋の父が大きな体を見せつけるように胸を張り、肩をいからせ、ズボンのポケットに両手を突っ込みながら町を歩く。僕はそんな父が嫌いだった。自分は正しい、世の中に必要とされている、そう言いたげな父の姿が、僕は無性に嫌いだった。
ああ、そうだ。あのころ、僕は学校で折り合いの悪かった連中に「死神」という裏あだ名をつけられていたんだ。夏休み明けにそれを知った僕はひどく傷ついて、家で父に文句を言ったんだ。最初は葬儀屋を辞めてほしいだとかそういうことだったと思うけど、次第に感情的になって暴言を吐き散らしたんだ。
生まれて初めてだった。あの夜、僕は生まれて初めて父に牙をむいた。
だけど、父はそんな僕を諭すのではなく、僕を超える勢いで逆上したんだ。当時の父は今よりもっと短気だったから、息子に生意気なことを言われてすぐにカッとなって、カッとなったからすぐに平手を飛ばしてきたのだろう。
僕は家を飛び出した。だけど、父が鬼の形相で追いかけてきて、この野池に逃げ込んだところで捕まった。確かお互い柵を乗り越えて、この狭い護岸上でとっくみあいになったんだ。僕も興奮していたから、父に歯向かい続けたんだ。
その結果、僕は父に勝ったのだ。たまたまバランスを崩しただけかもしれないけど、とにかく僕を羽交い絞めする父に抵抗したら、父が池に落ちたのだ。
どういうわけか、その後の記憶は途切れ途切れだ。幸い深い池ではなかったから大事には至らなかったけど、水浸しになった父がどうやって護岸に上がったのか、僕らがどうやって帰宅したのか、つまり父子喧嘩の結末は覚えていない。
あとで母から聞いたところ、父はそのときの衝撃で右手の甲を亀裂骨折したらしい。だけど、それを僕に知られるのが嫌だったから、父は包帯を巻くことさえ拒否して、母以外には骨折を隠したまま、やがて自然に治癒したという。

それを打ち明けてくれたときの母は妙にうれしそうだった。
「お父さんね、新一と喧嘩して骨を折ったんが、よっぽど恥ずかしかったみたいやで。なんや真っ赤な顔してな、『誰にも言うたらあかんぞ』って何度も念を押しよんねん。ごっつい痛いくせに包帯もギプスもせんと、顔から脂汗だらだら流しながらヤセ我慢してからに。ほんまアホな人」
当時の僕にとって、それは初めて知った父の意外な一面だった。やけに新鮮な気持ちになったから、夢中で母の話に耳を傾けたことを覚えている。
「わたし、お父さんに言うたんよ。怪我したんは自業自得やから、新一を恨んだらあかん、あの子も難しい時期やから反抗することもあるやろうって」母はそう言って、僕に笑みを送った。「お父さん、そしたらなんて言うたと思う?」
「いや……わからん」
「あの人な、なんや今まで見せたこともないような、うれしそうな顔して『わかっとるわ。これくらいのことで息子を恨む親がおるか』って言うたんよ」
「うれしそうな顔?」
「そう、新一に力で負けたんがうれしい気持ちもあったんやって。『新一も立派になったなあ。あいつ、ごっつ力強かったでー』って鼻をふくらませながら言うから呆れてもうてね。ほんまアホやで。骨折して喜んどる場合かっちゅうに」
母があんまりケタケタと笑うので、僕もその場では笑いを返しておいたが、心中は激しく波打った。まったく想像していなかった父の反応と言葉に、僕はおおいに驚いて戸惑って、やがて大きな敗北感と罪悪感が押し寄せてきた。
池に落ちたのは父だけど、本当の意味での敗者は僕だ――。
父は僕が思っていた以上に大きかった。僕が必死で手を伸ばしても届かないくらい、高度な境地に達していた。だから、僕はそんな父に歯向かったことを後悔した。うん、あれだ。あの後悔だ。もしかしたら、あの後悔の残り火みたいなものが、今も僕の中で生き続けているのかもしれない。
結局、その日は夜遅くまで外で時間を潰した。父と顔を合わせるのが気まずかったから、亜由美には知人と食事の約束があると嘘のメールをして、深夜0時前にこっそり帰宅した。この時間なら、父はまちがいなく二階の寝室に入っているため、一階に寝室がある僕と鉢合わせすることはないはずだ。

自室に入って電気をつけると、パジャマ姿の亜由美が声をかけてきた。
「ねえ、お義父さんとなにがあったの?」
いきなりかよ。僕は小さく息を吐いた。
「晩ごはん食べてるときね、お義父さんが言ってたのよ。『新一のやつ、また妙な癇癪を起こしよった』って」
「癇癪?」
「うん、癇癪って言ってたよ」
「それだけ? 事の経緯は?」
「わたしも訊いたんだけど、お義父さんがわかんないって言うから……。車の中で急に新ちゃんがキレて、わけがわからなかったって首ひねってたよ」
唖然とした。父はどれだけ鈍感なんだ。
けど、ありえる話だ。父は昔から自分の傲慢さに気づいていないところがあった。あの独特の口調も父の中ではごく普通のことで、なにが問題なのかわかっていない。祖父の事業を受け継ぎ、それをますます成功させて以降は特にそれが顕著になった。父に物を言える人が、誰もいなくなったからだろう。
僕が車内での出来事を説明すると、亜由美は目を丸くして言った。
「お義父さんに対して、新ちゃんが感情的になるなんて珍しいね」
「うん、自分でもびっくりした」
「よっぽど腹が立ったんだ」
「けど、今は後悔してる」
「なんで?」
「やっぱ、父親にあんな口の利き方はあかんなって」
「いいじゃん、親子なんだから」
「けど、お父さんを傷つけたかも」
「そんなことないと思うよ。お義父さん笑ってたもん」
「え?」
「新一の癇癪は昔からたまにあることだから今回も一緒だろう、って感じのことを笑いながら言ってたよ。一晩寝たら機嫌もなおるはずだって」
正直、そういう余裕綽々の父の姿は容易に想像できる。
昔から強い人だった。万事に動じない人だった。仕事で取引先なんかとトラブルを起こしても、常に自分が正しい、強者は自分だと思っているようなところがあって、高所から相手を見下ろしながら問題解決をはかるような人だった。父にしてみれば、息子の怒りなどヤブ蚊に刺された程度のものなのだろう。
なんだかショックだった。中学のときと一緒だ。僕はまたも自分の小ささを痛感する。父のメンツを保ちたいと思っておきながら、少しくらいは父に傷ついてほしいとも思ってしまう、そんな矛盾が忌まわしかった。
その後、亜由美は先に布団に入り、僕はシャワーを浴びた。
浴室から出ると、自室で缶ビールを飲む。七月に入ってから、一気に蒸し暑くなってきた。この和室にはクーラーがないので、扇風機で我慢する。
机の上に税務署から届いた封筒が置いてあった。たちまち憂鬱になる。
おそるおそる封を開けると、中身は予想通り市府民税の通知書だった。
請求額は八十三万九千六百円也――。
わざと大きな溜息をついた。以前届いた所得税や国民健康保険、国民年金、さらに予定納税の金額まで合わせると、全部で二百万円をはるかに超える。
あまりに高額すぎて、かえって苦笑してしまった。昨年の実質的な年収が三百万円台の僕に、こんな大金を支払えるわけがないだろう。からくりはわかっているだが、どうしても文句を言いたくなる。税務署ではない、父に対してだ。
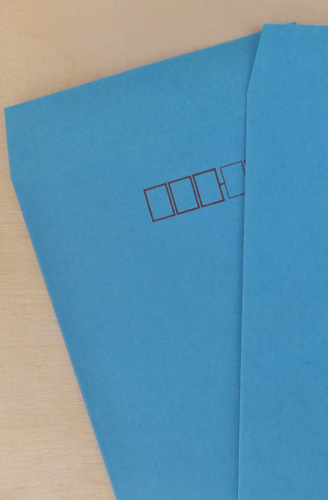
情けないことに、僕は自分の正確な申告年収を知らないのだ。
あれは十年くらい前、僕らが東京で暮らしていたころのことだ。孝介はまだ小さくて、秋穂は亜由美のお腹の中にいたんじゃないか。
当時、大阪の父が税金対策として、僕をいくつかの関連会社の役員にしたことで、僕に本業以外の別収入が生まれた。しかし、その収入は実質的には父のものなので、僕自身は一銭も使えないどころか金額すら教えてもらっていない。だから、僕の実感としては社会保険と厚生年金も完備されていない小さな会社のサラリーマンのままだったのだが、そのくせ東京で確定申告はしなければならなくなり、父に収入証明をもらおうとしたところ、あろうことか拒否されたのだ。
「そんな面倒くさいあれをできるか、アホ! うちは税理士にあれしとんのやから、おまえが送ってこい。こっちであれして、東京に申告したる」
今思えば、あのとき父にしたがったのが悪かった。父の会社の事情がよくわからなかったうえ、下手に長話をして無駄に罵られるのも嫌だったので、あまり深く考えることなく身を任せた。要するに、父との話し合いから逃げたのだ。
それからだ。毎年、莫大な税金と保険料の請求が届くようになったのは。
役所は僕の申告年収を知っているから、こういう計算になるけれど、僕はまったくわからないから最初はおおいに動揺した。安月給の中から家賃を支払い、孝介と秋穂のための積立貯金もするなど、なんとか財布をやりくりする生活だったのに、いきなり二百万円以上も請求されたら誰だってパニックになるだろう。
「それはお義父さんの都合なんだから、お義父さんに払ってもらうべきよ」
あのとき、亜由美は当然のようにそう言っていた。もちろん、僕も理屈ではその通りだと思ったのだが、当時まだ二十代後半だった僕は「自立」という言葉の意味を勘違いしていて、父に金の工面をされたくないという馬鹿な意地をおさえられなかった。だから一年目は貯金をはたいて、すべて自分で支払った。すべて自分で支払ったのだが、満足感は得られず、先々の不安ばかりが胸に残った。来年以降もこの請求が届くのだ。いつかパンクするのはまちがいない。
かくして、二年目からは亜由美の言にしたがい、請求書を大阪の実家に郵送するようになった。さすがの父もその支払いには応じてくれたので、これで一件落着かと思いきや、意外にそうでもなかった。
僕は自分の正確な年収を知らない。これだけ税金が高くなるのだから、きっとそれなりの年収なのだろうという曖昧な想像はできるものの、実際は年収三百万円台の生活しか送れない。そのくせ、父にはすべて正確に把握されている。役所はもちろん、父が懇意にしている税理士にまで正確に把握されている。
いざ、そういう状況になってみると、こんなに情けない話はない。毎年、確定申告が近づくと父に源泉票を送り、そのたびに「新一は安月給やのう」と余計な感想を述べられる。まるで父に支配されているかのようだ。
このシステムはいつまで続くのだろう。僕は税金の請求書をひとまず机の引き出しにしまって、缶ビールをちびちび飲んだ。いつかは父にわたさなければならないのだが、今はタイミングが悪い。父の前で激昂したばかりなのだ。
結局、父ときちんとした話し合いをしてこなかったから悪いのだ。不惑前の中年男がいまだに父にひれ伏してしまうのは、あらゆる面で父に支配されているからだろう。実家での僕は世帯主であって世帯主ではない。実感としては父の子供に成り下がっている。今の栗山家は、限りなく一世帯に近い二世帯だ。
それ以降も、僕はできる限り父を避ける生活を送った。朝は父が出勤したあとに起床して、梅田のレンタルオフィスで仕事をする。夜は父が寝室に入る時間までわざと帰宅を遅らせ、深夜三時ごろに就寝する。軽い昼夜逆転生活だ。
ただし、父が休みの日曜日はこの方法を使えなくなる。休日の父は、リハビリ中の母の面倒を見ながら、家でゆっくり過ごすことがほとんどだからだ。
そこで、日曜日は朝から外出することにした。亜由美と子供たちを連れて、父から逃げるように街に繰り出す。四人だけの時間は今や貴重だ。
大阪の繁華街といえば、梅田を中心とするキタ界隈と、難波や道頓堀、千日前など大阪のシンボル的なスポットが集中するミナミ界隈が有名だが、この日はそのミナミよりもさらに南に下った天王寺あべの界隈を目指した。
人生の半分ずつを大阪と東京で過ごした僕に言わせれば、この天王寺あべの界隈は東京の上野や浅草あたりに相当する、下町の繁華街だと思う。今年三月にオープンした日本一高いビル、あべのハルカスが最先端の空気を発しながらそびえ立っているかと思いきや、すぐ近くには膨大な数の日雇い労働者が集まる日本屈指のドヤ街があり、さらに足を延ばせばこれまた日本最大級の旧赤線地帯である飛田新地も控えている。だから、子供を連れて歩くのは治安的にも教育的にも不安があるものの、そこさえ回避すれば近くに動物園はあるし、昔ながらの盛り場の風情を残した新世界もある。混沌とした猥雑さ、それが街の個性だ。

孝介と秋穂はもちろん、亜由美にとっても初めて足を踏み入れる街だ。せっかく大阪に移り住んだのだから、もっと大阪のいろいろな街を知ってほしい。
思えば僕が子供のころ、父はこうやって家族を連れて出かけるようなことをほとんどしなかった。休日は仕事の付き合いを優先してゴルフやマージャンに興じることがもっぱらで、家族サービスという概念を感じさせない人だった。
僕はああいう父親にはなりたくない。特に孝介とは腹を割って話し合えるような、気さくに冗談を言い合えるような、そんな父子関係を築きたい。
天王寺駅に降り立つと、早速あべのハルカスを探検することにした。地上六十階建て、高さ三百メートルを誇る超高層ビル。池袋のサンシャイン60や横浜のランドマークタワーより高いという。どんなものなのか。
「まあ、高いビルってだけだから、結局は買い物くらいしかないよね」
一階の百貨店フロアに入るなり、亜由美がシビアなことを言った。
確かにその通りだ。僕は苦笑する。一般客はこの百貨店フロアと、さらに上階にあるホテルフロア、あとは展望台くらいにしか行けないわけで、そういう意味では特に新鮮なものではない。僕が試しに「展望台、行くか?」と亜由美に訊いても、「サンシャインみたいなもんでしょ。別にいい」と却下された。
一方、孝介と秋穂はまだまだ無邪気だ。二人とも初めての景色に目を輝かせながら、ちょこまかと忙しなく動き回っている。ダンスみたいだ。
ほどなくして、孝介が走り出した。「お兄ちゃん!」秋穂がそれを追う。
孝介が辿り着いたのは、壁に表示されてある百貨店のフロアガイドだった。人差し指を上下左右に動かしながら、なにかを探している。
秋穂が追いつくと、孝介は「上に行くぞ」と言って、エスカレーターに歩を進めた。秋穂もそれに続く。きっと、なにか目的があるのだろう。孝介が一人で突っ走るのはいつものことだけに、僕と亜由美もその背中を追うことにした。
ふと自分の小六のころを思い出した。僕は孝介みたいに、父に背を向けて動くことはできなかった。父と一緒に歩いているとき、どこかに行きたいという気持ちが芽生えても、いつも父の許可をとってから行動する子供だった。だから、僕は父の背中を見ることが多かった。父の後方を静かに歩き、父が曲がったら自分も曲がる、父が走ったら自分も走る、それがほとんどだったから、若いころの父の顔より、若いころの父の背中のほうが鮮明に思い出せる。
孝介の目的地は八階にある子供服売り場だった。欲しい服でもあるのかなと思って観察していると、孝介はどういうわけか女の子用の店に向かう。
「ほら秋穂、ここっておまえが好きな店じゃなかったっけ?」と孝介。
「あ、そうそう。なんで知ってるの?」秋穂の不思議そうな声が聞こえる。
「前にテレビ見ながら言ってたじゃん。ここに行きたいって」
「お兄ちゃん、そんなの覚えてるんだー」
「普通だろ、それくらい」
「ねえ、欲しいのが見つかったらパパに一緒にお願いしてくれる?」
「安いやつだったら、俺が頼んでやってもいいよ」

僕は目を細めた。孝介はなにもかも僕とちがう。小学生のころの僕は、妹の典子に代わって父になにかをお願いするなんてできなかった。とりわけ買い物については、父が怖くて一度もおねだりしたことがなかったんじゃないか。
だから、父になにかを買ってもらった記憶はほとんどない。僕は自分の自転車すら持っていなくて、祖母が使っていた錆だらけの古めかしい自転車をちょくちょく拝借していた。父は事業の成功者で、金銭的には裕福だったから、自転車くらい安いものだと思うのだが、どうしてもおねだりできなかった。
孝介を見ていると、僕は無意識のうちに自分の子供のころを重ね合わせてしまう。そして、いつだって僕より孝介のほうが自由闊達で、のびのびしていて、だけど頭が良くてしっかりしていることを思い知り、頼もしさを感じる。
そういえば、いつかの父はこれと逆のことを言っていた。
「新一と俺を比べるとやなあ、小学校のころも中学校のころも俺のほうがしっかりしとったわ。俺は新一みたいにひ弱なあれとちゃうかったからのう」
きっと父親とは少なからずそういう想像をしてしまうものなのだろう。息子が成長するにつれ、同じ年のころの自分を思い出して、そのちがいに喜んだり安堵したり、はたまた落胆したりする。僕はまちがいなく父に落胆された口だ。
父は自分と僕の性格のちがいだけでなく、僕が高校卒業後に東京に行ったことも、父の事業と関係ない仕事を東京で選んだことも、東京で結婚したことも、すべて落胆していたはずだ。大阪で裕福に暮らす父は、安月給でせせこましく暮らす息子、すなわち自分とあまりに隔たってしまった息子の人生を嘆いて落胆していたのか、それとも寂しくて落胆していたのか……。
それがわかるのは、いつか孝介が僕の望まない人生を選び、そこに苦しむようになったときだろう。だから、僕はわかりたいと思わない。
孝介と秋穂はにぎやかに服を物色していた。秋穂が気になったワンピースを手に取って自分の体に合わせるたびに、なぜか孝介が「それはいい」「それはあんまり」などと、えらそうなジャッジを下す。小六と小三のくせに。
僕と亜由美が近づくと、秋穂が腹を空かせた子犬みたいな目で僕の顔を見つめてきた。手にはピンクのミニワンピース。値札がちらりと目に入った。二万円オーバー。思わず眼球が飛び出しそうになる。最近の子供服はなんだ。
「秋穂、そんな高いやつはダメだって」
僕が思っていたことを、先に口にしたのは孝介だった。
「ええ、なんでよー」秋穂が口をとがらせる。
「一万円以下じゃないと、うちでは無理だって」
僕は複雑な気分になった。孝介はしっかりしているから、親の懐事情を自然に考慮するようになったのだろうけど、父親としては情けない。隣で亜由美も苦笑いを浮かべていた。子供服に二万円強。孝介の言う通り、僕には無理だ。
すると、秋穂が能天気な声で言った。
「じゃあ、おじいちゃんに買ってもらうのは? おじいちゃんだったら、お金いっぱい持ってるから、きっと買ってくれるんじゃないかな」
たちまち耳が痛くなった。孝介と秋穂から視線を外す。
「ああ、そのほうがいいかもね。よし、今度おじいちゃんに頼もう」孝介も無邪気な声で続ける。「俺も欲しいものがあるから、ちょうどいいや」
その瞬間、全身がカッとなった。父の顔が頭に浮かぶ。
途端に得体の知れない嫌悪感が襲ってきて、手足が勝手に動いてしまう。
気づくと僕は、秋穂から強引にワンピースを取り上げていた。
「あかん! おじいちゃんにだけは絶対に頼んだらあかん!」
自分でも驚くくらい、大きな怒鳴り声を発してしまう。秋穂の顔がみるみる蒼くなった。「ちょっと新ちゃん!」亜由美のたしなめるような声が聞こえる。
「うるさい! あかんもんはあかん!」
僕はもう引き返すことができなくなっていた。体が妙に熱くて熱くて、それを発散させたくてさせたくて、他のことが見えなくなった。
「お父さん、そんな言い方はないだろ!」孝介が顎を突き出した。
「ああん!?」ますますカチンとくる。
「なんでダメなんだよ。お父さんには関係ないじゃん」
「なんやと!?」
「おじいちゃんに頼むのは俺らの自由だろ」
「おまえなあ」
「前におじいちゃんが言ってたもん。お父さんはお金がないから、なにか欲しいものがあったときはおじいちゃんに言えって」
「孝介!」
「いたっ!」
あ、しまった――。僕はすぐに我に返った。
目の前に、頬を赤く腫らした孝介がいる。突然、声を挙げて泣き出した秋穂がいる。手のひらがじわじわ痛くなってきた。見ると、小刻みに震えている。
「最低!」
孝介が険しい目つきで吐き捨てた途端、僕の脛に激痛が走った。「うっ」鈍い声がこぼれ、脛を抱えて座り込む。あれ、おかしい。足に力が入らない。
頭上から孝介の声が聞こえた。
「先に殴ったのはそっちだから」
顔を上げると、冷たさを帯びた息子の顔が見えた。背筋がゾクッとする。脛の痛みはすぐに引いたけど、手のひらの痛みは強く残っていた。
(第11回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『家を看取る日』は毎月22日に更新されます。
■ 山田隆道さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


