Interview:三浦俊彦×遠藤徹 対談(1/2)

三浦俊彦:昭和34年(1959年)長野県生まれ。都立立川高等学校卒業後、東京大学文学部美学芸術学科を卒業。東京大学大学院人文社会系研究科(美学芸術学講座)教授。美学・哲学の研究者で小説家。和洋女子大学名誉教授。代表作に『M色のS景』、『この部屋に友だちはいますか?』、『サプリメント戦争』、『エクリチュール元年』など。文学金魚で『偏態パズル』を連載中。
遠藤徹:昭和36年(1961年)兵庫県生まれ。東京大学文学部英米文学科・農学部農業経済学科を卒業。同志社大学言語文化研究センター教授。アメリカを中心にした現代文化の研究者で小説家。代表作に『姉飼』(日本ホラー小説大賞)、『戦争大臣』(小説)、『プラスチックの文化史―可塑性物質の神話学』、『ケミカル・メタモルフォーシス』など。文学金魚で『贄の王』などを連載中。
三浦俊彦氏と遠藤徹氏は二十数年来のお知り合いで、共に大学で研究活動を行いながら小説を書いておられる。また小説の傾向は異なるが、必ずしも既存文学の枠組みにとらわれない作品を目指しておられる。今回は映画などを題材に、お二人の文学に対するお考えや、理想とする文学について自由に語っていただいた。なお司会は文学金魚編集委員の小原眞紀子さんに行っていただいた。
文学金魚編集部
■モンスター映画について■
遠藤 面白いと感じる作品ですか。小説じゃなくて映画なんですが、デヴィッド・クローネンバーグ監督の劇場映画デビュー作で『シーバース』(一九七五年)という作品があって、あれは寄生虫の立場で映画を撮っています。それは僕はすごく共鳴するところがあります。
三浦 人間を直接分析するんだったら、哲学や思想書などがありますからね。それをあえて小説や映画なんかのフィクションで描くとすれば、人間を主人公にしない方が、違う角度から描けたりしますよね。
遠藤 最近H・G・ウェルズの『タイムマシン』のことを論文に書いたんです。ウェルズは実は、人間が嫌いだったんじゃないかと思うんです。『タイムマシン』では、未来の人類がエロイとモーロックの二つの種族に分かれています。エロイは弱々しくて身長一二〇センチくらいしかない種族で、知的にも退化しているんだけど、果物だけ食べて優雅に暮らしています。エロイはブルジョワ階級のなれの果てを描いたものじゃないかと言われています。モーロックは地下に住んでいます。猿のような、蜘蛛とか齧歯類のような、あるいは昆虫とか動物との類比で語られる異形の存在です。モーロックは労働者階級のなれの果てということになっているんだけど、すごいのはモーロックがエロイを誘拐して食べるんです。しかもただ誘拐して食べるんじゃなくて、どうやらモーロックがエロイを養殖して食べている。
三浦 どのくらい先の未来の世界を描いているんだっけ。
遠藤 AD802701年の設定です。それだけなら人間が退化したっていう話で終わっちゃうんだけど、ウェルズはもっと先の未来に話を進めちゃったんです。そのもっと先の部分があって、カンガルーみたいな、ピョンピョン跳ねる生き物が出てきます。指が五本あって、顔に額があるからちょっと人間のような生き物です。つまり人間の特徴を残したカンガルーのような生き物なんですが、時間旅行者が観察しようとしたら、巨大な、確か十二フィートだったっけな、ムカデのような生き物が襲ってくるんです。カンガルーみたいな生き物は、巨大ムカデに食べられちゃう。この部分は単行本にするときに削除されましたけど。そのさらに先の未来で時間旅行者が見るのは、一つは巨大な蟹なんです。もう一つがやはり巨大な蝶々です。もっともっと先は世界の終末みたいなどんよりとした光景で、砂漠みたいになっている。そこにフットボールくらいの大きさの玉で、触手みたいな脚が生えている生き物が、ピョン、ピョンと跳ねているシーンで『タイムマシン』は終わります。
三浦 『タイムマシン』は映画化されているけど、今の場面は映像化されていますか。
遠藤 エロイとモーロックの部分しか映画化されてないんじゃないかな。普通の解釈だと、人間がどんどん退化していってラストシーンまで行ったということになるんだけど、僕が書いたのは違う説なんです。ウェルズはエロイとモーロックに人間を分割しちゃったわけだけど、その後はまったく違う生物が主人公になっているんじゃないかという説です。根拠は何かというと、ウェルズは『人間の絶滅』というエッセイを書いているんです。つまり人間がいつまでも地球の支配者である保証はどこにもないと論じている。じゃあ人間絶滅後に何が地球の支配者になるかというと、一つは蟹とか海老といった甲殻類が海から上がってきて巨大化するんじゃないか。もう一つは頭足類。烏賊とか蛸が知性を発達させ、しかも地上でも生きていけるような肺呼吸を始めるようになるんじゃないか。三つ目が蟻、四つ目が病原菌なんです。この小説で最後に残るのは蟹や烏賊や蛸、つまりは人間の絶滅後に現れうるとウェルズが予測した生物なわけです。ということは,ウェルズはもう人間に見切りをつけていたんじゃないか、ということを論文で書きました。

三浦 でもまあ、書かれた表面と本音はまた違ったりするからね。
遠藤 ウェルズはヴィクトリア朝の人で、当時のイギリスは大英帝国でしょう。世界を支配していたわけですが、大英帝国の軍隊が、タスマニアの原住民かなにかを滅ぼしちゃうんです。ウェルズは、そういうことをするヴィクトリア朝人に対して失望したということを『宇宙戦争』の冒頭で書いているんです。
三浦 だけど僕は人間は滅びないと思うな。
遠藤 ウェルズが言うような退化のし方はしないかもしれないけどね。
三浦 人間は多分、自分をどんどん改善していって、恐らく遺伝子操作で自ら違う生物へと進んでいくと思うよ。核戦争が起こったって、人間が絶滅するとは考えにくいわけだからね。好き嫌いは関係なしに、人間が強靱に生き延びる世界の方がリアリティがあると思うなぁ。滅びる話しって、僕はあんまりリアリティを感じられないんですね。SFでもサバイバルモノでも簡単に人間が滅びそうになる世界が描かれているけど、ああいう映画はどうも信憑性が欠けていますね。よほどうまく描いてくれれば別だけど。

小原 滅びた後の世界に関心があるのか、滅びるというのがメタファーなのかという問題はありますね。
三浦 映画なんかで人類の滅亡がよく描かれるのは、身も蓋もないけど、そういう設定が受けるからです。ネット上には小説の創作サイトがたくさんありますね。ちゃんと見たことはないんだけど、素人がどんどん投稿するわけだから、ものすごく多様化して自由な作品が並んでいるんだろうなと予想するわけです。今は誰もが小説を発表できる時代ですからね。ところが逆なんだってね。みんな同じような作品を書く。つまりみんなが書き始めると、多様化とはむしろ逆になってしまう。どういう作品が多いかというと、これはちゃんと自分で確かめてみなきゃならないけど、異世界転生物語が多いそうです。たとえば主人公が事故にあって死んでしまって、それと同時に異世界で別の人生を歩むようになるといったストーリーです。簡単に言うと自分の願望を書いているわけ。現実から逃れて別の世界に生まれ変わって、今とは違う理想の生活を送るといった。だから小説の民主化というのは、むしろ多様化を阻んでいるところがあるんじゃないかな。
遠藤 創造力が貧困になっているところはありますよね。
三浦 自分が本当に書きたい内容なのかどうかは別として、読んでくれる人に喜んでもらいたいから、多くの人が願望として抱えているテーマになっちゃうんだろうな。どうしても読まれやすいストーリーになっていく。ハリウッド映画だって、商業的に成功させたいと思ったら、似たような物語になっていくわけでしょう。家族愛を強調するとか、ヒーロー・ヒロインが二人組で活躍するとかね(笑)。それと同じような現象が起こっているようです。ああいう映画は何を見ても同じで、ジェームズ・キャメロン監督の『アバター』とか典型的だと思うんだけど、僕は心底つまらないと思います。でも学生なんかに感想を聞いてみると、そうでもないですね。みんなけっこう楽しんでいる。彼らに言わせると、「先生は見栄っ張りだ、あれを見て面白くないはずはない」ってことになるんです。本心では絶対面白いと思っているはずなのに、気取って、芸術家として斜に構えているから面白くないと言うんだと(笑)。でも僕は本当に、苛立たしいくらいつまんないと思うんだけど、遠藤さんはどうですか。
遠藤 僕もそういう映画は見ないようにしています。ただハリウッド映画で言うと、クリストファー・ノーラン監督の『ダークナイト』シリーズは素晴らしい。バットマンがジョーカーの罠にはまって、恋人を助けるか検事を助けるか、どちらか選ばなければならないという状況に置かれる。どちらにも爆弾が仕掛けられていて、同時刻に爆発するようセットされているんです。バットマンは知り合いの警官に検事を助けに行かせて、自分は恋人を助けに行くんだけどそれはジョーカーの罠で、人質が入れ替わっているんです。バットマンは検事を助け出しますが、警官の方は間に合わない。恋人は最後に何か言おうとするんだけど、その言葉も爆発音に掻き消されてしまう。
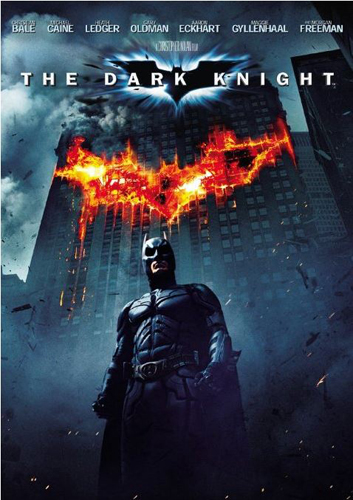
『ダーク・ナイト』(2008年)
クリストファー・ノーラン監督
三浦 バットマンって、シリーズ作品でしょう。『ダークナイト』だけ見てその魅力がわかりますか。
遠藤 バットマンシリーズは三部作で、『バットマン ビギンズ』、『ダークナイト』、『ダークナイト ライジング』と続くわけです。微妙に話しがつながっていますから、全部見ないとわからないかもしれない。ただクリストファー・ノーラン監督が何を表現しようとしたかと言うと、バットマンの人生を最初から終わりまで語り直そうとしたんですね。『ダークナイト ライジング』で、本当に死んだかどうかは曖昧に描かれていますが、バットマンは死ぬことになっています。だから誕生から死まで、一つの作品になっています。
三浦 それが僕は、ちょっとうんざりなんだな。どうしてもシリーズ化するでしょう。もっとコンパクトにまとめてほしいよ(笑)。
遠藤 でもどの作品もけっこう見応えがありますよ。特に最後の二作品が素晴らしいと思います。
三浦 じゃあちょっと見てみようかな。僕はモンスター映画はほとんど見ることにしてるんだけど、モンスターが人間型だとイヤなんだ。もっとちゃんとしたモンスターにしてくれよと思ってしまう(笑)。だからゾンビモノなんか大嫌いで、バットマンもそれで敬遠していたんだけど、見てみなきゃならないかな。数少ない見ていない映画をいいと言われてしまうと、なにかしくじったような気がしますね(笑)。
遠藤 そういう意味ではスーパーマン映画はつまらない。スーパーマンというヒーロー像自体はすごくアメリカ的で面白いんですけどね。
三浦 僕はスーパーマンとかスパイダーマンとか、アメコミ系の映画はけっこう見たんだけど、バットマンだけ見てないな。今度見てみることにします。映画は本当の傑作に当たれば快楽度が高いからせっせと見るんだけど、これは偏見かもしれないけど、見るにつけ、映画という表現はダメだなと思うんです。どんないい映画でも、物語が進んで意味が充満してくると、音楽が始まるのね。いかにもセンチメンタルな音楽とか、冒険が始まりそうな音楽とか、主人公がこういう心情になっているぞと説明するような、盛り上がりの音楽が必ず入る。こんないい映像なんだから、音楽はやめてよと思ってしまう。そんなに音楽で映像をサポートしなくてもいいよと。でもそこまでしないと、商業的に成功させて元を取ることができないのかな。
遠藤 アメリカ映画の場合、それはあるでしょうね。でもデビッド・リンチ監督なんかは、音楽を嫌味な感じで使っていますね。
三浦 そうですね。デビッド・リンチ監督とかはいいんだよ(笑)。いわゆるハリウッド大作とかの話しですけどね。でも日本の映画も同じだな。本当にいい映像だけで勝負して欲しいんだけど、なかなかそうはいかないみたいですね。
遠藤 アメリカ映画は金儲けの手段だからね。出資してどれだけ儲かるかというメディアですから。
三浦 それに徹してくれれば爽やかなんだけど、変に芸術ぶった凝り方をするときがあるじゃない。そういった中途半端な映画はやめてほしいですね。そう言えば最近いくつか感心した映画があります。ハリウッドではないけど、『アンダー・ザ・スキン』は見ましたか。
遠藤 いや、見てない。どこの映画ですか。
三浦 イギリス・アメリカ合作映画です。『アンダー・ザ・スキン』というタイトルの映画は二つあるらしいんだけど、新しい方で邦題は『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』です。これはちょっと変な感じで面白かった。一応モンスター映画なんだろうな、エイリアンが主人公だから。同じ頃に人間っぽくない仕草をするヒロインが登場する映画がもう一本公開されていて、『LUCY/ルーシー』という映画です。どちらもスカーレット・ヨハンソンが主演してる。最近公開された映画で、『アンダー・ザ・スキン』は二〇一三年制作、『LUCY/ルーシー』が二〇一四年制作です。
『LUCY/ルーシー』はリック・ベッソン監督作で、典型的な商業映画です。どうやったらお客が喜ぶかを考えて作られた予定調和的な映画だから、これはくだらない。『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』は『LUCY/ルーシー』とは正反対の映画なんだけど、同じ女優が同じような役柄で、正反対の雰囲気の映画に同時期に出ている。『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』のような映画がまだ作られ続けている以上は、映画を見なくちゃならないなって思うんです。

『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』(2013年)
ジョナサン・グレイザー監督
遠藤 吸血鬼モノですが、『アディクション 吸血の宴』は見ていませんか。博士論文を書いている女子大生が、最後に吸血鬼になっちゃうっていう映画なんだけど、それも普通の映画の撮り方じゃなくて面白かった。
三浦 さっきも言ったけど、僕は吸血鬼とかゾンビとか、人間の形をしているモンスターは敬遠しているところがありましてね(笑)。『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』も確かに人間の形をしているんだけど、それでもたまたま見てしまって、ああ傑作だなと思っちゃった。
■三浦氏と遠藤氏の出会いについて■
小原 お二人は会うなりいきなりモンスター映画の話しになって、それによって感受性が近いということがわかるわけですが、文学金魚の読者に、そもそもどういう関係なのかを説明してもらえませんか。お二人は同い歳なんでしたっけ。
三浦 遠藤さんは何年生まれですか。
遠藤 一九六一年の十月です。
三浦 じゃあ僕の方が二歳、二学年上だな。遠藤さんと出会った直接的な経緯をお話ししますと、もう廃刊になってしまいましたが、「O倶楽部」という後ろ下半身系の雑誌があったんですね(笑)。僕は研究のためもあって、その雑誌を愛読して編集部なんかに出入りしていました。もう三十年近く前のことです。その雑誌にH・Nさんという女性が、自分の食糞体験を連載していたんです。
小原 それは、誰のものを召し上がるのですか(笑)。
三浦 それはよくわからないんだ。ルポなんだか、体験談なのか、小説なのかわからない書き物だったから、はっきりしないまま話しが拡散しちゃったんです。でもああいう雑誌は人が思っているほどサクラが多いわけじゃなくて、けっこう本物のマニアが集まっているんです。もちろんモデルを使って撮影とかもしているわけですが、H・Nさんの文章を読んだときに、これは編集部が創作してるわけじゃなくて、真剣な執筆者がいるなと直観しました。それで編集部気付けでファンレターを出したんです。そしたら返事が来まして、その中には僕の質問に対してちゃんと正面から答えが書いてあり、お会いしてもいいようなことも書いてあった。それで確か、H・Nさんからバクシーシ山下監督の、上映できなくなった作品の試写会があるからいっしょに行きませんかというお誘いがあり、それで会うことになったんです。現地で会い、いろいろお話しをしてみると、大変な文学少女なんですね。僕はその当時はもう就職していて、ちょうど『M色のS景』という本を河出書房新社から出したところだったんです。彼女は僕の本を読んでくれていて、僕の小説についていろいろ言ってくれたりしてすごく熱心なんです。僕がファンレターを出したんだけど、向こうの方が僕のことをよく知ってくれていた。それであるときH・Nさんが、彼女の知り合いだった遠藤さんを紹介してくれたんです。

三浦俊彦著『M色のS景』
平成五年(一九九三年)河出書房新社刊
遠藤 最初は飲み屋で何人かで会ったんだよね。三浦さんは授業があるからって、ちょっと遅れてきたんです。
三浦 あれ、そうだっけ。最初から遠藤さんの家に押しかけたような気がしてたけど、記憶が曖昧になってるな(笑)。
遠藤 H・Nさんの小説は、「文學界」の最終候補にまで残ったことがあるんです。
三浦 小説家になりたいという野心がある女性で、文章も僕がファンレターを出すくらいだからけっこういいわけです。
遠藤 H・Nさんは最初の小説は「文學界」の最終候補に残ったんですが、それから選考に漏れるようになってしまいましてね。それからちょっとヤケになって、文章を載せてくれるならどこでもいいという感じで、「O倶楽部」に投稿して連載を始めるようになったんです。他のアングラ雑誌にも小説を書いたりしてましたね。
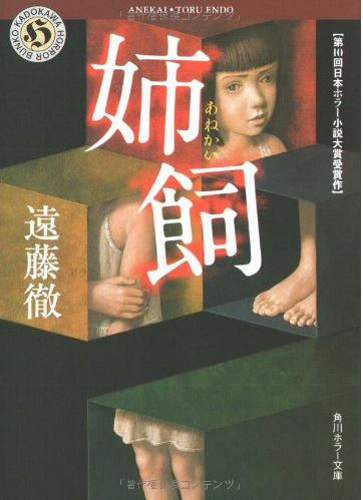
遠藤徹著『姉飼』
平成十五年(二〇〇三年)角川書店刊
三浦 今はもう暴露していいのかもしれないけど、H・Nさんの連載も食糞趣味も、ほぼ完全なフィクションだったんです。ただ最近「O倶楽部」の元編集長に会ってH・Nさんの昔話をしたところ、彼は彼女の話のベースは実体験だと信じていましたよ。文章がうまかったんだな。世に出るためにはなんでもするといった、激しい女性ではありましたけどね。ああいう女性はめったにいないな。
遠藤 H・Nさんは、一時期は映画評なんかも書いていましたが、今はどうしてるんでしょうね。同人雑誌も出していたようですけど、それも三号くらいで廃刊になっちゃって、その後、消息が知れませんね。
■小説を書き始めた頃について■
小原 H・Nさんも小説を書いていたわけですから、小説つながりでもありますね。遠藤さんは理系ですが、小説はいつから書き始めたんですか。
遠藤 あ、僕は元々は東大の英文科で、それから農学部に転入したんです。小説は好きだったんですが、就職した頃は小説を書くのをあきらめていたんです。でもH・Nさんと出会ったことから、彼女の情熱に煽られるような形で、僕もまた小説を書こうと思ったんです。
三浦 大学教員になってから小説を書き始めたという点では、我々は共通しています。
小原 三浦さんは、所属は文学部ですが論理学を専攻されていますね。遠藤さんは英文科から農学部に転入された。私も数学科を卒業してから文学部に学士入学しました。文系一本槍ではないという点では、たまたま今日集まった三人は共通しています。さきほどお二人はモンスター映画の話しで盛り上がったりしましたが、文学をアプリオリに捉える人は、社会的な人間の存在を前提として、そこでのわずかなバラエティを追っかけようとする。でもそれでは飽き足らない、もっとラディカルな追及をしたいという面が、お二人にはあるんじゃないですか。

三浦 こんなことを言うとマズイかもしれませんが、僕も小説を書き始めた頃は、編集者などに誘われて、いろいろと文壇の人と喋ったりしたわけです。ところが哲学者と喋っているのとはかなり違っていました。一時期、学界と文壇の両方とつながりがあったんですが、文壇の人たちの話しは圧倒的につまらない(笑)。なぜつまらないかと言うと、常識を前提とするんですね。常識から離れない。俗情を扇動するのが文学だと言えばその通りかもしれないけど、あまりにも世間的な常識に囚われているなという気がしました。だから文学者は賞とかにこだわるわけですね。世間的な名誉が欲しい、注目されたいわけです。そういう点は芸能人と同じなんだな。
だけど学者はそうじゃなくて、もっと気が長い。そりゃ学者だって注目されたいけど、真実に興味があるんです。だから自分の直観を裏切るようなものが好きですね。いかに日常的な人間の直観が信用できないものか、はかないものかを知って、そこから次のステージに上がってゆくわけです。
文壇の人たちは、そういった真実を求めるということに、まったく興味がないわけです。現状維持なんですね。現状にどっぷり浸かることで快楽を感じる人種なんで、しゃべっていて面白くない。新しい発見がないんです。なあなあの、お湯に浸かっているような状態で楽しい時は過ごせるんですが、学者と喋っている方が僕は楽しい。だから誘われてもあんまり文壇の集まりには行かなくなってしまって、あまりいいことではないかもしれないけど、自ら関係を断つような感じになってしまった。だから今文壇の人とつながりがあるのは、辻原登さんくらいかな。でも辻原さんにもだいぶご無沙汰していますから、今文壇とのつながりはほとんどないですね。
でもやはり理系的な、常識に囚われない、むしろ常識を次々に打破して次のステージにどんどん進んでゆく方が、人間の一生は一度限りですから、新しい展望が開けて面白いと思います。僕はその方が人間を深く理解することになると思うんだな。文学もいいんだけど、理系的にやりたい。数学ほどもっとやっておけばよかったなと思う学問はないんですよ。僕の電子掲示板を見てもらえればわかりますが、数学の人がどんどん書き込んでくれています。数学で議論をふっかけてくるわけです。けっこう険悪な口調になるんだけど、それは僕にとっては有り難いことなんですね。遠藤さんはどうですか。
遠藤 僕は『プラスチックの文化史|可塑性物質の神話学』とかを書いていますから、理科系的な文学論がメインですね。元々の専攻はウイリアム・ブレイクでしたが、ブレイクと十八世紀、十九世紀科学史という視点で研究していました。科学には常に興味がありますね。だからフランケンシュタインとか好きです。
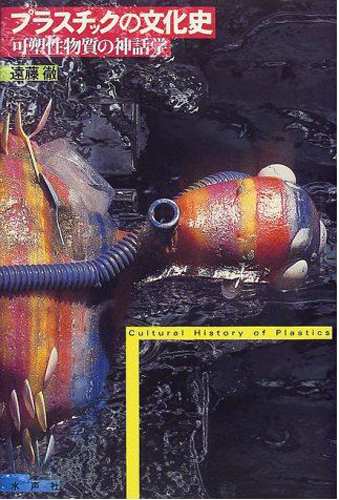
遠藤徹著『プラスチックの文化史-可塑性物質の神話学』
平成十一年(一九九九年)水声社刊
三浦 文学者とのつながりはありますか。
遠藤 ホラー系の作家たちとは会ったことがありますが、ホラー大賞の授賞式に東京まで来なくちゃならないから、最近はどなたともお会いしていませんね。
三浦 どうしようもない人がいっぱいいるでしょ(笑)。
遠藤 そりゃあね(笑)。
三浦 まあ文学者は作品さえ良ければいいんだけどね。学者は話しが弾むし、あんまり個人的な話しにならないんだよね。共通のテーマの話しになるんです。くつろいで話せる。でも文学者は自分の話しになるんだよね。そんな話し聞きたくねぇよ、こっちも話したくないよって感じになってしまう。
これは純文学もエンターテイメント小説も同じだと思うけど、日本ではあまり実験を好まないじゃない。でも理科系的な実験小説ってあっていいと思うんだな。ほんとに言葉遊びだけで書いてるとかね。言葉遊びは詩の領分かもしれないけど、小説でも、もっとやっていいじゃないと思うんです。だから文学金魚はありがたいですよね。やりたいことをなんでもやらせてくれる(笑)。
遠藤 特に僕が書いているのはエンターテイメント系の小説だから、ほんとうに自由がないんです。ホラーじゃないとダメとかね。
三浦 職人芸を求められてしまうんだよね。
遠藤 一番僕がカチンと来たのは、編集者に「エンターテイメント小説は謎が残っちゃいけないんです」と言われた時ですね。それじゃあ、ぜんぜん面白い小説を書けないじゃないですか。でもエンターテイメント小説の世界では、読んだ後に何も謎が残らないというのが大事らしいです。だけど僕はそういう小説が一番嫌いなんです(笑)。
小原 純文学文芸誌の編集者は、「最後はここまでにして、謎を残した方がいいんじゃないですか」なんて言いますけど。
三浦 文学業界を外から眺めている人のイメージだと、純文学の方が堅苦しくて、エンターテイメント小説の方が自由に見えると思うんです。でも実際は逆なんだな。
遠藤 純文学は、みんな自分がやりたいことをやっているわけだから。

三浦俊彦著『下半身の論理学』
平成二十六年(二〇一四年)青土刊
三浦 エンターテイメント小説の方が、現実離れしたことを書けるし、一見自由だよね。でも違うんだな。僕はエンターテイメント小説系の「小説新潮」誌からデビューしたんだけど、「群像」や「文學界」などいろんな文芸誌に投稿していて、たまたまレスポンスがあったのが「小説新潮」だったんです。まあはっきり言えば、デビューできるのならどこでもよかった。ただ文学金魚の僕の略歴に「小説新潮」新人賞受賞と書いてあるけど、あれは誤報で新人賞はもらってないんです。優秀作に選ばれたわけでもない。デビューさせてもらった雑誌についてこんなこと言うと怒られちゃうけど、「小説新潮」新人賞は大作家を輩出しているわけでもないし、そんなに権威のある賞ではないんです。当時の選考委員が井上ひさしと筒井康隆で、僕の好きな作家だったから応募しただけなんです。応募作は純文学雑誌の新人賞でもいいところまで行った作品だったですから、これはやはりエンターテイメント小説ではないということで賞はもらえなかった。だから「小説新潮」の参考作品なんですよ。ただ「小説新潮」に作品は掲載されました。
それが小説家デビューということになるんだろうけど、新潮社の編集者が二人つきまして、盛んに書け書けと言ってくれる。でも作品を書いても現場の編集者は喜ぶんだけど、最後のところ、雑誌には掲載してくれない。聞いた話しでは新潮社は当時は特に厳しいらしくてね。そうこうしているうちに河出書房新社の編集者が声をかけてくれて、そっちで最初の小説の本を出したという経緯ですね。だからエンターテイメント小説系の雑誌から、いつの間にか純文学系文芸誌に移行していった。もし「小説新潮」などのエンターテイメント小説系の雑誌で書き続けていたら、遠藤さんと同じようなジレンマを抱えたのかもしれません。ただ純文学系文芸誌は自由に書かせてくれるから、そういう意味では良かったのかなと思います。ただ最近は僕が他のことに興味を持っちゃったんで、純文学系文芸誌にはあまり書かなくなっちゃいましたけどね。そろそろ書かないといけませんね。
■ラディカルな文学について■
小原 純文学とエンターテイメント小説業界の違いはいろいろあるし、文学金魚の読者もそれについて聞きたい点もあると思うんですが、せっかくお二人揃ってくださったのだから、もう少し根源的はお話しをおうかがいしたいと思います。そもそも小説というのは俗なものでいいのか、なぜ今ある人間の姿をなぞらなくてはならないのかとか。さきほどのモンスター映画の話しでも、お二人は異端の、異形のモノが好きというよりは、そこにむしろ本源や本質があるというお考えなのではないでしょうか。たとえば物語が好きな子供は、本の世界ってすごく自由だと思うわけでしょう。でも大人になって小説を読むと、あれ、本ってこんなに窮屈だったっけと感じてしまう。子供は動物も好きですよね。だけどいわゆる小説の世界では、動物が主人公ではいけないんですよね。人間が描けているかどうかが問われる。
三浦 人間は何を書いたって、人間のことになってしまうわけだから、むしろ人間以外のものについて書いた方が人間っぽくなると思いますね。これは今は反省していることの一つなんだけど、芥川賞候補に三回なったあとで、ちょっと新しいタイプの小説を書こうと思ったんです。今から考えると少し傲慢なんだけど、「すばる」誌で、編集者も内容について同意していたので、人間がまったく出てこない小説を書いたんです。特に話題にもならなかったですが、その連載は二回ぐらい「群像」の合評で取り上げられました。注目してくれようとした批評家もいた連載だったんですが、そのうちの一つにはまったく人間が出てこない。部屋の隅の埃がどうとか、何かが地震で崩れたとか。僕はこういう実験小説もありだろうと思って書いたんだけど、やはりもうちょっと普通の小説を書いてから――僕が最初から普通の小説を書いていたかどうかは別として――普通の小説で実績を積んでから書くべきだったな、と今は感じています。でも何を書いたって絶対人間の話になるだろうとは思います。だから人間を正面から、生活に密着した形で書かないと、人間の本源のようなものがわからないというのは、ちょっと短絡的じゃないかな。江藤淳なんかは、まさにそういう立場だったわけですが(笑)。もちろんそれが日本文学の主流だということは理解していますが、ちょっと違うタイプの小説が目立ってもいいんじゃないかと思いますね。

小原 言葉を使うのは人間だけですから。ただ小説というジャンルでは、人間という存在の輪郭を、少しずつ拡げていくことしかできないのかもしれません。でも、単に輪郭をなぞっているだけの人と、少しでもその輪郭を外そうとしている人が書くものとでは、自ずと違う作品になってくると思います。
三浦 輪郭をなぞっても、書いている人はそれで楽しいだろうし、書く快楽を感じているだろうね。そういえば僕は又吉直樹の芥川賞受賞作『火花』を読んでみたんです。お二人はお読みになりましたか。
遠藤・小原 いや、読んでいないです。

三浦 面白いですよ。僕はあまり芥川賞受賞作を読んでいないですが、数少ない読んだ作品に比べて『火花』は質が高いと思いました。あの作品は堂々芥川賞受賞でいいし、売れて当然だと思うんだけど、第一ページを読んでもらえればすぐわかりますが、いかにも文学やってますって感じの作品なんだな。形容詞とか副詞とかの使い方からして、うまく文学やっていますよ、と。よく出来ているし、確かにこれは日本の文学でいいんだけど、どうせやるならもう少し変わったことをやってみてもいいのにと思いました。この書き方だったら他の人でもできるよね、と感じてしまったなぁ。
遠藤 そういうのが受けるんですよ(笑)。
三浦 元々芸術というものは、そういった型にはめるものではあるんですけどね。僕は前任校で 文化芸術コースというところにいたんだけど、お隣が書道コースだったんです。担当の書家とよく話したんだけど、書道には今、前衛書とかアート書がありますよね。ぜんぜん今までとは違う書を書こうとしている人たちです。ところが僕が話した書家は、それはつまんないって言うわけです。今までのやり方で切磋琢磨して、ほんのちょっとの差で抜きん出る、その発見が書の醍醐味だと言うわけですね。それは僕はよくわかるんです。芸術はそれでいいんです。いいんだけど、そういう型にはめるやり方は、徹底してそうしなければいけない。よほど様式化された微差がわかる世界ですよ。文学の世界で言えば、俳句とか和歌だったらそれでいいけど、小説はそうじゃない。小説は様式があって、その中でやるという芸術ではないですから。
(2015/09/08 後編に続く)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■三浦俊彦・遠藤徹さんの本■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


