Interview:辻原登 (2/2)

辻原登: 昭和二十年(一九四五年)、和歌山県印南町に生まれる。十代の頃から小説を書き始め、平成二年(一九九〇年)、『村の名前』で芥川賞を受賞。その後『翔べ麒麟』で読売文学賞、『遊動亭円木』で谷崎潤一郎賞、『枯葉の中の青い炎』で川端康成文学賞、『花はさくら木』で大佛次郎賞、『許されざる者』で毎日芸術賞、『闇の奥』で芸術選奨文部科学大臣賞、『韃靼の馬』で司馬遼太郎賞、『冬の旅』で伊藤整文学賞受賞と小説界の文学賞を総なめにする。三島由紀夫賞、川端康成文学賞、日経小説大賞などの選考委員もつとめる。
辻原登氏は『村の名前』で芥川賞を受賞後、純文学にとらわれず、エンターテイメント系の作品も含めて数々の小説を量産し続けている作家である。純文学雑誌からデビューした作家で、辻原氏ほど広範かつ旺盛な執筆活動を続けておられる作家はほとんどいない。辻原氏はまた、東海大学文芸創作科で教鞭をとられる教育者でもある。金魚屋では『辻原登奨励賞』の選考をお願いしているが、今回は創作に対するお考えはもちろん、作家デビューするまでの経緯や資料集めの方法など、小説作家ならではのお話をお聞きした。
文学金魚編集部
■小説の取材について■
───文学金魚の読者には作家志望の方が多く含まれているのでお聞きしたいのですが、『遊動亭円木』や『円朝芝居噺』は落語を題材にしていますよね。あれはどのくらいの資料を集めるのでしょうか。
辻原 『円朝』で資料にしたのは古い『圓朝全集』と、藤浦敦さんの落語随筆集『三遊亭円朝の遺言』なんかですね。敦さんのお父さんの周吉さんは明治末の人ですが、青果問屋、いわゆるやっちゃ場の家の息子で円朝のパトロンでした。円朝について書かれた本はほとんど当たったと思いますが、メインはこの二つです。あとは岸井良衛さんの『女芸者の時代』とか、当時の風俗がわかる資料を読みました。それプラス速記の資料ですね。『円朝』で書きましたが、明治維新以降にヨーロッパから速記術が入ってきて、国会なんかの議事録作成に使われたのはもちろん、円朝らの落語の噺の速記にも活用されたんです。
───辻原さんの取材力はすごいと思います。
辻原 取材は自費でこっそり一人で行くことが多いです。ただ『闇の奥』を書く時はボルネオに行かなきゃならなくて、この時は出版社の方に同行してもらいました。だから取材も含めて、井上ひさしさんや松本清張、司馬遼太郎さんのように、膨大な資料の中から小説を書き上げるということはしてないです。ほんとうに、ちまちまっとした資料から小説を書いています。
───そっちの方がすごいですよ(笑)。『円朝』はどのくらいの準備期間で書き始められましたか。
辻原 一年くらいです。
───江戸モノの小説についてはどういう資料をお使いになられますか。
辻原 もう忘れちゃいましたけど、『武江年表』とか安政の地震関係の資料です。僕が必要とする資料は、古本屋に行ったり図書館に行けば、誰にでも手に入るようなものばかりです。特別にすごい資料を必要としているということはないですね。
───『韃靼の馬』はどうですか。対馬の宗家文書は全部お読みになっていないでしょう。
辻原 あれは全部読めないですよ(笑)。でも『韃靼の馬』がきっかけで、宗家文書のファクシミリ版を、僕が勧めて東海大学の図書館で購入することになったんです。重要な宗家文書に関しては、慶應大学の田代和生という女性の先生が何冊か本を書いておられます。それを読めば僕には十分です。あとは朝鮮側の資料ですね。それは東海大学にお二人、立派な専門家の先生がいらっしゃいます。一人は大谷光瑞が専門の片山章雄先生、それに満州、モンゴルに詳しい浅井紀という先生ね。このお二人のところに行って、今度こういう小説を書こうと思うんですが、何を読んだらいいんですかって相談しました。そしたらこういうのがありますよって、本なんかを紹介してくださった。
───古い朝鮮風俗に関しては、手軽な本ではなかなか資料が集めにくいと思いますが。
辻原 取材のために韓国に二度行きました。どうも僕は、最後に鬱陵(うつりょう)島に渡った日本人らしいですよ(笑)。鬱陵島は竹島に最も近い島です。五年前くらいのことですが。で、韓国で資料を集めたんですが、ハングルはできないから、友人の弁護士に彼のところで研修した韓国人を紹介してもらって、通訳をかねて韓国を案内してもらいました。内モンゴルにも取材に行きました。全部自費ですよ。

───古い習俗を扱う場合、考証的に正しいとか間違っているとかは当然あると思いますが、辻原さんの場合、小説での取材内容のこなれ方がすごいですね。手練れの作家です(笑)。
辻原 僕の高校時代からの親友で、日本古代史が専門の吉村武彦という男がいるんです。『翔べ麒麟』を書いた時は、彼に一回ごとに原稿をチェックしてもらいました。
───対馬にも取材に行かれましたか。
辻原 四回くらい行きました。やはり対馬は実際に行かないと、いい作品は書けないです。
■小説の裾野を拡げるということ■
───前にも申しあげましたが、辻原さんはバリバリの純文学作家から、中間小説と呼ばれるような作品にも小説の裾野を拡げていかれた。こんなことを言うとちょっと失礼ですが、たいていの純文学作家は私小説と前衛小説の合間で潰れていくところがあります。名前は知られていても本が売れないから、徐々に一般読書界から忘れられていく。辻原さんはそういう純文学作家的な道を嫌ったところがあると思います。そこにはどういう目的があったのでしょうか。
辻原 僕は小説を書きながらずっと仕事をしていました。でも会社に結局バレちゃうわけです。芥川賞を受賞したのは四十四歳の時ですが、もう芥川賞をもらえそうだなって時に商社を辞めたんです。小説は書いてないと嘘をついていたわけですからね。辞める理由は、母親が倒れて介護しなければならないとか言いましたけど(笑)。僕はその頃、常務取締役営業部長だったんですよ。けっこう偉かった(笑)。だけどそのあとも食っていかなきゃならない。芥川賞なんかでは食っていけませんからね。
で、家内の兄がコンピュータビジネスで割と成功していたんです。大阪に本社があって、東京と横浜支社がありました。その頃、中国の優秀な人材をプログラマとして雇い始めていたんです。一九八〇年代の終わり頃かな。当時は募集をかけると五十人の定員に、千人とか二千人の応募者があったんです。本国より日本の方が、給料が比べものにならないほどいいわけです。中国で募集して日本に呼んで研修して、日本に残る人と、北京支社に勤める人がいました。それで商社を辞めなきゃならないという時に、義兄がうちに来いよと言ってくれた。それで大阪本社に総務部長として勤めたんです。仕事は中国関係の人材の採用です。芥川賞作家が総務部長で来たとか言われてね(笑)。
神戸から阪神電車で大阪の梅田に通ったんですが、何といっても神戸というまちの素晴らしさは忘れられないですね。後(うしろ)に六甲、前方に大阪湾と瀬戸内海と淡路島。とにかくまちが美しい。人間はセンスが良くて、食いものはうまい。神戸に転勤した人間は出世を忘れる、という言葉がありますが、まさにその通り。そこに地震が来て、それから十年後、僕は『ジャスミン』を書いた。
話を本筋に戻すと、芥川賞受賞後に『森林書』という小説を「文學界」に連載し始めたんですが、連載が終わる頃にこんなことをしていちゃダメだと思った。会社勤めもいいけど、自分がなんのために小説家になりたかったのを改めて考えた。ちまちまとした純文学を書くために小さい頃から小説家になりたかったわけじゃなくて、自分は鷗外や漱石、尾崎紅葉や泉鏡花、谷崎潤一郎のような作家になりたかったんじゃないのかとね。そのためにはどうしたらいいか。そうだ、新聞連載をしなきゃって考えたんです(笑)。じゃあ新聞連載をやらせてもらうにはどうしたらいいか。純文学作家のままじゃダメなんで、新聞に向く小説を書かなきゃならない。
当時はまだ中国に行っていた時期で、いろいろ考えて、阿倍仲麻呂を主人公にした小説を書こうと思ったんです。『翔べ麒麟』という作品です。それで物語を組み立てて、企画書を作って新聞社に送った。日経新聞や朝日、読売、毎日新聞など、全部の新聞社に送りました。それが平成八年(一九九六年)、阪神大震災の翌年かな。その前年に僕は東京に引っ越してきて、横浜支社の総務部長になった。義兄が僕のために転勤させてくれたんです。小説を書くにはやっぱり東京にいなくちゃダメだということでね。だけどあの頃は、芥川賞系の作家はほとんど新聞連載をしていなかったですね。
『翔べ麒麟』
平成十年(一九九八年) 読売新聞社刊
───多くの純文学作家はプロットが立てられないですからねぇ。長編は無理です。
辻原 新聞小説は近代小説のお家元なんです。明治維新以降、名だたる作家はみんな新聞小説で活躍して来たんですから。それで僕も必死になって、またYさんを始めとして友人に恵まれていたものだから、みんなに教えてもらって作品を書き上げた。そしたら丸谷才一さんが「これはいい」と誉めてくださって、読売文学賞小説賞を受賞できたんです。結局僕が小説家としてやりたかったことは、新聞小説を書くことだったと思います。
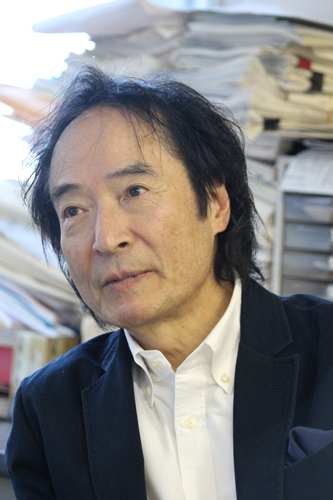
たとえば読売新聞は公称発売部数一千万部でしょう。そのうち一パーセントが読んでくれたって、十万人が毎日読んでくださるわけです。それはすごいことですよね。これは失敗できない、失敗したら、ちまちまとした作家で終わっていくだろうと思ったので必死でした。でも読売で『翔べ麒麟』を書き上げたから、次に日本経済新聞で『発熱』を連載することになった。それから朝日新聞に『花はさくら木』を書いて、毎日新聞で『許されざる者』を連載し、また日経で『韃靼の馬』を連載しました。
そうやって作品を書いていくことが、さっきおっしゃったような作品の裾野を拡げることに役立ったと思います。でもそれはなにかに妥協するということではないですよね。
■辻原小説のエクリチュールについて■
───ただ辻原さんの小説の裾野の拡げ方は、やはり大衆作家とは違うと思います。大衆文学は乱暴な言い方をすればネタ勝負です。また純文学は物語としては極めて特殊な小説だと思います。これも乱暴に言えば、純文学は前衛と後衛の両極端のベクトルを行き来する。現代だとポスト・モダン的な小説を書いて前衛を装うか、あるいは古典的な私小説に徹底的に後退してみせるかです。このベクトルの中にいわゆる文壇のコアがある。でも辻原さんの小説は終わらないんだなぁ。大衆小説のように作品の最後にピリオドがあって、ああ面白かったという作品ではない。でも純文学的な前衛や後衛意識もない。たとえば『抱擁』はヘンリー・ジェイムズの『ねじの回転』が下敷きになっていて、『闇の奥』はコンラッドの同名小説が強く意識されている。ボルヘスの『ドン・キ・ホーテ』的エクリチュールであるわけです(笑)。それが辻原さんの小説を、特に文芸批評家などが評価するときにわかりにくくしている面があると思うんですが、ご自身ではどうお考えですか。

辻原 どうなんですかねぇ。評論家、批評家という人たちから見ると、僕の作品は論を立てにくいんじゃないですかね。もっとわかりにくい作品の方が批評の対象にしやすいのかもしれない。日本の小説批評の流れがそういうものですから。僕の小説の欠点は面白いことにあるのかもしれない(笑)。ただ僕の作品が誤解されているとか、理解されていないというわけではないと思います。まあ今くらいでいいんじゃないでしょうか。僕は批評家の評価よりも、もっとたくさんの読者が欲しいですから(笑)。
───前衛の方向に小説を持っていこうというお気持ちはまったくなかったですか。
辻原 一度もなかったかというと嘘になります。たとえば『森林書』を書いた時はそういう気持ちがあったかもしれない。ところが今読み返すと、やっぱり物語性を追求している作品です。僕には資質的に、前衛的なものに対する不信感があるんじゃないかと思います。ただ高校生の頃とか二十代前半の頃は、一種のファッションとして、前衛的なもの、秩序破壊的なものをまとう必要があったと思います。そういう試行錯誤は繰り返してきたけど、僕自身の中では、そういうものにあまりシンパシーがないと思います。たとえばカフカとかゴーゴリーの作品は、前衛とかそういう問題ではないですよね。カフカにあるのは物語性だと思います。
───その通りだと思います。
辻原 そういう意味では、僕は資質的にはカフカだと思っています。
───そうですね。異空間、謎、でも謎解きはないなど、辻原さんの小説はカフカ的です。
辻原 小説が造形化すべきものは物語であって、それ以外に小説でなすべきことは、僕にとってはないということです。
───賛成です。今のポスト・モダン的な小説は、ほぼ全部文学史の上から消え去るでしょうね。ただ現代がポスト・モダン的な状況にあるのも確かです。ポスト・モダン的な小説にはいわゆるエクリチュールしかない。でも矛盾するようですが、辻原さんの作品も十分ポスト・モダン的です。作家の出生にまつわるトラウマとか、作家固有の主題は一切ない。作品ごとに主題や中心観念がズレていくという意味で、辻原さんの作品も極めてエクリチュール的だと思います。でも辻原さんの小説はあくまで物語を中心にしている。それが辻原文学の現代性をわかりにくくしている要因かもしれません。最近の若い作家の作品はよくお読みになりますか。
辻原 あまり興味ないですね(笑)。文学賞の選考委員をやっていますから、その時は一生懸命読んで良い作品を選びます。ただ若い作家と言われても、あんまり思い浮かびません。それは同世代でも同じで、別に気になる作家はいないなぁ。まあ、僕は元々そういう人間なのかもしれませんが(笑)。
───辻原さんの小説は、プヴァールとペキシェ的エクリチュールでもあると思うんですね。でも全ての物語を書き尽くすことはできない。辻原さんの小説はこれからどうなっていくんでしょう。
辻原 それはわかんないな(笑)。特定の方向性というものはないです。いいテーマやエピソードが浮かんだ時に小説の構想が始まります。海に潜って綺麗な石を見つけて、これはいいやと思って浮かび上がってみたら、なんてことのない石だったってことは何度もあります(笑)。でも小説は、地上に持ってきても消えなくて、拡大しても魅力が失われない石のきらめきを発見するということに尽きますね。どんな石が魅力があって、きらめいているのかはその都度違います。だけど方向性はなくても、プラトン主義的なイデアみたいなものが最初にあれば、そういう石は見つけられると思うんです。もちろん石はきっかけにすぎなくて、そこから色々取材や勉強したりして小説を組み立てていかなければならない。僕の小説はその都度違うでしょう。それは特に違うことをやろうとしているわけではないんだけど、やっぱり石によって作品が変わらなければ面白くない。
『遊動亭円木』
平成十一年(一九九九年) 文藝春秋社刊
───でも辻原さんの小説は一貫してるんだな。純文学作家の作品だと思います。
辻原 僕は自分では純文学作家だと思っています。でも小説は妄想の世界だから(笑)。それがなくてはなにも始まらない。
───純文学作家としては、売れすぎているかもしれませんよ(笑)。
辻原 読者の方が、一万部とか二万部本を買ってくださるわけですから、いつもこれで良しとしなければいけないなぁと思っています(笑)。純文学の世界は厳しいですから、これ以上なにを望むのかっていう感じはありますね。
───辻原さんは若い頃は映画監督におなりになりたかったそうですが、その欲望は、今お書きになっている小説からも読み取れます。映像とも音楽とも違って、『遊動亭』が典型的だと思いますが、盲目の人が触ることで何ごとかを認知していくような感じがある。『遊動亭』は谷崎潤一郎賞受賞作品でしたか。
辻原 そうです。あの時の選考委員も丸谷才一さんなんです。
───『遊動亭』は傑作です。やっぱり小説の世界の評価は、なんやかんや言って正確だなぁ(笑)。丸谷さんについては今一つ納得できない部分があったんですが、辻原さんの追悼文を読んで、ああなるほどと思いました。戦後文壇的知性は丸谷さんで終わりです。辻原さんの文章を読んでよくわかりました(笑)。
辻原 丸谷さん的な知性の対局にいるのが吉田健一です。吉田健一については、僕はまた別の意味で愛着があるんです。
■若い創作者へ贈る言葉■
───辻原さんには金魚屋で「辻原登小説奨励賞」の選考をお願いしているわけですが、最後に若い創作者に向けて、アドバイスをいただけませんでしょうか。
辻原 とにかくいいテーマを見つけなさい。よくテーマなんかいらない、とにかく書けばいいんだって言う人がいるけど、そんなことはない。もちろんいいテーマだったかどうかは、作品を書き終えてみなければわからない。だけどとにかく書く前に、いいテーマを見つける必要があります。これは絶対に必要です。で、見つけるために何をしたらいいのかは自分で考えてください(笑)。書き終わってみていいテーマだったら、それは必然的に傑作になります。
───貴重なアドバイス、ありがとうございます。今日は長時間、ほんとうにありがとうございました。

(2013/12/13)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■辻原登さんの本■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


