 偏った態度なのか、はたまた単なる変態か(笑)。男と女の性別も、恋愛も、セックスも、人間が排出するアノ匂いと音と光景で語られ、ひしめき合い、混じり合うアレに人間の存在は分解され、混沌の中からパズルのように何かが生み出されるまったく新しいタイプの物語。
偏った態度なのか、はたまた単なる変態か(笑)。男と女の性別も、恋愛も、セックスも、人間が排出するアノ匂いと音と光景で語られ、ひしめき合い、混じり合うアレに人間の存在は分解され、混沌の中からパズルのように何かが生み出されるまったく新しいタイプの物語。
論理学者にして気鋭の小説家、三浦俊彦による待望の新連載小説!。
by 三浦俊彦
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 橘菜緒海を恨みの糞ゲリラへ駆り立てひいてはおろち文化の一翼を担わせることになったあの風呂盗撮ビデオは、γアソシエというメーカーの『盗撮 若い娘のオンリーのお風呂 厳選バージョン 関西編2』(VHS、60分)という商品だった。本当は清里のリゾートホテルなのに「関西編」は無意味な詐称もいいところだが、一つには盗撮場所をカムフラージュする防御策であること、もう一つには、当時、『盗撮 関西女風呂』(マジカル:TKO-01~)『関西発 素人盗撮ラブホテル』(素人JACK:KANSAI-01~)『なにわパンチラストリート』(関西映像倶楽部:3NP-01~)『盗撮 大阪女のパンツ』(TOP-01~)等々、風呂・ラブホ・パンチラを問わず盗撮ものにやたら関西系統のタイトルが使われてそれが一時的にヒットした風潮さなかの製品だったことが一因であろう。エロイメージ誘発フレーズの筆頭が「関西」だという知られざるトレンドがAV業界に長らく定着していたのである(少し遅れて『隠撮前下アングル 関西公衆和式便所』(エボビジュアル:E68-01)等、トイレ系にも「関西」が隆盛を極めることになる)。ともあれγアソシエの社長・染谷晃司25歳(当時童貞)は、女盗撮師から買い取った風呂盗撮ビデオを何度も吟味の上、「ブスとババァを消す」べくモザイク処理に専念したのだった。しかしババァはともかく、ブスについては、微妙な判断基準を採用していた。すなわち、紛れもない美人や可愛い系ははっきり顔出しにし、明らかなブスは潰したが、残りの約7割の多数派――ちょい可愛いからちょいブス至るまで――に関しては、個人的な基準を採用した。「これは隠しておこう」という女についてはモザイクをかける、という扱いをしたのである。
「これは隠しておこう」とは? その選択基準はなかなか難しい。基本的には顔出しが多くないと売れないので、熟慮の末「これは隠しておこう」に分類してモザイクをかけたのはビデオ一本につき一人もいない程度、正確には染谷晃司が手がけた全50本のビデオのうち計17人が「これは隠しておこう」系にピックアップされ、真正ブスといっしょにモザイクがかけられた。ある意味厳選された被写体である。
「これは隠しておこう」系とはどんな女だったのだろうか? 正確には「これはとっておこう」系と呼ぶべき女である。簡潔にいえば、染谷晃司の「好みの女」ということなのだ。人に見せるのはもったいない、自分だけの女にしておきたい、商品化したりすればどこのクズ野郎のズリネタになるやもしれない、どこのキモヲタの妄想の中でなぶられるかもしれない、そういう汚されかたは思うだに耐えられん、穢されるに忍びないといった「好みの女」。無数に登場する入浴娘たちの中から、計17人が厳選されて、外部の有象無象の目に触れぬよう染谷晃司ひとりのために顔を保存されたのである。そして橘菜緒海はその「これはとっておこう」系のナンバー・ワンだったのである。
ブス認定どころか、囲われていたわけだ。
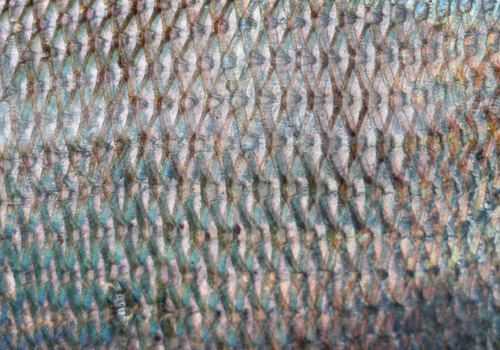
染谷晃司の審美眼では、橘菜緒海は「ちょい可愛い系」に分類された。前述のように、自分がモザイク組に入っているのを見た橘菜緒海はショックのあまり「ちょい「ちょい「ちょい「ちょい「ちょい「ちょいブス」」」」」くらいに言われても文句言える筋合じゃないかもしれない……」的弱気の内省に沈み込んでいたのだったが、実は少なからぬ客観的な視線の先で橘菜緒海は「ちょい「ちょい「ちょい「ちょい「ちょい「ちょい可愛い」」」」」以上には高確率で認識される部類に属していたのであって、染谷晃司ははっきり「ちょい可愛い」と判断し、しかも童貞特有の狭小なストライクゾーンで再三熟慮判断しなおしたうえでのピッタシ好みだったのである。端的にいえば染谷晃司は橘菜緒海に恋したのである。この女を有象無象に見せてはなるものか……商品化バージョンから顔消去した独占的な形で、自分用モザイク処理前バージョンの橘菜緒海の顔アップ場面を日夜繰り返し観賞、シゴイていたのだった。
ブスだから消去されたのではなく実は好まれて尊重のあまり消去されていたという、まさに正反対の論理によるモザイクを、橘菜緒海本人が当然の誤解というか恨みをもって内面化しおろち文化主導者への道をツッ走ることになったというのは、おろち文化史上最大の、あまりに微妙といえば微妙、瑣末にしては瑣末にして最大の皮肉といえよう。
皮肉といっても、そもそもモザイクの正統的機能は「好まれすぎる対象を消せ!」だったのだから、菜緒海顔モザイクは単に本来正統のモザイク用法に復帰しただけのことであり、正統が「皮肉」になってしまうところにおろち文化の骨肉的因業が仄見えるのだ。
なお染谷晃司は、γアソシエ風呂盗撮専門に限定していたことからわかるように、トイレもの、ひいてはスカトロもの全般が大の苦手であった。染谷晃司という男は自称フジアキコ隊員似の「見た目中性系ちょいハンサム」風ダンディであって(常々自らを女性に喩えていたところが〈この業界人〉の面目だったともいう)、ゴキブリ・クモ・ヘビ・ナメクジ各々への出会い頭に直立悲鳴というありがちシーンが各々につき二度以上目撃されており、ブスとババァーは心底大嫌い、とにかく汚いもの嫌い汚いとされるもの残らず大嫌いという徹底通俗の業界人種であって、おろち文化との親近性は限りなく薄い。後のおろち文化隆盛に伴って、世の潮流と体質が合わなかったゆえだろう、おろち21年に「麦茶を喉に詰まらせて」という低確率の原因によってひっそり死亡している。死ぬまで独身だったが(そしておそらくは童貞だったが)、画面内の橘菜緒海にあまりに恋しすぎたがゆえの貞節だったという説が有力である。いとしの君がおろち文化の第一人者であること、しかも自分の恋心に発したモザイク処理が彼女をそちらへ走らせたことを知ったら、AV界の反おろち強硬派急先鋒だった染谷晃司、さぞ胆汁苦い名脇役的自覚を噛みしめたことであろう。
■ くしゃみというのは排泄行為の一つである。食物が口いっぱい詰まっているときに込み上げて爆発するくしゃみほど腹立たしいものはない。むろんくしゃみなどという抽象的な存在に真に腹を立てることは不可能なので、その怒りは自分自身に向けられる。人が自己へ最も強い怒りを向けるのは、咀嚼中のくしゃみというごく些細な瞬間においてなのである。しかも蔦崎公一の場合は、単なる一過性怒りということではすまない永続的な刻印をくしゃみが残したのだった。
中宮淑子路線が途切れた現実においては、蔦崎公一生涯最愛の恋人は、香坂美穂一人に絞られる。大学入学直後に「西洋哲学史B」の授業でたまたま斜め前に座った美穂の印象は、「なんて美人なんだ!」というものだった。蔦崎の美意識は当時、二重瞼アーモンド形の目がややつり上がり、鼻筋が狭く高く、鼻の頭と唇と顎が一直線をなす、なめらかな色白の顔を、自動的に「美しい」と判定するモードになっていたのである。あまりに眩しく清潔すぎる美穂には常に心理的・物理的距離を置き、自分なぞとは無縁の存在と見なしていたために、彼女が席から立った姿を見たのは夏休み前の最後の授業終了時が初めてだったのだが、そこで蔦崎は一転して美穂に参ってしまうことになる。美穂はすっきりした上半身からは想像もつかぬ鈍重な腰とパンスト越しにも吹き出物だらけの極太O脚の持ち主で、意外と背も低く、その歩き方は鰐足ドタ足の愛嬌に溢れていたのだった。しかもそのあまりの愛嬌にすれ違いざま思わず意味もなく声をかけたときエッ、とはにかんだような美穂の反応が、クールな容貌に似合わぬうぶさで、このアンバランスの昇差、というべき落差が、後のプチ流行り言葉を合成使用すれば天然ツンデレというか、蔦崎眼中の美穂に、もう無縁の遠い存在でない、最上級の愛らしさを付与したのであった。

二人がどのようにして初めて言葉を交わし、つきあい始めるようになったかについては記録が残されていない。名前をご記憶の通り、香坂美穂というのは実は蔦崎にとっては小学校時代の因縁の少女であった。美穂は蔦崎と初めて話した瞬間に(あ、ツタゲソ……)小学校の同級生であることを見抜いていたのだが、蔦崎はしばらく気づかなかった。まもなく美穂の指摘によって事実を認識したとき、美穂の方に容易に気づかれていたにもかかわらず自分が失念していたというメタ事実に蔦崎はショックを受け、恋愛感情は己れの方が強いのに、一方的に憧れるところから出発していたはずであるのにという捩れた自負とない交ぜになって、なんですぐに思い出せなかったんだ、ああなんという……妙に敗北主義的マゾヒスティックかつ自罰的な精神的負い目を美穂に感じつづけることになったのである。(一方的に、という蔦崎の自負は、百%妥当とは言えないかもしれない。というのも、蔦崎は最後まで知ることがなかったが香坂美穂は、再会を予想していたはずもないにせよ四年2組のとき蔦崎公一に「カンチョー」されたときのパンツを、尻部中央に茶色い突き染みのついた当時のまま未だに保存していたという事実があるからである。美穂転校後の一方的な暑中見舞と賀状とも思い合わせると、蔦崎と香坂美穂の再会も、偶然とは思われないふしがある。女性サイドからのおろち史記述が遅れているとはしばしば指摘されることだが、その一つの突破口が香坂美穂研究であることは間違いない)。
蔦崎公一と香坂美穂は、五秒と沈黙が生じないほど話が合い、かといって疲労するわけでもなく、文字通りあっというまに時間が過ぎてしまうという、つまり後で日ごと想起すればとてつもなく長い時間に引き延ばされて感じられるたぐいの超濃厚なデートばかりだったのだが、とにもかくにも悦楽の限りだった。理想の恋人同士だったといっていい。どうして小学校時代にはあんなにいがみ合ってばかりいたのか。小学校時代の下半身がらみの反省話は最初の二三度を除いて互いに口にしなかった。
かくも最愛の恋人と再会し交際開始しておりながら、蔦崎には当時平行して、もう一つの体験があった。最愛に嘘はないものの、疑似愛ですらないどうでもいい別口異性関係において一種開眼プロセスの進行せざるをえなかったところが、最愛生活のアイロニーと言うべきか(アイロニー一般については笹原圭介の天然尻哲学を参照せよ)。この「アイロニー」あるがゆえに、最愛が最愛の輝きを天然光として放つことができるのであるし、別の一面から言えば、あれほどの最愛生活の中ですらこうだったというのは蔦崎公一の食ワサレ体質の根深さ・重症ぶりが証明されて余りあるということにもなるだろう。【以下、蔦崎公一の篠田辰則への談話、蔦崎公一の印南哲治への「懺悔」、『蔦崎日記』などより再構成】
美沙子という新たな女の部屋に呼ばれたことで有頂天になっていたなどと思ってもらっては心外だ。僕には美穂がいるのだし。
ただ迂闊だった。油断していた。美穂との極上恋愛生活に気を奪われて、自分の呪われた体質を忘れていた。無念だ。気がつかなかったのも僕の落ち度ではない。やっぱ浮気なんてするもんじゃないよな。でも美穂と結婚してたわけじゃないんだから。人間関係は自由なんだから。ただ、「俺って、嫌いなものはないぜ。不味いと思ったものがないんだ」と断定したのがそもそもの始まりでしたね。何がきっかけになってそう断定したのだったかは忘れたけど。ただし、旨いと思わないものはあるけどね。赤飯なんか全然好きじゃないし、うどんってやつは何度食べても首を傾げざるをえないし、そう言うとすぐ、おまえ関東だからだよって、神戸出身の男だの大阪在住の女だの、一度ちゃんと関西のうどん食ってみろよと、まあよってたかってすぐそう言われるんだけど、そう躍起になられてもなあ、うどんはうどんだろ、汁とか具の話してるんじゃないんだから。うどんの話になると関西関西って卑猥なほど関西攻撃受けるんでかなわんですよ。鮨ネタのなかじゃイカとタコがいまいちかな。ぷりっぷりのサバの棒寿司なんかと比べるとイカタコっていかにも低級な食いもんって感じ。いくらなんでも格が違うって感じ。卵焼きもいらんな。店の腕前を計るには卵焼きとかよく言うけど。あとあらゆる種類の餅が食い物としてインチキだと俺思ってるし、むしろ俺にとっちゃ旨くないもので溢れかえってると言っていいくらいだな、この世の中は。シュークリームなんかどーしてあんなに女の子たち好きなわけ? カスタードクリームなんて物質なんであえて存在するの、みんな限られた人生だってのに? スポンジケーキ、ホットケーキ、バニラアイス、ドラ焼き、やれやれどれも旨いと思ったこと一度もないよ。いや、俺味覚は正常だと思うけどね。甘いもん基本大好きですよ。たとえば月餅なんてなかなか乙じゃん。あくまでなかなか程度だけど、種月餅じゃなくて餡のぎっしり重いやつね。ゴマ餡、いやナツメ餡だったら最高。あと烏龍茶なんか五十銘柄を目隠しして言い当てられるくらい舌は敏感だぜ、340ml缶に限るけどさ。その俺が言うんだよ、旨いもんってほんとにないもんだよね。……って感じの俺のこの気まぐれっちゃ気まぐれな断定が、美沙子を面白がらせたようだ。「こんな面白い話聞いたの久しぶり」とかって。それじゃあ、てんで美沙子は、明日、もう一度来てくれる? とっておきのスペシャル料理用意しておくから。と頬を紅潮させたのだった。あ~ア、本命の恋人とこの上なくうまくいってるってのに、ただ先輩の義理で顔出した合コンで目が合った女の誘いになんかホイホイ乗ってアパートまでついてっちゃう俺ってつくづく男だよな。差別語つうか侮蔑用語としての「男」ね。
翌日、朝食も昼食も抜いて、美沙子の部屋に行きました。反省なし。
その日から、六日おきに俺は、半年にわたって美沙子の手料理をご馳走されることになったのだった。美穂とうまくやりながらですよ。我ながらあの頃の自分を殴ってやりたいね。
美沙子ってのはやっばほら、僕のこの面相に惚れたくちです。単純な野性味主義。
うんざりだけど、今度ばかりは俺も素直だった。
俺は正直に感想を述べた。
松の実入り赤飯、柳葉魚卵あえのタコマリネ、トマトポタージュうどん、イカそうめんの湯葉包み、しめじのヨモギ餅綴じ、無花果の天ぷら……
俺があえて旨くないと言った食材を使って次々と繰り出してくるのだが……、困ったことにこんなところが美沙子のたまらない魅力の核心だ。率直なところ、四割は「旨い!」と唸らざるをえなかったのだから頭が下がる。もちろん「不味い」ことは一度もなかった。いや、一度もというか……、
今になってみるとあの頃はずっと、僕の「食ワサレ体質」が初めてまともなものを食わされていた唯一正常な、ということは全体から見ればアブノーマルな時期だったと言えますかね。美沙子はとにかく、どんどんいろんなものを僕に食べさせたがりました。そして感想を言わせたがりました。そんな中であの日の料理が、印象にひときわよみがえってくるわけで。
あの日というのは美沙子の誕生日だったんですが、あの日だけ、なぜか美沙子は頬を染めて、上目遣いで、何かを隠しているような後ろめたいような。でも俺は、何もおかしいとは思わなかった。いつもと違うことだけはすぐ見て取れたが、「かわいい」としか感じなかった。もうこの頃には俺もうっかり有頂天になっていたんだろうな。馬鹿だよね、男って。いや一般化してもしゃあないな。馬鹿ですよね俺って。

どう? まずくない?
どう? だいじょうぶ?
食べられる?
美沙子は正座したまま身を乗り出して、不安そうに覗き込み続けるのだ。
やけに味を気にしている。前菜のスープ。いつもなら「どう、おいしい?」と朗らかに聞いてくるのに、何か特別、わけありだ。
どうしてそういう聞き方するの? おいしい? って聞けばいいじゃん。おいしいよ。俺がもう何遍も口へ運びながら自然に答えると、
厚かましいような気がして…… あ、でも、そう。おいしい?
美沙子はホッとしたような笑顔を輝かせたが、まだ何か心配そうな、猜疑に翳った上目遣いでちらちら僕のもぐもぐする口元を見つめている。
肝心のメインは、普通のトマトシチューらしき汁の中にロールキャベツが四つ沈んでいるのだが、その中身が挽肉を固めたものには間違いないらしいのだが妙に鮮やかな青紫色は、なにやら特別な野菜がフィーチャーされているようでもある。雰囲気も確かに今までの料理とは違う。しかし、二つ目をホクホクとの見込み三つ目を口に入れかけたところで、ジーンと、それこそなにか、美沙子の無根拠な心配の波紋が空中を伝播して染み込んできたかのように、じわじわっと、とてつもなく苦いというか生臭いというか、滲み出てくる汁を舌と頬に染み込ませているうちに、何ともいえぬ不味さが……、
うっ……、
どうしたの? 不味いの? 口を押さえた俺を、美沙子は本気で覗き込んだ。
うっ……、
小学生の頃、低学年の頃いろんなものが、たとえばセロリがどうしても食えなかった記憶が膨張してきた。忘れていた嘔吐感。
俺はこらえた。
こらえ抜いた。
完食した。
強烈なげっぷが出た。
美沙子が俺に毒を食わせるはずなんかないんだから、もう気にしないことにした。
翌朝、唇の左端下の脇に、でっかいおできが出来ていました。はじめは肌色がそのまま直径三ミリ盛り上がっていたのが、やがて茶色に、真っ赤に膨らみ、しまいに黄色くしぼんで、二週間目にポロッ、とはがれて。でかいニキビというか脂肪の塊だった。唇の脇にでかいクレーターが残りました。その後はほら、まだここにこう、ポコッとした火傷の痕みたいなテカリになって残ってます。
結局、その食べ物が何だったのか、美沙子は教えてくれなかった。
最近ですよ、印南先生のとこで修業しはじめてからです。あれの味を正確に思い出したのは。そしてあれが何だったか納得がいったのは。
(第25回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『偏態パズル』は毎月16日と29日に更新されます。
■ 三浦俊彦さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


