 様々な音楽を聴きそこから自分にとって最も大切な〝音〟を探すこと。探し出し限界まで言葉でその意義を明らかにしてやること。音は意味に解体され本当に優れているならさらに魅力的な音を奏で始めるだろう。
様々な音楽を聴きそこから自分にとって最も大切な〝音〟を探すこと。探し出し限界まで言葉でその意義を明らかにしてやること。音は意味に解体され本当に優れているならさらに魅力的な音を奏で始めるだろう。
ロック史上最高のバンドの一つとして名高い「ザ・バンド」(ロビー・ロバートソン、リチャード・マニュエル、ガース・ハドソン、リック・ダンコ、リヴォン・ヘルム)を論じ尽くした画期的音楽評論!
by 金魚屋編集部
第五章 ザ・バンドを読む
●永井荷風の「西洋音楽」事始め
ぼくのように、昭和期の日本で普通に育ち、専門的な音楽教育を受けなかった者に、西洋音楽を「理解」することは可能なのだろうか。もちろんミュージシャンや音楽学者に限らず、西洋音楽を理解することができている人も多いだろう。ぼくだって自分は西洋音楽を理解しているはずだと思いたい。しかし、歌謡曲しか知らなかった子どもの頃を思い起こすと、自分の「理解」は、西洋人が自然に西洋の音楽を聴いて理解していることとは異なる事態であるように思える。
永井荷風は、アメリカで初めて西洋の音楽を聴いた時のことをこう書いている。
「西洋へ行つては、其時を機会としてまづ第一に音楽を聞かうとした。然し西洋の音楽は単音の日本音楽のみを聞いて居た耳では騒々しいばかりで、少しも美感を誘はなかつた」(『音楽雑談』)
荷風は尺八は得意だったが、ポリフォニックな音楽は聴いたことがなかったので、西洋の音楽をどう聴けばよいのかがわからなかったのだ。しかし、歌舞伎に通じるところがあるオペラを手掛かりにして、すぐに西洋音楽の聴き方をマスターし、やがて同時代の音楽としてリヒャルト・シュトラウスやドビュッシーについても深く理解するようになった。とりわけドビュッシーに関しては、マラルメなど象徴主義の詩をフランス語で読んでいた荷風は、現在の日本の普通のリスナーより深く理解していたに違いない。だが、永井荷風は自分が日本人であり、「日本」には元々西洋音楽がなかったことを前提としてよくわかっていたのだとぼくは思う。この前提を外してしまえば、いまでも、本当の意味で日本人が西洋の音楽を「理解」したことにはならないのではないだろうか。
ぼくは、外国人が日本の詩歌を理解することができないとは思っていない。ピーター・J・マクミランが朝日新聞に連載している「星の林に ピーター・J・マクミランの詩歌翻遊」を読めば、彼がアイルランド人であることを前提として、いかに深く日本の詩歌について理解しているかがわかる。前提を踏まえて、手続きを踏み、豊かな感性があれば、外国人でも日本の詩歌を理解することは可能だ。
●ザ・バンドを「読む」
第四章まで書いてきた内容で誤解を与えたような気がするが、ぼくはザ・バンドの音楽をただ繰り返し聴くだけですべてを「理解」できると思っているわけではない。もっとも、ぼく自身は、無理してロックを西洋人と同じように聴けるよう努力する(英語をマスターする)必要もなければ、異文化として理解しようと努力する(文化人類学的に研究する)必要もない、ただ「音楽」として聴けばよい、と思っている。ロックは自由な音楽だ。誰がどう聴いたってかまわない。
ワンダーミンツのダリアン・サハナジャ(ブライアン・ウィルソン・バンドの中心メンバー)は、大滝詠一のアルバム『イーチ・タイム』についてこう語る。
「伸びやかなトーン、ゆったりとレイドバックしたフレージングで歌われる彼のヴォーカルは、まるでそれ自体がオーケストラの楽器であるかのように聴く者の心を和ませる。歌詞を〝聴き取る〟ことができないからこそ、言葉の意味を読み解くことができる者以上に、僕にはそれが感じられるのだ」(丸山京子訳、「大滝詠一『イーチ・タイム』40周年の考察」、ERIS第41号)
これこそ、まさにぼくがザ・バンドの音楽を聴くときの聴き方だ。「歌詞を〝聴き取る〟ことができない」ことは、音楽を聴く上では必ずしも問題ではない。なぜなら、「歌詞」は「詩」ではなく、「音楽」だからだ。音楽を聴く上では、「理解」することより「感じる」ことが大切なのは今さら言うまでもないことだろう。
だが、もしザ・バンドの音楽について「理解」を深めたいと思うのであれば、本を読むのがよいと思う。バーニー・ホスキンズの『ザ・バンド 流れ者のブルース』(奥田祐士訳)と『ロビー・ロバートソン自伝 ザ・バンドの青春』(奥田祐士訳)およびリヴォン・ヘルムの自伝『ザ・バンド 軌跡』(菅野彰子訳)を読めば、メンバーの背景にあった「文化的環境」がよくわかるはずだ。
日本では近年ザ・バンドに関する重要な本が次々と刊行されている。刊行された順に取り上げていくと、まずは五十嵐正著の『ザ・バンド全曲解説』(シンコーミュージック、二〇二一)。ひとりでザ・バンドの全曲を解説した、すばらしい労作だ。著者自身によるザ・バンドのメンバーや初期のプロデューサーとしても知られるジョン・サイモンへの貴重なインビューも収載されており、ザ・バンドの音楽をより深く理解するためのすぐれたガイドブックである。五十嵐はザ・バンドについてこう言っている。
「ザ・バンドの残した音楽自体はまったく古くなっていない」「僕はそんなザ・バンドをなんのためらいもなく、ロック史における最高のバンドの座に置く。彼らの作品はロックという音楽の地図を描き、そこを旅するためのコンパスともなった。カントリー、ブルーズ、R&B、ゴスペル、伝統のバラッド、ロカビリー、ジャズ、宗教歌など、あらゆる種類のルーツ音楽をとりこんだ先駆的なミックスは、90年代後半以降アメリカーナと呼ばれるようになったルーツ指向の音楽のテンプレートとして、今もなお多くのアーティストにとっての重要な指標である」(五十嵐正「はじめに」『ザ・バンド全曲解説』)
五十嵐はザ・バンドの音楽を「アメリカーナ」という観点を導入して分析しており、ただひたすらザ・バンドの音楽に耳を傾けているだけではわからない、ザ・バンドの音楽の文化的背景への手引き書にもなる。日本人のリスナーにはハードルが高い歌詞の世界を理解するのにも役立つ貴重なガイド本だ。この本を参照しつつザ・バンドの全曲を聴いた後は、グリール・マーカスが一九七五年に出版した『ミステリー・トレイン ロック音楽におけるアメリカ像』(三井徹訳、日本語版注釈:五十嵐正)を読むことをおすすめしたい。この本を読めば、「ロック」という音楽がいかに「アメリカ」と深く結びついているのかがわかるだろう。

五十嵐正著『ザ・バンド全曲解説』(シンコーミュージック)
さらに、この本を読んだ後に、『ミステリー・トレイン』の原型とも言えるレスリー・A・フィードラーの『アメリカ小説における愛と死 アメリカ文学の原型Ⅰ』(佐伯彰一ほか訳)を読めば、小説を通して「アメリカーナ」についての理解を深めることができるだろう。フィードラーがユニークなのは、テクスト分析による批評ではなく、さまざまな文化的コンテクストの中にテクストを位置づけるコンテクスチュアルな批評を意識的に行ったことだ。「アメリカーナ」という概念を頼りにザ・バンドの音楽を理解しようというアプローチは、コンテクスチュアル批評と考えてもよいだろう。フィードラーはこう書いている。
「コンテクスチュアルな批評家が目ざすのは、芸術作品を位置づけること、コンテクスチュアルな各周円が互いに接し、重なり合う地点を確かめることであり、というのも、この地点こそ作品の両義性(アンビギュイティ)(曖昧さ)と豊かさがそのまま息づいている場所だからである」(「第一版の序文」一九六〇年)
フィードラーのこの表現を借りれば、ザ・バンドの音楽世界は「曖昧さと豊かさがそのまま息づいている場所」とも言えるだろう。
●THE BAND playing THE MUSIC
和久井光司責任編集の『ザ・バンド完全版』(河出書房新社、二〇二二)もすごい本だ。帯のキャッチコピーに「究極のヒストリカル・ディスコグラフィ」とあるとおり、ザ・バンドに関係のある多種多様なアルバムを取り上げたり、複数の筆者の「耳」でザ・バンドやメンバーの作品にコメントしたり、ツアーデータまで細かく調べてあって、「完全版」の名にふさわしいガイドブックだ。この本の「まえがき」で和久井はこう書いている。
「よりディープにアメリカ音楽の深淵に迫った感のある「オールド・ディキシー・ダウン」に(誤解をおそれずに言えば)カントリーの要素はほとんどなく、曲のつくりは〝プログレッシヴ〟でさえある。〔中略〕 それを簡単に〝カントリー・ロック〟と言ってしまうことに違和感を覚えた私は、〝ザ・バンドのようなグループはほかにいたのか?〟を50年かけて秘かに検証してきたように思う。/結論を言えば、ザ・バンドのほかにザ・バンドのようなバンドはない。〔中略〕 3人のヴォーカル・ハーモニーとガースのキーボードをどこに置くかで見せるマジックは、表裏をひっくり返したような頭脳プレイだった。/だから、ルーツなんて知ったことか、アメリカなんかクソ食らえ、という意識でザ・バンドを聴き直してほしい。それが50年後に見えてくる真実だ」(和久井光司「まえがき」『ザ・バンド完全版』)
和久井には及ばないものの、ぼくも四十五年以上かけてほぼ同じ結論に達したと言ってよいだろう。ぼくが第一章で「ザ・バンドだけ」が好きと言っているのは、「ザ・バンドのほかにザ・バンドのようなバンドはない」という意味なのだ。
本の帯にある「伝説の正体はロビー・ロバートソンがつくりあげた「幻想のアメリカ」だった」というコビーは、和久井の卓見だ。カナダ人のロビー・ロバートソンが、南部アメリカ人のリヴォン・ヘルムを通してアメリカを「発見」したアルバムが、セカンド・アルバム『The Band』なのだ。「America」というタイトルにしてもよかった、とかつてロビー・ロバートソンはインタビューで語っていた。このロビー・ロバートソンがつくった「幻想のアメリカ」から、「ザ・バンドの音楽=アメリカーナ」というイメージが生まれることになったのである。
興味深いのは、先に取り上げた『ザ・バンド全曲解説』は、カバーに「アメリカーナ」を想起させる初期ザ・バンドのメンバー写真を使っているのに対し、『ザ・バンド完全版』は、ファンからはいちばん評価の低い最後のスタジオ録音『アイランド』のジャケット写真をアレンジして使っていることだ。専門家の間でも、ザ・バンドの音楽について「アメリカーナというアメリカの音楽だ」という観点からとらえている人と、「アメリカーナはロビー・ロバートソンがつくりあげた幻想のアメリカ音楽だ」という観点からとらえている人がいることを示唆している。
「幻想のアメリカ」ということで言えば、松本隆は、アルバム『HAPPY END』の録音で初めてアメリカに行った時に、音楽の中のアメリカは現実のアメリカのどこにも存在しないのだと気づいたとどこかで言っていた。『源氏物語』を英訳したアーサー・ウェイリーも、「自分は日本には行ったことがないが、自分にとっての日本は『源氏物語』の中にしかない」というようなことを書いていたが、それが芸術の本質でもあるだろう。

和久井光司責任編集『ザ・バンド完全版』(河出書房新社)
ぼくはザ・バンドの音楽を聴いて「幻想のアメリカ」を思い描いたことはなかった。というのも「The Night They Drove Old Dixie Down」を聴いても、日本人のぼくには南北戦争がイメージできなかったからだ。
「THE BAND playing THE MUSIC」。これは『ザ・バンド完全版』21ページに掲載されている写真「『ブラウン・アルバム』リリースの際にキャピトルが出した巨大な宣伝看板」に書かれてあるキャッチコピーだ。一九六〇年代のキャデラックの全長より長い幅の巨大な看板には、セカンド・アルバム『ザ・バンド』のジャケット写真から切り抜いた五人のメンバーの写真が使われており、バストショットの胸のあたりに「THE BAND playing THE MUSIC」という文字があしらわれている。よくこんな看板写真まで集めたものだと感心するが、すばらしいキャッチコピーだ。ザ・バンドというバンドとその音楽を的確に表現している。
●『南十字星』と「ラスト・ワルツ」の間にあるアルバム
『ザ・バンド完全版』には、『南十字星』からコンサート「ラスト・ワルツ」への道程を考えるうえで欠かせないアルバムが取り上げられている。それは、一九七六年六月にリリースされた、ロビー・ロバートソンのプロデュースによるニール・ダイアモンドの『ビューティフル・ノイズ』だ。
中学生の頃ニール・ダイアモンドから洋楽を聴き始めたぼくは、このアルバムも繰り返し聴いていた。ある日、ニール・ダイアモンドが「ラスト・ワルツ」というザ・バンドの「解散コンサート」に出たという記事を音楽雑誌で読んでザ・バンドに興味を持ち、『南十字星』を聴いてその音楽に魅せられたのだが、実際にはそれと知らずに、洋楽の聴き始めから『ビューティフル・ノイズ』に参加しているロビー・ロバートソンとガース・ハドソンの演奏を聴いていたわけである。
一九七五年十一月リリースの『南十字星』の次に来るアルバムは、一九七六年六月リリースの『ビューティフル・ノイズ』だ。そして一九七六年の十一月二十五日に最後のコンサート「ラスト・ワルツ」が行われることになる。このアルバム評を担当している和久井光司だけが、このことの意味に気づいている。
「エルヴィス・プレスリーからも地続きの堂々たる〝エンタテインメント〟は、アメリカに妙な憧れを持つ日本人がいいかげんな気持ちで聴いているルーツ・ロックなんかよりも何倍も〝プロフェッショナルな仕事〟だと思う。ルックスがロックっぽくないからダイアモンドは当り障りのないポップ・シンガーに見えるけれど、フォーク、カントリー、ロックンロールをアメリカの日常に収めてしまえる懐の深いポップ解釈は、ロビーの〝公平さ〟とみごとに共鳴していた。『ノーザン・ライツ~』と『ラスト・ワルツ』のあいだにこれがあったと受けとめると、ザ・バンドに引導を渡したロビーの気持ちもわかる」(和久井光司「Neil Diamond Beautiful Noise」『ザ・バンド完全版』)
いろいろな誤解があるが、ロビー・ロバートソンと音楽的に類縁性があるのは、ボブ・ディランではなくてむしろ『ビューティフル・ノイズ』のニール・ダイアモンドだ。ニールはブルックリン育ちの「都会っ子」で、ティン・パン・アレーの流れを汲む、ブリル・ビディングの作曲家としてキャリアをスタートした人だ。シンガー・ソングライターとして成功したが、ボブ・ディランのように「自分が歌う」作品として創作するタイプではなく、プロの作詞・作曲家として「歌手が歌う」作品として作った曲を自らが歌っているという感じのアーティストだ。
『ビューティフル・ノイズ』は、ティン・パン・アレーの下積みのソングライターの目から見た一九六〇年代のニューヨークという「街」をテーマにしたコンセプト・アルバムで、「物語」を作詞の手法とし、メンバーが歌う作品として創作するトロント育ちの「都会っ子」ロビーと響き合うところがあったのだと思う。

ニール・ダイアモンドのアルバム『ビューティフル・ノイズ』。デザインはセカンド・アルバムの『ザ・バンド』以降、最後のスタジオ録音『アイランド』までザ・バンドのアルバムを手掛けたBob Cato。タイトルの下には「Produced by Robbie Robertson」と入っている。ハンドレタリングは、ビル・グラハム主催のイベント「ザ・ラスト・ワルツ」用のポスターも担当したMichael Manoogianによるもの。タイトル文字の色使いは、Dan Perriがデザインした映画『The Last Waltz』のタイトルバックにヒントを与えたのではないかと思う
ロビー・ロバートソンは自伝の中で、「ニールはこのアルバムをつくっているあいだ、自分のアートに全身全霊を傾け、曲づくりの技術を上げることに心をくだいていた。おかげでぼくはこの経験全体から、深い感銘を受けることになる。〔中略〕新たな、すばらしい音楽経験が積めたことを心からありがたく思った」(『ロビー・ロバートソン自伝 ザ・バンドの青春』奥田祐士訳)と述べている。
ロビー・ロバートソンがニール・ダイアモンドのアルバムをプロデュースしている間にも、リヴォン・ヘルム、リック・ダンコ、リチャード・マニュエルの三人は「酒とバラの日々」を送っていた。「ぼくはガースとふたりで三人のジャンキーと、名ばかりのマネージャーの面倒まで見なければならないのかと不安になった。そしてとうとう「もういい」と音を上げたのだ」(同前)。
ザ・バンドが最後のコンサート「ラスト・ワルツ」を経て「解散」に至った背景には、こういった事情があったのだろう。
●ロックと詩が交わる場所
コンサート「ラスト・ワルツ」は、有名なプロモーターのビル・グレアムが経営するサンフランシスコの「ウインターランド」で行われた。
コンサート後半の休憩時間には、サンフランシスコの詩人たち七人がリレーで朗読を行った。映画『ラスト・ワルツ』では、ボブ・ディランと交流のあった、ビート派の詩人ローレンス・ファーレンゲティ(Lawrence Ferlinghetti)とマイケル・マクルーア(Michael McClure)の朗読シーンが採用されているが、ブラック・マウンテン派のロバート・ダンカンやダイアン・ディ・プリマも朗読した。
このリレー朗読は、リック・ダンコのソロ・アルバム『Rick Danko』の「Sweet Romance」ほか数曲を共作しているエメット・グローガン(Emmett Grogan)が、ロビー・ロバートソンに提案して実現したという。ヒッピーの活動家集団「ザ・ディガーズ(The Diggers)」を、一九六六年にサンフランシスコのヘイト・アシュベリーで創設したグローガンらしい企画だったと言えよう。ザ・バンドはヒッピー・ムーブメントに背を向けて『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』でデビューしたというイメージがあるが、それは音楽上のことであって、マネージャーのアルバート・グロスマン(ボブ・ディランやジャニス・ジョップリンのマネージャーとして有名)を介して、グローガンとの交流もあった。グローガンの「The Band’s Perfect Goodbye」は、「ラスト・ワルツ」について書かれた最も詳しく、信頼できるリポートである(「The Band web site」で読むことができる)。
ヒッピー文化発祥の地ヘイト・アシュベリーがあるサンフランシスコは、ローレンス・ファーレンゲティが一九五三年にシティライツ書店/出版社を設立し、一九五六年にアレン・ギンズバーグの『吠える その他の詩』を出版するなど、ビート派の詩人たちの本拠地でもあった。ギンズバーグが初めて『吠える』を朗読し、ビート派のポエトリーリーディングのスタートとなった一九五五年十月七日のシックス・ギャラリーでの朗読会は、マイケル・マクルーアの発案だった。
マイケル・マクルーアは自作の詩ではなく、チョーサーの『カンタベリー物語』の冒頭の一節を中英語(Middle English、一一〇〇年~一五〇〇年の英語)で朗読している。「ラスト・ワルツ」を観に全米各地から集まった観客と、出演するためにつどったカナダ、イギリス、アイルランド、アメリカ各地出身のミュージシャンたちのことを、『カンタベリー物語』の冒頭の一節に重ねたのだと思われるが、観客でその意図がわかった人はどれくらいいたのだろう。だが、意味はわからなくてもよい(暗唱しているマクルーアも原文の一行を飛ばしてしまっている)、以下のテキストを見ながら映画の朗読を「音楽」として聴いてみてほしい(実際は冒頭から暗唱していったのだが、映画では途中から始まっている)。
〔※フェードイン……Hath in the Ram his halve cours yronne,〕
〔……(若い太陽が)白羊宮の道程の半ばを通過し、〕
And smale foweles maken melodye,
小鳥たちがメロディをさえずり、
That slepen al the nyght with open ye
一晩中目を開けて眠る頃になりますと、
(So priketh hem nature in hir corages);
それほど自然は彼らのこころをかきたてるのですが、
Thanne longen folk to goon on pilgrimages,
人々は巡礼の旅に出かけたくなるのです。
〔※この一行読み飛ばしAnd palmeres for to seken straunge strondes,〕
To ferne halwes, kowthe in sondry londes;
諸国に知れ渡った聖廟へと赴きたくなり、
And specially from every shires ende
特にイングランドの津々浦々からは
Of Engelond to Caunterbury they wende,
人々がカンタベリィに向かい、
The hooly blisful martir for to seke,
病気のときに癒して下さった、あの聖なる、
That hem hath holpen whan that they were seeke.
有難い殉教者に詣でたくなるのです。
(原文は市河三喜・松浪有編注『カンタベリー・テールズ(新訂版)』、訳文は『原文対訳「カンタベリィ物語・総序歌」』苅部恒徳ほか訳)
マクルーアが『カンタベリー物語』を朗読したのは、おそらくグリール・マーカスの『ミステリー・トレイン』のザ・バンドの章が「Pilgrims’ Progress」(ジョン・バニヤンの『天路歴程』)と題されていることを踏まえてのことだろう。「ラスト・ワルツ」が行われたのは、メイフラワー号に乗ってイギリスからアメリカに渡ったピルグリム・ファーザーズ(Pilgrim Fathers)が収穫を祝った感謝祭(Thanksgiving)の日だったのだ。
マクルーアは肝心の「palmeres」(palmerは各地を巡る「プロ」の巡礼者のこと)という言葉が出てくる一行、「And palmeres for to seken straunge strondes,」(巡礼者達は異国の岸辺を訪れ、)を読み飛ばしてしまったが、彼が『カンタベリー物語』の朗読に込めたメッセージは、「巡礼者達(ゲスト・ミュージシャンたち)は異国(アメリカ)の岸辺(サンフランシスコ)を訪れ、諸国に知れ渡った聖廟(コンサート会場)に赴きたくなり、特にイングランド(アメリカ)の津々浦々からは人々(観客)がカンタベリィ(ウインターランド)に向かい、病気のときに癒して下さった(音楽で人々を癒してくれた)、あの聖なる、有難い殉教者(ここで「解散」するというザ・バンド)に詣でたくなるのです」ということだろう。
ローレンス・ファーレンゲティはアレン・ギンズバーグと共にビート派の中心人物だった。一九一九年生まれで、第二次世界大戦では海軍中尉としてノルマンディー上陸作戦に参加している。二〇二一年二月に何と一〇一歳で逝去したが、日本の詩人で言えば一九二〇年生まれの鮎川信夫と同世代である。鮎川信夫は荒地派の詩人だが、ウィリアム・バロウズの『裸のランチ』を翻訳しており、意外なところでビート派につながっていた。
ファーレンゲティが朗読した詩は「主の祈り」(The Lord’s Prayer)のパロディ「The Lord’s Last Prayer」だった。「主の祈り」のパロディを朗読したのは、これも感謝祭のメインがディナーであり、当日はビル・グレアムの計らいで観客に七面鳥など感謝祭の食事がふるまわれたからでもある。映画では観客の笑い声がする。「Last Prayer」なのは、もちろん「Last Waltz」だからだ。ファーレンゲティの朗読シーンの後にボブ・ディランが登場するであろうことは、ディランとビート派の詩人たちの関係を知っていれば容易に想像がついたと思う。
W・H・オーデンは「詩は本質的に話されることばであって、書かれたことばではない。ことばの実際の音で聞かない限り、人はその読んでいる詩を把握できぬ。そして、その詩の意味は、詩に用いられていることばと、それを聴いている人の反応の間の対話の所産である」と言っている(中桐雅夫訳「人間のことばと神のことば」『第二の世界』)。
ボブ・ディランが、ホメロス以来の詩の「口誦性」の文化的伝統に連なる「詩人」としてノーベル文学賞受賞に至った背景には、「朗読」を媒介にして詩とロックが交わる「文化的環境」があったのだ。
だが、誤解してはいけない。「歌詞」は「詩」ではない。「歌詞」を「詩」として読めば、それは「歌詞」ではなくなってしまう。「歌詞」を朗読してみれば、「詩」にある「音楽」が「歌詞」にはないことがわかるはずだ
ロックは「文学」ではない。ロックは「音楽」だ。
(第05回了)
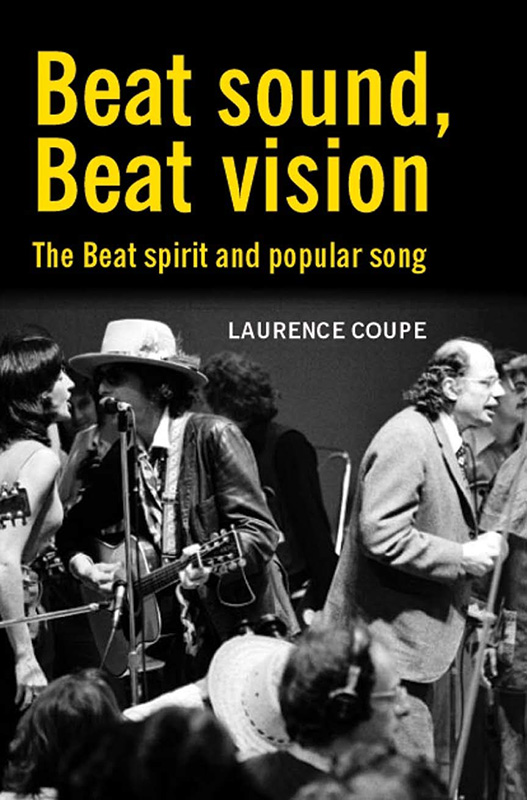
Laurence Coupe著『Beat sound, Beat vision: The Beat spirit and popular song』(Manchester University Press)。右にいるのがアレン・ギンズバーグ。左はボブ・ディランとジョーン・バエズ。一九七五年十二月八日にマディソン・スクエア・ガーデンで行われたハリケーン・カーターのためのベネフィット・コンサート(第一次ローリング・サンダー・レヴュー・ツアーの最終公演)の写真。トリミングされているが、元の写真ではギンズバーグの右にロバータ・フラックがいる
(第05回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう』は毎月21日にアップされます。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


