 男がいて女がいて、二人はふとしたきっかけで知り合った。運命的な出会いではなかった。純愛でもなかった。どこにでもいる中年男女のママゴトのような愛だった。しかし男は女のために横領という罪を犯し、社会から追いつめられてゆく。では女は男からなにを得てなにを失ったのか、なにを奪いなにを与えたのか・・・。詩人、批評家でもあるマルチジャンル作家による、奪い奪われる男と女の愛を巡る物語。
男がいて女がいて、二人はふとしたきっかけで知り合った。運命的な出会いではなかった。純愛でもなかった。どこにでもいる中年男女のママゴトのような愛だった。しかし男は女のために横領という罪を犯し、社会から追いつめられてゆく。では女は男からなにを得てなにを失ったのか、なにを奪いなにを与えたのか・・・。詩人、批評家でもあるマルチジャンル作家による、奪い奪われる男と女の愛を巡る物語。
by 文学金魚編集部
「健ちゃん、どうしたの? すんごい顔色悪いよ。ズボンも靴もびしょ濡れだし」
いつものように仕事用のスーツを着た女が言った。女の白い指の間に鮮やかな赤のカンパリソーダのグラスがあった。
「会社出て、ちょっと歩き回ったから」
「この雨の中を?」
女は大きく目を見開いた。もう八時をまわっていた。
「昨日から変だよ。どっか旅行いこうとか。ねえどうしちゃったの?」
「うん」と生返事をしたが、昨日女に送ったメールが脳裏に浮かんだ。現実から逃げ出したかったので、涼子と旅行に行きたいとは書いた。本気ではなかった。しかし男の不安は現実になり、自宅待機を命じられてしまった。このまま家に帰り、会社からの電話を待つことに耐えられそうになかった。
「その話なんだけど、これからすぐに旅行に出ないか」
男は唐突に言った。
「旅行ってどこに?」
「どこでもいいけど・・・。そうだ、名古屋ならよく知ってる。あそこは三年いたから」
「無理よ。ねえどうしちゃったの? ちゃんと答えて」
男は霧のように不安な表情を浮かべた女を美しいと思った。しかし言葉は出てこなかった。横領の露見は時間の問題だから、女にもそれを話しておかねばならなかった。だが女の反応が怖かった。女が席を立って、去っていってしまうことを恐れた。男は現実味のない旅行にしがみついた。

「明日は金曜だから一日くらい休めるだろ。それで土曜か日曜に戻ってくればいいじゃないか」
「会社にはなんて言うの? 家にも何も言ってないし」
「風邪で休むって言えばいいだろ。旦那には親戚が危篤だとか死んだとかで、これから急いで実家に帰ることになったって言えばいい。旦那はお前の言うことなら、なんでもハイハイって聞いてくれるんじゃないのか。一日二日くらい、だいじょうぶだろ」
「それはそうだけど」と言って女は口ごもった。
男は女に家庭のことを聞かれても、曖昧に答えて話題をそらすのが常だった。しかし女は夫との生活をあけすけに話した。男といて遅くなっても「メールしたから」と涼しい顔で言った。夫が女を信頼し、母親のように頼り切っているのは確かだった。
「健ちゃんのお家の方はいいの?」しばらくして女が聞いた。
「女房とは離婚する」
自分でも思ってもみなかった言葉が男の口から出た。
「ほんとに?」女が驚いた顔でたずねた。
「ああほんとうだ」
男は言葉に力をこめた。
これまでも男は妻と離婚して、お前といっしょになるつもりだと女に言い続けてきた。しかし何も知らない妻に離婚を切り出す勇気は出なかった。だが横領と女との関係が明らかになれば、間違いなく離婚になるだろう・・・。
「やっぱ健ちゃん変だよ。お願い、理由を言って」
女は懇願した。男は黙った。喉元まで「横領」という言葉がわき出た。しかし言葉にならなかった。男は両手で女の手を包み込んだ。「一日二日でいいんだ、いっしょにいてくれないか」と声を絞り出した。
「理由を言ってくれなきゃ」
女の顔が歪んだ。今にも泣き出しそうな顔に見えた。男は両手に力を込めた。「お前としばらく会えなくなるかもしれない・・・。頼む、いっしょにいてくれ」と繰り返した。
「会えないって、転勤? それとも病気かなにかなの?」
男は答えなかった。ただ強く女の手を握りしめ続けた。
男の必死さは伝わった。しばらくして女は視線を上げ「いいよ、名古屋でもどこでも行ってあげる。でも理由を話して」と男の目を真っ直ぐに見て言った。
男は「東京を出たら必ず話すよ」と答えてようやく女の手を離した。女は溜息をついてうなずいた。
小降りになっていたが外はまだ雨だった。男は傘を拡げて女と品川駅に向かった。「そんなにしたら健ちゃん濡れちゃうじゃない」という言葉にかまわず小さな傘を女の上にさしかけた。
駅前にたくさんのプランターが並んでいた。白い花が咲き乱れていた。さっきビルの前で見た花と同じように思えた。男は足を止めて「あの白い花の名前ってなんていうの?」と女に聞いた。
「あれ? 多分、アネモネ」
女は男を見上げながら答えた。
「ああ、アネモネね、アネモネ」
男はつぶやいた。なにか世界の神秘が一つ解けたような気がした。
「やっぱ健ちゃん変だよ」と女が笑った。
女が夫に電話をかけている間に、男はATMで百万ほどの現金を引き出した。これも会社から横領した金だった。使えばさらに罪が重くなるだろうが、いまさらとも思った。男は売り場に向かい名古屋までの新幹線の切符を二枚買った。切符を背広の内ポケットに入れようとして、男はなぜ名古屋に行くのだろうと人ごとのように思った。

娘の亜美はまだ塾で、帰るのは九時過ぎのはずだった。それから妻と食事をして眠るのは十一時近くだろう。いつものことだから「パパ遅いね」とも言わないはずだ。しかしすぐに妻と娘は男の横領を知ることになる。女との関係もバレるだろう。男の背中がまた汗でグッショリと濡れ始めた。
「月曜か・・・」
男はつぶやいた。今までのコトの運びからいって、週明けの月曜には男は会社に呼び出され、監査から厳しく帳簿について問い質されるだろう。だとすれば女房にすべてを打ち明けるのは、土曜か日曜の夜しかない。
男はケータイを取り出すと「急に出張になった。日曜の夜に帰る」と妻に短いメールを書いた。無意識に告白のタイミングをギリギリまで引き伸ばしていた。替えのワイシャツも下着も持たずに家を出たのだから不審がられるだろうと思ったが、男はそのまま送信ボタンを押した。ディスプレイに「送信終了」と表示されると電源を切った。「俺には時間が必要だ、時間が必要なんだ、少しだけ時間をくれ」と頭から妻子を追い払いながら考えた。
顔をあげると通路の先で電話を終えた女が男を見つめていた。女の周囲だけポッと明るんでいるようだった。男は足早に女に近づいた。肩を抱くと「行こう」と言って改札口に向かった。今この瞬間、自分にはこの女が絶対に必要なのだと思った。男と女は名古屋行きの最終に乗り込んだ。
車内は静かだった。一人客が多く、雨で平日のせいか座席は三分の一も埋まっていなかった。男は座席に身体を投げ出すと、腕を伸ばして女を引き寄せた。三十代くらいのサラリーマンが歩きながら二人に露骨な視線を投げた。男はにらみ返した。サラリーマンは視線を外して通り過ぎた。
「ねえ、もう話してくれてもいいでしょ」
新横浜を過ぎたあたりで女が口を開いた。男は黙ったままだった。答えるかわりに肩に回した手を女の背中からお尻の方に何度も滑らせた。女は身じろぎもしなかった。
男は女の耳元に唇を寄せ「涼子、愛してるか?」と聞いた。「うん、愛してる」と女は甘い声で答えた。
「涼子、セックスしたい」
女はパッと身体をこわばらせて顔をあげた。「なに言い出すのよ」と小さく強い口調で言った。
「いいじゃないか、ここでしようぜ」
「バカなこと言わないで。できるわけないでしょ」
「できるよ。誰も見ちゃいないさ。ここがいやなら・・・そうだ、トイレでしようぜ。お前が先に行けよ。俺は少し後から行くから」
「なんで今日はそんな無茶なことばっか言うの」
女は必死に太ももに伸びた男の手首を抑えた。男は引かなかった。俺の女だろ、やらせろよと乱暴な口調で迫った。卑怯だと思った。しかしそうせずにいられなかった。ついさっきまでは萎え切っていた性欲が強烈に湧きあがった。
激しく言葉と身体でもみ合うことに女の方が疲れた。女は「もういい。好きにして。でも終わったらちゃんと話して」と言って怒りの目で男を見た。
席を立ちかけた女が「健ちゃん、あれ、持ってるの?」と聞いた。「あれ? ああ」男は鞄の中に手を入れ底敷きの下を探った。男が避妊具を取り出そうとすると、「見せなくていい」と言って女は足早に通路を歩いていった。
狭いボックスに入ると女が立ったままじっと男の目を見た。男は無言で女の肩に手をかけ、後ろ向きにさせた。スカートをまくり上げ、パンストとパンティをいっしょに下ろすと、勃起したそれに避妊具を付けて女の中に強引に突き入れた。女が低く呻いた。男は両手で女の腰をつかんで動いた。手すりにしがみついた女の背中が丸くなり、大きく身体を震わせた。
男は避妊具を外すと便器に投げ入れた。アルミの便器にピンク色の避妊具がへばりついた。射精はしなかった。女は肩で息をしながら「先に戻って」と囁いた。
「実は会社の金を使い込んで、それが今日、上司にバレてしまった・・・」
男は女の身体を抱きながら、上司に自宅待機を命じられたこと、来週早々には会社に呼ばれ、監査の人間に横領について問い糾されることになるだろうと話した。

女は息を詰めて男の話を聞いていた。男の話が途切れると「そしたら健ちゃん、つかまっちゃうの?」と不安な声で尋ねた。
「それは、どうかな・・・」
男は言葉を濁した。男の勤め先は政府系の天下り会社だった。主に公共事業や第三セクターで手がける道路や建築用資材の受発注を行っていた。利幅は薄いが大量取引する資材のマージンで、相当の利益を上げていた。使い込んだ金はもちろん弁済を求められるだろう。しかしそれは民事の話で、告訴するかどうかは会社次第だった。
「どのくらい、使っちゃったの?」
「そうだな、だいたい二千万くらいかな」
「それじゃ、あのお金って・・・」
「うん、涼子、すまない。許してくれ」
男は女の肩に回した腕に力を込めた。男の胸に顔を押し付け、小刻みに身体を震わせながら女は泣いた。男は女から視線を外して窓の外を見た。雨滴が一面にはりついた暗い窓の外に、ビルや民家の光りが淡く流れた。
最初は単純な経費の水増しだった。妻に給与のすべてを握られているサラリーマンが、たび重なる女との食事やホテル代を捻出できるはずもなく、男は領収書をすり替え時には白紙の領収書に金額を書き込んで差額を手に入れた。会社に内緒で取引先に収入印紙代を負担させ、それで得た印紙を金券ショップで換金した。しかしそれでは足りなかった。
付き合いが深まると、女は夫と離婚して男と結婚したい、いっしょに暮らしたいと言った。男は夫一人でローンを払い続けるためには、千五百万くらいの金が必要だと試算した。まずそれを埋めるのが先だと考えた。
男の会社は純粋な民間企業に比べれば監視の目が緩かった。ほとんど出社しないで高給を受け取っている役員が三人いたが、男を含む実働社員は人数が少ない割に大きな権限が与えられていた。男はそれを利用した。
元証券マンだった男の仕事には会社保有の株式の管理も含まれていた。ほとんどが取引先の持ち合いの塩漬け株で、売買するには役員たちの決済が必要だった。男は発行数の多い株を選んで勝手に動かし始めた。口座は証券マン時代に作った妻や親戚名義のそれを使えばよかった。監査では株の保有数を確認するくらいなので、それまでに買い戻しておけばよかった。
最初のうちは自分でも驚くくらい順調だった。男は不遜な自信を抱いた。いくらでも儲けられるような気がした。俺は株のプロだ、その気になれば簡単さと得意げに女に話した。今までに女に渡した金は総額で五百万を超えていた。
しかしそんなにうまい話が転がっているはずもなく、思い切って勝負に出た仕手株で大きな損を出した。男はしかたなく信用取引を始めたが赤字はなかなか埋まらなかった。一気に負けを取り返すために証券時代の知り合いで、さして親しくもなかった投資家がほのめかした情報で先物を買いさらに負債は膨れ上がった。
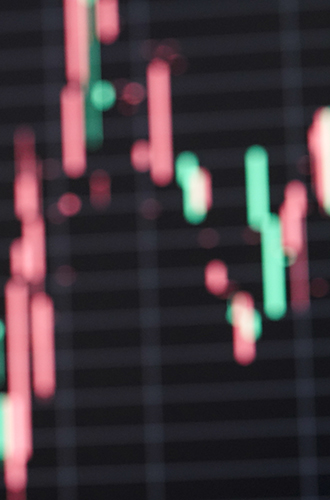
決済で現金が必要になった男は複数の架空取引の出金伝票を作った。一番露見しやすい帳簿操作だということはわかっていた。しかしまだ先だが実際に取引は行われるはずなので、その時までに伝票を差し替え金を埋めておけばだいじょうぶだと自分に言い聞かせた。臨時監査で露見し、役員が男に突き付けたのはこの伝票だった。損切りできずに放置してある証券類などを精算すれば、全部で二千万近い金を男は使い込んでいるはずだった。
女は黙って男の言葉を聞いていた。「健ちゃんどうなっちゃうの?」「わたしたち、どうなるの?」と聞いたが男の行為を責める言葉は口にしなかった。男はそれだけでもありがたかった。横領を知った女がまだそばにいてくれることを感謝した。しかし女を安心させる言葉はなかった。女は声を殺して泣き続けた。
(第04回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『横領』は毎月11日に更新されます。
■ 鶴山裕司さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■




